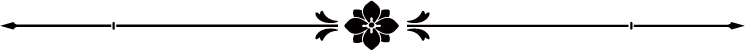ゆめである
からん。ころん。下駄の音が石造りの地面を鳴らす。足元を照らす提灯の火が風に吹かれて揺れる度、自分の影もゆらゆらと揺れて形を失っていた。
道の両端を草木が覆っているため月明かりは全くもって届かない。頼りになるのは手に持ったたったひとつの提灯だけ。普段着ることの無い着物の裾がひらひらと脛を掠めてくすぐったいのを我慢する。なんとなく黒に近い色を選んだのは、こうして闇夜に紛れることが出来るからだった。
風が吹けば草木が踊る。火も踊る。不意を突かれて吹いた強風は、着物だけではなく足元すら揺らした。反射で閉じた目を細めて前を見据えれば――見えてきた。
一見破棄されたように見えるボロボロの日本家屋には、きちんと人が住んでいることを証明するように一箇所だけ明かりが灯されていた。迷わず足を明るい方へ動かせば、誰かの気配が近くなる。玄関から入らずにわざわざ裏手まで回って下駄を脱ぐ。腐りかけの板が悲鳴をあげた。
ぼんやりと柔らかい明かりが漏れ出る部屋の襖を開けた先。人が来るのを待っていたように座る男がひとり、そこにいた。
「久しぶりっすね〜」
「そうだね。ところでもう少し来やすい場所にしてくれない? ここに来るの大変なんだけど」
「いやぁ気に入っちゃって」
「だからってさぁ……。まあいいや、お邪魔します」
「おっ! いらっしゃい!」
元気だなぁ。くふくふと笑って、素足で畳を踏み歩く。男の傍に腰を下ろす際に着物がはだけるが、ここには男しかいないので気にすることもない。毎度毎度、この男はそっと元に戻すけれど。今更そんなことを気にする仲でもないだろうに。畳だからと言って正座をする程のものでもない。
男の手にある盃の中はもう空っぽだった。一瞬だけ視線をやっただけだからその視覚的情報が正しいのかは未だ分からない。空っぽに見えたはずの盃を口元へ注ぐのを見て、やっぱわかんねぇな、と独り言つ。
何度か繰り返し口に注がれるそれを見ながら、立てた膝の上で肘をつく。まだ成長しきっておらず、肉のある頬が潰れる。
黄金色の長い髪は畳に垂れていた。よくわからない装飾をたくさんつけて重そうに見えるのに、この男は重力なんて一切感じていないように身軽なことを知っている。
「ガクくんさぁ」
呼び慣れた己の相方の名前を口にする。黙っていれば不気味な雰囲気を醸し出す見た目をしているはずなのに、どうしてかその表情は若く見えた。猫目をぱちりと開いて、その瞳の中に僕を映す。
なんですかー? 軽い音を発しながら首を傾げるこの男は、みなまで言わずとも僕の言いたいことなんて察している。長い時間を共にしているのだから、僕だってこいつが言いたいことがあればなんとなく察することが出来るのに。それでも言葉でやり取りをするのは、職業病か、それとも。
「いつまで僕をここに呼ぶつもりなの?」
「はて? なんの事だかさっぱりだなぁ」
「わかってるくせに…………」
いひひ、と声を高くして笑った相方は、柔らかく目を細める。それにもういいの? 声をかけると、笑顔を崩さないまま満足だと言った。
「それに、そろそろ目覚める時間だろ?」
「わかんない、わかんないよ僕には、ここでの時間の経過なんて」
「そういうもんすかね」
「人間を舐めるなよ」
観念するように瞼をおろせば、視界は遮られて真っ暗闇に放り込まれるはずなのに眩い光に包まれる。何回経験しても慣れないし、どういう原理なのかもわからない。
次に目を開いた時には、見慣れた天井がそこにあった。カーテンの隙間から溢れ出る光は太陽のもの。
屋敷内にいる時間よりも移動時間の方が長くなるのは如何なものか。過去に何度か伝えたことはあったけれど、やっぱり僕の初期地点は変わらなかった。本当にあれで満足なのか。本人が言っているから嘘では無いのだろうが、それはそうとして。
体感じゃ数分しか経っていないはずなのに目が覚めれば朝になっているのだから、相変わらず寝た気がしない。それでも普通に眠った時よりも溜まった疲労感が全て取り除かれているように感じるのだから、不思議で仕方がない。
枕元に置いていたスマホがぴこん、と通知を知らせる。相手が誰かなんて見なくてもわかった。僕が目覚めたということは、相方の男も目が覚めているはずだ。
画面を開いて表示される内容に、呆れたようにため息を吐き出すつもりが、笑みが零れていた事実なんて知らない。
途切れた会話の始まりが〝ありがとうございました!〟なんて、意味が通じるのは僕たちだけだ。