藤真さんと付き合うことになって、気がつけばすでに約二ヶ月が経とうとしていた。付き合うといっても『好きだから』とか言葉の確認があったわけではない。「付き合ってみないか俺たち」と突然言われた。しかも駅のホームで。久しぶりに訪れた地元……神奈川からの帰り道で。幼馴染に婚約者を紹介されたすぐあとに。まるで、お試しで使ってみてくださいと、試供品を渡す百貨店の美容部員みたいに。
べちゃべちゃに泣いて一人駅のホームのベンチに座り込んでいた奇行人物に彼は言った。「俺と付き合ってみないか」と。「どんなに辛いこともいつかは過去に変わる」——って。
初めの出会いこそ最悪だったはずが、あっさりこうして付き合って仕舞いには久しぶりに会った高校時代の親友二人にバレてしまって気がつくと二ヶ月も経っていたのだから驚いてしまう。
だが、いまとなれば思うことがある。あの駅のホームで話しかけてきた相手が、藤真さん以外の異性だったらこんな展開にはなっていなかったんだろうなって。たとえば水戸くんやリョータくんだったらいつも通り話を聞いてもらって励ましてもらって、今回も親身になって話を聞いてくれてありがとう、また迷惑をかけてしまったね……で終わったはずで、あれが藤真さんだったからこそこんなかたちになったんだろうな、って。
前は……まだ、出会ったばかりのころは距離があった。藤真さんが作る硬くて、エベレスト級の高すぎる壁。それでいて間合いの取り方や、ギリギリのラインで、身体には触れてこない距離感。しかし、この二ヶ月の間に急速に進展する関係になってしまい戸惑ってはいるが日々は癒すようにやさしく過ぎていく。いつか、このふわふわした気持ちを懐かしむ日がくる事を教えるように——
*
「——それで?アンタたち、どうなのよ」
彩子が真顔で急にそんなことを言うから持っていたポテトをぽろっと手から落としてしまった。
「え?」
「だーかーらー!アンタと藤真健司よっ。うまくいってんの?いってないの?」
「えっ」
「別に隠してるわけじゃないでしょー?ていうか相手のほうは、隠す気なんか更々なさそうよね」
都内のファストフード店のざわざわした二階。最近いい感じの彼の話をする女子高生の大声が、店内に響き渡っている。不意に私もあの女子高生と同じでいくつになっても恋愛が下手だなぁと、そんな事をぼんやり思って、彩子から視線を外に移す。窓ガラスごしに真っ黒い夜空の色が透けて店内の様子を鏡のように照らしていた。その視線をまた戻せば彼女はきれいな口元でアイスティーを飲みながら私を一瞥する。早く教えろ、と言わんばかりに。
「隠してるわけじゃないけど、わざわざあれこれ公表する事もないかなぁって……」
「まあねぇ〜。で?ヤッたの?ヤッてないの?」
「なにを?」
「ちょっとー、こんな公共の場で言わせるつもりぃ〜?アンタ性格悪いわよっ」
「いやそもそも始めに話を振ってきたのは……」
「すぐに否定しないってことは、シたって事ね。さすがスマートね、あの男。誰かさんと違って」
「……」
そうなのだ。彼、藤真さんは確かに以前から、まったくと言っていいほど、性に関して無関心というか、興味なさそうというか。男女の触れ合いとは?みたいなオーラで私に対してその類の絡みを求めてこなかったし、そんな素振りすらも見せなかった。それでも時折ちゃんと優しくて、頼りになって、強くて、ちょっといじわるで、バスケットが上手で、仕事が全てで……私なんてただの知り合いの一人みたいな感じだった。たとえお付き合いをしている身でも。
でも、関係を壊したくなくて何か自分からアクションを起こすなんて事はしないと決めていた。彼の存在が私の生活の中で実は重要な部分をしめていたのは確かで、そばにいるだけで嬉しかったから。それなのにこういう関係になるなんて……こんな事もあるんだなぁとしみじみと思う。この現状が何とありがたく、なんと奇跡に近いことであろうか。私はいまも夢じゃないだろうかという疑いを捨てきれない。だって抱かれてびっくり。彩子の言うとおりで彼はめちゃくちゃにスマートで優しいのだから。もっと淡白なセックスを求めてくるようなイメージを勝手に持っていたから、意外だったといえば、意外だったけれども……。
「どんな感じなのよ?優しい?」
「……」
「やだ、そっちの話じゃないわよ?性格よ性格」
彩子のフレッシュな色味の唇が美しい弧を描いている。昔からお姉さんみたいな存在。心配性で強くてとても優しい彼女にはついすべてを聞いてほしくなる。しかし、あんまりなんでもかんでも話すのは藤真さんに悪い気がする。昔はそんな事も気にせず彼女にはあれもこれもと彼氏のことを話したものだが、今はそうはいかないだろうと、さすがの私も考えを改めたのだ。けれど藤真さんはきっとそんな事なんて気にしないだろうけど。
「うん、優しいよ」
本当に、優しいとは思う。私を大切にしてくれているんだろうなぁって分かる。どこを好きかと問われると難しいけれど、何してるかなって考えたりするし、他愛もない会話なんかも思い出す。彼のたまに見せる、笑顔のような柔らかい表情が浮かんでくる度に、あの幼馴染を想うような痛くて苦しい、どうしようもなく愛おしい気持ちにはならないけれど、言葉に表せないような抑えきれない胸の音が響いているのは確かだった。
きっとこのまま一人でいたら気付けなかった。誰かを想うことで強くなれるってことを。そう、私をあの闇から救ってくれたのは紛れもなく藤真さんだったのだ。
「……そう。大事にされてんのね」
からん、からん、と氷をストローで鳴らしながら彩子は目を細める。まるで自分のことのように彼女も喜んでくれている。その事に胸がいっぱいになった。
*
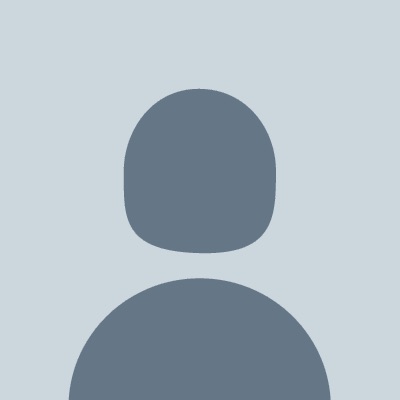
藤真 健司
お疲れ様。いまどの辺?迎えに行くよ
彩子と別れた事をメッセージで伝えると、藤真さんからそんな返信が届いた。駅にいる旨を送ったら『了解』と打った文字だけが来た。やはり、今流行りのSNSを使っているとはいえ、スタンプなどの類は使用しないタイプらしい。いつだったか怖いもの見たさで軽めのスタンプを送ったら、文字にして『?』と返ってきて、思わず慌てて『ごめんなさい、間違えました』と送ったことが今となれば懐かしい感じがする。
見慣れた、通い慣れたこの駅前には色んな人々の姿がある。きれいなお姉さんやサラリーマンや高校生やカップル……そんな雑踏をまっすぐ彼が歩いてくるのが見えた。艶のある茶髪に高価そうなスーツとこれまた高価そうな腕時計がキラキラと一際目立っていた。そして私に向ける目を細めて息を吐く独特の笑み。こんな人ごみの中でも、淡い光を纏っているように、特別に見える。彼は私のそばまでやってきて「待ったか?」と、短く問う。
「ううん、全然。藤真さんこそ早かったですね」
「……ん?なんだか今日はおしゃれをしてるな」
「えっ……まぁ、そうかもですね」
「いつもとちょっと雰囲気が違う。可愛いよ」
一瞬、時が止まった。まさかさらっと……え、今わたし可愛いって言われたの?この人に?嘘だそんなのありえないと思って、思わず「どういう意味?」と聞き返してしまった私に彼は言った。
「そういう意味。さて、行くか」
悪びれず、淡々と彼は言う。でも、いじわるな微笑が横顔からでも分かって、ちょっとイラッとしたけれど珍しくそっと握ってくれた手が優しかったから、そんな事はもうどうでも良くなった。
「マネージャーとランチ行ったんだろう?じゃあ腹は減ってないか。どこか、飲みにでも行くか」
「うん、おいしいダイキリ飲みたい」
「ダイキリ?なかなかシブいチョイスだな」
「藤真さんは?今日なにしてたんですか?」
「俺は仕事だ。まぁ後処理ってやつだな」
「そっか、お疲れ様でした」
手をつないだまま、街の中を歩く。歩く速度に応じるように夜風がやわらかく顔を撫でる。湿った空気の匂い、左手を包む男性らしい、けれどもなめらかな手の感触。彼は前を見て歩いている。彼との沈黙は、共有のひとときだな、と思った。彼が黙っているのを今となれば私も黙って楽しんでいる。景色や匂いや感触が彼の隣にいると鮮やかだ。なんでもないことが、ひどく心地よい。
感じのよいバーでお酒を飲んで、それから高級ホテルのスイートルームで、シャンパンと夜景を堪能して、じゃれ合ううちに、セックスになだれこんで——シャワーを個々に浴びて、それから、少しぶらぶらと街を歩きながら彼のマンションに来た。そうして最終的にはベッドに倒れた。どうやら今日は一緒にこのベッドで眠りについてくれるらしい。今日の藤真さんやけに機嫌がいい気がする。でもそれを口にして、すぐに気が変わって別々に寝る、なんてことになったら嫌なので私は余計なことは何も言わずに口を噤んだ。
「今日——マネージャーとどんな話をしたんだ」
腕枕をしながら藤真さんが私の顔を見下ろしている。レースのカーテンを透けた、青白い灯りの端っこしか光源はないのに、彼の茶色がかった目だけが、きりりと光る。スーツや腕時計を外した彼はなんだか別人みたいだ。外した時計は几帳面に脇のサイドテーブルの上に置かれている。黒いTシャツと質感の良いスウェットパンツでベッドに横たわる藤真さん。表向きな武装を解いた彼はきっと恋人という立場でなければお目にかかれないのだろうなと思う。その特別を独り占めしているという優越感にひっそりと浸ってみたりする。
「近況報告ですかね。そういえば藤真さんとの事公表しないの?とか聞かれました」
「隠すつもりだったのか?」
「そうじゃないですけど、別に報告する人なんてあの二人くらいしかいないから」
「お友達が少ない私を慰めてほしい、って?」
くすくす、といじわるっぽく笑う顔がきらきらしている。スーツという名の武装がない、というだけで、こんなに幼くてきれいになるとは。まだ数えるほどしか見ていないけれど、まだまだ慣れなくて見とれてしまう。ふつうの会話をしているだけなのになぁ……。
「実際に、彼女は何て言ってるんだ?」
「喜んでくれてるよ。お似合いだって」
「おお。さすがあの問題児軍団のマネージャーをやってただけはあるな。見る目がある」
「言い方が刺々しすぎて返す言葉がありません」
「ハハ、そうか」
「でもまあ、そうだね。だけどちょっとびっくりしたみたい」
「ん?」
「藤真さんみたいなタイプの人が、私を選ぶのは意外だったって。逆も然り」
「へえ……」
さっきから彼の唇に緩い微笑が浮かんでいる。そうして目を伏せながら、耳を澄ませて私の声を聴いている。
私のお腹を撫でていた人差し指がするりと上がってきて、鎖骨と鎖骨の間のくぼみで止まった。
「意図して選んだわけじゃないけどな。感情とか元から表に出さないクセがついているんだ」
「元キャプテン兼、監督ですもんね」
「だから、いざ自由の身ってやつになっても慣れないんだよ。しがらみはまだ生きてる訳だしな」
「しがらみかあ。そっか、私には想像もつかないけど、すごい苦労があったんでしょうね……」
「……、名前。」
「なに?」
「ありがとな」
驚いて息を飲む私に彼、藤真さんは微笑むように目を細めた。最近急にこんなふうな彼が現れるから、慣れなすぎて当たり前に動揺してしまう。
「前はこんなふうにはなれなかった。そもそも、簡単に他人に入れ込むなんて色んな意味で危ないマネもできなくてな、まぁ性分みたいなものだ」
「そう?一歳しか変わらない同じ高校生だったのにね。あの頃からそんな感じ?藤真さんって」
「さぁ……でもあの頃に、お前と出会ってなくてよかった気もする」
藤真さんはそこで軽く口を噤んだ。私は、彼の眼差しを必死に見つめ返した。長い睫毛、二重目蓋の優しくも厳しくもなる瞳。考える目、傷ついた苦しみを知っている目……。
この人は色んな経験をしている。私が思うよりもずっと暗い闇に染まって、そしてそんな自分を客観視しているのだ。スーツをバリっと着こなしたままの彼では、わからなかった。こういう目をした人だったのだ。高校生のときに出会ってたら私……いや、こんなに近づく事は許されなかっただろうな。だって私にはずっと幼馴染の彼が——
「嬉しいんだよ。こんなに、他人に惚れることができて」
「……」
「昔なら名前のよさに惹かれはしても、気づかないふりをしていただろうからな」
「……、」
「名前、こっち」
「うん」
軽く引っ張られて藤真さんの胸に体を寄せる。目の前に彼の唇がある。その唇は秘密を打ち明けるように、ゆっくり瞬いた。三文字の——掠れた囁きがじんわりと胸を打った。やわらかな口上と違い、真剣な響きがあった。三文字、はっきりと聞こえなかったその言葉は〝寒い〟なのか〝寝るぞ〟なのか、はたまた——〝好きだ〟なのか……私は泣きそうな気持ちになる。いつも飄々としている彼が、なんでも器用にこなしてしまう彼が、危険な中でこそあざやかで自由な彼がいま本心を見せてくれている。まるで弱みを見せるように、切実な心を——。
「わたしも好き。大好きだよ」
やっとの思いで震えるように伝えた言葉に彼は「急にどうした」とか「何を言ってるんだ」とか冷たく遇らうわけでもなく、優しい顔でただただ聴いてくれていた。どこかおかしそうに、そして
……とても嬉しそうに。
「知ってるよ……ありがとう」
ふふっと鼻にかかった声がいとしい。やっぱり藤真さん、とっても機嫌が良さそう。だったら、それに肖って、さっき言った三文字が〝好きだ〟って言葉だったって、思ってもいいかな。今日の藤真さんなら、きっと許してくれるだろう。
これからもこんな夜を繰りかえして同じときを一緒に過ごしていくのかな。彼と出逢って、こうしてかけがえない時間を重ねていく。いつの日か忘れていた、人を好きになる気持ち……苦しくて切なくて、でも温かくて。どんな景色も、眩しいほど綺麗だなって思えるこんな——奇跡みたいな気持ちを、大切にしていきたい。
いまでもまだ藤真さんは謎めいているし過去はあまり語らないしこんな一面もあったんだと驚かされもする。だけど、距離はもうない。ようやく恋人同士になった実感が後から追いかけてきた。これは夢じゃないと、はっきりとわかる。
躓きながらも、選んできた道。どれか一つでも違ったならあなたに会う事はなかった。そう思えば悪くないかもしれないって思える。見つけた物を繋ぎ合わせて紡いでいく幸せも、手を取り合い笑い合い過ごす日々の喜びも、ずっとそばで感じていたい。
ゆっくりでいい。焦らなくていい。私達は私達のペースでゆっくり愛を育んでいけばいいんだ。
藤真さんの触れる指先が、眼差しが——唇から漏れた呼気が、体温が……愛情をゆたかに与えてくれて痛いほどに今は、幸せだから。
あのとき、本当 は……。
(というか、俺たち会ったことあるよな)
(えっ、いつ?電車の中とかですか?)
(——いや、やっぱり俺の勘違いだと思う)
(……?そう?)
※『 Love Song/Uru 』を題材に
Back / Top