今から45億年前、火星と同じ規模の天体が地球に衝突。そのとき飛び散った欠片が地球の重力に引っ張られて形成されたのが〝月〟だ。
つまり月は、永遠に孤立した地球のかけら。その通り月は永遠に切り離された地球の一部。月は、地球とふただびひとつになりたくて常に引き寄せられていると言う。
満月は繁殖力を上げ
—
——頭が痛い。二日酔いだ。
何度も経験したことのある痛みに額を抑えながら体を起こす。朝だとは思うがあの二日酔いの朝特有の頭痛とともに瞼の裏に感じる不快感がない。もしかしてまだ夜明け前かと思えばもったいなく感じる。
二度寝しようにも気怠い体は水分を欲していて、飲んだ日の夜にはいつも枕元に置いているはずのペットボトルを探るも一向に手に触れない。昨日に限っては用意せずにそのまま寝てしまったのかなと目を閉じたままため息をついてベッドに腕を戻す。
そのときに触れた感触にはじめて違和感を覚えた——なんだか隣があたたかい気がする。しかも、自分の家のベッドじゃ、ないような……?
そこでようやく目を開ける。薄暗い室内は完全遮光のカーテンのせいで外の光が入らないが、まったく見覚えのない部屋に置かれた大きなベッドとそこで寝ていた自分と見慣れない男の姿に一気に血の気が引く。今度は二日酔いじゃない頭痛に、顔がどんどん青くなる。
「……」
……もしかして、もしかする……?わたし見知らぬ人と、夜を越しちゃった感じ——!?
頭がはっきりしてくると同時に体の感覚もはっきりしてきた。あらぬところが痛むのは、そういうことなのか。ふと壁にかけられた、これまた見慣れないシンプルな掛け時計はしっかり朝の七時を回っている。ハッとして、反射的にベッドの下に置いてあるゴミ箱を恐る恐る覗いてみる、が……ない。
「……ねぇな」
背後から声が聞こえて私はぎょっと振り返った。こちらも寝起きらしい男が私の背後からゴミ箱を覗き、こめかみを指で押さえて頭をブルブルと振ったあと溜め息をつく。そして一度舌を打ち鳴らした。あからさまにチッって。え、感じ悪……
「——っ!!?」
「……ハァ。」
「あ、あの………………どなた、ですか」
「あ?……覚えて、ねえのか?やっぱりな。」
「——っ申し訳!ございませんンっっー!!!」
咄嗟に土下座をかました私にその男が驚いたように目を丸くする。
「——痛っ、たぁ……!」
勢いよく土下座したお陰で下半身に激痛が走る。股を両手で押さえながら悶絶する私の頭上で男が落ち着いた声で「だろーな」と言った。
「あんま動かねーほうがいいぜ。つか、そもそも謝るのは俺の方だろうが」
「……」
「俺も昨日は久々に酔ってたんだよ」
彼はもう一度、ハアと浅く溜め息をついた。私はゆっくりと顔をあげて彼のことを盗み見る。
「普段なら、こんなことはしねぇんだけどな……加減も出来てなかったしゴムすらつけてなかったみてえだわ」
や、やっぱり——!!!?
「とりあえず——今からでも処理したほうがいいよな、一人で出来るか?」
「そ、そうですよねっ!やる、やりますから!」
見知らぬ男にそんなことまでされてはたまらないと両手を突き出しぶんぶんと振る。そして慌ててバスルームに駆け込もうとしたが腰が痛くてその場に蹲る。刹那、蹲る私の身体が宙に浮いた。
「うぇ!?」
「安心しろい……運ぶだけだ」
まさかの人生初の俗に言うお姫様抱っこをされ咄嗟に目の前の首筋に縋り着いてしまった。きっと条件反射というやつだ、お姫様抱っこ=首に縋り付くという。そしてそれは、想像していたよりも安定感があって思わず目の前の胸板をまじまじと見つめてしまう。
「……筋肉、すっごい」
「あのなあ……お前はもう少し危機感を持った方がいいぜ」
「あっ。すみません……」
「……いや、別にいーけど。今更だしな」
バスルームに下ろしただけで何もせずに踵を返した彼にきょとんとしたあと、実はこの人いいひとかも知れない、なんて思った。
「——っ、いやいやいや!」
頭をブルブルと振って、そんなことよりも出されたものをなんとかしなければと私は躊躇いながらもそこに指を伸ばした。……情けない、ほんと私なにしてんだろ。
色々な意味で疲れ果てて部屋に戻れば、彼がまだ居てまたもぎょっとした。普通こういう場合っていなくなってるもんじゃないの!?と、軽く混乱状態の私に彼は息を吐いてスーツに着替え、私に真新しいタオルを被せてくる。
「わっ、」
「髪がまだ濡れてるぜ。風邪ひいたらどうすんだ拭けよ」
「ご、ごめんなさい……。てか……あの、」
「——悪ィ、俺もほとんど記憶がねえ」
「あ……ああ。そっ、そうですか……」
「……言いづれぇだろうけど、昨日は、その……周期的には、」
無遠慮にも気まずそうに、そうストレートに質問されて一瞬ぽかんと口を開けてしまう。
「……! だ、大丈夫なはず、です!たぶん!」
「……そか。じゃあ、これ」
「……」
男はそう言って、たぶん自分の連絡先を書いた紙を渡してきて私は驚いた。受け取らずにいる私を一瞥した彼はまたもう一度溜め息をついて言う。
「もしなんか問題があったら連絡してくれ」
「……」
「まあ……問題がなかった場合でも、してくれると助かる」
「——結構です」
私のはっきりとした口調に彼は「は?」と目を見開く。このままヤリ逃げすればいいのに……お互いに記憶はないし、昨日は満月の夜で、自分でも随分と飲みすぎたこと自体は自覚している。
——浮気をされた。一年半真剣にお付き合いして勝手に結婚まで考えていた相手と私の友人が浮気していたのが発覚して飲み過ぎた。まるで海外ドラマみたいな展開に涙は出なかったけど、すぐに笑顔で受け流せるほど大人にはなれなかった。
二人を目の前にして散々汚い言葉を吐き散らかし来たことのない飲み屋街までふらふらと来て、ひとりで酒を呷っていたのだ。そして気付けば見知らぬ人とこうしてラブホテルにいる。その相手はヤリ逃げもせず、蹲る私をお姫様抱っこしてバスルームまで運び最後には連絡先まで渡してきた。
類は友を呼ぶと言う。きっと、目の前の彼も私と同様にロクでもない人種なのだろう、そう思って昨晩起こったハプニングをさっさと忘れ去って無かったことにしてしまいたいのに、そんなふうに大人の対応をされると、逆に惨めで虚しくなってくる。
〝もしなんか問題があったら連絡してくれ〟
問題とは子供が出来てしまっては——という意味だと瞬時にわかった。ここでようやく涙が溢れてきた、今更になって。信頼していた二人に裏切られたこと、一気に二人との交友関係が破断したこと、ずっと浮気を見抜けなかった自分、酒に溺れて見知らぬ男性と寝てしまった情けなくて惨めで憐れな自分に——自然と涙が頬をつたう。
「いや……結構ですって、そういうわけには」
「気を遣わないでください。大丈夫です、かりになにかあっても迷惑はかけませんから」
彼の動揺している声。その相手の言葉を遮って、私がそう冷たく言い放てば目の前の男がムッとした気配がした、が、私は決して目を合わせない。
「意地張んなよ、なんかあったら困るだろうが」
「困るのは私じゃなくてあなたのほうですよね」
「あ?……そうじゃねーって、俺は——」
「ホテル代、私が払いますよ。ちょっと待っててください」
くるりと踵を返してソファに投げ捨ててあった自分の鞄の中から財布を取り出している私の背中に「もう、払った」と弱々しく呟いた彼の声が突き刺さる。なぜか背筋がさっと冷えた。
「そうやって自暴自棄になって、女ひとりで酒に溺れてっからこんなことになるんじゃねーのか」
「……」
「いい歳してよ——記憶のねえ俺に言われたって説得力の欠片もねぇだろうが、面倒な集団に襲われてたらマジでおまえ、どーしてたんだよ」
「……」
「ちったァ、自分の身を——」
「記憶無くして女の人とホテルに入ったあなたに言われたくないですしねっ!」
振り返って声を張った私は彼をキッと睨む。けど彼は、そんな私に慈悲の視線を送ってくるのだ。その目——やめてほしい、ますます惨めになる。
「ほんとにお前……危なかったんだぜ。それだけは俺だって、しっかり覚えてんだよ」
「……」
「——連絡先、ここに置いてくからよ……なんかあったら、連絡くれ」
「……」
「じゃあ、気ィつけて帰れよ」
「マジで……昨日は悪かったな」と、そう言い置いて彼は私の真横を通り過ぎ部屋を出て行った。バタン——と重い鉄の扉が閉まった音を背後で聞いて私は深く溜め息を吐き、彼がベッドサイドに置いて行った連絡先の書かれた紙を手に取る。
意外と字は綺麗で驚いた……とは言っても書かれた数字だけで判断したから本当のとこはよくわからないけど。だって、名前も何も書いてないし、見た通り番号のみ。彼の性格がそのまま滲み出ているかのようだ。無遠慮でストレートで……女心なんかまったく知らないって感じの。
意地張るな。自暴自棄になって、いい歳して——なんて見ず知らずの、しかも、互いに記憶をフッ飛ばして寝てしまった相手に言われてイラっとしたけど最後には〝マジで……昨日は悪かったな〟なんて吐き捨てていきやがった。……クソっ。
「だから——謝られると余計惨めになるってば」
私はそのメモ用紙をくしゃくしゃに丸めてベッド脇のゴミ箱に捨て、ホテルを後にした。
—
予告なしに彼氏——いや
私はすっかりいつもの調子で元気に週明けの月曜日、勤め先である職場に出勤していた。
「名字さん、おはよーございまーす!」
「ああ、おはよ」
「なんすかー?何かいい事でもあったんスか?」
「え、なんで?」
「なんか顔がスッキリしてるっていうか憑き物が取れたみたいっていうか」
「あー......まぁ、そうかもねっ」
部下の男の子とそんな会話を交わしてから、いつも通り自分の仕事に取り掛かる。こうして何事もなく時間は過ぎていくのだ。いままでだってそうだった。だからきっと今回も大丈夫。
たくさん飲んだ、記憶をなくすくらいに。そしてたくさん泣いた。だから、もう大丈夫。もう自分ひとりの力で歩いて行くしかない。
わたし、決めた。
一生彼氏もいらないし、結婚もしません!
昼休み、デスクに座って、コンビニで買って来たサンドイッチを食べていると、今朝も会話をした部下が隣の席にやってきて声を掛けてきた。
「名字さん、バスケ興味あります?」
「……バスケって、バスケットボール?」
「そうっす、今度一緒に観に行きませんか?」
そう言って私の目の前にバスケットボールの雑誌を広げてみせる彼。「俺このチームのブースターなんすけどー」と言い指差したページに映っていたバスケットボール選手を見て私は目を見開く。すぐにサンドイッチをデスクに置いて雑誌を両手で持った。そのページを、射抜く勢いで見ている私に部下の彼が呆れ口調で言う。
「あー、やっぱり名字さんも三井選手かぁ」
「……」
「男前スよね、一番人気っすよ」
「——三井、って言うの?このひと」
「はい。まだシーズンオフなんすけど。シーズン始まったら一緒に行かないかなーって」
そのとき、彼の同僚が呼びに来て「あ!それあとで俺の机にあげといてください!」と言い残し、彼はその場を去って行った。言葉を失うとはまさにこのこと。あのひと——バスケットボール選手だったのか。バスケなんてあまり興味がなかったから完全ノーマークだった……。
〝もしなんか問題があったら連絡してくれ。まあ問題がなかった場合でも、してくれると助かる〟という彼の言葉を改めて反芻する。そりゃそうだ何かあっては困るのは、間違いなく彼のほうだ。
「困るのは私じゃなくてあなたのほうですよね」と勢いで言ってしまった自分の言葉を思い返し、がっくしと肩を落とす。今頃SNSに書き込みされないかとか、週刊誌にネタを提供されないかとかビクビク怯えているかもしれない。
きっと向こうもあの日なにかあったに違いない。それはお互い様だ。私と一緒でめちゃくちゃな厄日だったとしても、二人とも記憶がないとはいえ律儀にも連絡先を渡してくれた彼を私は突っぱねた。迷わず捨てちゃったし、あの連絡先を書いてくれたメモ用紙。しかもラブホテルのゴミ箱なんかに。
ああ……どうしよう。今後、問題がなかったにしろ、あったにしろ、そんな有名人ならちゃんと連絡をする方がいいに決まっている。え……まじでどうしよう。これだから自分を好きになれない。
—
その週の土曜日。仕事が休みの今日わたしは気晴らしに買い物でもしようと外に出た。ぶらぶらと適当にウィンドウショッピングをしたが気晴らしになるどころか、彼のことばかりが頭を過ぎってショッピングどころではなかった。
そう言えば一週間前の今日だっけ……目覚めたらラブホテルにいたのって。
ただ、謝りたかった——記憶を無くすだけ飲んで潰れたことも、ヤケになって強い口調で彼のご厚意を突っぱねたことも。そして改めて「何かあっても迷惑はかけません」と伝えたかった。あなたの選手生命に関わることは絶対にしませんって。
実は彼がプロのバスケットボール選手だと知ったあと彼のことを調べてみようかとも思ったが調べたとて、彼にした失礼な行いが晴らされることはない。知ったら知った分だけ罪悪感が募りそうで結局、彼のリサーチはしなかった。……二年後、バスケットボールのW杯があるらしい。それに彼も選ばれるだろうなんて部下の男の子から聞かされたのは、一昨日の木曜日の帰り際。
マジで……どうしようかなぁ。
そんなことを考えながら歩いていると、ドン!と誰かとぶつかった。「すみません…」と言ったが私に体当たりしてきた女性はそのままフラフラと先を歩いていく。しかし、そのままそばにあったガードレールに寄り掛かってしまった。見れば、お腹が高い——妊婦だ、と思った。顔も青いし、薄っすら額に汗もかいている。思わず駆け寄って私は彼女の肩に手を置いた。
「だ、だいじょうぶですかっ?!」
「……、はい……」
「具合が悪そうですけど……どこか座る場所、」
「——子宮がっ……収縮してる……と、思うっ」
「えっ!!? い、いま何週目ですかっ!?」
「さっ……38週目……っ」
「待って!い、いますぐ救急車呼びますから!」
妊婦を支えながら「誰か!救急車呼んでください!」と声を張ったが道行く人はジロジロとこちらを見るだけでその場を歩き去って行く。これだから都会は——!と、慌てふためきながら私が鞄から携帯電話を取り出そうとしたとき背後からこちらに軽やかに駆け寄ってくる足音が聞こえた。
「——大丈夫ですか?」
高い位置からの声に顔を上げれば、そこには一週間前にラブホテルで一夜を共にした、プロバスケットボール選手がいた。向こうも私を見て一瞬、目を見開いたが互いに今置かれている状況を把握して自分たちのことは後回しにし、私は現状報告をする。
「あ、あの……妊婦さんで38週目で、えっと」
「と、とりあえずわかった。で、救急車は?」
「あっ、それが……いま呼ぼうと」
「ダメっ——破水したっ!」
「「えっ!!?」」
妊婦の言葉に私と彼は声を揃えて驚愕する。わたわたと私たちが慌てる中、咄嗟に私が彼に問う。
「——あのっ! あなた出産の経験はっ!?」
「は?バカ!あるわけねーだろっ!お前は!?」
「んなっ!!あっ、あるわけないでしょーが!」
「あ、産まれるっ——四人目だから分かるのっ」
「「はぁ!?」」
「え、え……どうしたらいいんだろ……」
「あっ!じゃ、じゃあお前、救急車とタオル!」
またも二人で驚いたあと彼がそう言って私と代わって妊婦さんを支える。そしてそう指示を出すので私も焦りながら聞き返す。
「え!? タ、タオルって!?」
「あー、ほらっ!あそこに、ニトリあんだろ!」
「あ、はいっ! ニトリね、わかった!!」
急いで目の前のニトリに駆け込み事情を説明すると快く新しいタオルを手渡された。お店のスタッフに他に手伝うことはないかと問われ、救急車を呼んで欲しいと伝えた。もらったタオルを抱えて外に出ると彼のほかにもう一人、男性がいて妊婦さんに話しかけている。通行人かな?意外といい人もいるもんだな。都会も捨てたもんじゃない。
「子宮収縮の感覚は一分間隔ですね」
「それって、前駆陣痛じゃないですよねっ!?」
「はい、本番です。産まれますね」
通行人らしき男性と妊婦の会話を側で聞いていると彼が「医者らしい」と男性を親指で指差しながら言って私からタオルを奪い取った。それをその男性に差し出したとき、妊婦が苦しそうに言う。
「救急車——まだ、ですかっ!?」
「いま到着するでしょうが、ここまで間隔が短いと、いま下手に移動しては危険です」
「あのっ、でも……っ」
「お母さん安心してください。心配いりません」
「……えっ?」
「私は何度も子供を取り上げたことがある医師です」
「——は、はいっ」
「あなたたちも、指示を送りますので手伝って」
淡々と医師と名乗る男性に言われて私たちはまたもや同時に「はいっ!」と返事をし救急車が到着するまでのあいだ、医師の指示に従って人生はじめての出産を手伝うことになった。
—
無事に妊婦と医師の男性が救急車に乗るのを見届けて、ようやく二人で大きく溜め息をつく。彼は自分の私物らしきバスケットボールの入った袋を地面から拾いあげ、私と向かい合う体制を取ると躊躇いながらも右手を差し出してきた。
「……三井だ。」
私はその行動に思わず目を見開いて一瞬だけ困惑したが、すぐに彼が自分の名を名乗り私に握手を求めているのだと悟った。そう思ったらなんだかおかしくなってきてクスッと小さく笑う。そんな私に対し怪訝な顔をして「あ?」と言う彼。
「なんだか……海外ドラマのはじめましての挨拶みたいですね。右手を差し出して名乗る感じが」
「まぁ……海外ドラマみたいな展開だったわな、まさにさっきのシーンは」
「たしかに。まさか見ず知らずの人の出産に立ち会うなんて、ほんとドラマみたい」
「ああ」
そう相づちを打って優し気に目元を細めた彼に、私も左手を差し出し彼の差し出されている手を握る。さすが手を商売道具にしているだけあって、男らしくゴツゴツしているわりにはスベスベで、繊細そうな手の感触だった。
「——名字です。名字、名前。」
ガシッと握手を交わしたあと彼は軽く頷きその手を離し、バスケットボールの入った袋をもう一度肩に掛け直すと思いついたように言う。
「あのよ。もし時間あんなら茶でも行かね?あんなの見た後じゃ何も口にしたくねーかもだけど」
「いえ、喜んで。お話したいこともありますし」
「よし。でも、その前に服——買いに行こうぜ」
言われて自分と三井さんの服を見れば、二人して先ほど起きた死闘のお陰で上着が派手に汚れてしまっていた。
「二人してこんな格好じゃ殺人でも犯してきたと思われちまうだろうしな」
「ははは、言えてる」
「それこそ海外ドラマのワンシーンになっちまうぜ」
思わず緩く笑い合いとりあえず近くにあったユニクロに二人で入り、間に合わせで服を買って着替えた。お代はしれっと三井さんが払ってくれた。レジで「払う」「遠慮する」と言い合いするわけにもいかず、ここは素直に彼のご厚意に甘えることにした。
近くのカフェに入って、互いに温かいコーヒーを注文する。当たり前に訪れる沈黙に言葉を選んでいると、先に会話を振ってくれたのは彼のほうだった。
「その——連絡……なかったからよ」
「はい……実は頂いたメモ、捨てちゃって」
「はぁ!? 捨てたァ?!」
「……ごめんなさい」
三井さんは呆れたように小さく溜め息をつくと、静かに目の前のコーヒーカップを手に取りそれをひとくち啜った。
「悪かったな、いい歳してなんて言って」
「え? ああ、いえ。いい歳ですし」
「でも、同い年くれーだろ?まぁ……だとしてもいい歳か」
ジロと彼を睨むと彼はまた、あっ……と言い淀んで私からあからさまに目を逸らす。相変わらず無遠慮だけど、嫌味がないから全く気に障らないんだけどね。
「無神経だって……よく言われんだよ」
「へえ、」
「悪気はねーんだ、いやマジで」
後頭部に手を当て面食らう三井さん。またも訪れた沈黙の中、そりゃあ言われるだろうねえ、あなたの性格だったらきっと。なんて思いながらも、今度は私から言葉を繋げる。
「あの日は、ほら——満月だったので」
「……ん? 満月?」
三井さんはコーヒーカップを置き怪訝な顔をしてそう聞き返す。
「大荒れになるって言うじゃないですか。交通事故も多くなって変なことが起きるって昔から言われてません?」
「あー。俺は満月の夜のくだらねぇ都市伝説は、信じてねーからな」
「信じてないの?あれは科学ですよ、満月の夜は異常事態が起きて犯罪も救急患者も増えるって」
「ドラマの見過ぎだっつの。俺の経験からいけば満月の夜におかしい奴らは半月のときも三日月のときもおかしいだろ」
「えー、そうですか?」
「おう、新月のときでもな。それを裏付ける統計データだってねぇっていうじゃねーか」
「だってあの日クレーンゲームの中から子供を救出したってニュースが流れてたじゃないですか」
「ほぅ……それはしっかりと覚えてんのか」
「——!!」
そう——あの日……満月の金曜日の夜。居酒屋のテレビから流れていた速報でそんなニュースが流れていたのは覚えているのだ。そのとき隣に三井さんがいたかまでは覚えていないけれど。
「とにかくっ!……実際に
「ふはっ。その狼って、もしかしていま目の前にいる男のこと言ってんのか?」
「さぁ、それはどうでしょうかね」
そんなふうに冗談を言い合っていてふと思った。わたし案外落ち着いて一夜を共にした見ず知らずの人とコーヒーを飲んでるなって。まあ、もう名前も名乗りあったし、一緒に道端で生命の誕生を見届けたし、見ず知らずではないだろうけど。
「あのとき帰り際に泣いてたからよ……後悔してんだろうなって思って、ずっと気になってた」
「ああ、あれは——あなたとのことを悲しんでたんじゃなくて……その、自分自身が情けなくて」
「……」
「あなたの職業はあとで知りました。なので迷惑は絶対におかけしません。安心してください」
「だからっ——そういうことじゃなくて」
「ほんと、大丈夫ですので」
「……」
またも流れる沈黙。あんなに何度も後悔して謝りたいと思っていたわりには、あの日の朝と、同じような台詞を吐いてしまう自分に溜め息をつく。気を取り直して、「連絡先、教えてください」と言おうと口を開けかけたとき彼がすっと目の前に自分の携帯電話を滑らせた。
「——俺の連絡先だ。そっちのも教えてくれると助かる」
「はい。もちろん。何かあったら連絡しますね」
「……」
「——なにか、なくても連絡します」
ニコッと微笑んで言えば彼がようやくほっとして口元を緩めた。「サンキュ」とつぶやいて。
三井さんと生命の誕生を見届けてから約二週間が経った。連絡先を交換したとは言え、もう彼とプライベートで会うことはないだろう。とは言ってもこのあいだは本当に偶然、街中で出くわしただけだからアレをプライベートとは言えないけど。
——ブー、ブー......
メッセージを受信したと知らせるマナーモードのバイブにハッとして携帯画面をつける。
もしも
また会う約束をするのなら、それは——
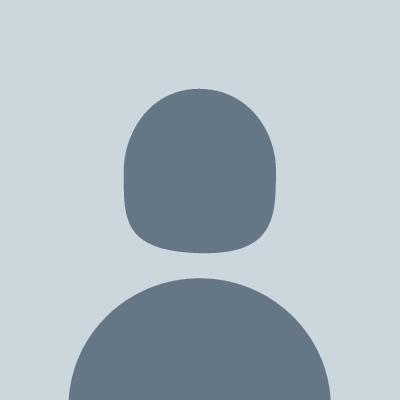
三井 寿
こないだ道端で見かけたカルガモの親子
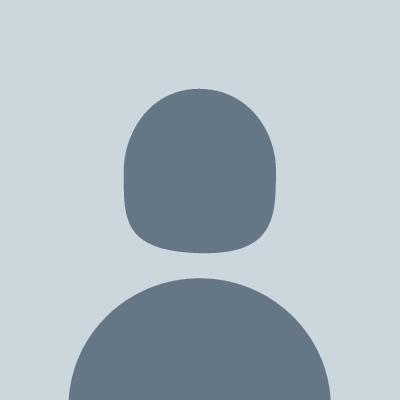
三井 寿
【画像】
〝問題〟が起こった場合のみ。
その、はずだったのに——。
—
あいかわらず彼はあれから、毎日かかさず連絡をくれる。電話はかけてこないけれど、メッセージを送って来るのだ。話題は決まって〝あの日〟の二人に起きた出来事とは無関係の内容。一般的な挨拶……おはよう、おやすみの他、今日なにがあったとか明日は晴れらしいとか、こんなもの見つけたとか……そんなことばかり。
気付けばいつしか彼から届く連絡が私にとっての精神安定剤みたいなものになっていた。好きとか嫌いとか、そういうのは全く関係ないこの彼との関係性が今の私にはとても居心地がよかったのだと思う。
毎日の〝おはよう〟に〝おやすみ〟。恋人と勘違いしそうになる。けど今は全部考えない。だって離れ離れになる日は、そう遠くないかもしれないから。
——プルルルル……ガチャ、
『……あー、もしもし?』
「あっ三井さん?こんばんは。今いいですか?」
『おう……てか、そっちから電話くるなんて思ってなかったから驚いたぜ。どーしたよ』
「あの……単刀直入に、言いますね。無事に月のモノが来たので報告しようと思って」
『……へえ、そうか』
「ご迷惑を……お掛けしました」
『……いや。でも……よかったな。』
「……はい。」
きっとこれで終わり——。
そう、思っていたのに……
三井さんは次の日もまたその次の日も何ら変わらず連絡をくれた。無視するいわれもないので当たり障りのない程度に返信していたけど三井さんと一夜を共にしてから約一ヵ月ほど経った頃、つい聞いてしまった。確信に迫る一手を。

名前
彼女さんがいたりするなら悪いので、連絡とか気を遣わなくていいですよ
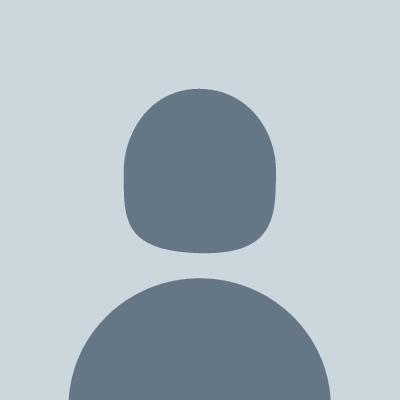
三井 寿
出来る予定もない。連絡取るのやめたいのか?
——なんというズルい返信。決断は人任せタイプか……遊んでいる男の常套文句だ。
このままいけば、確実に彼を本気で好きになってしまうだろうということは明確だった。なのに私は……気付かないフリをした。
あの日の……恋人と友人が同じベッドで寝ているところを目撃してそのまま酔いつぶれた満月の夜の私に問いたい。〝欲情〟の相手が、誰だってよかったわけじゃないんでしょ?って。当然だよ。
でもさ、あの日わかったはずでしょ?
恋愛なんてなくても生きていけるものなはずなのに……って。
あれからひとりで飲みに出歩くことをやめた私は手にカフェラテを持って帰路につく。仕事が休みの今日、美容院に行って気分転換でネイルサロンにも行って来た。気付けば時刻は夜の七時過ぎ。夜空を見上げれば大きな月。そう——今日はあの日と同じ、満月だった。
——ブー、ブー、ブーッ
携帯のマナーモードに気づき立ち止まった私は鞄から携帯電話を取り出す。映し出された画面には『三井さん』の文字。ひとつ大きく溜め息をついたあと、観念して私はその着信を取った。
「——はい、」
『あ、もしもし?いま、大丈夫か』
「うん、大丈夫です」
『悪ィな、急に電話なんかしちまってよ……』
「いいえ、今ちょうど私も帰宅途中だったから」
『……なにしてんだ?また一人で飲んだくれてたんじゃねーだろうな?』
「まさか、美容院に行ってきました。あとネイルも。自分のメンテナンスってとこ、かな」
『へえ……そりゃいいな』
彼も出掛けるところだったのか、電話の向こうからは外を歩いている音や、鍵か何かをポケットに入れたらしいカチャカチャとした物音が聞こえて来る。
「三井さん——もう、大丈夫ですよ」
『あ?』
「連絡取り合うの……もう、やめましょ?」
『……』
「あなたとこうして連絡取ってると楽しい。でもこういうのをこれからも続けてたら……絶対に、いつか間違いが起きちゃうと思う」
『……』
近くにあったベンチに座って一呼吸置く。そして出来る限り丁寧な言葉選びをして今、素直に思っていることを三井さんに伝える。
「本当に今日までありがとう。こうして気遣ってくれたことだけじゃなくて、あの日のことも」
『あ? あの日……?』
「たぶん、私のこと助けてくれたんですよね?」
『……』
「変な人たちに絡まれたことまではなんとなく覚えてて、でもその中に……三井さんはいなかったって、記憶してるから」
『……』
「あのとき、朝目覚めたとき隣にいた人が、三井さんでよかった」
『まぁ、役に立てたなら……よかった』
「うん。——いま、どんな気持ちでも行きずりの人なんかとエッチしないでね?」
『ふはは。バーカ、しねーよ』
「えーほんとかなぁ」って冗談めいて言えば電話の向こうで三井さんが柔らかく笑った。
「ただひとつ。キスはしたのかなって思ってて」
『あン?……キス?』
「そう、キス。エッチより大切なんです、私の中でキスって」
『……さぁ。どうだろうな、二人とも覚えてねーわけだし、してねぇってことにしとけばいいんじゃねーの?』
「そっか、じゃあそうする」
『次は、本気で想ってる奴みつけてしたらいい、その——セックスより大切な、キス?ってやつ』
「ハハ……そうだね」
沈黙が流れる。これ以上話してると別れが辛くなりそうだ。私は「——じゃあ」と小さくつぶやいた。向こうもややあって「おぅ」と返したことで私から電話を切った。
もしも……彼と普通に出会っていたら。もしも彼がバスケットボール選手じゃなかったら。もしもあのとき——そこまで考えて私は頭をブルブルと振りベンチから腰をあげる。
——ダメだ。外では飲まないと決めたが缶ビールでも買って、アパートでひとり酔いつぶれよう。そう思い立って、私はコンビニでいくつかお酒を買ってから自分のアパートへと戻った。
なんとなく今は無音が嫌で、とりあえずで付けていたテレビから流れるバライティー番組をBGMにして缶ビール片手に考え込む。こういったときに限ってお酒が進まないのはなぜだろう。酔いつぶれて忘れてしまいたかったのに、本能が忘れたくないと訴えているからだろうか。
——涙は出ない。胸は苦しいけど。
ふと私は携帯電話を手に取り『三井さん』と映し出された電話帳を眺める。メニューを呼び出して〝削除〟の文字をタッチしようとしたとき、ピンポーン!とインターホンが鳴り響く。時刻は夜の11時半。徐に立ち上がって、モニターを見れば相手は、いまでは随分と見知った顔だった。
鍵を外してガチャ、と玄関のドアを開ける。果たしてそこには、三井さんが立っていた。
「三井さん……どうしたの?なんで、家わかったんですか?」
「さっき偶然コンビニでお前のこと見掛けてよ。あ、ストーカーとかじゃねえからな?実は俺あそこのマンションに住んでて」
あそこと言って親指を指す。私もチラと指の先を見て「ああ、」と返した。
「別にあとを追うつもりなんてなかったんだけどよ……お前との電話切ってからマンションに帰る途中、手前の信号が赤になったんだよな」
「……」
「んで、空を見上げたら満月だった」
「……」
玄関先で話し込んでるのも近所迷惑だと思い入ってと言うように手招きすれば彼は「んでもって」と先の話を進めながら、すんなりと中に入った。私は静かに玄関の扉を閉めて鍵を掛ける。
「気付いたらコンビニに戻ってワイン買ってた。お前と二人で、飲みてぇなって」
「……」
「その足で、ここに来た」
「へえ、もしかして満月が魔法でもかけた?」
「ああ。月の力……重力ってやつだな——人を、惹き付ける力」
三井さんは狭い玄関内で私を壁に追い込むようにそっと距離を縮めてくる。咄嗟に私は焦る気持ちを隠すため会話を続ける。
「んー、それはどうかな、知ってるでしょ?月の満ち欠けは太陽との位置が要因で、月の大きさが変わってるわけじゃなくて——」
「おいおい、また難しい話かよ。でもそれ、真実じゃねーんだろ?」
「いやっ、あきらかに真実」
「……ホントか?」
「うん、ほんと。」
「じゃあ結論は——これが月の影響じゃねぇなら何なんだよ、やっぱ魔法か?」
「魔法でもない、ただの偶然。一緒に夜を明かしたのも生命の誕生を一緒に見届けたのも……私を行きつけのコンビニで見掛けたのもね」
「でもよ……偶然も、三回目なら〝運命〟だって言うだろ?」
三井さんは目元をすこしだけ細め、口の端を吊り上げてそう言った。
「ううん、魔法とか運命とか全然関係なくて——三井さんが私に、会いたかっただけだよ。」
私のその言葉に三井さんが勝気に笑って私の唇にそっとキスをした。唇が離れて額と額をくっ付け合うと彼が至近距離で、ぽつりとつぶやく。
「——大事なんだろ?セックスよりも」
「……え?」
「俺とキスしたっつーことは……俺を受け入れてくれたって解釈して、いいんだよな?」
「ズルい……したあとに、言う?それ」
三井さんはフッと笑って、ワインを持っていない空いた手を私の腰に回す。私も素直にそれを受け入れて彼の首に腕を回すと自然と引き合うように唇を重ね合わせた。
——いま、気付いたけど……
たしかに今日は満月で、こういうのを……なんて言うんだっけ。
ああ——ルナティック?狂気、か。
残念ながら、前回の満月の夜のことは全く記憶にないけれど、キスだけでこんなに気持ちいいのにセックスしたら、どうなっちゃうんだろう?
——でも、
惹かれ合う者たちは二人を引き裂く重力の法則に逆らっている。それがもたらす結果など今はどうでもいい。
人は、重力の法則とは無関係に惹かれ合うから。
大事なのは、触れ合うこと。
心と心を裸にして温もりを感じること——。
引き寄せ合う さびしさ の引力。
(問題解決したから見捨てられると思ったのに)
(バーカ、見捨てたりなんかしねーつの)
(それってさ、一種の責任感的なやつ?)
(いや——もしも投げ出すんなら)
(うん?)
(あの連絡が来た時点でそうしてたわ)
(えっ……)
Back / Top