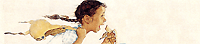「三門中の椿姫ってのはお前か?」
野太い声に呼ばれて振り返ってみれば、数人の見知らぬ男女。女の方は知っている。同じ学校だった筈だ。ただ知り合いと言うわけではない。数人の女のうち、リーダー格と思われる子がこれまたガタイのいい男の腕に巻き付いて笑っている。明らかに中学生ではないように思うが当たっているだろうか。
「こいつだよ〜何やっても無反応なんだよね〜」
つまんなーい、と可愛らしく間延びする女の顔がニタニタと不気味なこと。別に初めて見る光景ではなかった。囲まれることに恐怖は感じない。無反応なのはなんとも思えないから。付いてきてもらうぜ、なんてお決まりの台詞を吐き周囲を塞がれる。私もそれに大人しく付いていく。そう、付いていくんだ。そうした方が後々面倒にはならないから。
そして、こいつらの『色』が不気味に揺れる紫から、冷め冷めとした薄い青になれば、それは勝敗が決まる時。最低な奴等だ。自分達が勝てると思える相手にしか手を出せない。殴る、蹴る。簡単に、他人を気付けられる非道な奴等。でもそれは、私だって同じ事で。私は私を守る為に身に付けたのは、こいつらと何ら変わらない。暴力だった。
─────それから数十分後。
女達の居なくなった男達だけの無惨な姿が転がる路地裏で、一人佇む少女の携帯が着信音を響かせた。
☆ ☆ ☆
「条件?」
姐さん争奪合戦(ジジ抜き)が終幕したすぐ後の事。姐さんが几帳面にトランプを箱に直すのを見つめながら、自分の携帯でチャットアプリを立ち上げる。最後の二宮くんのメッセージから一時間は経っていた。大分楽しんでいたようで、そんなに時間が経っていたことに驚くも自然と笑みが溢れる。カードゲームなんて久々にやったけれど、何気に楽しかったようで時間なんて忘れていたようだ。『終わったから食堂に行ってるわね』そう打っている途中で友人、紅香のすっとんきょな声が飛び込んできた。
手元の携帯から話の中心である二人へと視線を持ち上げれば、真正面に座っていた二宮くんと被ってしまった。ピシリ。微かな空気の軋む音は恐らく自分達にしか把握できない現象だろう。現に姐さんと紅香には聞こえていないようだった。二人して静かに固まり、仏頂面な彼と笑いながら無言の攻防をしつつ、耳は二人の会話を拾っている。
「んー条件って言うかお願いなんだけどね」
「なんですか?」
困り顔でその癖っ毛に彩られる花簪の片方を弄くりながら、ちょっとね、と姐さんにしては歯切れの悪い。そして意を決したのか、うーんとさ迷っていた視線が紅香を捉える。
「会って欲しい子がいるのよ。出来ればその子も隊に入れて欲しい」
渋っている割には何て事ない話だった。問題は紅香がそれを受けるかどうかだけれど。チラリと紅香の方を見れば紅香も紅香で首を傾げていた。それは「なんだそんなことか」なのか「条件に合う子なの?」なのかは判断に困るが嫌という訳ではなさそうだった。
「どうするの?」
「うーん、その子って」
紅香が唸りながら姐さんに詰め寄れば、それを見越したかのように姐さんが先に口を開く。待ったと手で制止しながら「あ、その子も名前に花の名前が入っているから条件としては申し分ないと思うけど」とまるで紅香の質問を読んでいたかのようにさらりと答える。それだけ友人が分かりやすいと言うことだろう。
「会いましょう」
ええ、分かりやすいと言うより単純よね。知っていたけれど。
そうして数十分後、姐さんの召集でやって来たのは無表情の女の子だった。
☆ ☆ ☆
ずいっとお師匠につき出され、つんのめりになりながら前に押し出された。寸でのとこで爪先に力が入ったので転びはしなかったものの、目の前の赤い人がじっと此方を見つめていて居心地が悪い。赤い人だけじゃない。見るからに高校生だと思う茶髪の男の先輩に色素の薄いベージュの髪の女の先輩も物珍しそうに見てくる。一体これはなんの観覧ショーなんだ。
上から下へゆっくりと視線が動く。もうそれこそ頭の天辺から爪先の先まで見られているようだ。はっきり言って質の悪い不良を相手にしていた方が幾分もましだ。叩きのめせば終われるのだから。でもこれはそうも出来ない。目の前の三人は多分、先輩だ。歳とかじゃない。歳は見ればそれこそ分かることだから。歳じゃなくて、学校でもなくて、ボーダーの、先輩だ。
だってこの人達って確か─────、
「ふーーーん、この子が姐さんの弟子ですか」
「どうかしら?ちょっと問題のある子だけど紅香なら懐くと思うのよ」
「さらっとマイナスポイント提示してきましたね」
「隠しても仕方ないじゃない?」
「だがログを見る限りいい動きをしているが」
「ねぇ、だがなんだよ。だがなんなんだよ」
お前関係ないだろ、と喧嘩腰に茶髪の先輩、二宮先輩の胸ぐらを掴み力の限り揺する赤い人、牡丹道先輩。そんな二人をニコニコ笑いながら傍観する色素の薄いベージュの先輩、加古先輩。ボーダーの人なら知っている、ずっと上にいるA級隊員だ。一人違うみたいだけど実力はA級並だと聞いているから別に間違いではない筈。そんな先輩達が揃いも揃って私なんかに一体なんの用なのか。切実に帰りたい。
「………………………要件、何」
早く立ち去りたいのと居心地の悪さから我慢できず、自分から口を開く。すると、今まで無言を貫いていたからか、私の言葉に言い合いをしていた先輩三人は水を打ったように一斉に静かになってしまった。逆に気まずい。帰りたくて聞いただけなのに、またじっと、見つめられ最初に逆戻りしてしまっただけで、さっきから中々先へと話が繋がらない。一体全体何故、私は素直にこんな所に来てしまったのか。果てしなく疑問だ。疑問、なのだが答えは簡単で、お師匠に呼ばれたからに他ならない。
じっと見つめてくる牡丹道先輩の真紅の瞳を見つめ返す。『色』を見なくても、目を見れば分かる。ああ、この人はきっと真っ直ぐな人なのだと。お互いに何を言うわけでもない。その時間が数秒だったか数分だったか続いた後、牡丹道先輩は顎に手を添えた状態で、うん、と一人頷くとにっこりと笑った。それは、私の苦手な優しい頬笑み。
「椿姫、閑ちゃん、だっけ。ポジションはオールラウンダー。だけど元々はガンナーで主に散弾銃を使用。たまに拳銃型も使ってるわね。自分から取りに行くこともあるけど基本的にサポートに回るのが多く上手、だけど誰かの下に付くことはまず考えてない、と」
単独行動が多いからすぐわかっちゃったわ、とつらつらと述べられたのは自身のことで。何が言いたいのか分からずに真顔に八の字が刻まれる。眉間の皺に気づいたのか牡丹道先輩は「ああ、ごめんね」と苦笑気味に溢す。
「さっき皆で椿姫ちゃんのログ見てね、いい戦いするなぁって感心しちゃって」
「まるで紅香ね」
「え、どこが」
「戦えるのに人嫌いなところが」
「違う、私人好きするよ」
「貴女極端なのよ」
横から投げられた加古先輩の言葉に牡丹道先輩は違う違うと首を振り否定する。よく知ってるって言うことは、よく見えてるって言うことで。この二人は仲がいいのだろうなぁと二人の『色』が暖色になるのを見てそう感じた。数回の言い合いの後、ハッと我に返った牡丹道先輩のちょっと黙っててよ、の一言でそれは終わり、ごめんねーと此方に戻ってきた。
頬をポリポリ掻き、牡丹道先輩は一秒で真剣な面持ちになった。そして、その一言に、私は呼吸の仕方を忘れてしまった。
「椿姫ちゃん、単刀直入に言うね。私の隊に来て欲しいの」
16.12.26
二宮さんが何も喋らない……。