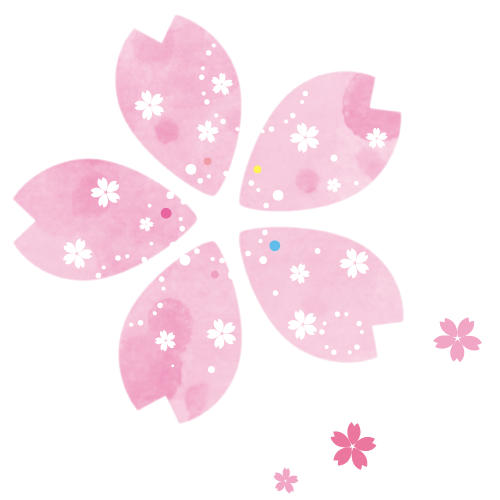
Main
問答無用の魔法
12それから一週間後。
汐音は麟太郎と美和に頼まれて結婚式で撮った写真の整理をしに2人のマンションにいた。
兄弟達の写真が多すぎて、まだ手つかずの状態だった。
それにしても、やはり兄弟が揃うと壮観だ。
写真を見ているだけでも楽しめる。
ついつい作業が疎かになってしまったが、ようやく整理のめどが立ってきた。
早く終わらせてからゆっくり眺めることにしよう。
汐音は美和に言われた通り、未使用のアルバムをシェルフから探した。
だが、それらしいものが見当たらない。
代わりに真新しい箱が隅に置いてあり、その中にはいくつかの封筒と一冊の手帳があった。
少し古ぼけた手帳は母子手帳だった。
何の気もなしに見た汐音はパサリとその手帳を足元に落としてしまう。
『氷見汐音』…子の氏名のところにそう書かれていた。
両親の名前は、氷見研二と由紀絵。
『由紀絵』は汐音の母親の名前だった。
嫌な胸騒ぎがする。
汐音は一緒に入っていた封筒を開けた。
するとそこから何枚かの古い写真が出てくる。
麟太郎と赤ちゃんを抱く知らない男の人。
裏を見て汐音は愕然とした。
汐音の誕生日と共に書かれた『研二、汐音と』の文字。
…意味が分からない。
どういうこと…?
私はパパの…日向麟太郎の子じゃないの?
頭が真っ白になってしまって、何も考えられない。
ただ激しい動悸に襲われて、汐音はぺたりと床に座り込んだ。
「ただいまー。」
聞き慣れた声が帰宅を告げる。
ガチャリと音がして、ドアから顔を覗かせたのは麟太郎だった。
「ああ、汐音。もう来てたんだね。」
「パパ…」
「今日は、思ったよりも仕事が早く終わってね。汐音が来るって聞いてたから、急いで帰ってきたんだ。」
「…」
「…汐音?」
「…」
座り込んだまま何も答えない愛娘を訝しそうに見た麟太郎の目に、その周りに落ちていた手帳や写真が飛び込んでくる。
わかりやすく動揺した麟太郎に、汐音の涙腺が緩んだ。
「ごめん…散らかしたままだけど、帰るね。」
「…汐音、ちょっとだけ話をさせてほしいんだ。」
どう声をかけていいか分からないと言った麟太郎の言葉に、汐音は小さく首を振る。
「…聞きたくない。」
「え…?」
「ごめんね…1人になりたい…」
そう言って汐音はふらりとマンションを出て行った。
冷たい風が頭を冷やす。
公園のベンチに腰を掛け、ズルズルと体を預ける。
…きっと私はパパの子じゃない。
さっき見た『氷見研二』という人が父親で、ママは『日向』ではなく『氷見』由紀絵だったということだろう。
頭では理解していた。
ショックだったけれど…もう成人しているのだからある程度の納得はできる。
ただ…心が追いつかなかった。
たった半年の間に色々なことがありすぎた。
「疲れた…」
ポツリと零した言葉に、体がずんと重くなる。
けれどいつまでもここにいても何の解決にもならない。
「どうしようかな…」
なんて言ってみたものの、汐音は溜息と共に立ち上がった。
いつもよりゆっくりなペースで歩いていても、足が勝手に行き先を決めていた。
1人になりたいのに、誰とも会いたくないのに…
考えなくても歩けてしまうぐらい慣れてしまっているのだ。
無意識でも帰ろうと思っているのだ。
サンライズ・レジデンスに。
…朝日奈家に。
「…嫌に…なっちゃう、な…」
しばらくして見慣れた玄関が目に入ってくる。
そこには壁に凭れかかっている椿がいた。
「汐音…っ!!」
「…椿さん…」
「あー、もう…こんな時間まで何やってんだよ!!どれだけ、心配したと思ってんだ…っ!」
「…」
「とりあえず、無事で良かったーっ。」
「…椿さんはどうしてここに?お仕事は、どうされたんですか?」
「な…っ、あのな!仕事なんか、後回しだ!お前のことを待ってたに決まってるだろ!?」
「私、を…?」
仕事に対しては真面目な椿がそれを後回しにした。
驚いて思わず聞き返した汐音に、椿は怒った顔で近づいてきた。
「麟太郎さんから、ウチに連絡があったんだよ。…お前が、麟太郎さん家を飛び出したって。…麟太郎さんから事情も聞いた。今、みんながキミを待ってる。」
「…そうですか。みんな、もうご存じなんですね。」
「なあ、帰ってきたんだろ?早くリビングに行こうぜ?」
「…私のことはいいですから。椿さんは、早くお仕事へ行ってください。」
「はあ?なあ、汐音。お前、それマジで言ってんの?」
「はい。」
「俺がさ…お前のことを放り出して、仕事へいけるとでも思ってんの?演技できるとでも思ってんのかよ?わりーけど、そんなに器用じゃねーんだよ。」
「…それでもしなきゃダメなんじゃないですか?仕事なんですから。」
「俺のことはいーんだよ。それよりもまず、ウチに入ろーぜ?麟太郎さんが汐音と話したがってた。大事なことだから、ちゃんとわかってほしいって。」
そう言うや否や、椿は汐音の手を痛いぐらいに握った。
そして一言もしゃべらずみんなが待っている部屋へと汐音を連れて行った。
「汐音…」
「…」
「おかえり、汐音。」
「…ただいま。」
娘から返事が来たことに、麟太郎は安堵のため息をつく。
「よかった、無事に帰ってきて。みんなも心配してたんだよ。」
「…」
「話を、させてくれないかな?」
「それじゃあ僕達は部屋に戻ります。ゆっくり話をして…」
切り出した麟太郎に、雅臣は弟達を促してリビングを出ようとする。
「…聞きたくない。」
けれど、汐音の拒絶の言葉に足を止めてしまった。
「汐音…?」
「ごめんなさい。今は…聞きたくない。」
「だが…」
「いま聞いても処理しきれない。」
「…」
「私の本当のお父さんは『氷見研二』なんでしょう?ママは、本当は『氷見由紀絵』って言うんでしょう?」
「…ああ。」
掠れ声で聞いた汐音の問いを、麟太郎は苦しそうに眉を寄せながら肯定する。
事実を唯一知っているその口から聞いたことに汐音も兄弟達もショックを受けた。
「…それだけ分かればいいから。今はこれ以上のことは知りたくない。」
少しして汐音がポツリと言った。
「ごめんなさい…疲れたから休みたい。みなさんにも遅くまで迷惑をかけてしまってすみませんでした。」
「汐音ちゃん、迷惑だなんて誰も思ってないよ。君は僕達の家族なんだから。」
「…」
「僕達は今まで通り、君のことをかわいい妹だと思っているからね。」
「…」
「汐音、一つだけいいかい?」
「…」
「汐音は…僕の娘だよ。確かに、血はつながってないけど…。汐音は僕が育てた、僕の大切な娘だ。汐音と過ごした時間は、僕にとってかけがえのないものなんだよ。」
言い聞かせるような雅臣と麟太郎の言葉に、汐音はギュッと目を閉じる。
どんなに優しい言葉をかけられても、どんなに励まされても、私はパパとも朝日奈家とも他人なのだ。
かわいい妹だとか、僕の娘だとか、優しい言葉に流されてはいけない。
私はここにいる人達とは関係していなかったのだから。
甘えては…いけない。
「…私もよ、パパ。」
汐音は麟太郎の顔を見てにっこりと笑った。
できるだけ穏やかに、少し甘えた声で…震えそうになるのは精一杯おさえる。
単に意地だった。
2015.07.02. UP
(12/24)