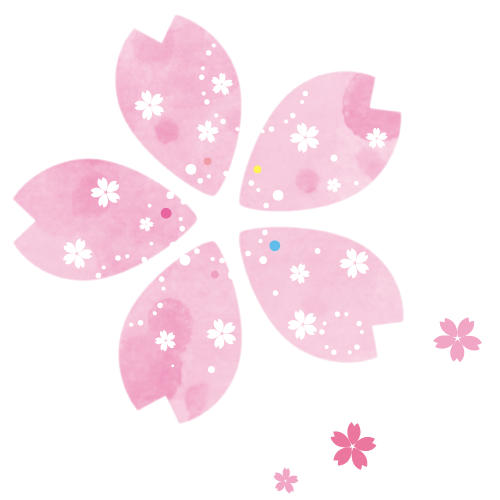
Main
それは、甘い
69庭から聞こえるのは、パンパンとリズムの良い響き。
単調な動作なのに、さっきから子供達が飽きずに繰り返しヨーヨーで遊んでいた。
リビングのテーブルを庭に移動させ、その上には屋台街で買い込んだ大量の食べ物。
それだけじゃ足りないからと、急遽ご飯を炊いておにぎりを大量に握っているところで。
ホント、よく食べること。
いいんだけどね。
むしろ、食べっぷりがいい方が見ていて気持ちいいんだけどね。
「…結局作ることになっちゃいましたね。ごめんなさい。」
こんな日は楽してほしかったんだけどなぁ。
「まりが気にする事じゃねえ。屋台のもんはどれも量が少ない割に高すぎだろう。」
「そうそう。あんなちょっとしかないんだったら、作っちゃった方が安上がりだよね〜。」
「腹にたまりそうなもんは買ったのと握り飯があればなんとかなる。あとはつまみを作ればいいんだから、いつもより楽なもんだぞ。」
「まりちゃんも手伝ってないで庭に出てればいいのに。せっかく休みの日なんだからさ。」
…おかんが2人いる。
スーパーで買った鶏肉をジューシーに揚げている佐助さんと、野菜スティックにつけるもろ味噌の味を調えている小十郎さん。
ヤバい、労りの心が身に沁みる。
炊きたてのご飯が熱くて手がヒリヒリしてる、とか言えないんだけど…。
「…さっさと終わらせちゃいましょう。もうすぐ時間ですし。買ってきたものも温かいうちに食べた方がおいしいですしね。」
「俺はもう終わるぞ。猿飛はどうだ?」
「俺様ももう少しだよ〜。終わったらまりちゃんを手伝うからね。」
「いえ、私ももうすぐ終わりそうなんで。」
「それなら長曾我部達に運ばせるか。」
「了〜解。その前にまりちゃん。はい、あ〜ん!」
菜箸でつまんで差し出されたのはトリカラ。
まだ衣がジュワっているそれをハフハフと口の中で転がす。
「…おいしいっ!すっごいジューシー!」
「ちょっと濃いめに味付けしたけど、問題なさそう?」
「はい!これなら冷めてもおいしく食べられますね。」
「うん、そう思って味付けしたんだ。よかった。」
佐助さんが嬉しそうにへにゃりとした笑顔を向けてくる。
それがもう、何と言うか誰が見ても嬉しいんだって分かる表情で。
私も思わずニコニコ返していると、ますます笑顔が崩れた。
「まりちゃんがおいしそうに食べてくれるの見るって、幸せだね〜。」
「そうですか?佐助さんのお料理はどれもおいしいから、毎日食べられる私の方が幸せ者ですよ。」
「いやいや、俺様の方が幸せだって〜。いっぱい食べてね。俺様があ〜んってしてあげるから!」
…それは遠慮願いたいかな。
若干引いてしまった私をよそに、佐助さんはレタスをパリパリとちぎって盛りつけ始める。
気を取り直して残りのおにぎりを、と思った時。
小さめの器がずいと目の前に出された。
「こっちはどうだ、まり?」
中に入っていたのはもろ味噌で、一見すればなんの変哲もない…けど。
いや、でも作ったの小十郎さんだし!
絶対に美味しいはずでしょ!
綺麗に等分された胡瓜を一本拝借して味見すれば、これまた絶妙は味加減で文句のつけようがない。
「うわっ、お味噌おいしい!野菜の甘みをすごく感じます。」
「そうか。旬の野菜はそれだけでうまいからな。」
「小十郎さんの野菜の目利きって、最早プロですよねぇ。」
「ぷろ…?」
「名人って事です。その道のエキスパート…あぁ、達人とか。比べるようなレベルじゃないですけど、私が選んだ野菜より絶対に美味しいですもん。」
「まりに褒められるのは悪い気がしねえもんだな。っと、味噌がついちまっているぞ。」
「え、やだ!どこですか!?」
「取ってやるから動くな。」
うわっ、やだ!
子供みたい!
なんて焦っている間に、小十郎さんの親指が私の唇を拭うように動いた。
しかも、端っこじゃなくて割と真ん中近く。
「…こじゅっ…!?」
「相変わらず柔らかいな。」
「は…あっ!?」
ぺろり、と指についたお味噌を舐め取りながら小十郎さんが意味あり気に片方の口角を上げる。
チラリと見えた舌と一連の動作は色気を必要以上に醸し出していて、頬に熱が集まった。
「ははっ!顔が赤いぞ。」
「ちょっ…こじゅっろ、さ…な、何を…」
「ちょっとちょっと〜!?聞き捨てならない言葉が聞こえてきたんですけど〜!?」
険呑な声を発したかと思うと、乱暴な音を立てて菜箸を置きながら佐助さんが笑顔を向けてくる。
だけど、口端もこめかみもピクピクとしていて…。
「まりちゃんの唇が柔らかいのは同意するけど、な〜んで右目の旦那が知ってんのかな〜!?」
「ちょっ…佐助さん!?」
「ほう?猿飛こそ何で知っているんだ?」
「小十郎さんっ!」
何で2人ともそこに焦点を当てるの!?
どうでもいいことでしょっ!?
「何でって…ねえ?まりちゃんと俺様の仲だし〜?ほら、まりちゃん。そんな年増なんか放っておいて、こっちおいで?」
ぐい、と引き寄せられたのは腰で。
「何言ってんだ…まり、こっちを向け。」
くい、と掬われたのは顎で。
…。
ダメ!イケメン、ゼッタイ!
この人達、絶対に自分の顔の良さを知ってやがる!
しかもそれを効果的に武器にすることに慣れてやがるっ!!
「…っ、元親っ!慶次っ!!」
この人達を相手にしてたら、心臓がいくつあっても足りやしない。
いつの間にか作り上げてしまっている2人の足を踏みつけて逃れる。
痛い、なんて言ってるけど。
それ、一欠片も思ってないでしょ!?
笑いを隠しきれてないよ!
ご飯の残りを乱暴にかき集め、一つにまとめる。
ふんだっ!
心なんか込めてないこのおにぎりは、2人が食べればいいんだ!!
「なんだあ?」
「できた!運ぶの手伝って!」
「おう…って、まり。顔、赤くねえか?」
「そっ、そんなことないでしょ!?変なこと言ってないで、ほら!これ運んで!!」
「あ、本当だ。耳まで赤くなってるよ。まりちゃん、風邪でも引いちまった?熱が出ちゃったかい?」
「大丈夫だから!慶次も、ほら!」
大皿に盛られたおつまみを2人に押し付け、私はおにぎりを乗せたお皿を両手に持って。
逃げるように出来上がったものを庭に運べば、子供達がキョトンとして私を見る。
ホント、佐助さんも小十郎さんもなんなの!?
私をからかうなんて…。
後で覚えておきなさいよっ!!
2018.11.26. UP
(69/91)