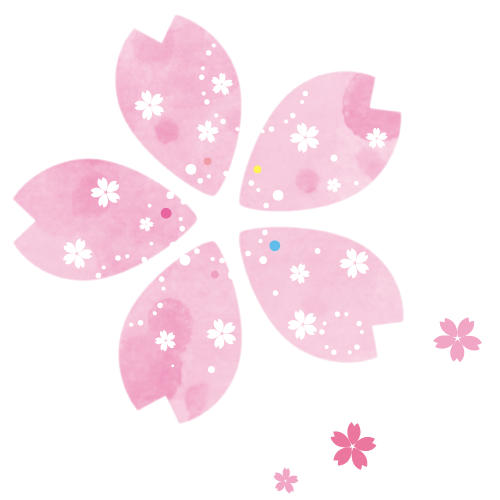
Main
それは、甘い
76食事後、着替えるために私と倭は自室へ。
ほら、洋服と着物って体の動かし方が違うでしょ?
慣れるためにも、ここにいる間はできるだけ着物で過ごしたかった。
だって、無様なところなんて見られたくないし。
お祭りを壊すようなことなんかしたくないし。
盛夏の着物は透ける素材が使われている上に、我が地区のシンボルカラーは青。
清涼感たっぷりなコーディネートを楽しめる。
この町の雰囲気に合わせて着物で過ごす人も多いから、変に浮く事もないし。
最近は丸洗いオッケーな着物も増えているし。
普段着に着るなら、そんなもので充分。
これからイヤって言うほど汗かくし、お祭りの時期は質より量を取らせてもらっている。
久し振りとは言え、着慣れているからそれほど手間も取らず。
袴をつけ、髪を纏めて。
みんなのところへ戻ると、目を丸くされた。
「…まりどの!」
「なぁに、弁?」
「その おすがたは なにゆえ…っ!?」
「お祭りの練習に行くんだから、着物じゃないと。」
「はかまなど、 おのこが はく ものに ござろう?」
「基本はそうなんだけどね、すっごく動くから女でも袴は穿くの。」
「…おどろきもうした。 そのような おすがたの まりどのは、 りりしゅう ござるな!」
「そう?ありがとうね。」
「よく似合ってる。くーるだぞ、まり。」
「梵もありがとう。」
「…姉ちゃん、待たせた。これ。」
先に着替え終わっていた倭が蔵から取り出してきたのは、以前のお祭りで私が使っていたもの。
帰省するたびに手に馴染ませているもの。
受け取れば、しっくりと収まる。
「…それは、小刀(しょうとう)か?」
「はい、私達は脇差って呼んでいます。まぁ、真剣じゃないですけど。」
鞘からすらりと抜いて刀身を見せる。
ついでに、腕に当てて思いきり下に引いた。
「なっ…!?」
「ほら、ね?切れてないでしょう?いわゆる、『竹光』ってものです。ただそれなりに
硬いものでできているので、全力で当てれば痣ぐらい平気でできちゃいますけど。」
「…驚かすな。」
「あはは、ごめんなさい。」
慌てて私の手を掴み上げていた小十郎さんの口から、長く息が吐き出される。
「それより、ホントに見学に来るんですか?」
「ああ。見ちゃまずいか?」
「まずいと言うか、見ててもそんなに面白いものじゃないと思うんですけど。ねぇ、倭?」
「…行くぞ、姉ちゃん。」
私の問いかけは無視ですか、そうですか…。
自分の脇差を持った弟は、渋い顔をしながら練習場所へ歩き出してしまう。
私は溜息をつくと、武将ズを見た。
「愛想のない弟でごめんなさい。行きましょうか。」
「ああ。」
「それにしてもさ〜。まりちゃんってやっぱりお姫さんじゃないの?」
「は?」
「いやね、城から近い屋敷とか、敷地内に家や蔵がいくつもあるとか、それにおじじ様への挨拶の
仕方とか。町人じゃこうもいかないでしょ〜?あ、もしくは大店の娘って線もあり得るかも。」
「何度も言ってますけど、ホントにただの一般人です。お城から家が近いのは、ご先祖様が武家でして…
川の内側、実家がある区画はみんなご先祖様が武家なんです。その街並みを『武家屋敷群』って
言ってそのまま保存しているんです。だから、みなさんが見慣れたものが多いでしょう?」
「確かにな。」
「町の真ん中に川が流れていたでしょ?その川の向こうが町屋群って言って、天下統一後の町人が
住んでいた建物がそのまま残っているの。区画割りもほとんど当時のままなんだよ。みんなより
ちょっと後の時代かな。武家屋敷にしても町屋にしても今でもそのまま使っているから、勝手が
悪いところもあるけどね。」
「だがご先祖が武家と言う事は、まりはやはり姫御前で…」
「天下統一後の更にもっと後に、やっぱりまた大きな時代の変化があったんです。
その時に身分ってものは廃止されたから、今の人はほとんどが一般人として生きています。
武家とか町人とかそんなものありませんし、あったとしても関係ないんです…って、これ。
初めて会った時に説明しませんでしたっけ?」
「…」
「いい加減納得して下さいよ、小十郎さん。」
「だがな…」
「もういいじゃん、竜の右目ー。まりちゃんがそうなんだって言ってんだからさー。」
「慶次の言う通りです。」
「それより、まりちゃん!これから行くところはどんなところなんだい?」
「お寺だよ。そこの境内を借りて練習するの。お寺もいっぱいあるから回ってみたら?」
「暇になったらねー。」
練習場所として借りているお寺は笹穂の端にあって、普段は静かに佇んでいるが毎年お祭りの時期は賑やかになる。
他の地区にも同じようにお寺があり、そこが練習場所となっていた。
着いてみれば、既にお祭りに出る人達が集まっていて。
あらら、最後になっちゃった。
知っている顔も、新しい顔も、私達を見て大手を振ってくれた。
「まり!久し振り!!」
「まり先輩!待っていました!!」
次々と声を掛けてくれる中、倭が持ってきたものは。
「今年の槍。姫用の特別なヤツだからな。」
藍漆塗りの打柄には、蒔絵細工。
穂の樋には、細工彫刻。
「…まり。その槍も竹光、なのか?」
「そうですよ。」
「笹穂槍を使っているんだな。」
「そうなの。昔の御殿様が槍は笹穂で統一してね。樋にご加護があるように八幡大菩薩を
彫ったんだって。実家がある地区は槍を得意とした武士が住んでた一角だったから、今は
『笹穂』って呼ばれているの。」
「柄が短くねえか?」
「地形を見れば分かると思うけど、家が密集してるし、周りは山だし。長柄だと
戦うのに不利でしょ。だからだんだん短くなっていったみたい。槍に詳しいの、元親?」
「特別詳しいわけじゃねえけど。そんくらいは、なあ?」
「そうだね〜。笹穂で揃えるって割と珍しいんじゃない?と言う事はじゃあ、『巴』が薙刀で、
『中直』が刀ってところ?」
「その通りです。やっぱり分かるんですね。」
「そりゃ、毎日見聞きしてたものだからさ〜。それにしても…これだけ痕跡として残ってるとはね。」
「それもまたこの町の売りなんですよ。昔ながらの…佐助さん達からしてみたら昔じゃない
かもしれませんけど…歴史あるものを大事にしながらこの町は続いていくんです。」
「この地を治めていた御武家様方も嬉しいだろうね〜。」
「そう感じてくれていれば、私達も嬉しいんですけど。」
それにしても、今年の槍はなんとまぁ…
「…今年のは随分と豪華に作り上げたのね、倭。」
「ここのところ、城が取れてないからな。願かけのつもりで。」
「これは…負けられないなぁ。」
「姉ちゃんなら大丈夫だろ。」
「総大将を守れるように頑張らなきゃ。」
「姉ちゃんに守られるほど弱くねえよ。」
私に襷を渡し、自分も素早く袖を纏める。
ふんと鼻を鳴らした倭の横顔は、弟と言う身内贔屓を抜きにしても頼もしかった。
2020.10.05. UP
(76/91)