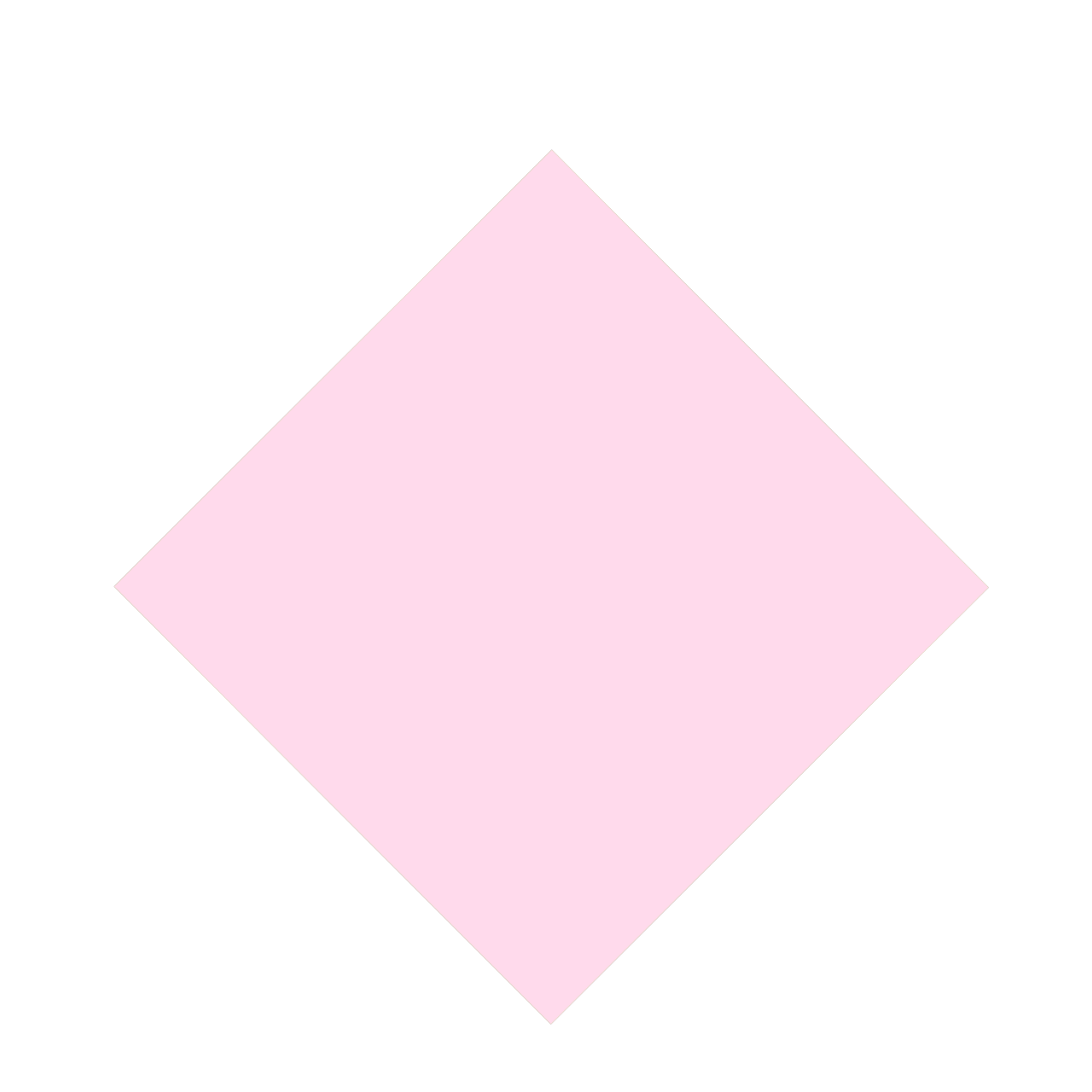※頂いた挿絵が1番最後にあります。
素敵なフォロワーさんに描いて頂きました。
苦手な方は自衛の程、お願い致します。
鬼舞辻無惨が死んで、全ての鬼がこの世から消えた。
あの夜がなかなか明けない戦いから五年の歳月が経った。
生き残った者は各々の人生を歩んでいる。
禰豆子は人間に戻ることが出来て、いつの間にか善逸と恋仲になってた。それを知った時は驚いたもんだ。
善逸は優しくて強い人だからだろう。炭治郎も驚きはしたが、彼なら禰豆子を任せられると思って、それを祝福していた。
私はと言うと仇である鬼の頸を斬り、男のフリをする必要もなくなった。だから、一人称を"俺"から"私"に変え、髪を伸ばした。
あれからずっと伸ばし続けた髪はもう腰の辺りまできている。
だからこそ、あの最終決戦から月日が経ったと思うことが人より多いのかもしれない。
帰る場所はあれども、なかなか帰る気にならなかった。
あそこは悲しい記憶がこびり付き過ぎてしまっていたから。だから、私は頂いた屋敷で炭治郎と禰豆子と善逸と暮らしている。
ちなみに伊之助は蝶屋敷に居候していているそうだ。カナヲ曰く、アオイさんといい雰囲気らしい。
やっと本業に戻った私は、妖怪や悪霊を相手に仕事をしている。
相手が鬼から妖怪や悪霊に変わっただけで対して代わり映えはしない。だって、彼奴らが現れるのも夜が耽ける時間帯なのだから。
けれど、たまに妖怪の類ではない依頼が来ることがある。
それはとても気分が悪くなるものだ。
呪詛。呪いだ。
妬み、恨み、怒り、嫌悪からくる感情を持った人間や他人の不幸を見て悦に浸る人間。
他にもあるが、そう言った感情を持ってしまった人間は一線を越え、他人に呪詛をかけることがある。
とても頭が痛いことに。
呪詛をかけるということは下手をすればその人の命を奪う行為。
呪詛をかけるならば、己の命を対価として懸ける覚悟が必要だ。
そんなくだらないことに私は自分の命を懸ける程、暇ではないから断っている。
体調が悪い。不運続き。原因不明の病。
寝たきり目を覚まさない。
医者に診てもらっても、治らない。
しかし、そう言った類になると陰陽師の仕事になる。
だから、人からの呪詛とは限らないから依頼主の元へ様子を見に足を運ぶ。
だいたい、呪詛をかけられていたり、呪詛返しをされていたりする訳だ。
前者の場合、問答無用で呪詛返しをする。後者の場合、自業自得だから依頼を断りたいところだが、安倍家の名前もあるから簡単に断れない。
だから、私は脅すだけ脅して二度と呪いなど考えないようにさせてから、呪詛返しを解くようにしている。
今日もまた、似たようなことで駆り出された。
人というものはどうしてそうなのか。
「はあ……」
思わず、ため息が出る。
見上げれば、青い空が広がっている。
ピチチチチと鳥は鳴きながら、遊んでいるように空を飛んだ。
鬼がいなくなった世の中は割かし平和だ。
表だけを見れば平穏そのものだと思う。そう、表だけは。
◇◇◇
「ただいまー…って、あれ、誰もいない?」
「あ、今帰ってきたのか?」
「炭治郎…!」
藤は屋敷の門をくぐり、玄関の扉をガラガラと引いて内側へと一歩足を踏み入れ、帰宅したことを口にする。
そうすれば、だいたい禰豆子がバタバタと足音を立てて、迎えに来てくれるのだが、今日はその音もない。
シーンとした屋敷の様子に彼女は首を傾げ、ぽつりと呟くと背後から明るいどこか嬉しそうな声が聞こえてくる。
その声にくるっと振り返るとそこには緑と黒の市松模様の羽織を羽織り、空の籠を背負った青年が立っていた。
彼女は目を見開き、その青年の名前を口にする。
「お疲れ様」
「ありがとう…炭治郎は炭を売りに?」
「ああ!隣町まで行っていたんだ」
柔らかく優しい笑みを浮かべて労わりの言葉をかける炭治郎に彼女は安堵したような表情を浮べ、お礼を口にすると彼の姿から何をしていたのかを理解したのだろう。
それの答え合わせをするかのように問いかけると彼はコクリと頷きながら、玄関先に籠を置き、どこまで足を伸ばしていたのかを答えた。
「お疲れ様……行先、同じだったんだ」
「ありがとう!そうだったのか?一緒に行けば良かったな」
その言葉に彼女もまた炭治郎に労わりの言葉をかけると少し驚いたような表情を浮べる。
彼女の仕事の依頼先もまた同じ隣町だったようだ。彼はお礼を口にしては残念そうに眉を下げて、言葉を紡ぐ。
「でも、私の方が早く出たから仕方ないよ」
「言ってくれれば、合わせて出られたぞ?」
その言葉が嬉しいのか。彼女は少し頬を赤らめるが、申し訳なさそうに眉を下げて言葉を返すと二人は家の中へと上がり、居間へと足を向ける。
彼女が炭治郎が炭を売りに行っていて家を空けていた理由を知らなかったのは彼女の方が先に出ていたからのようだ。
彼はムッとした顔をして、提案をする辺り、過去のこととは言え、諦められないらしい。
「夜明け前だよ?」
「長男だから起きられたぞ」
「……変わらないな…炭治郎は」
そんな言葉が返ってくるとは思わなかったのだろう。
彼女はキョトンとした表情を浮べては眉を下げて笑みを浮かべ、冗談ぽく問いかけた。
如何せん。炭治郎は良くも悪くも真面目で頑固だ。それに加えて、謎の長男論を持っている。彼は胸を張り、よく分からない自信を彼女に言い切ってみせた。
五年前、まだ幼さを残した少年の姿の彼が似たようなことを言っていることを思い出したのだろう。
彼女は懐かしそうに微笑み、ぽつりと言葉を零し、自分より随分と背が高くなった彼を見つめる。
「ははっ、どうしたんだ?急に」
「ううん、何でもない」
「…そうか?」
「うん」
彼女が何を思ってその言葉を口にしたのか、分からない炭治郎は思わず、声を上げて笑い、問いかけた。しかし、彼女はその笑顔にまた小さく笑みを浮かべると首を横に振ると今に辿り着く。
二人は居間へと足を踏み入れると互いに居心地のよい距離を保ちながら、隣に座った。
あまり心の内を語らない彼女だからだろうか。炭治郎は少しの変化も見逃したくないのだろう。
少しの違和感を感じながら、再度問いかけてみるが、彼女は笑みを浮かべて今度ははっきりと肯定してみせる。
「……藤、何かあったのか?」
「え?」
藤は元々表情にも匂いにも感情が出ない人ではあったが、あの戦いの後は少しずつ感情をどちらにも出すようになったのだろう。
その笑みはやはり彼が知っているものよりぎこちなく見えたようだ。彼は心配そうに見つめ、真剣な表情をして問いかける。
まさか、気付かれるとは思っていなかったらしい。彼女は驚いた顔をして、問いかけ返した。
「悲しい匂いがする」
「………変態」
炭治郎は彼女の手をそっと取り、見つめ続けながら、言葉を紡ぐ。
ひとりで抱え込もうとするな。
まるでそう言っているように彼のあたたかく、強い手は彼女の手を握った。その言葉とあたたかさに藤は複雑そうな表情を浮べ、ポツリと言葉を零す。
それは褒め言葉でないことは明らかだが、それは少しの変化に気が付かれたために取った照れ隠しでしかない。
「誤魔化すときはいつもそうだな」
「ふふっ、……そういえば二人は?」
炭治郎もそれが分かっているのだろう。
困ったように眉を下げて微笑みながら、言葉を返すと彼女はつられた様に笑うとさらりと話をそらした。
そらしたと言っても、気になることではあるのだろう。
「……禰豆子と善逸はデートで帰ってくるのは夕方だって言ってた」
「そっか」
話をそらす彼女に炭治郎は眉根を寄せ、目を細める。しかし、夜明け前に立った彼女が二人がいないことに疑問を持つのは当然のことだ。
彼はため息を一つ零し、彼女の問いかけに答えると藤は納得したらしい。コクリと頷き、受け止めた。
「………なあ、藤花」
「……どうしたの?」
少しの間の沈黙。それは気まずいものではなく、心地よい時間の流れ。
しかし、話をそらされたことが気になる炭治郎はチラッと藤に視線を向けると彼女の字名ではなく、真名を口にした。
まさか、真名で呼ばれるとは思っていなかったのだろう。
彼女は少し驚いたような表情を浮べて、彼に目を向け、問いかける。
「………」
「……な、何?」
彼は名前を呼んだっきり、黙ったまま藤をじーっと見つめ続けた。
なんで、黙っているのか。なんでそんなに見つめてくるのか分からない彼女は居心地が悪くなったのか、戸惑った表情を浮べ、もう一度問いかける。
「ここに座ってくれ」
「え、いや……あの、なんで…?」
炭治郎はくるっと彼女の方を身体全体を向け、胡坐をかいている自身の両ひざを両手でポンと叩き、彼女へ言葉を紡いだ。
はい、そうですか。
そんな唐突の発言にそう言って、言うことを聞く人間なんているだろうか。大半の人間は困惑し、素直に実行なんてしないだろう。藤は混乱したように、言葉をどもらせ、理由を聞こうとする。
「いいからいいから」
「ちょっ……!!」
頭の上に疑問符をたくさん浮かべる彼女に炭治郎はどこか楽しそうに笑みを浮かべると問答無用で藤に手を伸ばした。
困惑していた彼女は反論しようと言葉を紡ごうとしたが、時すでに遅し。
藤は抵抗するタイミングを逃し、彼に横抱きされ、炭治郎の膝の上に座らされ、がっちりと抱き締められてしまっていた。
「なんだ?」
「…………」
満足そうに微笑む炭治郎は文句を言いたそうにしていた彼女に問いかけるが、顔が近い上にキラキラとした笑顔を向けられた
藤はただ黙って俯き、自分の顔を両手で覆うしか出来ない。
彼女は自分自身でも頬が火照ってるのを感じる程、照れていた。その熱は耳まで上昇しているのが傍から見てもそれが分かる。
何故なら、耳まで真っ赤に染まっているからだ。
「………私を甘やかすのは炭治郎くらいだ」
くすくすと笑いながら、彼女を抱き締め、頭を優しく撫でる炭治郎に彼女はそっと顔から手を離し、小さく呟く。
「俺以外に甘やかされたらダメだ」
「ふふ…炭治郎しか私を甘やかさないよ」
その言葉に炭治郎は眉根を寄せ、先程よりも硬い声音で言い返すと藤は彼がヤキモチを妬いていることに気が付いたのだろう。
力なく笑い、眉を下げて彼の胸に擦り寄り、言葉を紡いだ。
「どうかしたか?」
「うん……ちょっと、疲れちゃった」
「……うん」
彼女のその行動は甘えの意思表示。
やっと甘える気になった彼女に柔らかく微笑み、問いかけると彼女は遠くを見るように目を細め、炭治郎の胸辺りの衣服をぎゅっと掴み、ぽつりと言葉を零す。
スンっと匂いを嗅ぐとさきほど感じた悲しい匂いが彼女からするのが分かったのだろう。
彼は藤から紡がれる言葉の続きをじっと待った。
「どうして…人は人を呪おうとするんだろうね」
「……今日の依頼か?」
藤は彼の服を掴む手に力を入れ、苦しそうに眉間にシワを寄せ、心の内に溜めていた毒を吐き出す。
その言葉に炭治郎は目を丸くさせた。あまり彼女は仕事の暗い話はなかなかしないからだ。
それを見せるということは余程、彼女が参っていることを意味する。
彼は閉じていた口をゆっくり開き、優しく問いかけた。
「……鬼がいなくなっても、人は人を恨み、妬み、欲を見せる。強欲な人間ほど不確かなものに手を出す…困ったもんだよ…」
「…………」
藤はこくりと静かに頷くと瞳を揺らし、言葉を続ける。
あの戦いで命を懸けて、鬼殺隊が鬼を倒して、人にとって平穏な日常が多少戻ってきた。
それでも、人間という生き物は欲深い生き物だからこそ、人が踏み込んではいけない領域に踏み込み、地獄を見る。それを助ける羽目になる彼女にとっては頭が痛い事案なのだろう。
藤が困っており、呆れて、怒っていることが匂いを嗅ぎ取っているからか、炭治郎は何も言わなかった。
「ごめん、愚痴を言って……自分が決めたことなのに」
内にある毒を吐けたから、少し楽になったのか。
彼女は眉を下げ、謝罪の言葉を口にする。
彼女の仕事は楽でも簡単でもない。
まあ、普通の仕事も楽でも簡単でもないが、妖怪や、幽霊、呪い、それらを対処するには強靭な精神力が必要だ。
それらを視て退治することが出来る仲間がいれば、まだ心強いかもしれないが、安倍の本家は全て鬼によって喰われてしまった彼女はたった一人だ。
探せば仲間はいるかもしれないが、そこまで大きな組織にするつもりがないのだろう。
だから、彼女は一人でそれらと対峙することを選んだのだ。
藤にとって彼が愛しい人であることは間違いないが、炭治郎に見鬼の才があるわけでも退魔調伏の力があるわけでもない。
鬼殺隊の時のように一緒に戦える同志でもなく、今はただの一般人だ。
頼りたくても頼れる人ではない。頼ってはいけない人、だ。
まだまだ弱いな。
頼りそうになる心に自嘲するように小さく消えそうな声で藤は呟く。
「なあ、藤花…もし、陰陽師じゃなかったら……どうしてたと思うか?」
炭治郎もまた頼って欲しくても、無理なことを分かっているからもどかしいのだろう。
言葉を詰まらせていたが、閉じていた口をゆっくり開いた。
もし、そんな人生があったら、彼女はどうしていたのかが気になったようだ。
「そうだなぁ…きっと世界に表と裏があることも知らずにのうのうと生きて、結婚して、子供を産んでいたかもしれないね」
「………そうか」
唐突の疑問を投げかけられた藤は、んーっと唸りながら考え込む。
きっと今の人生より能天気に生きられたという思いがあるらしい。彼女はそんな未来もまた合ったら良かったと思っているのかもしれない。
先程より柔らかい表情を浮べ、炭治郎を見上げると彼は悲しげに微笑んだ。
「でも、そうだったとしたら、炭治郎に会えてない…きっと、鬼殺隊とも縁がなかったはずだから」
「………」
藤は炭治郎の頬にそっと触れ、彼を愛しそうに見つめながら、まだ続いていた言葉を紡ぐ。
その言葉に、彼女から与えられる柔らかくあたたかい温度に、炭治郎は目を見開いた。
「だから、私は陰陽師の家系であることを悔いてない……よかったと思ってるよ」
「……」
彼女は綺麗に微笑みながら、はっきりと言い切る。選んだ人生に後悔は一切していないと。
その言葉に嘘はない。嘘の匂いはしない。
そんな彼女に炭治郎は瞳を揺らし、見つめ続けた。
「ごめんね、いつも心配させて…待ってるのだって怖いよね」
「……藤花が無事に帰ってきてくれれば何でもいい」
彼女はもう片方の手も彼の頬に添えると額と額を合わせ、眉を下げ、目を閉じて謝る。
危険な仕事だと分かっていて見送る方の辛さも分かっているからこそ、そんな思いをさせている炭治郎に申し訳ないと思っているようだ。
彼は目を閉じ、彼女を抱き締める腕の力を強め、言葉を振り絞りって紡ぐ。
無事に帰ってくればいい。
それが切実な一番の願いなのだろう。
「やめろって言わないでくれてありがとう」
「………本当は言いたい」
「うん」
藤はそっと瞳を開け、至近距離で彼の顔を見て優しく微笑みながら、お礼を口にした。
鬼が居なくなった今。
命の危機があるかもしれないことを生業にすることを望む人間なんて誰がいるだろうか。
そんな危ないことはやめてくれ。
もういいじゃないか。
あれだけ、苦しくて辛くて、悲しいことを乗り越えたのだから。
そう言って止めることはいくらでもできるだろう。
それでも、炭治郎は一度もそう言って止めることはなかったようだ。
彼はゆっくり目を開けると不服そうに本心を打ち明ける。
本当は止めたいということを。
藤はそれも分かっているらしい。ただ、頷く。
「でも、それは藤花の選んだ道を否定することになるから俺は見守るしかない」
「うん…」
彼は真剣な顔で彼女を見つめ、言葉を続けた。
何という男気だろうか。長男だから出来ることなのか。それは分からない。
藤は嬉しそうに口角を上げ、見つめ返してはもう一度、こくりと頷いた。
「でも……もし、もし、辞めたくなったらいつでも辞めていいんだからな」
「ふふ……引退して…炭治郎のところに嫁ぐのもありかぁ」
炭治郎は彼女の負担にならない範囲でまだ紡ぎ続ける。藤が陰陽師を辞めるは誰も責めやしない。むしろ、喜ばれるだろう。
失うかもしれない不安から解放される彼女の周囲の人間にしてみれば、当然のことだ。しかし、一人で背負い込みすぎてしまう癖がある彼女にはそれくらいの言い回しが丁度いい。
提案はされても、選ぶのは自分だということに安心する彼女だからだ。
炭治郎の優しさを身に染みて感じるとまた微笑むと彼の背に手を回し、ぎゅっと抱きしめながら、ぽつりと言葉を零した。
「嫁に来る気になったのか!?」
「……本当はずっとあったんだよ」
彼は耳を疑ったように目を見開き、彼女の両肩に手をかけ、ガバっと抱きつく彼女を離し、大きな声で問いかけるが、それは予想外で驚く言葉だったのか。炭治郎の声は興奮気味に聞こえる。
まさか、本人に引きはがされ、問い詰められる勢いで聞かれるとは思わなかったようだ。
藤は目を真ん丸にさせるとくすっと笑い、眉を下げ、照れくさそうに紡ぐ。
どうやら、彼女は炭治郎の嫁になる気は本当はあったらしい。それでも、ずっと断り続けていたのは、きっと彼女の仕事柄だろう。
「引退しなくてもいいから結婚しよう!!」
「……ふふ、はい」
炭治郎は頬を赤く染め、嬉しそうな表情をしては彼女を力強く抱き締め、何度目か分からない求婚を申し込んだ。
彼女は急に抱き締められ、驚いた表情を浮べると彼の背にもう一度手を回す。
そして、幸せそうに目を閉じ、微笑みながら、炭治郎の求婚を受け入れたのだった。