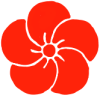
夜の歌に約束した
今日は待ちに待った、彼が極修行から帰還する日だ。
政府より義務化されていたとて、きちんと真面目に書いてくれた、彼から届いた三通の手紙に改めて目を通す。
此れまで、数振りと修行へ出て行くのを見送り、その見送った分だけ届いた手紙は、彼等の個性がはっきりと表れた言葉達で綴られていた。
何れも、主である私の事を案じてくれるものばかりだった。
だから、私は彼等が一時の間居なかった寂しさを堪える事が出来たし、待つ事が出来た。
今回も、其れは同じ。
涙は、最初の見送った時のみと決めていたから、泣いてはいない。
例え泣いたとしても、彼は喜ばないだろうと思ったから、泣かないと決めた。
帰ってきた後で、“私が泣いていた”と聞いて、思い詰めて欲しくなかったから。
故に、自ら宣言していた“極力泣かない”という目標は、達成出来たのではないか。
結果としては、なかなかに僥幸だと思えた。
二年も審神者を勤めているのだ、初めの頃と比べて成長しているのは当然である。
我ながらやるではないか、と内心で自画自賛して誉め称えた。
ただの泣き虫で居たあの頃とは違う。
私だって、この二年で成長したのだ。
其れを、強くなって帰ってきた彼に見せ付けてやろう。
彼から届いた手紙を綺麗に折り畳んで文机の引き出しに仕舞いながら、彼が帰ってきてからの予定を頭の中で組み立てていく。
極まった祝いに、今夜はきっと盛大に派手な酒盛り兼宴が催される事だろう。
今の内に必要な物などの買い出しを済ませておかねば…。
今夜は、きっと今までの宴の中で一番賑やかな宴会になりそうだ。
恐らく、派手に酒が振る舞われる事は折り込み済みなので、其れ用に大量の酒を用意して置かなくてはならない。
せっかくの祝杯だ、彼も思う存分飲むに違いない。
ならば、この際いっその事、樽ごと用意した方が良いか。
其れなら、荷物持ちとして、誰か大柄で力持ちな者を伴として付けて行かねばなるまいか。
そうと決まれば早い方が良い。
誰か手空きな者に手伝ってもらう事にしよう。
今日、内番も無しの非番の者は誰だったか。
その日一日の予定表を覗き込みながら思案する。
体格が大きくて力持ちそうな人、且つ今日一日非番で手空きな者は…蜻蛉切と最近来たばかりの祢々切丸だった。
予定表を確認して、一人頷くと、早速声をかけにその場を移動した。
彼が帰ってくるのは、丁度昼過ぎ頃…。
正式な祝杯を兼ねた宴は夜に行う予定だが、出来る事なら彼が帰ってくるまでに色々とした物事を済ませておきたかった。
何せ、彼が帰ってきたら、そりゃあもうてんやわんやの大賑わいになるだろうから。
強くなって帰ってきた彼の強さを改めて確認する為にも、帰還して早々現在開催中の大阪城イベに出陣してもらう予定だし。
…まぁ、帰ってきての最初の食事休憩を挟んだ後ではあるけども。
兎に角、今は宴の用意をするべく、諸々の準備を進めなければ。
各々の部屋と道場の方を見て回り、目的の二人に呼び掛け、お使いへの伴をお願いする。
本丸を出て行く前に、一度厨に寄って、本日の食事当番達に酒の種類や必要な物はあるかの打診をしておくのも忘れない。
決められた予算内で遣り繰りするのを目指して、いざ城下町へと繰り出す。
立て続けにあったイベント事で、此処のところずっと本丸に引き籠っていたから、久々の外の空気は新鮮で心地良かった。
「いやぁ〜、荷物持ち任せちゃって御免ねぇ〜…っ。流石のお酒樽ごと運ぶのは一人じゃ無理だったからさ。手伝ってくれて有難う…っ!」
「当然の事だ。我で良ければ、力になろう」
「自分も、お役に立てて嬉しく思います」
「あはは…っ、そう言ってもらえると少しは気が楽かな。本当、今日二人が非番で良かったぁ〜…。今夜は盛大な宴が開かれる予定だからね。買い足す物も多いからマジで助かったよ」
「うむ…、此れを女人である御主一人が運ぶのは厳しかったろう。我等に声をかけたのが幸を期したな」
「本当ね〜。もし、自分一人でやるって話だったら、リアカーか何か持ってきて何回か往復しなきゃいけないところだったもん…」
「そ、そうなる前に一度我々にお声掛けを…っ!主は大事な御方なのですから、お躰を大事になさってください…!無理は禁物です!」
「例えばの話だよ、蜻蛉さん…っ。本気にしないでよ」
「は…っ、す、すみません……つい…っ」
「良き臣下を持ったな」
「へへへ…っ、皆さん自慢の臣下ですよ。勿論、祢々さんもね!」
「…そうか。其れは良い事を聞いた」
沢山の荷物を手に抱えた道中、終始にこやかな空気で話す事が出来て嬉しかった。
刀数が八十振りを超えた今、皆と平等にコミュニケーションを取れるかと言われたら、少し不安が残っていたが、今ので粗方の杞憂は拭われた。
もっと皆と接せられる機会を作らねばとは常々思うのだが…如何せん、何事にも不器用な自分では、現状を維持するのが精一杯である。
本丸へ来たばかりの新参者達には申し訳ないが、今暫くは少しの機会のみとさせてもらおう。
そんなこんな話していたら、あっという間に本丸へと着いていた。
まぁ、買い物した量も量だった為に、帰りは寄り道する事無く真っ直ぐ帰ってきただけだ。
買ってきた物は全て厨に預けて、後の事は厨組に任せよう。
伴に付いてきてくれた礼と手伝ってくれた礼を述べて、さて己は次なる仕事に取り掛かるとするかと厨を出掛かると…。
不意に、厨で色々な準備をしていた歌仙より引き留められた。
「主、今ちょっと良いかい…?」
「ん?俺に何か…?」
「うん。この後、少しの時間で良いんだ。時間は空いているかい…?」
「え?う、うん…。日課の鍛刀と少しの出陣(大阪城掘り進めの任務)が終わった後なら、たぬさんが帰ってくるまでの少しの間空いてるけど…っ」
「よし。じゃあ、今日の昼餉の支度、主も手伝ってはくれないかい…?せっかく彼が極めて帰ってくるのだし、今日という日くらい良いだろう?」
「え……っ」
普段、料理もとい家事をするのが苦手だからと厨に立つ事はあまりしてこなかったのだが、帰ってくる彼の為だと手伝いをする流れになってしまった。
いや、彼の為に昼餉の支度を手伝うくらいは、別に問題無いのだ。
しかし、私なんぞの不慣れな者が台所に立つのは、手伝いと言えども足手纏いになるのは必至だし、邪魔になるだけなのではないか…?
正しくそんな表情を浮かべていたのだろう。
歌仙は耳打ちするようにこそりと私に言ってきた。
「大丈夫さ。君が不器用なのは、彼も知っている事だ。だから、どんなに仕上がりが不恰好であったとしても、君が手ずから作った物だと言えば、彼は喜んで食べてくれると思うよ?」
「え………っ、まさかの調理までも担当させる気か…?マジで?大丈夫か、本当に…っ。自慢じゃないけど、俺…合宿行った時、同年代で同じ班だった女子に戦力外通達された程の不器用さだよ…?せっかくの御馳走用意するんだし、俺なんかが出る幕じゃないと思うんだけど…」
「だからこそだよ。普段厨に立たない君だからこそ意味があるんだ。分かってもらえたなら…早めに用事を終わらせてきておいで。なぁに、心配する事は無いさ。この僕と燭台切二人が付いて教えるのだからね…っ!」
「…逆に不安しかなくなったんだが、どうしたら良い…?」
何故かやたらとやる気に満ちた彼の圧に流されて、唐突に今日の昼餉の支度の手伝い(しかも調理込み)をやる羽目になるのだった。
その為、急遽予定に無かった予定が組み込まれる事となり、午前の仕事はおもに日課の鍛刀と少しの任務のみに留め、早めに切り上げる事となった。
―歌仙に言われた通り、午前の仕事を早くに切り上げた私は、厨に向かうなり前掛け(又の名をエプロン)を付けさせられ、二人に挟まれた上での指示を受けながら昼餉の支度に取り掛かる。
慣れない包丁捌きで野菜を切り、しごかれながらも、彼の好きな地元料理で有名なあの郷土料理を作っていった。
皆の分を作るとあって、量も半端なければ、作るのに掛かる時間も慣れないせいで大幅に掛かってしまい…気付けば時間はあっという間に進み、もうじき彼が帰ってくる頃合いとなっていた。
「主ぃーっ、そろそろ正国が帰ってくる時間だぜぇーっ?」
「ええ…っ!!もうそんな時間っ!?時間経つのはっっっや…!!」
「さあ、此処はもう良いから。君は一足早く彼を出迎えに行っておいで」
「あわわ…っ!何かドタバタになってすまん、歌仙…っ!!後宜しく…!!」
近侍の御手杵に呼ばれ、慌てて時計を見遣り、すっかり時間が経っていた事を知る。
厨当番の者達を除く出迎えに出る者達の声に促され、慌ただしく厨を飛び出すと、慌てるあまりに付けっ放しだったエプロンに気付き、もうこの際しょうがないと門へと向かう最中のながらで外す事にした。
門前へと視線を遣れば、焦がれて止まなかった黒きシルエットが早々と出迎えに行った面々に囲まれて笑う姿を目にした。
その姿を目にした途端、どうしようもない感情が胸に溢れ返ってしまって、私は堪らず駆けた勢いのまま彼の懐に飛び込んだ。
勢い付いた私の熱烈な歓迎に、彼は一瞬驚いたように目を丸くさせたが、前よりも確実に強くなったんだろうその逞しき躰で私を受け止めて笑った。
そして、ずっと聞きたかったその声で、私を呼んだ。
「うお…っと、随分と熱烈な歓迎だなァ?そんなに俺が居なかった間寂しかったのかよ、主?」
たった四日…然れど四日の期間、彼と離れ離れであった。
その短くも長い時間は、私にとって、とてつもない程に寂しいものだった。
やっと、やっと言えるのだ。
心の内で温めてきた台詞を、言葉達を。
私は、彼に盛大に抱き付いたまま、言いたかった言葉を口にした。
「……お帰りなさい、たぬさん…っ!待ってたよ…!!」
もう、彼の姿を認めた時から、嬉しくて嬉しくて堪らなかった。
故に、潤んで涙目になってしまっているかもしれなかったが構わなかった。
“極力泣かない”と決めていたのは、彼が帰ってくるまでの間だから、もう我慢しなくても良いのだ。
ちょっぴり目に浮かんでしまった涙を拭う事はせず、私の精一杯の気持ちを乗せて絞り出した言葉に、彼は目を細めて笑って返した。
「おう…っ、ただいま。…約束通り、ちゃんとアンタの処に帰ってきたぜ」
そう言って、優しげな表情をかんばせに乗せて笑う。
…嗚呼、ずっとその顔が見たかったんだ。
愛しき彼に再び触れる事が嬉しくて、離れていた僅かな時間さえも埋めるつもりで彼の身を抱き締めた。
溢れて止まない感情に、とうとう涙が頬に伝ってしまったけども、其れに彼の手が伸びてきて触れる。
「あーあ…、せっかく綺麗な顔してんのに結局泣いちまったら台無しになっちまうじゃねェーか。…全く、相変わらずアンタは泣き虫だなァ」
「…ふへへ…っ、此れでも最初に比べたらマシになったし、宣言してた通り“たぬさんが帰ってくるまでは極力泣かない”って約束、守ったんだよ…!今は、もう帰ってきたから良しって事で許してね」
「そうか…。アンタも強くなったんだな」
「当たり前でしょ…?たぬさんが強くなったのなら、その主である俺も強くなるのは必然…っ。皆が成長するのと一緒に俺も成長してきたんだから、当然だよね…!」
少しだけ彼から身を離してそう返せば、彼は柔らかに笑んで頷いた。
ついつい感極まって流れてしまった涙を硬い掌で拭いつつ、修行を積んでより逞しくなった胸板に引き寄せる。
そうして改めて私を腕の中に閉じ込めた彼は、至極満足したように安堵の溜め息を吐き出して頭を擦り寄せた。
「……嗚呼、やっぱアンタの側が一番落ち着くわ…」
「ぇ………っ?た、たぬさん…?」
少し苦しいくらいの抱擁に、ちょっと息苦しくなりながらも身を捩ると、彼の頭が肩に埋められているのが目に入った。
もしかして、彼もほんのちょっぴりくらいは寂しいと思ってくれていたのだろうか。
勝手な憶測だが、もしそうだったのなら嬉しいと思った。
心の奥底から温かい感情にぽかぽかしていると、不意に肩口に顔を埋めた彼からポツリと零された。
「…何か、アンタから良い匂いがするな…」
「へ…っ?良い匂い…って、嗚呼…其れ、たぶんさっきまで厨に居たからだ。たぬさんが帰ってくるまでの間ずっと厨で飯作ってたからさ。作るのに夢中になってたらすっかり時間立っちゃってて、慌てて走ってきたんだよなぁ。…まぁ、正確には“作らされた”ってのが正しいんだけど…」
「其れでアンタめちゃくちゃ走ってきてたのか…。道理で焦った空気してると思った。つか、今飯作ってたって言ったが…アンタがか?」
「え?う、うん……っ、一応、ね…。せっかくたぬさんが極めて帰ってくるからって、歌仙に言われてさ。今日の昼餉限定で、俺も作りました…。ちなみに、献立はだご汁です…」
「俺の好きなもんじゃねーか。やったな…!こりゃ、修行終えて真っ直ぐ帰ってきた甲斐があったぜ!」
歌仙が言ってた通りかは分からないが、凄く嬉しそうに喜んでくれたみたいで、ホッと安堵する。
まぁ、まだ本人に味を確かめてもらってないから、本当の意味で安心は出来ないけど。
取り敢えずは一安心して、彼を本丸の中へと導く。
「一先ず、お帰りなさいって事で、お昼にしちゃおっか。旅から帰ってきて、お腹空いたでしょ?たぬさん」
「おうっ、今滅茶苦茶腹減って仕方ねぇわ」
「なら、早速御飯にしようかね…!あ、前以て言っとくけど、俺が作ったと言えども歌仙達に監督してもらっての事だからね。仮に味不味くても、あんま文句言わないでよ…?後が怖いから」
「へーへー、わぁーってますよ。…ところで、その手に持ってんの何だ?」
「え…?嗚呼、此れ…ただのエプロンだよ。本当ギリギリまで作業してたから、ぎねに言われるまで時間に気付かなくてさ。言われて初めて“やっべ!!もうたぬさん帰ってくんじゃん…っ!!”てなって、慌てて走り出したまでは良かったんだけども、エプロン付けたまんまだったのすっかり忘れてて…っ。こっちに向かう途中慌てて外して来たんだよ。流石に、エプロン付けたまま出迎えるなんて雰囲気に欠けるかなって思ったからさ。其れで…?」
「…アンタなぁ……いや、やっぱ今は良いや。さ、とっとと飯食いに行こうぜ。んで、アンタが作ったって言うだご汁、腹一杯食わせてくれよ」
何ともまぁ、男前さが上がったものだ。
元々極めたら皆男前さに磨きが掛かる事は分かっていたが…何だろう。
彼の場合、別の意味でも磨きが掛かっているように思えて、内心落ち着かない。
単純に言えば、直視するには憚られるものがある、といった具合だ。
“何が”と問われたら、一概に何とも答えられない気がするが、何となくそんな感じがするのだ。
違和感という程でもないが、気になる微妙な変化に内心戸惑っているのは確かだった。
執筆日:2020.06.10
Title by:ユリ柩
Title by:ユリ柩
表紙 - 戻る