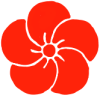
その魔法は素直を促す
防具の類いを外し、上着を脱いだだけの格好となって広間の何時もの位置に腰を据えると、忽ち彼は周りの者達に取り囲まれていた。
「田貫さん、せっかく極めて格好良くなったっていうのに、衣装ほとんど変わり映えしないんだね!勿体ないなぁ〜!!」
「あ…?俺達は武器なんだから、わざわざ着飾る必要なんて無ェだろ…?武器は強けりゃ其れで良いんだよ」
「はは…っ、田貫の旦那らしいぜ」
「けど、逆にあんま変わってなくて安心した感じもするよなぁ〜っ。極めても“正国は正国!!”って感じでさ!」
「どういう意味だ、其れ?」
「なぁ、たぬき…!さっき俺見てたぞ!帰ってきてすぐ主の事抱き締めてたの…っ!!あんなに熱い抱擁交わしちゃうなんて、二人はアツアツに出来上がってたんだなぁ〜!全く狡いぞ…っ!何でもっと早く主が田貫のものになって人妻になってるって事教えてくれなかったんだよぉ!!俺が人妻を愛して止まないのは知ってただろ〜っ!!」
「んなの知ったこっちゃねーよ。…大体、何時主が人妻になったって言うんだよ。ただ抱き合ってただけだろ?つーか、彼奴を俺のもんにした覚えはねぇ。強いて言うなら、“俺が主のもん”だ」
「大して変わらないじゃないk、(もごもごご…ッ!!)」
「すみません、同田貫殿…っ!弟が先走った事を勝手に口にしてしまって…!後でしっかり言い聞かせておきますので、今はご勘弁を」
「…いやまぁ、俺個人は別に其処まで気にしちゃいねぇーけどさァ…彼奴本人が何て言うか分かんねぇから、あんま大声で言わねぇでやってくんねぇか?たぶん、彼奴の事だから変に気にしちまうだろうし」
「…!其れもそうですな。他の者達にも、そう伝えておきましょう」
私の居ない処でそんな会話が成されていたとは露知らず。
彼の私への態度が以前よりも軟化し変化した事に気付いた一期は、やんわりと微笑んで思った。
(いやはや…あの同田貫殿がこんなにも変わられたとは、愛の力は偉大ですな。強ち、包丁が言った事も間違いではなかったのかもしれない)
ガヤガヤと賑やかさ半端ない大広間へ、皆の分の食事を運びながら声をかける。
「はぁーいっ、皆御飯持ってきたよぉ〜!帰ってきたたぬさんが気になるのは分かるけど、各々席に座った座ったぁー!」
「よっ、待ってましたぁ!!主お手製特別メニュー!!」
「そんな大袈裟な…っ。俺が作ったのは精々一品だけで、後は厨組の面子が作ってくれたから。味の保証はするし、安心してください…!」
「もぉ〜、主ったら照れちゃってぇ〜…!其処は堂々と“田貫さんの為に愛を込めて作ったぜ!!”って宣言しなくちゃあ!」
「これ、鯰尾…っ!!」
「はっはははっ、ずお兄は極めてから素直に物を言うようになったな?まぁ、お前は元から結構ストレートに物を言うタイプだったけど。…うむ、ぶっちゃけ普段飯作ったりとかしてないから、改めて言うと何か照れくさいんだが…ま、此処は素直になるべきかね…っ」
「お…っ?という事は…?」
其処で一旦言葉を区切ると、一呼吸挟んで口にした。
「本日の昼餉メニューにある内の一品は、俺自ら頑張って作りました…!ちなみに、其れはだご汁の事ね。たぬさんの地元である肥後国、もとい熊本地方での郷土料理となりまぁーっす。一応、量だけは沢山作ったので、おかわりしたい人はご自由にどうぞーっ!」
「やった…!だご汁だ!俺も阿蘇出身だから、此れには馴染みがあるんだよねぇ〜っ!」
「主が一生懸命作ってくれたんだ。冷めてしまわぬ内に有難く頂くとしようか」
三日月の音頭に、皆が揃って一斉に手を合わせ『頂きます…っ!!』と掛け声を上げる。
其れに続くように、私も席に着いて箸を取り、同様に手を合わせ食事の挨拶を口にした。
すると、すぐ側に座っていた彼が嬉しそうに感想を漏らした。
「美味ぇ…っ、数日振りの本丸での飯っつーのもあるが、やっぱりアンタが作ってくれたってなだけはあるな…!躰に染み渡るくらい美味ぇ!」
「もう…っ、そんな大袈裟なリアクションしなくても…っ。でも、喜んでもらえて良かった…。幾ら歌仙達監修の元で作ったとはいえ、料理苦手な俺が作ったもんだからなぁ…美味しいって直接言ってもらえて安心した〜っ」
「何だよ…んな卑下する程悪くねぇだろ、別に」
「いやいや…実際に食べてもらって感想貰うまで不安しか無かったって。だって、この俺が作ったんだよ…?言われずとも分かるじゃん。お陰で、作り上げるのに滅茶苦茶時間掛かったよ…。最後の仕上げも、結局間に合わなくて歌仙に任せる形になっちゃったし…不器用も程々にしねぇとなー…」
「だったら、練習も兼ねて、此れから毎日少しずつ簡単な物から作っていけば良いじゃないか。僕達が協力するよ!前々から、君には女性らしい雅さが欠けてると思っていたからねぇ。今回のは良い機会になったよ」
「おっ、ソイツは良い考えだな…!毎日作ってもらえるんなら、毎日アンタの美味い飯が食えるって訳だな!」
「あはっ、其れ良いなぁ!俺も正国に賛成!だって美味い飯は最高だもんな…っ!」
「わしも賛成ぜよ〜!!」
「ち、ちょっと待ってよ…!俺、まだ作るなんて一言も言ってないからね!?というか俺、初めの方で言っといたよねぇ!?“今回のは特別限定だ”って…!!」
「え〜?でも、主は田貫にベタ惚れだから、田貫にお願いされたら例え苦手な事であっても頑張っちゃうでしょ…?」
「うぐ……ッ、…まぁ、そうかも、だけども…っ。うん…そう、ね…正直にぶっちゃけると…そうよね…。たぬさんに惚れた弱みって言うんですか……?…たぶん、たぬさんにお願いされたら聞いちゃうかも、って………うん……ッ」
「マジか…っ」
「あうぅ゙…ッ、自分で言ってて恥ずかしくなってきた……今すぐ爆発したい…!」
「ふふふ…っ、良かったですね同田貫さん!」
「主様が珍しく素直で、僕も嬉しいです…っ!」
「はははっ、主君のほっぺ林檎みたいに真っ赤ですよ!」
「むふふ〜っ、あるじさまもいっぽおとなになったんですね!よくがんばりました!」
「うわぁ〜んっ!今剣ちゃんが弄ってくるよぉ〜う…っ!」
思わぬ展開に、自分で言っときながら何か可笑しな方向に傾いたなと分かって羞恥に爆発しそうになり顔を覆い隠した。
何だろう、本来なら言うつもりは無かった事まで口にしてしまっていて、ちょっと変だ。
どうしたんだろう、自分。
そんな風に思いながら、彼からちょっとそっぽを向いた状態で御飯に手を付けていたら、不意に視界の左端から
「ん、おかわり」
「え、うぇ…っ?も、もうっすか…?」
「おう。だって、滅茶苦茶腹減ってたしな。其れに、アンタの作った飯美味かったから、何時もよりも食が進んだ。そもそも俺が飯いっぱい食うの知ってんだろ?そんな俺が一杯だけで満足すると思うか?」
「お、おぉ…っ、そうっしたね…分かった。今おかわりついで持ってきてあげるから、たぬさんは座って待ってて」
隣から差し出された、いつの間にかすっかり空になっていた丼鉢を受け取って、着いて少ししか経っていない席から腰を上げる。
「量は最初についでたくらいで良いんだよね?」
「おう、頼んだ」
「はぁーい。んじゃ、ちょっくらついできますね〜」
そうして、半ばその場から逃げるようにして厨へと向かった。
一度、其処で一人となってから、変に詰めていた息を吐き出した。
(っはあぁ〜………なぁんか調子狂うなぁ…!)
元より彼とは極める前から“そういう関係”だったから、今更素直になったとしても別に変という訳ではないのだけれど…私自身はまだ少し遠慮がちだったというか、そんなストレートに物を言うような感じじゃなかった筈なんだけどなぁ…。
(ゔぅ゙ん…っ、違和感半端ないな………前は、逆にこんな不自然な感覚ならなかったんだけど…何でだろう。よく分かんないな…)
お鍋の蓋を外して横に置いてから、中身を掬う為のお玉を持ったままで動かず、手に持った空の器を見つめる。
器の中は綺麗なくらいに空っぽに平らげられていた。
初めて作った料理だったのに、彼は衒う事も無く真っ直ぐに“美味い”と感想をくれた。
その事自体は、純粋に嬉しくて安心したのだ。
だけど、胸に残るこの微妙な蟠りみたいな違和感は何なのだろう。
分からなくて、再び一人溜め息を吐き出しかけたところで、不意を突くように背後から声をかけられた。
「おや、つがないのかい?」
「ぅわ…っ!?びっくったぁ〜…パッパか…いきなりで超吃驚しちゃったや」
「突然声をかけてしまったから、驚かせてしまったかな?すまないね。私もおかわりをしにきたのだけれど…良いかな?」
「あ、うん…良いよ。器、こっちに頂戴?私がついであげるから」
「君がついでくれるのかい?では、お願いしようかな」
声をかけてきたのは、躰の大きな大太刀のパッパこと石切丸であった。
大きな躰を少し屈めて暖簾を潜った先で私が居たから、声をかけてきたようだ。
其れで予想以上に驚かせてしまった事に申し訳なさそうに謝ってきた。
軽く返してやりながら、持っていたたぬさんの器を一度空いたスペースに置き、代わりに彼の器を受け取って中身をつぐ。
中身の具材が偏らないようにバランス良くよそっていくのを意識しながらついでいく。
たっぷりとつぎ終わってから、前以てつぐ量を訊くのを忘れていた事を思い出し、慌てて彼に満杯の器を返しながら問う。
「あっ、何も訊かずにいっぱいついじゃったけど、つぐ量大丈夫だった…っ?」
「うん、私は此れぐらいで十分だよ。初めにつがれていたのと同じくらいにおかわりしようと思っていたから、丁度良かったよ」
「そっか、なら良かった」
彼のをつぎ終わった後で、先に持ってきていたたぬさんの器の方を持って改めて中身をよそっていく。
その間、私は無言で鍋の中と器の中を見つめていた。
その様子に、何かを察した様子の彼に静かに声をかけられた。
「もしかして、極めて帰ってきた彼への接し方に戸惑っているのかい…?」
「…あ゙ー、分かっちゃうくらいにはバレバレでした?」
「君は、あまり物事を隠すのが得意じゃないみたいだからね。一応隠しているつもりの様だったけれど、分かりやすく顔に出ていたよ」
「あ゙ぁ゙ーっ、俺隠し事すんの下手だからなぁ〜…そうっすか…バレバレっしたか…」
「何か気掛かりでもあるのかい…?話だけなら聞くよ」
たぬさんの器を満杯に満たしてやってから、このまま持っていくには熱いからとお盆を用意しながら、何となしに封じ込めていた心の内を吐露していく。
「……何か、極めてからのたぬさん…前よりストレートに物を言うようになったというか、素直に言葉を表現するようになったというか……俺への接し方が少しだけ変わって、慣れない感じがするんだ…。何て言ったら良いか分かんないんだけど、こう…ちょっと違和感がある感じで……っ。俺自身もどうしたら良いのか分かんなくなってきちゃって…現在複雑な心境です」
「ははは…っ、成程、そういう事だったか。うん、思ったよりも平和な悩みで安心したよ」
「え゙ぇ゙〜……っ」
「大丈夫さ。確かに、今の彼は前の時よりも素直さが目立つようになったけれど、其れは元来彼が持っていた性質をより表出すようになっただけで、根本的なものが変わった訳ではないからね。何時も通り接したら良いよ」
「…ゔぅ゙ーん…っ、何かしっくりこないんだよなぁ…」
カチャリ、食器の音を立てながらお盆の上に彼の器を乗せて運ぶ。
しっかりと手に持った事を確認してから歩き出した私の後を付いていくように石切丸も暖簾を潜った。
「ふふ…っ、君はあまり素直になれない質のようだからね。此れを期に素直になってみるのも手だと思うよ?」
「素直、かぁー………そんなに今までの俺って素直じゃなかった?」
「うーん…“素直じゃない”というより、どちらかと言うと“素直さが足りない”といった感じだったかな?」
「え…そ、そんな……?」
「うん。君は、もう少し感情に素直になるくらいが丁度良いと思うよ」
思わぬお言葉を年長者な彼より貰いつつ、私は首を捻って唸るのだった。
執筆日:2020.06.16
Title by:ユリ柩
Title by:ユリ柩
表紙 - 戻る