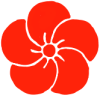
君と至る遅い春に包まる
午後の出陣も終えて、すっかりとっぷりと夜も更けた頃、彼の極を祝しての宴はピークを迎えていた。
「いやぁ〜っ、やっぱ田貫の極姿は格好えいのぉ…っ!!」
「うんうん…っ!!俺、一緒に出陣したけど、前にも増して雄々しくなったというか、漢らしさが増した感じするよね!!錬度もステータスもまだまだなのは同じだけど!」
「でも、敵に与える一撃が前よりも重くなったと言いますか、見ていて凄く格好良かったです…っ!!」
「そうか?まぁ、そう言って褒められんのは悪くねぇな…!ありがとサンクス!!」
「おお…っ!?何だよ、其れ…っ!!今までそんなの言わなかったよなぁ!?」
「へへ…っ、修行先でちっとな!まぁ、んなに変わっちゃいねぇだろ?」
「まぁまぁ、今夜はテメェの祝杯だ!遠慮しねぇで飲んだ飲んだ…っ!!」
「ほぅらっ!アンタの為に主が取って置きのお酒用意してくれたんだから、どーんどん飲みなぁっ!!お酌ならアタシがしてやるからさぁ〜!」
まさにどんちゃん騒ぎ。
賑やかそのものの空気が漂っていて、その場に居る皆浮かれ切っていた。
しかし、夜もだいぶ深くなってきている事もあってか、一部の面子達は舟を漕ぎ出していた。
短刀の子等は既に夢うつつで、それぞれの保護者達が回収するなり掛け布団を持ってきてやるなどしている。
どんちゃん騒ぎで酒盛りをする彼等から離れた席に座っていた私も似たようなもので、朝からずっと動きっぱなだったせいもあって疲れが出たのか、酒気も及んでうつらうつら頭を揺らしていた。
そんな様子を見兼ねた清光がそっと肩に手を置き、声をかけてきた。
「あーるじ…っ、おーきてっ」
「……ん゙ん…っ、やば…一瞬意識飛んでた……」
「主、朝から動きっ放しで疲れたんでしょ?彼奴帰ってくるまでよく眠れてなかったみたいだし。今日は早く寝ちゃいな?お酒飲んだのもあって眠いんでしょ。今頭が起きてる内に歯磨きとか寝る準備済ましてきなよ。潰れる前に動かないと、主確実にこのまま此処で寝ちゃうよ?」
「…うん〜…そだね…もうだいぶ頭ぼやけてきちゃってるから、寝た方が良いね……」
既に寝惚け眼な目を擦って欠伸を漏らしながら受け答える。
そんな子供染みた動作に、テーブルの片付けを手伝っていた安定も笑って手を貸してくれた。
「あー、もうだいぶやばい感じにキちゃってるねぇ〜。ほら、しっかり立って主…!」
「ん〜…眠い……っ」
「此処で寝ちゃ駄目だから…!ほら、歯磨きしに行ってらっしゃい!道中寝惚けて転ばないようにね…っ!!」
「あ〜い…っ、気を付けまぁ〜す…」
眠気でふらふらとした足取りで歩き出しながら間延びした返事を返す。
途中、片付け係の巴形や堀川、寝転けてしまった小夜を回収しに来た宗三達と擦れ違い、一言二言程言葉を交わして別れた。
あまりにも眠たそうにしていた為か、巴形に離れまでの付き添いを申し出られたが、其処までではないと言って断らせてもらった。
少しだけだが、会話した事で幾分頭も眠気が飛んだようだし。
今の内に諸々済ませてしまおうと足を急いだ。
―私が一人離れの自室の方へと向かった頃、宴の中心に居た彼は厠に行く為に席を立ち大広間から出て来ていた。
その際に、私の姿が無くなっていた事に気付いたのか、厠からの帰り道に通りすがりの者に尋ねる。
「なぁ、主が何処行ったか知らねぇか…?」
「え?主…?主なら、さっき離れの方に向かってったよ。結構眠たそうにしてたから、たぶん加州君達辺りが気を利かせて部屋に返したんじゃないかなぁ?お酒も入ってた事だし。何より、今日は君が修行から帰ってくる日だからって朝から張り切ってたから、疲れたんだろうね」
「そうか。ありがとサンクス。んじゃま、彼奴が寝ちまう前にちっとだけでも顔見せてくるわ」
「うん。是非そうしてあげて。主、君が帰ってくるまでの間ずっと気を揉んでたみたいだから。あんまり表には出さないように努めてたみたいだけど…彼女、強がりの意地っ張りだからさ。内心では凄く心配してたんだと思う。だから、君が無事帰ってきてくれて安堵したのもあって眠気が来たんだと思うよ。完全に寝落ちちゃう前に君の顔見たら、きっと心の底から安心するだろうから、顔だけでも見せに行ってあげて?何だったら、そのまま寝ちゃっても構わないから…!部屋でまだ飲んでる人等には、僕から言っておくからさ」
気を利かせた光忠の台詞に頷いた彼は、話に聞いた通りにその足で離れの方へと向かった。
そして、寝る準備の為に歯磨きと洗顔を済ませてきた私と鉢合わせたのであった。
タオルを片手に持ったまま欠伸を堪えていると、前方から彼がやって来て、其方へと意識が向く。
「お…っ、まだ起きてたか。丁度良かったぜ」
「あれ…どうしたの、たぬさん?こっちは俺の部屋の方だよ?」
「アンタに用があったから間違ってねぇよ」
「俺に用…?何でしょう…?」
「アンタ、今から寝るところだったんだろ?」
「え?あー、まぁそうだけども…。今にも寝転けそうだったから、清光達に促されて歯磨きしてきて、ついでに顔も洗ってスッキリしたからちょっとだけ目が冴えてるよ。眠いのは変わんないけどね…っ」
「嗚呼、其れは燭台切から聞いたから知ってる」
「はぁ…まぁよく分かんないけど、修行から帰ってきたばっかで色々と話したい事があるってんなら部屋で聞くよ」
取り敢えず、話を聞くなら部屋が良いかと思って、眠気に抗いながら廊下に居るままから部屋の中へと導いた。
大人しく付いてきた彼は、後ろ背に戸を閉めると、静かに床に座して此方を見遣った。
私はというと、使ったタオルをハンガーに引っ掛け壁際に吊るした後、敷いた布団の上に腰を据えた。
「ところで…まだ宴会続いてた筈だと思うんだけど、主役のたぬさんが抜けてきて良かったの?」
「おう。厠行くついでで抜けてきただけだし、ちょっとしたらまた戻るつもりだ」
「…そっか。で…、俺んとこに何の用だったの?」
「アンタが寝ちまう前に、一目顔だけでも見ときてぇなって思ったから来ただけさ。ついでに、時間が許せば、少しだけ寝話に話でもしてやろうかなって」
「わざわざその為だけに宴会抜け出してきたのか…?別に、俺の事なんて放っといて良かったのに…」
「別にアンタの為ってなだけじゃねーよ。強いて言うなら、俺の為に此処に来た訳だしな」
言われた言葉の諸々に、未だ理解が及ばないまま首を傾げていたら、不意に私の方へと彼の掌が伸びてきて目元を擽られた。
その感触に、反射で目を瞑りながら反応を返す。
「え…っ、急に何……っ、」
「うっすらだけど、隈出来てんな…。あんま寝れてなかったのか?」
「え…あ、うん……ちょっとだけ、ね…。(――相変わらず目敏いなぁ…)」
「俺が修行に行ってた間、そんなになるまで眠れなかったか」
「え……いや、その……、」
「今更変に取り繕うたってバレバレだかんな。俺が居なくて眠れなかったって素直に認めろ」
「………ウッス…すいません、変に誤魔化したりしませんから怒らねぇでくだせぇ……っ」
「分かれば良し」
さわさわと目の下の薄黒い線をなぞるように触れる手が擽ったくて、瞬きをしながら微妙に視線を外す。
まだ何となく慣れない感覚に戸惑いつつも、内心で今まで通りを意識して彼の事を考える。
そうして、一寸ばかり思考の海に落ちかけていたら、再び発せられた彼の声に中断させられた。
「…俺が居ない間、寂しかったか?」
「ぇ……そ、そりゃあ、まぁ…寂しいに決まってるよね…っ。一時的とは言え、俺の大事な刀の一振りが完全に本丸から居なくなるんだから。寂しくない訳ないよね…?」
「アンタの事だから…きっと、俺が側に居なくなっちまった事で泣かせちまうと思ってたが…案の定、泣かせちまったな。宴の席で、御手杵から聞いたよ。…俺が修行へと旅立った直後、見送り終えた瞬間にアンタが泣き崩れたって。“極力泣かないって決めたから、せめて今だけは泣かせてくれ”って言われたと、彼奴が語って聞かせてくれた。アンタが俺達の前であんなに泣いちまってるとこ見たの、加州や前田達とかの時以来だっても言ってた…。そんなに泣いちまってたのか、アンタ?」
「ぐっ………何でそういう事本人が居ない場で喋っちゃうかなぁ…ッ。……確かに、あの時めちゃくちゃ涙腺ぶっ壊れて泣いた記憶はあるけども…!泣いたのはそん時だけで、後は本当にたぬさんが帰ってくるまで泣いてなかったんだからね!!」
「“泣かないようにしてた”の間違いだろ…?アンタは変なとこで意地っ張りだからなァ…寂しいなら寂しいって素直に言えば言いだろうよ」
「…其れだと、審神者足る者としての威厳に欠けると言いますか…色々と問題があると思ったからそう努めたまでですよぅ…っ」
「其れでアンタが無理してたら元も子もねぇって前にも話してたの、忘れてたとは言わせねぇぞ…?下らねぇプライドなんて捨てちまって、さっさと素直になれっての」
「いやいや、せめて最低限の体裁は保たないとこの先やって行けな……ッ、」
言葉を最後まで言い切る前に、遮るかのように彼から身を抱き締められてしまった。
途端に、此れ以上何かを言うのも憚られて口を噤がざるを得なくなった。
そして、唐突に私の身を抱き締めた彼が口調は変えずに静かに言葉を紡いだ。
「この際になってまで無駄に足掻こうとなんてするな、って言ってんだよ…。下手に我慢しねぇで、泣けば良いだろ。俺はもうアンタの元に帰ってきたんだから…憚る事無く泣いて良いんだよ。アンタが泣き虫なのも、寂しがり屋なのも知ってんだからさ。離れてた分取り返す気持ちでぶつかって来いよ」
「……………」
「アンタは前より強くなった…其れはちゃんと分かってるつもりだ。けど、今は我慢しねぇで俺を求めて欲しいって思う。刀の癖に何言ってんだって笑われるかもしれねぇが、アンタの元から離れて色々と学んだんだ。存外、俺は人に近いところに在って、人と近い欲も感情も持ち合わせてたんだってな。よくよく考えてみりゃそうだよな…アンタも知ってる通り、俺は同田貫という量産された刀を集合して顕現した刀であり、数打ちだった分数多の人間の手に渡って使われてきた刀だ。なら、人と同じような欲を抱いちまっても仕方ねぇってもんだよな…?ずっと人の側に在ってきた刀なんだからさ。そんで、俺は気付いたんだ…アンタが求めるもんを返してェって。刀としてだけじゃなく、人の身を得た今だからこそ出来得る限りで」
彼が零す一言一言を、私は黙って彼の腕の中に閉じ籠ったまま耳を傾けた。
「勿論、此れからも俺は武器である事を変わるつもりはねぇ。だけど、アンタに選ばれた刀として、他の奴には出来ない事もやって行けたらなって思ってる。…俺は、アンタを大事にしたい。主としても、好いた女としても。だから、アンタもそろそろ心決めてくれねぇか…?俺の感情から逃げねぇって。アンタが俺の事を好き慕ってくれてんのは、もう十分に分かってるつもりだからさァ」
随分と逞しくなってくれたんだな、と純粋に思った。
外観的にも精神的にも。
此処まで強くなってくれて、成長してくれて嬉しいと思った。
半ば親目線で見ていたといっても過言ではないくらいに。
でも、同時に寂しくも怖くもあった。
極めてしまった暁に、彼は戦ばかりを求めてしまうのではないかって。
其れは、彼が武器であるからにはしょうがない事であって、分かり切っていた事でもあった。
加えて、彼を人にしてしまった事が災いして、彼の刀としての刃生を狂わせてしまわないかとも危惧していた。
私の存在が、彼の刀としての本分を邪魔してしまわないか…其れが気掛かりでならなかった。
しかし、極めた彼は自ら全てを解して私の元へ帰ってきてくれた。
刀としての本分もこなしながらも、私の側で私の刀として在る事を選んでくれた。
此れ以上の応えなんて無いんじゃないかとすら思えた。
ならば…私も、彼の主として真摯に向き合わねばなるまい。
彼の意志に応える為にも。
此れからの己が進んでいく為にも。
強められた腕の力に、彼の胸に縋り付くようにして額を付けながら言葉にする。
「……すぐに、とは…たぶんいかないと思う…。でも、俺もそろそろ覚悟を決めなきゃな…って思ってたから、たぬさんの気持ちにちゃんと応えたいと思う。…だから、もうちょっとだけ待ってて。俺、全てにおいて不器用だからさ。色んな事を一気にこなすの出来ない鈍くさ野郎だから…もうちょっとだけ、猶予をください……っ。そしたら…今度こそ、きっと心決まるだろうから」
「おぅ…アンタの気持ちが落ち着くまで待っててやるよ」
「……有難う、たぬさん…。こんな不器用でどうしようもない俺を好いてくれて」
「俺は、何処まで行ったってアンタの刀である事は変わりねぇんだ。だったら、必然的にアンタの事を好いたって可笑しくはねぇだろ。かといって、今更手放そうったっても問屋が卸さねぇからな?俺は、もうアンタから離れるつもりなんて一切無ェんだから。仮にアンタがこの先俺の事を嫌いになったとしても、もう離してやれねぇから…其れくらいにはアンタに惚れてんだって事、極めた上で思い知ってくれよ?」
「………何か、たぬさん極めたら余計に諸々大胆になりました……?」
返す言葉が其れしか思い浮かばなかったくらいには、もう己の語彙力は溶けて消えて無くなってしまっていた。
おまけに、顔から火が出るくらいに熱く真っ赤に染まってしまっていた。
いっそ恥ずかしさで涙が浮かんでくるくらいには顔を上げられなくなっていたのである。
彼の胸に押し付けるように抱き締められたままで良かったと心底思った。
会話の最初の頃とは別の意味で今は泣きそうになっていたので、助かった…。
話の内容のせいで、若干眠気も吹っ飛んでしまった気もしないが、暫くはこのままで居させてもらおう。
内番着の上からでも分かる厚さを増した彼の胸板に頭をくっ付けたまま目を閉じる。
(パッパが言ってた“素直になる”って、こういう意味で合ってたのかな…よく分かんないままだけど。でも、たぶん今は此れで良いんだって納得出来るから…良いんだよな)
側に在る事にすっかり馴染んでしまったこの温もりに、今は寄り添っていたいと思う気持ちに素直でいよう。
漸く本当の意味で息を吐けると安堵して、深く息を吐く。
深呼吸したら、彼の匂いが鼻先に触れて思わず笑みが漏れた。
…嗚呼、もう私はこの匂いが側に無きゃ安心出来ないんだなって。
存外、私も惚れっぽかったのかなぁ〜、なんて今更ながらに思ってみたりする。
知らず知らずの内に両片想いしていただなんて、誰が分かり得たのだろうか。
きっと、そういうのは本人達の知らぬところで、周りの者達は初めから気付いていたんだろうな。
気付かないのは、本人達ばかりってヤツだ。
そんなこんな彼の腕の中に居るまま思考していたら、安心感やら何やらで眠気が戻ってきたのか、段々と意識が揺らぎだしてきた。
目を瞑ってしまっていた事も手伝って、余計に環境が整ってしまっていたようだ。
その事に、私が何も発さなくなってから体感的にも時間的にも長い時間が経過した事を察した彼は、既に私が夢見心地に入ったかと思ったらしく。
子供を寝かし付ける其れの如く、背中をぽんぽんと叩いてきた。
其れがまた眠気を加速させるもんだから、遂には睡魔に抗う事を止め、そのまま身を委ねる事にしたのだった。
意外にもあっさりと陥落したものであった。
静かな空間に私の規則正しい寝息が聞こえてきた事で、初めて腕の力を緩めた彼はそっと腕の中で寝入る私を見遣った。
「……警戒心も無く、随分と安心し切った顔してんなァ…。ちっとは男として身構えてくれても良いとこなんだが…まぁ、今回は仕方ねぇか。寝不足のまんま、ここ数日動き回ってたっていうし…寝かせてやんねぇと、またどっかで倒れられても困るからな。…休める時にゆっくり休んどけよ」
結局、拭わないまま眦に浮かんで残ってしまった滴を、彼の指が代わりに拭う。
そして、しがみ付いたままの身を抱いたまま自身も一緒に転がして布団に包まる。
(どうせ、もう何度も同衾してんだ。今更̪
彼はそう決め付けて、共に寝てしまう事を選んだ。
此処へ来る手前に、光忠から許可を得ていたのもあってすんなりとした流れであった。
彼の存在が側に居るからと安堵し切った私は、すっかり夢の中だ。
スヤスヤと静かに寝入る私を優しげな目で見つめた彼は、部屋に灯っていた薄明かりを消して目蓋を閉じる。
己も離れる気は無いのだと彼の服を掴み握り締めた手の上から、武骨な掌が包み込むように重ねられる。
互いに向かい合ったまま抱き合って眠るのは、季節的には少し暑かったけれども、初夏の夜の涼しさが其れを心地好く和らげてくれていたのだった。
執筆日:2020.06.16
Title by:ユリ柩
Title by:ユリ柩
表紙 - 戻る