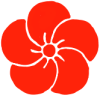
強かな口許は怯懦を隠す
何をしているのかと見遣れば、池の畔に身を屈めた主は、指先を池の中に突っ込んでいた。
思わず気になって問うてみれば、主は何の気無しに答えてくれた。
「何の遊びだ?」
「ん…?こうして指突っ込んでみたら、果たして池の中に居る鯉が食い付いてくるかどうか試してる感じのお遊び…?」
「どんな遊びだよ、其れ…」
「えへへ、でもまだ一度も釣れた事無いよ」
「釣るの前提の話かよ」
「釣れたら面白いよね、ってだけな話だよ」
そうして暫く池の中に指を突っ込んでユラユラと揺らして遊ぶ主の様を眺めた。
見ていて分かったが、俺の主は、時折こうして童子のような子供っぽい事を何の気無しに始めたりする事があるようだ。
ふと道場から聞こえる打ち合いの音が気になって、主から視線を外す。
その直後、主が猫が鳴いたみたいな甲高い声を上げて悲鳴を上げた。
途端に、俺は弾かれたように主へと意識を戻して声をかける。
「にゃあ…っ!?」
「ッ!?おい、どうした!何があった!?」
「…く、食われた…っ。マジで鯉に指食い付かれちった……び、吃驚したぁ〜っ!」
「……いや、驚いたのは此方の方だっての…。指、見せてみろ」
「あ、大丈夫。何ともなってないよ?パク付かれた瞬間はちょっと痛かった気ぃすっけど、驚きの方がデカかったから大した事ないっす」
「なら良いけども…ったく、気を付けろよな?人間は脆くてすぐに死んじまうんだからさァ」
「うん、此れからはちゃんと気を付けるよ。吃驚させちゃって御免ね?俺、吃驚するとつい変な悲鳴や奇声上げたりするからさ。聞き慣れてないとたぶん驚かせちゃうよね。此れ、俺の癖みたいなもんだからさ、頼むから引かないでくれると助かるな〜…」
「いや、まぁ…いきなりの事でビビりはしたが、引くまではしねぇから安心しろよ」
「良かったぁ〜!来たばかりの子なのに、嫌われたらどうしようかと思っちゃった…!」
酷く安堵したみてぇにそう口にするから、俺は思わず思った事をそのまま口にしてしまった。
「俺達は刀だろ…?武器が、んな人みてぇな事思う訳無ぇだろ。考え過ぎだ」
「いやいや…元は刀であっても、今は人の身を得てる訳だからね。人と同じように心があるんだから、そう考えちゃっても何も可笑しくはないんだよ?」
「俺達は武器で、アンタはその主だ。ただの主従の関係に、んな感情を一々挟んだりする事自体無用だろ…?」
「そんな事無いよ。だって、心がある以上は、感情は切っても切り離せないものだもの。だから、たぬさんもそんな寂しい事は言わないで、出来るだけ思った事は口にして言葉にしていって欲しいな。勿論、言いたくない事は言わなくても良いよ。無理強いはしたくないからさ」
俺の言葉にそう返してきた主は、少しだけ寂しそうな顔をして俺を見つめた。
その意図が掴めなくて、俺はまた不必要に言葉を吐き出した。
「…アンタは何処までも俺達を人と同じように扱うんだな」
「人の身を与えた以上は、そうするべきであるかなぁ〜と勝手に思ってるだけですよん。本当、個人的な話だけどね。せっかく自身で動ける身を持てたんですもん…人がするように刃生を謳歌するのも悪くないと思いますよぅ?」
変な事を言うな、と怒られるかと思ったのに、主からは全く別の言葉を貰ってしまった。
其れすらもまだよく分からなくて、俺は溜め息を混ぜた口調で言葉を吐き出した。
「…そういうもんかねェ…」
「まぁ、まだたぬさんは顕現したばかりだからね。分からない事があっても仕方がないよ。そういう事柄についても、何れその内分かるようになるだろうから、焦らなくても良いさ。色んな事も含めて、ゆっくり覚えていこう?」
そう言って、主は濡れていない方の片手を俺に差し出してきた。
握手を求めたつもりだったのだろうか。
一先ず、そう結論付けて、俺はその手を緩く受け取った。
少し冷たく感じるも、其れは温かな熱を纏った生きている人の女の手であった。
己の武骨で固い傷だらけの掌と違って、主の掌はすべすべで真白く、柔らかかった。
この手が今の俺の主のもので、此れからずっと守っていかなきゃならないものなんだろう。
そう思うと、途端に随分非力で小さく細い腕だと思えた。
こんな腕で己が本体を振るえるのかとも疑問に思った。
…が、其れを口にはせず、そのまま何事も無かったかのようにその手を離した。
後になって、己の手の内に残った体温が妙に気になって、腑の内側がざわついたような気がする。
まだ今の俺には分からない感情ばかりだった。
ふと尻餅を付いていた主が立ち上がった様子を見下ろすと、鯉に指を食い付かれて驚いた拍子にか、膝から下の裾部分に池の水が掛かって濡れてしまったようで、生地の色が濃く塗り変えられていた。
俺は、呆れて溜め息を吐いた後に、其れを指摘してやった。
「アンタなぁ…せっかく綺麗な服着てんのに、しょうもない事で服濡らすなよ…」
「あれま、本当だ。さっき鯉に飛び付かれた拍子に飛沫が掛かっちまったのかねぇ…?思いの外びっしょりだ。あははっ、何かウケる…!」
「いや、何も笑えねぇよ。あーあー…、そのまんまじゃ部屋上がれねぇじゃねーか」
「ははは…っ、自業自得だから気にしなくても良いよ。放っときゃ乾くし。アレだったら後で着替えれば良いしね。
「も、もーまんt…、何だって?…いや、そいつはともかく、アンタ的に問題は無くても、俺達からしたら問題有りまくるからな?…ったく、世話が焼ける御人だなァ…。ほら、アンタの部屋が在る離れの縁側ん処まで連れてってやるから、適当に掴まれ」
「えぇ…っ?別に其処までされなくても自分で歩ける…、」
「良いから掴まれって。ほらき落とすぞ」
「はぁっ?ちょ、待っt、うわぁ…ッ!?」
「こら、暴れんなって…っ。大人しくしてろ」
「いや、無理無理無理…!!前抱きとかお姫様抱っことか柄じゃねーって…ッ!!頼む、今すぐ降ろしてくれ!其れかせめて俵担ぎに変えてください!頼むッ!!審神者からのお願い!!マジで頼むから、今すぐ降ろすか抱え方変えてください同田貫さん…ッ!!本っ当此れだけは勘弁してくだせぇって後生ですからぁ〜…ッ!!」
「うっるせぇーなァ、ちったぁ静かにしてろ!」
「ひぇ…っ!?ご、御免なさい!うるさかったよね!?御免なさい、すいません大人しくしてます、本当御免なさい、だから怒らないでぇ〜…っ!」
自分が抱えて運んだ方が移動が早そうだと思ってそうしたら、思いの外驚かれた上に騒がれて暴れられた。
至近距離でギャーギャー騒がれるのが耳に障って、つい語気強めに叱るみてぇに言い放つと、途端に大人しくなった主は声小さめに謝ってきた。
本気で怒った訳ではなかったが、其処まで潮らしくされると、正直気まずくなってしまうのも確かだった。
其れ故、離れの縁側に着くまで無言を押し通して歩く。
その間、主も先程の様子とは嘘みたいに異様に静かさを保っていた。
あまりの静かさに、一瞬“此奴生きてるよな?”と確認がてら腕の中の存在に目を遣ったくらいだった。
見たら、主は掌で己の顔を押し隠した上で俺の肩口に頭を押し付けていた。
女故の恥じらいか何かか。
隠したつもりなんだろうが、明らかに真っ赤に染まってしまった顔以外にも赤くなっちまったものはあって、僅かに赤らんだ耳が隠される事無く此方に覗いていた。
敢えて其れを指摘してやる事は無かったが、何を其処まで恥じらうのかが分からなかった。
そう思いつつ、縁側へ向かう道中、抱え直すのにちょっとだけ身を浮かせて確りと抱え直すと、其れだけの事なのに酷く吃驚したような主が顔から手を離して声を上げた。
宛ら、大きな物に怯える小動物のようだった。
「ひぇ…ッ!?きゅ、急に浮かせたりしないで吃驚するから!ただでさえ不安定で支え無くて怖いのに、マジで吃驚するor心臓に悪いから頼むお願い…ッ!!」
「だったら、もうちょい確り掴まっといてくれねぇか…?じゃねーと安定しねぇから」
「掴まるって言ったって、何処に…っ!?服じゃ駄目なの!?」
「服とかそういうの以外に俺の首があんだろ…?俺的にはそっち掴まれてた方が安定するから助かるんだが」
「うぇ…っ。ま、マジか…いや、まぁそうだよな……そうだよ、なァ〜………っ」
何か抵抗でもあるのか、凄ェ戸惑った後に意を決したように俺に一言「し、失礼します…ッ」と緊張した面持ちで断りを入れてから、おずおずと俺の首へと腕を回してきた。
其れでもやはり危なげな緩さで、俺は仕方なく自身の腕に力を込め直して、より己の身に凭れ掛からすようにしてから運んだ。
そうして主の身を抱えている内に、一つだけ胸の内に落ちる事があった。
(何食ってたらこんなに軽くなるんだかなァ…)
そう思ってしまう程には、想像以上に見た目よりも大分軽さを感じる重さだった。
己とは違って女の身だから、という事を抜きにしても軽過ぎるものだった。
そして、その事に、今朝見た主の食べていた朝餉の量を思い出し、或る事に思い至る。
(この人間はもっと食わねぇと、その内倒れちまいそうで危ねぇな…)
そう感じてしまうには必然的な程に軽さを伴った重みであった。
もし、今朝以上に食わねぇ事があったなら流石に物申してやろう。
密かに胸の内で誓って、不安定な体勢に怖がる主の為にも離れの縁側へと急ぐのだった。
―次の日の事だった。
その日は内番だけで、不満は有れど、任された仕事はちゃんとこなすべくして畑を耕し、苗を植えたり、植わった野菜を収穫したりした。
共に当番として組まれていた御手杵と一通りの作業を終え、収穫で得た成果を見せに野菜を詰めた籠を手に離れの方へと向かうと。
丁度、主も母屋の方に用があったのか、此方へと向かってきている最中だった。
その姿を認めて、すぐに収穫の報告をしようと口を開いた先で目に入ったものに、俺は眉根を寄せて問うた。
「どうしたんだよ、その腕…今朝から今までの間で何があったよ?」
「うん?あぁ〜、此れ?あはは…っ、実はこの状態に自分でも困っててさぁ〜。腱鞘炎悪化させても湿布貼ってりゃ大丈夫だろって思ってゴリゴリ仕事するわ、利き手首酷使するわで、挙げ句の果てにぶちギレた薬研に説教された上でこうなり、腕吊るされる羽目になりました(笑)。此れじゃ事故にでも遭ったか怪我で故障しちゃった人みたいだよねぇ〜?お陰で、骨折した人みたいにめっちゃガッチリ固定されてて動かされん上に全く使えんのだが。此れじゃ仕事になんないし、箸も握れなくね?って思ったんだけど…俺が間違ってんのかね?」
「いや…“みたい”じゃなくて、事実そうなんだろうがよ…。アンタって本当見た目凄ェ真面目そうなのに、意外と自分の身は大事にしねぇっていうか省みねぇとこあるよなァ〜…。いや、アンタの場合は意外じゃなくて見たまんまか。そりゃ、彼奴もぶちギレるだろうし、そうまでして無理矢理使われねぇようにするだろうよ」
「マジか…ッ!薬研の反応が大袈裟なばっかりだと思ってたのに…他の子達にも同様の反応もらっちゃうと流石にそうなのかなって思い始めたわ…」
「逆に、他に何があるんだと思ったんだアンタは…」
呆れを通り越して、最早感心すら抱いてしまった。
駄目だ、此奴…放っといたらマジで死にそうだ。
そう思ったのは俺だけじゃなかったようで、一緒に付いてきた御手杵の奴も心配そうな目で主の吊らされた右手を見ていた。
「うぇ〜っ、だ、大丈夫か?主…っ!見るからに痛そうなんだが、そんなに利き手悪かったのか?」
「いやまぁ、此れは大袈裟に治療した薬研の過保護さの表れであって、実際は此処まで酷くないよ…?今何もしてなくても痛む程度ではあるけども」
「いや、其れ全然平気じゃないヤツじゃんか!?何で今まで無理してきたんだよぉ…っ!!」
「うーん…何でかって言われると、そうなるまで仕事するしかなかったから…、かな?あはは、まぁ自業自得だよねぇ〜っ」
「仮にそうだったとしても、普通は其処までなる前に手当てするなり治療したりすんだろ…っ!?何でアンタは其れを痛み無視してまで無理したんだよぉ〜!馬鹿なのか?麻痺ってるのか!?」
「ん〜、まぁ軽く麻痺っちゃってんのかもね…っ!」
「笑って誤魔化すな、馬鹿…っ。おら、仕事はちゃんとしてやったから、その成果持ってきてやったぞ」
「おぉ…っ!立派な胡瓜にトマトと茄子ですねぇ〜っ!ぶっちゃけ、俺トマトも茄子も嫌いだけども、季節物の野菜は栄養価高くて躰に良いからね。早速厨組に見せに行こうか…!たぶん、みっちゃん辺りが喜ぶと思うよ〜っ。今夜辺りにでも調理されて出て来るかもなぁ。胡瓜は是非とも浅漬けにしてもらおうっと…!」
また、変な既視感を覚えた。
主の明らかに逸らされた流れに、怪訝な顔をしながら見つめる。
何処となく、主は無理矢理自分から無理をきたすようにしているんじゃないかと見えたからだ。
何故そうまでして己の身を酷使するのかまでは不明だったが、明らかに今後において宜しくない傾向であった。
だから、俺は敢えて直接的には物を言わずに訴えた。
「…アンタ、何時かそのまま行くと破滅すんぞ」
何時の日か己が主に言われた台詞そのものであった。
「うん、分かってるよ。でも、今の俺にはこんな風にしか出来ないから…御免ね?」
はっきりとは口にしなかったのに、事を理解したらしい主が複雑な表情で笑みを浮かべて困ったように笑った。
取り敢えず、今は言及する事は避けた方が良いんだろうな、って事は理解した。
そして、あんま触れられたくないんだろうなって思って、気になる事に対して一度蓋をする事にした。
主がまだ話したくねぇと思ってる事なんだったら、其れを圧してまで今無理矢理聞き出す必要も無ェだろう。
そう思う事にして、俺は主の一時的に使えなくされた利き手を見遣った。
今は、白い布地に覆われて直にその手を見る事は叶わなかったが、恐らく見ただけでは分からない状態なんだろう。
其れでも、確実に主の利き手は痛みを発する程にはもう限界を訴えているんだろう。
どうして其処まで無理をするのか。
訊いたとしても、恐らくはぐらかすか誤魔化すかされて答えちゃくれないんだろう。
その事実に思い当たって、俺は初めて戦以外の事で歯痒さを感じた。
何故、俺は気付いてやれなかったのか、と…。
まだこの本丸に顕現して日が浅いからと言えど、この数日で主の人と成りは理解した。
けれども、主を主足らしめる本当の部分はまだ見えちゃいなかった。
一先ず分かったのは、主は注意して見ておかないとすぐに無理をしやすいという事だった。
何とも面倒くさい質をしているなと思うのと同時に、其れが俺の主で、主の刀としても支えてやらなきゃいけないんだなァ…と思うのであった。
執筆日:2020.07.10
Title by:溺れる覚悟
Title by:溺れる覚悟
表紙 - 戻る