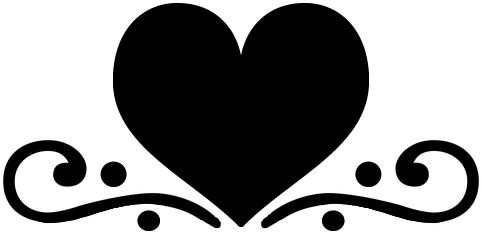
September
せめてもの月夜//豊川風花今日は軽く飲んだ。アイドルになった風花のライブを見に行った記念って言って、風花自信を呼び出して。忙しい中で私のために来てくれたんだって思うと、嬉しくてちょっとだけお酒に伸びる手も進みそうだなって考えてたけど、案の定風花に止められた。いつも飲みすぎるなって怒られる。風花にかまってほしくていつも以上に飲んでるんだなんて、言ったらどんな顔するんだろう。
「ふうか〜もうちょっとゆっくり歩いて〜」
「十分ゆっくりだよ、なまえちゃん!」
「もうちょっとだけ……おいてかれちゃう……」
「終電間に合わなくなっちゃうよ?」
「後一時間あるじゃん!」
健康志向というか、看護師だったからなのか、本当にだらしのない飲み方を許してくれない。それは時間も同じで、風花と飲むときはすぐにお開きになる。
「ちゃんとメイク落として、お風呂はいるんだよ! 歯磨きも!」
「うんうん。ちゃんとするちゃんとする」
「そういってなまえちゃんすぐに寝ちゃうんだから〜!」
夜道をちょっとおぼつかない足取りで歩く。風花を困らせたいわけじゃないけど、私のことをたくさん考えてくれている瞬間は大好きだ。あ、月きれいだなあ。
遠くは蒼く見えるもの//最上静香
「よしっ!」
うまくいった。そう思える絵だった。緑に濁った青が、この絵のメインとなる色だったけど、良く映えている。うん。すこしだけ息苦しかった世界をどうにかしようと、窓を開けると、絵の具特有のにおいが風に乗ってどこかにいってしまった気がした。
「失礼します」
ガラガラと大きな音を立てながら扉が開く。
「あの、先生は?」
そう私に問いかけてきたのは、最上静香さん。クラスは違うけど、アイドルをやっているらしく、時折学校を休んでいると聞いた。友達はライブを見に行ったらしい。テレビにも最近は出ているとか。私は毎日絵を描いてばかりで、そういうことには疎いからわからないのだけれど。
「今日は多分画材買いに行ってます。そのうち帰ってくると思いますけど」
「あの、これを先生に渡してもらってもいいですか?」
最上さんから渡されたのはなんとも形容しがたい絵の描かれた紙だった。108円で買ったことが丸わかりのやすっぽくて水に濡れるとすぐに波打つ紙にはきれいな青がたくさんあった。何を描いているのかはわからなかったけど、美しい青だということはわかる。純粋な青、すこし赤みがかったり、黄色が入っていたり、不思議な色彩に思えた。
「これ、あなたが描いたの?」
「ああ、そうです」
私が最上さんの青に見惚れていると、最上さんは私の絵を見ていた。なんだか恥ずかしい。こんなにもきれいな青がつくれる人に、私の絵を見られるのは。
「きれいな絵ね。私は芸術のことはあまりわからないけど、それでも惹かれるものがある……もうこんな時間! 先生に遅れてごめんなさいって伝えて!」
「うん。いってらっしゃい」
私の言葉を最後まで聞かないで、最上さんは駆け足で美術室を出ていった。敬語が取れているのは、なんだか親しくなれた気がするから、あまり気にしないでおく。色をのせすぎるともっと濁ってしまうかもしれないけど、どうしても最上さんの青を入れてみたくて、私は筆に手を伸ばす。窓からやわらかな風が私と最上さんの絵をなでた気がした。
彗星軌道でゆける場所//永吉昴
なにかに熱くなる人が好きだ。なにかに熱くなれる人は尊敬できる。そういう人の、熱い瞬間を切り取ってみたい。だからカメラマンになった。もしも、この職業に就いてよかったって思える日がきたら、それは私史上最高の写真が撮れた時だって、確信できる。その日がくるのかわからないけど。
「……すごい」
ごくりと、喉が鳴る。圧巻されている。写真を撮りたいけど、うまくシャッターを切れているように思えない。こんなにも素敵な瞬間なのに。なんでだ。どうしようもなく目の前の彼女の姿に魅入ってしまって、写真を撮ることに集中できない。この、熱い気持ちを、ここにある熱気を、すべてこの画面に収めたいのに。この場にいる人だけじゃなくて、色んな人に伝えたいのに。そうやって、自分が体験したことのない感情と、熱さに葛藤していると、気づいたらライブが終わってしまっていた。劇場から出て、真っ先にポスターを探す。永吉、昴。ポスターにカメラを向けて、シャッターを切る。絶対、また来て、もっとすごい写真を撮りたい。この子のライブの魅力を余すところなく伝えられる写真を撮る。そう、私は誓ったのだ。
最果てまでは一人きり//ジュリア
「ジュリア、ギター教えて」
「なんであたしが……? っていうか、あんたギターに興味あったのか」
ジュリアは持っていたギターからゆっくりと目を離すと、私の方を見た。別にギターに興味があるわけではない。いや、あるにはあるが、どちらかといえばジュリアの方に興味がある。彼女がライブで弾いていたから、っていうのと、もともとはパンクロックの道を歩みたかったらしいと聞いたからだ。
「とりあえず、ギター選ぶのだけでもいいから、手伝ってほしい」
「まだ選んでもなかったのか……でも、あたしが決めるより自分で好きなの選んだ方が長続きすると思うけど」
「しょ、初心者向けのやつとか、教えてほしいの。はじめから、お気に入りのギターだとしても、弾くのが難しくて挫折とか、嫌だし」
どうしても、ジュリアに近づきたかった。ジュリアのいる孤高の、ひとりぼっちの場所に、近づきたかった。悲しいくらいに真剣な音で、どうしてもロックを諦めきれていないということがわかる。だから一緒にギターを弾いて、ライブをすればどうにかできるんじゃないのかって、私は思った。本来、近づきたい相手のジュリアに頼み込むというのも変な話だが、あいにくうちの事務所にはギターを弾けるアイドルはジュリアしかいないらしいから、ここは目を瞑るしかない。
「まあ、そうかもしれないな。とりあえず行くけど、きょうは絶対に無理だからな。今週末は多分空いてると思うけど」
「ありがとう! これからよろしくおねがいします!」
「へいへい」
ゆるゆると右手をあげながら軽い返事をするジュリア。はやくその隣に追いつきたい。ジュリアがいる、ひとりぼっちの場所に。