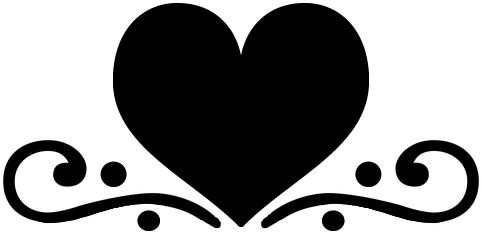
September
豊川風花へのお題は『手間のかかる子ほど可愛い』です。ぴこぴこという電子音をBGMにしながら、今日の仕事をまとめる。なんとなくでこの事務所に所属してから初めた日記も、今では三冊目に突入しているのだから、何事も続けるべきだなと思えた。
「ねえねえ、ふうかさ〜ん。明日の仕事ってなんだっけ?」
彼女はみょうじなまえちゃんと言って、この事務所に所属する、現役学生アイドルだ。普通の学校に通いながら、アイドルをしているというのはけっこう大変だと思う。事務所の待合室はそれなりの頻度で学習室となることがあるから、勉強との両立の難しさがわかる。今日も未来ちゃんと杏奈ちゃんは、英語の宿題を静香ちゃん教わっているのだろう。容易に想像できることだ。
「もう、なまえちゃん覚えてないの? 明日は雑誌の撮影だよ。昨日も私言ったんだからね!」
なまえちゃんは、私に頼ることが多い。それも毎日のように。なんでも、“ふうかさんはなんでも知ってるし、とっても優しいからいっつも甘えちゃうんですよね〜”だと。
「は〜い。ありがと〜ございま〜す。いつもいつも忘れっぽくてごめんなさ〜い」
「謝る気、ないでしょ」
「あ、ばれた?」
この子は、すこし大人を甘く見すぎている気がする。それはもちろん、私やこの事務所の人達が優しすぎるからなんだろうけど、この先のことを考えると、アイドルを続けるとしても、社会に出るとしても、あまりいいことではない。優しさも必要だが、時にはきちんと叱らないと。飴と鞭の使い分けはとても大切なのだから。
「……私はもう慣れちゃってるけど、そんなんじゃいつまでたっても誰かに頼らないと生きていけないよ?」
「別にいいよ。ふうかさん、私の面倒見てくれるでしょ? アイドルやめても、死ぬまでさ」
……。なにも、反論できない。その通りだ。この際はっきりと言ってしまうが、私はこの子の面倒を見るのが好きだし、この子のお世話をするのが好きだ。人のために尽くすことが好きなわけじゃなくて、この子のために尽くすことが好きなのだ。敏い子だとは思っていたが、まさかそこまで理解されているとは。いや、私がわかりやすいだけだったのかもしれない。
「私だって、結婚するかもしれないよ。子供も出来て、家には旦那さんが居て……」
これが、私の精一杯の言い訳であり、逃げ道であった。結婚願望はあるにはあるが、本当にそれは遠い未来のことで、まだ見ぬ世界の話。明日や明後日のことではないから、そこまで考える必要もなく、今後の生活に影響を大きく与えるわけでもなかった。
「押しかける。ふうかさんの妹ですっていって、住まわせてもらう」
この子なら、やりそうな気はする。私の好意に甘えて、堕落した生活を送りそうだ。
「……それ、本気?」
「本気本気。マジのガチ」
「はぁ、いつからこんなにわがままになっちゃったんだか」
この子は生まれたときから、周りに甘やかされて生きてきたんだろうな。それでいて、その生活を続けるための知恵を得てしまっているから、もうどうしようもない。他人に甘えることを、自分がなにもしないことを良しとする世界を作り上げてしまうのだ。
「ふうかさんが優しすぎるから、仕方ないよ」
「なまえちゃんじゃなきゃ、ここまで面倒は見ないよ」
はぁ、と溜め息を吐きながら本心を口にすると、なまえちゃんが目を輝かせた。
「ホント? それって告白って捉えていいよね! 私の事、お嫁さんにしてくださいね。ふうかさん」
手間のかかる子ほど可愛いとは私は思う。だが、こんな風に意味のない嘘を吐かれても困りものだと、私は強く感じるのだった。
貴方は音無小鳥で『砂糖菓子のように甘く』をお題にして140文字SSを書いてください。
撮影が終わったテレビ局から、私がまっすぐに向かうのは765プロ。本当は、日付が変わる時間に近くなると、事務所に電話を入れれば家に帰っても良いのだが、私は毎回事務所に帰る。
今日もきっと、鈍い蛍光灯の灯りがブラインドの隙間から漏れているのだろう。なぜならうちの事務員さんは、とっても頑張り屋さんだから。
「小鳥さん、お疲れ様です」
可愛らしいマグカップに紅茶を淹れ、小鳥さんの隣の机に置く。資料が濡れたりすると、後処理が大変だから。それと同様の理由で、この事務所にはティーカップはおいてあるけれども、大抵はこの場所に居ることの少ないアイドルが使っている。ずっと前にティーカップを倒してから資料を扱うときに使うことをやめたのだ。
「あら、なまえちゃん。帰ってたのね。言ってくれればお茶も私が出したのに」
「いいんですよ。私が好きでしてるんですから。それで、この資料って、奥の棚の水色のファイル、ですよね」
小鳥さんは、いつも自分から動こうとする。たくさんいるアイドルたちのスケージュール管理やら、仕事を取ってきたりと、毎日大忙しなのに。誰かに頼ろうとしないのは、あまり良くないと、私はいつも口にしている。それが小鳥さんの仕事だとはわかっているけれども、私に少しくらい甘えてほしい。
「ありがとうね。アイドルのお仕事でも疲れてるっていうのに……」
「それは、小鳥さんも同じですから。いくら二人いるからって、五十人ものアイドルを扱うのは、とっても大変だと思いますよ。それこそ、私達以上に」
「そんなことないわよ。私の仕事は、みんながいてこそできることなんだから」
こうして私が小鳥さんのことを気遣ってしまうのは、下心あってなんだけど、多分それに小鳥さんは気づいているんだと、私は思っている。それでも、何も言わないで隣においてくれる優しさが嬉しい。疲れているからって無理に追い返さないで、仕事が終わるまで事務所に残ることを許してくれる、そういうところに私は惚れた。だから、何だってしたくなってしまう。小鳥さんのためなら、火の中水の中。それくらい、大好きなのだ。
「小鳥さんも、頑張ってますよ」
「へ?」
「小鳥さんも、私達と同じくらい。私達よりももっと、頑張ってますよ。みんな言葉にしないけど、感謝してるんです」
「あ、ありがとう……ごめんなさいね。この歳になると、涙腺がどうも弱くて……」
ほろり、なんて音が聞こえそうな涙を流し、小鳥さんは弱々しくつぶやく。綺麗だ、なんて思ったけど、決して言葉には出さない。
「温めたタオル、持ってきますね」
「ご、ごめんなさい。なまえちゃん」
「いえいえ。今日はたくさん泣いて、明日からまた、頑張りましょう」
甘い甘い笑顔で、私なりに癒やしたつもり。この瞬間に、小鳥さんの溜め込んでいたものが少しでも軽くなってくれたのなら、私はとても嬉しい。今はこうして気遣うことしかできないけど、何時かはきっと、きちんと言葉にしてこの想いを伝えたいと思う。それまでは、ゆっくりとこの気持ちを温めていくつもりだ。無理になんて、言い寄りたくない。小鳥さんが好きだから、小鳥さんの意思を大切にしたい。その日までは、小鳥さんが愛してくれている、アイドルでいたい。
「そうね。今日は、一緒に帰ってもらってもいいかしら」
「はい。涙が止まるまで、隣にいますよ」
貴方は最上静香で『腹を括れ』をお題にして140文字SSを書いてください。
突然、なまえに呼び出された。筆で書かれた恋文と呼ばれるそれを突きつけられ、今日の十八時に事務所の屋上まで、と言われてしまってから、断ればよかったと気づいたが、もう遅い。
正直に言ってしまえば、なまえのことは好きだ。だから、断ると言っても、それは嫌いだから、とかではない。似たようではあるが、想いに答えられないからだ。それはもう、私だって思春期真っ盛りの女子中学生。恋に恋する乙女ではあるが、それでも私にはアイドルという夢がある。絶対に叶えなきゃいけない、夢が。
恋は障害でもあるから、ただの好きという感情で、付き合ったりなどしたくないのだ。アイドル活動に支障が出てほしくないから。それでいて、私はなまえとの関係を壊したくない。
今の、付かず離れずな曖昧な関係が一番心地よく、誰もが望む関係なのだ。
断ればよかった。今更後悔しても無駄なことだが、そう思わずにはいられない。後悔先に立たずとは、まさにこのことだなと、私は筆書きの恋文を握りしめながら感じていた。
「その、今日は申し訳ない。レッスンなどで、静香も忙しいと思うが、どうしても、言っておかなければならないことがあってだな……」
相変わらず、言い回しは最近の女の子らしくない。月日をいくら重ねたって、きっとこの言葉遣いは変わらないのだろう。
それにしたって、相手への好意が伝わりづらい性格をしているものだ。一言で片付けてしまえば古風という彼女は、感情があまり表に出づらく、それでいて馴れ合いを好まず、言葉数も少ない。なによりその言葉もわかりづらいものが多いという、コミニュケーションがなかなか深い仲まで行かないと、もしくは鋭い観察眼がなければ満足に会話もできないという。
「どうしたの、いきなり改まって」
こういう性格をしている人は、あまりアドリブに応用が効かないと、私はなまえで勉強した。だから、なんとなく何も知らない状態でこの場にいるようなふりをしつつ、顔色をうかがう。改めて考えてみると、とても面倒くさい性格をしているものだ。
「いや、この気持を隠していても、あまり良くないと思ってな」
うん。知ってる。もう手紙になまえの気持ちは書いてあった。好きだってことだよね。口にしたいのは山々だが、面倒くさいことはしたくない。それに、まだ穏便に断ることを考えている私は、付き合ってほしいと言われれば、ぎりぎり何処にと聞き返して回避することができるかもと思い、なまえに言ってもらいたいのだ。
「私は、その、だな……」
あ、これ、長くなりそうだ。なんて、思いながら、目の前の耳まで赤く染まった顔を見つめる。
「うん」
「あ〜っと、その。ええっと、う〜ん」
くるくると髪の毛を指先でいじりながら、先の言葉をなかなか言わないなまえ。たったの二文字だって言うのに。自分から時間指定してきたんだから、心構えくらいしてきなさいよ!
「えっと、私はその、静香が……」
「あれ、静香ちゃんとなまえちゃん、どうしたの〜?」
きっと、好きと言葉にしてくれたんだろうが、それはドアの開く音にかき消されてしまった。何も知らずに屋上に入ってきた未来は、柵に掛けられたタオルと直ぐ側に置いてあった水筒を取りに来たよう。
「み、未来のばかあ……」
「え、なまえちゃん!? ほんとになまえちゃんなの!? だ、大丈夫?」
「未来のせいだからなあ……!」
「ご、ごめんね! なにがなんだかよくわかんないけど、とりあえずごめんね!」
今度は静寂にドアの閉まる音が響く。普段古風で硬派な彼女が涙を浮かべながら馬鹿などと言葉にするなんて、誰だって驚くだろう。空気が微妙に読めていないような登場の仕方だったが、いきなり罵倒されたままなのもかわいそうだから、私からあとでアイスでもおごってあげるか……それにしても、嵐のような人だ、未来は本当に。
「静香、ごめん」
「未来のせいなんだから、気にしなくてもいいわよ」
「あの、それで話なんだけどね……」
なまえの顔を見ながら、逃げられないんだろうな、と感じた。断って感じが悪くなるのも嫌だし、それこそ仕事に支障が出てしまうかも。それに、逃げるなんて、私らしくない。あくまでも仕事を第一に考えて、なまえと楽しく過ごす、というのも悪くはないのかもしれないと、目の前の緊張で震える手を取った。
永吉昴へのお題は『知らないふりが上手くなった』です。
目の前には、愛しの近所の妹ちゃんがいた。それも、私の知らない可愛い女の子のバイクの後ろに乗って。きらきらとした彼女らしい笑顔を振りまきながら。
永吉昴とは、私の向かいの家の夫婦の子供で、それはそれはたいそう可愛らしい女の子だった。周りには男の子が多かったためか、スカートよりもズボンを、ロングヘアよりもショートヘアを、おままごとよりも野球を選ぶようになったのは、ちょっと当時女子高校生だった私にとってそれなりに悲しかったことは、いい思い出だ。なにせ姉も妹も従兄でさえも皆女に囲まれ、挙げ句の果てには小中高と女子校通いの私には野球やサッカーといった男の子の遊ぶものの楽しさやルールなどを知らないから、なにも昴に教えてやれなかったのだから。子供は大人に憧れを抱くものだが、それ以上に薄情で気が使えなく、自分の欲望に素直な生き物なので、最初の頃は私を慕ってそれなりに遊んでくれていたが、段々と私が誘ってものってくれることはなくなった。
だがしかし、昴はもとより、周りの男子にもかなわないようなことが私にはある。それは、年齢と金銭面についてだ。高校に入ったと同時に始めた飲食店でのアルバイトのお給料約数カ月分、私はその全てを“鉄の塊”に捧げた。そう、そいつの名は、バイク。まさに、男の浪漫と言ってもいいようなそいつに、父の影響で魅了された私は、買ってしまったのだ。ちなみに免許は高校生になってすぐ取った。父に勧められてね。
バイクの風を切る感覚はひどく気持ちがいい。自分が人ではなく、ただ自然に生きる何かになったようで、思考回路が働かなくなる。新しく買ったそいつで住み慣れた街を走り回り、手に馴染まない太いグリップを握りながら、私はゆっくりと家に帰って来た。父がバイク乗りでいるために、車庫にバイクもしまえるように作られていてありがたい。そんな時、ふと視線を感じた。ここらへんでは家にしかバイクを乗っている人はおらず、みな車や自転車などを使うため、珍しく感じた近所の子供が見ているのかもしれないなと考えながら振り向くと、私の目線の先には昴が居た。
小さなかすり傷と、絆創膏にまみれた手足。バットとグローブ、ボールを持つその手にもまた、女の子には珍しいような傷が目立つ。そんな男所帯に馴染んでいる身体よりも、私の興味を引いたのはその爛々と輝く瞳だった。熱く脈打つ“鉄の塊”を見つめながら、頬を染めるその姿は女の子らしい。見つめる対象がバイクでなければ、他の女のことももっと仲良くできているのかもしれないのに、と頭の中でぼんやりと思っていると、いつの間にか昴が私の目の前に来ていた。
「ねえちゃん。それ、なに?」
くりくりとした大きな瞳が、目の前の固く熱い乗り物を見て輝いているはずなのに、まるで私に向けられたかのように思えて、胸の奥がキュンとしてしまった。
「バイクって言ってね。かっこいいでしょ」
昴は可愛らしい顔をしながら、私に問う。ちょっとかわいすぎやしないだろうか。お姉さん誘拐されちゃわないか心配だよ。
「うん! ねえちゃん、オレも乗れるの? その、バイクに」
「多分大丈夫だと思うよ。大型だし……」
たしか、一般道路で二人乗りするのは、免許をとってから一年経っていて、50cc以上ならできる、はず。後ろに乗せる人の年齢制限はない、と思う。
「ほんとう! 乗せて乗せて!!!」
「う、うん」
ものすごく、私の腕に強い力で捕まっている。それなりに鍛えているから、このまま上に持ち上げれば上に浮くだろう。ちょっとそれで遊んでみたい気もしたが、腕への強い力は昴の強い意志を表しているかのように思えて、私は諦めた。
乗り始めて数時間、人を後ろに、しかも子供を乗せていると思うと、どきどきと心臓が激しく脈打つのが分かる。昴は、少し大きなヘルメットをかぶりながら、私の腰に強く捕まる。
「す、昴。どうかな」
「気持ちいい!! すごいよ!!! オレが風になったみたいだ!」
びゅんびゅんと自分が思い切り楽しめる速度でいたのだが、昴にはちょうどよかったようで少し安心した。怖いと思われたら、バイクで頭がいっぱいの父に叱られる可能性もあるからだ。
「そっか、うん。バイクはいいよね」
「うん!! すごいすごい!!! ずっと乗ってたい!!」
わかるぞ、昴。その語彙力がなくなる感覚。何もかもがすごいとしか思えなくなって、本当に自分自身が自然に同化したみたいな、絶対に日常では得られない感覚。私も父に乗せられた時、そういうふうにバイクに魅了されたのだ。
「気持ちはわかるけど、もう到着ですよ」
「ええ!! もっと乗ってたいよ……」
だが、今日はもうお仕舞いだ。後ろのシートがまだ冷たい頃は、空が赤く染まるくらいだったのに、今はもう殆どが闇に呑まれている。夜の運転もまた、好いものであるのだろうが、まだ中学生でもない昴を乗せるのは、いささか不安でもあるし、両親も心配するだろう。
「また今度ね。今日はもう遅いしさ」
「うん。絶対、また乗せてよね!」
だから、私は日を改めようと約束したのだ。昴が次の日、引っ越すなどとも知らずに。
私と約束したのに、何だ。昴の乗っているバイクの主は私ではなく、金髪のあの子だ。なんでだよ。
いや、もちろん、幼少期の彼女の日々に、きっと私とのバイクでの激短旅行記みたいなものは残されているはずだ。たった一時間ほどのものだったとしても、見知らぬ鉄に乗り、自然と一体化したことを忘れるはずもない。私だってそうだったんだから。
「あ、なまえさん! お久しぶりです!」
悶々とあの日のことを回想しながら、今日の永吉昴に想いを馳せていると、不意に声をかけられた。いつの間にか歩みを止めている私に気づいたのだろう。
「うん。久しぶり。懐かしいね。まだ、バイク好きなの?」
平常心平常心。誰もここで私が声を荒げたって喜ばない。というか真面目に気持ちが悪いだけ。十五歳の女の子に執着しすぎているのがバレたら社会的に死ぬぞ。初恋をこじらせすぎた野郎になんてなりたくない。私は野郎じゃないけど。
「はい! 今年から乗れる歳なので、頑張って教習所通ってるんですよ!」
「そっかそっか。昴も大人になったのか」
あと五年で成人しちゃうんだもんね。時の流れは早いものだよ。それにしても、あの 金髪の女の子のことを放っておいていいのかな……?
「免許取って、バイク買ったらなまえさんを後ろに乗せてあげますんで!」
「二人乗りは免許取ってから一年経たないとダメなんだよ」
そう私が口にすると、一気にショックを受けた顔になった。そんなにも私のことをすぐに乗せたかったのか。まあ、それは良い点数を取ったテストを母親に自慢するような気持ちであるのだろうけども。
「そ、そうなんですか……でも、来年、絶対乗せますんで!」
「うん、そのときは、よろしく」
本音を言うと、昴には大変申し訳無いが乗る気はまったくない。なぜかと問われれば、それは一種の決別でもあるからだとしか言いようがないのだが、もっと詳しくするならば、大人としての自覚を持った今、そのようなことをするのはいささか恥ずかしいし、私だけが昔のことに縛られているのを身にしみて実感するのが嫌だから、といったところだろうか。
「昴、もう時間ないよ。別れの挨拶、しときな」
後ろでエンジンをかけながら、昴に伝える金髪の女の子は、また可愛らしい。偶然会った昴の親御さんから聞いていたが、どうやら本当にアイドルになったようだ。改めて考えると、昴はずいぶんと遠くで生きているように思えて、なおさら、自分が知り合いでいることに引け目を感じた。
「マジで! なまえさん、それじゃあまた。オレもテレビにでれるくらい有名になったんで、寂しくなったらオレたちの番組見て下さいね!」
すこしだけ、胸が痛くなる。私のほうが少し大人なだけだというのに、こんなにも気を許した笑顔は見たことがないし、あの子に見せる自然体な昴がつらいのだ。
「うん。お仕事頑張ってね」
「はい!」
電車に揺られながら家に帰り、ベッドに倒れ込みたい気持ちでいっぱいだったが、そのままずるずるとバイクを引きずりながら歩く。量産型であり進化し続ける中で置いて行かれた想い出のバイクを、その日私は売った。
ジュリアへのお題は『大切にもさせてくれないの?』です。
久々に、地元に帰ってきた。ジュリアという名として上京したあたしだが、この場所ではその名前は捨てる。アイドルではなく、ちょっとギターが好きな女の子に戻るのだ。いつもは浮き足立った気持ちでこの家に帰るというのに、今日は少し違う。
あたしは、私自身を捨てにきた。別に、親と離別しようとかいうわけじゃないけれども、ジュリアとしてこれから生き続けることを誓う、というだけ。そのための第一歩として、家に残っている作った曲、別名黒歴史をあたしは消しにきたのだった。
ちょうど太陽が真上にあがり、今日の半分が終わった時に、あいつはやってきた。みょうじなまえ。私の幼馴染だ。
「あ、お久しぶり〜。お母さんがね、来てるから入っていいよって、さ。お邪魔しちゃいました〜」
にへら、なんて擬音が似合うような笑みを浮かべながら、手にしたお盆の上のお茶とお菓子を机に置く。あ、これあたしの好きなお菓子だ。
「あいにく暇じゃないから。遊ぶんなら他を訪ねろよな」
「いやいやあ、困っているとお聞きしたので、お手伝いに参りました」
持っていた捨てる予定の楽譜を、その言葉を聞いた時、床に落としてしまった。うそだろ。あの暇さえあれば遊びまくってテストの点なんて一桁ばかりだったのに。なにか悪いことでもたくらんでいるのかもしれない、と勘ぐってしまいそうになったが、嘘が顔に出やすいなまえだから、それはないだろうとすぐにわかった。
「そうか。なまえは昔っから片付けだけはうまかったからな。一人じゃ終わらない量だったから、そう言ってもらえるとありがたい。そしたら、窓際の段ボールにある紙の中から、作詞か作曲名があたし以外の奴をこっちの箱に移してくんないか」
部屋にある押し入れから出してきたダンボールの中身は、全てあたしが作った曲が入っている。一部には既存の曲を自分で楽譜に書いたものもあるが、ギターを父から与えられたあの頃から、毎日のように作っていた。勉強だって、遊びだって、何から何までを放り投げて、私の魂を紙に写し込んできたのだ。手をかけて育てた子供のようであり、私自身を成長させてくれた親のような五線譜たちを捨てるのはあまりにも苦痛だったが、あたしはもう、ここで生まれ育ったんじゃなくて、アイドルのジュリアとして生きていく。見返すことも殆ど無いんだから、捨ててしまう方が、いいんだ。
「書類の仕分けだね。任せて〜」
「おう、ありがとう!」
**
風のうわさであの子が帰ってきたことを知った私は、今日の予定を全てなし崩しにして、この場所に来た。
「この歌、すてちゃうの?」
手のひらにある紙には、私の青春が詰まっている。遊びに全てをかけていた私は、ギターの音に誘われて、この場所にくることは少ししかなかった。それでも、あの子の弾くギターが嫌いなわけではないし、今だって東京の方でアイドルとしてデビューしたジュリアの歌もよく聞いている。周りに合わせてためらってばかりいた私には、あの頃一匹狼でいられるほど強くなかったから、そこまでこの家にお邪魔することはできなかったのだ。それでも、私の胸のうちに残る中学生という世界は、ほとんどが彼女の歌で彩られている。選ぶ言葉の一つ一つが、弾く音の心地よさが、大好きだった。
「ああ、それか。まあ、もう弾くこともないからなあ……」
「そっか。ちょっとさびしいなあ」
「なまえは、その歌好きだったよな。でも、ごめんな。全部捨てるって決めちゃったからさ」
昔のことを思い出しながら、儚げに微笑む。その表情も、もう見られないのかもしれない。
「うん。この歌の所有権は私にあるわけじゃないから、仕方ないよね」
「本当はあげたいところなんだけど、ほとんど黒歴史みたいなもんだからさ……」
持ってきていた大きな鞄を開くと、中からファイルを取り出して、捨てない楽譜をわけていく。いつかの日に訪れたこの場所は、たくさんの色に染まっていたというのに、今ではとても殺風景なものになっていた。
「ほんとに、アイドルになっちゃうんだね」
「最初は手違いだったんだけどなあ。今は、すごく楽しいからさ、アイドルって仕事が」
愛おしそうに、壁に立てかけられたギターケースを見つめる。苦手だと言っていたふりふりのスカートと、赤い光に染まる客席。本当は何度だって、会いに行ったんだよ。
「テレビで見てるけど、わかるよ。すっごく楽しそうだよ。ジュリア」
「そ、その名前で呼ばれると、ちょっと恥ずかしいなあ……」
「あ、おばさん呼んでるよ。行ってきな」
お昼ごはんでもできたのだろうか。ばたばたと音を立てながら階段を降りる後ろ姿に、いつの日かの面影を感じた。
握っていた楽譜を見る。内緒でカバンにしまおうかとも思ったが、あの子の頼みだから、くしゃくしゃにしてから捨てた。