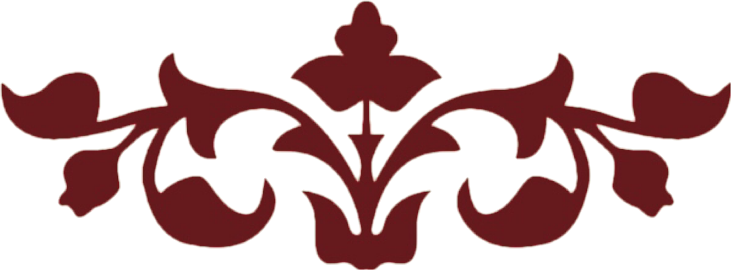
Valentine's Day Kiss
それは始業時間前のことだった。キンブリー少佐はいつものように、窓の外の登庁してくる人々を眺めながらコーヒーを飲み、私は自分の席でベストセラーになった本を読んでいた。
私たちの優雅な朝の時間、それを邪魔したのは、多すぎるノック音だった。立ち上がってドアを開ければ、入って来たのは十人ほどの女性たち。驚愕する私の横を通り過ぎて、彼女たちは一目散に少佐の元へと駆けて行く。そして一言、「ハッピーバレンタイン!」と告げてすぐさま執務室を後にする。
過ぎ去った嵐に目を丸くした少佐の両手には、大量のプレゼントが残されていましたとさ。
「ってことがあったんだけど」
にぎわいを見せる食堂の白いテーブルを一緒に囲むのは、士官学校時代からの友人だ。彼女とは毎日昼食を食べる仲で、話題の事物について語り合ったり、仕事の愚痴をもらしたり、恋愛相談をもちかけあったりする。そして今日も、昼食の日替わりランチである白魚のソテーを食べながら、今朝の騒動を身振り手振り交えて話した。
「そもそもバレンタインってなに? なんの呪文なの?」
そう尋ねると、流行に敏感な彼女はちょっと待ってて、と席をはずした。食堂の隅に設けられたブックスタンドから、一冊の雑誌を抜き取ってこちらに戻って来た。彼女は席に着きながら、ぱらぱらとページをめくる。
「確かこれ……あ、ホラ。このページ」
「バレンタインデー特集?」
見開きいっぱいに、ピンクのハートマークがデザインされたページ。その見出しには大きくバレンタインデー特集と書かれてある。その横には今日の日付である、二月一四日の文字が。どうやら今日は、バレンタインデーという日らしい。
「東の国では、女性が好意を寄せる男性にチョコを贈るんだって。それから別の国では、男性が好きな女性に花を贈るらしいよ。ま、小さな感謝祭みたいなものじゃない?」
「初めて聞いた……」
「アメストリスには全然なじみのないイベントだもんねー。雑誌で取り上げられてから急に話題になったって感じ」
だから少佐にチョコを渡す女性が大勢いたのか、と納得する。つまり、それだけ少佐の隠れファンが多いということだ。
「キンブリー少佐、人気者なのねー。アヤ、油断してちゃまずいんじゃない?」
「今、同じこと考えてた、どうしよう。私もチョコレート贈ろうかな」
確か三番通りにチョコレート専門店があったはず。仕事帰り、そこに寄ってみようかな、と思いつつ、ソテーを口にした。
彼女との昼食を終え、執務室に戻ろうと廊下を歩いているときだった。執務室の方向からやってきたひとりの男性に気づくと同時に目が合った。
彼のことは知っている。私がいつも登庁するとき、門の前で挨拶を交わす人だ。口元にほくろがある、穏やかな笑顔が印象的な人だ。けれど、彼に関する情報はなにひとつ知らない。肩章の星の数から、階級は私と同じ少尉であることは分かっても、所属がどこかも知らないし、名前すら分からなかった。
彼はなぜか顔を真っ赤にしてうつむいたので、微笑みかけて通り過ぎようとした。そのとき、ラシャードさん、と呼ばれたものだから、びっくりして立ち止まった。
向きなおって相手の言葉を待っていると、彼は後ろにまわしていた手をおずおずと前に出す。その手に握られていたのは、一本の赤いバラだった。包装の中には、小さなカードも顔を覗かせている。
彼は突然、受け取ってください、と言って深く頭を下げた。私は戸惑った。親しくない方から贈り物を貰うなんて。
手を伸ばさないでいる私を見かねてか、彼は受け取るだけでいいんです、と懇願するように言った。そこまで言われたら、受け取るしかない。お礼を述べ、そのバラをついに受け取った。
顔を上げると同時に、ぱあっと花が咲いたように笑った彼は、ありがとうございますと言って、一目散に廊下を駆けて行った。これはまるで、今朝少佐の元に来た女性たちみたいだ。まさか、これが例のバレンタインデーの贈り物? 私にくれる人がいるなんて、と信じられない思いでいたけれど、添えられたカードにはやはり“Happy Valentine's Day”と書かれていた。
先の一件で、昂ぶった心が静まるのを待ってから執務室に戻ると、すでに少佐は自分の席に座って貰ったチョコレートをひとつずつ消費していた。デスクの脇にはこんもりとうずたかく積まれたチョコの山がある。今朝よりも高くなっているそれが、昼休憩中も今朝と同じシチュエーションが繰り返されたことを物語っている。
人気者は大変だなあ、と悠長に構えられたら良かったのに。少佐を狙っている女性はたくさんいる、とモヤモヤする気持ちがふくらんだ。
ただいま戻りました、と挨拶した私に気づくなり、少佐はちょいちょいと手招きした。彼は浅いため息をついて、チョコの山を指差した。
「少し、協力してくれませんか。好きなだけ持って帰ってくれてかまいませんよ」
だめです、と首を横に振る。だって、これは少佐宛のものなんだから。女性たちの気持ちが詰まった、愛情たっぷりのそれを、ほかの人が食べるわけには行かない。
「貴女好きだったでしょう、甘い物」
「いえ、遠慮します」
「では、ひとつだけでも」
「だ、だめです!」
「なぜそこまで、かたくなに?」
少佐は眉を寄せてこちらを見る。そうか、少佐はバレンタインデーのことをまだ知らないのか。
「友人から聞いたのですが、今日はバレンタインデーという日なんです。女性は好意を持った男性にチョコレートを渡し、男性は好きな女性に花を贈るんだそうです」
「む。ということはこのチョコレートは……」
「少佐を想う女性たちのお気持ち、ってことですね」
少佐ってばモテモテなんですから、と冗談めかして付け加えたけれど、胸がちくりと痛む。そう、チョコの数だけ少佐を想っている女性がいるのだ。もし、彼が心変わりでもしたら、と思うといても立ってもいられなくなる。少佐を信じていないわけじゃないけれど、どうしても一抹の不安を感じてしまうのだ。
彼は、チョコの山を一瞥して呟いた。
「……そうだと分かっていれば、ひとつも受け取らなかったんですがね」
その言葉を聞いて、嬉しいと感じる自分と、複雑に感じる自分とがいた。もちろん、ほかの女性からのチョコはいらない、と断ろうと考えてくれたことは嬉しい。けれど、ほかの女性の気持ちを無下にはしてもらいたくない。彼女たちだってきっと、たくさん悩んで、勇気を振り絞って渡したに違いないのだから。
とはいえ、彼の気持ちを聞いて、少し安心した。自然と頬が緩んでしまう。
もし、私がチョコレートを贈ったら、喜んで受け取ってくれるだろうか? 待ってましたよと、これが欲しかったんです、と微笑んでくれるだろうか?
「ところでラシャード少尉、その手に持っているのはなんです?」
どきりとして両肩が跳ねた。名も知らぬ男性から貰ったお花だ。
「あ、えっとその……」
「なにか、言いづらいことでも?」
微笑を浮かべる彼を前に、焦って作り笑いをした。言えるわけがない。バレンタインデーを知っておきながら、男性から花の贈り物を貰ってしまったなんて。
けれど、受け取る前にバレンタインデーのそれだと気づいていたら、私だって貰わない。そのことに気づかぬまま受け取ってしまった、と素直に言って、少佐は信じてくれるだろうか?
見せなさい、と笑顔のままで少佐は告げる。だから、恐るおそる手の中にあるものを見せた。
「なるほど、赤いバラとはキザですね。プレゼントされたのですか?」
「……ハイ」
「ほう。確か貴女は言いましたね、今日は男性が好意を寄せる女性に花を贈る日だと」
「……ハイ」
「受け取ったということは、了承した、という意味にとられかねませんが?」
彼のくちぶりがどんどん棘々しいものになっていく。すでに少佐の目の奥はもう、笑っていない。
もう、こうなったら誠意を持って詫びるしかない。私は目をぎゅっとつむって腰を折った。
「申し訳ございませんでした! ですが、そんなつもりで受け取ったのではありません。これがバレンタインの贈り物だと気づいていたら、告白と同じ意味を持つと分かっていたなら、絶対に受け取りませんでした!」
「顔を上げなさい少尉。……では貴女も私と同じということですね? 告白にイエスと言ったわけではない、そういうことですね?」
「そうです!」
「本当に?」
「本当です!」
彼はよろしいと言うように頷いた。普段の微笑が浮かんでいるのを見て、ほっと胸を撫で下ろす。良かった、許してくれたみたいだ。
彼はおもむろに立ち上がった。そして、こちらの方に歩いてくる。
「赤いバラを一本贈る。貴女はその意味をご存知ですか?」
存じ上げません、と首を振る。なんだろう、花言葉のことだろうか。
「ひいきにしている花屋の店主から聞いたことがあります。花の種類、色、本数、組み合わせを変えることで、多彩なメッセージを伝えられるそうですよ」
彼は目の前で立ち止まると、貸しなさい、と告げた。言われるまま、彼に花を手渡した。深い真紅のバラに視線を落とし、彼は続ける。
「私が聞いた話では、バラを一本贈ると、『一目惚れ』『あなたしかいない』という意味が」
花に添えられたカードをすっと抜き取った彼は、“Happy Valentine's Day”の文字を眺めている。
「そして赤いバラには……『あなたを愛してます』という意味があるんですよ」
くるりとカードを裏返し、手書きで書かれたアルファベットと数字の羅列――おそらく贈り主の名前と連絡先――を見て、彼の笑みが一層深くなる。
そのときだった。錬成反応の光と、ボンッという爆発音が響く。
驚いた私は、声を上げて顔を覆った。指の隙間から見れば、花は無残にも爆ぜて、煙を出していた。
「ああ失敬、手が滑ってしまいました」
煙のにおいが鼻をかすめる。花はもう、灰色の燃えかすになってしまった。それに、カードだって跡形もない。
「少佐、どうして……」
燃えかすだらけの彼の両手から、赤い花びらが二、三枚こぼれた。それはひらひらと、涙がこぼれるように落ちていく。
手が滑ったなんて、口実だと分かっている。けれど、なにも言えない。責めることなどできやしない。やはり、彼の機嫌を損ねてしまっていたのだから。
「残念ですが私は、ほかの男からの贈り物をみすみす見逃せるほど寛容ではありません。ですがまあ、罪のないこの花には、少々かわいそうなことをしました」
彼は手のかすをぱんぱんと払い、私との距離を詰めた。にこやかな笑みを浮かべながらも、私が退くのを阻むために、腰に手をまわす。そして、ぐいと引き寄せられ、自然と少佐と密着する形になる。鍛え上げられた少佐の胸板が硬くて、軍服からはかすかに少佐の匂いがする。たったそれだけで心臓がどくんと波打った。
「もちろん、こちらの花にも罪はありませんが……」
顎をすくわれ、深い海のような青の双眸と視線が交わる。見つめていると、だんだん熱に浮かされたような気になってしまう。
「二度とこのようなことが起きないよう、少々罰しなくてはいけませんね」
少佐の唇が、呼吸を奪う。どうして、と尋ねようとしたのに、くぐもった呟きに変わってしまう。
「ん……っ」
このキスに遠慮などなかった。さっそくねじ込まれた舌先が、熱い。逃げたくても後頭部を押さえられていてそれは叶わず、無遠慮な熱い舌にあっという間に絡めとられた。少佐の体温は低いはずなのに、そういうときだけ燃えるように熱いのだから、なにがなんだか分からなくなる。
「……っは、アヤ」
歯列をなぞる舌先のせいで、なにかが背中を駆け上がる。息が苦しい。少佐が好きだ。反省している。許して欲しい。ぜんぶ、奪って。
脚が、がくがくと悲鳴を上げている。立っているのがやっとの状態になると、彼は一層強く私を抱きしめた。まるで絶対に離さないというように、強く。
そうして長いこと、彼に罰せられたのだった。
『仕事帰りに、貴女に渡す花を買いに行きます。一緒にいかがです?』
少佐に誘われ、私たちは花屋を目指して夜の大通りを歩いていた。外灯にほんのりと照らされた街は、心なしか人通りが多く、それも大半はカップルでにぎわっているように見える。これもバレンタインデー効果なのだろうか。
「三番通りにチョコレート専門店があるんです。そこにも寄りたいんですけど、あ、でももう閉まっちゃったかな……」
「この時間ですから、どうでしょうね。ああ、ここが例の花屋です」
少佐の行きつけという花屋は、案外この近くにあった。大通りに面したところで、私も見たことはある。バスに乗って駅まで向かうときに、毎回車窓から見かける店だった。
シャッターが三分の一ほど下ろされているのを見る限り、もう店仕舞いするのかもしれない。少佐は、店の前の従業員さんに会釈をし、店内に入っていく。話し声が聞こえたので、もしかするともう注文してくれていたのかもしれない。
私は、店先に並ぶパンジーやビオラなどの、植木鉢や花壇に植えるタイプの花を中腰になって見ていた。
「いらっしゃいませ。ただ今無料で、こちらのカードをお配りしています」
にこやかな店員さんに声をかけられて顔を上げると、小さなメッセージカードを渡された。開くと、花の写真とともにメッセージがざっと並んでいた。赤いバラは『あなたを愛しています』、白いバラは『私はあなたにふさわしい』……。
「花言葉の一覧表になっております。お花を選ぶ際に、ぜひお役立てください」
そう言って微笑む彼女に、私も笑みを返す。
花言葉、か。花の数だけ、いやもしかしたらそれ以上に、花に託されたメッセージがあると思うと、なんだか素敵に思える。今度、少佐に花を贈るときの参考にしよう。
「お待たせしました」
店の奥から彼が出てきた。手にしているのは白いバラの花束。それも結構な本数だから、思わず笑ってしまった。
「ハッピーバレンタイン、アヤ。どうぞ、受け取ってください」
ありがとうございます。そう言って、とびきりの笑顔で受け取った。
そういえば、白いバラの花言葉は……。
うん、とっても彼らしい。
(了)20170214
(改)20181223