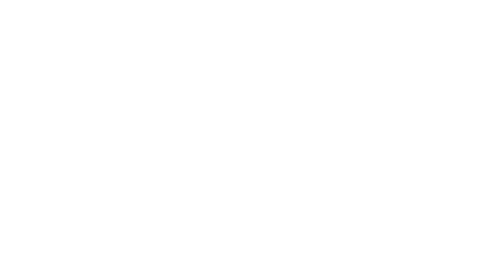
あかいあかい、ふたつの星
島崎は、私が帰宅した後も眠り続けていた。
人の気配のあるところでは熟睡できないとか、そういうタイプかと思っていたけど。まああれだけの傷を負って、その治療のためか体はあれだけ熱を持っていたんだし、いくら超能力者とはいえ昏睡状態になるのも致し方ない。包帯やガーゼを外して、深い眠りにつきながらも時折苦しげに喘ぐ彼の体をお湯で濡らしたタオルで丁寧に拭いてゆく。いや、ここまでする必要あるかな?と思う気持ちもあるけれど、拾ったのはわたしだし、最後まで責任持って世話しないといけない気がしていた。まるでペットか何かを拾ったような口ぶりだと自分で思いながら自分で笑ってしまう——多分、この非現実に体がまだ追いついていないのだと思う。淡々と体を拭き終えて再び傷口を消毒し、ガーゼをのせて包帯を巻くと、買ってきた下着や服を取り出した。昨日ここへ運び込んだときも思ったけれど、気絶した成人男性の体重はいくら鍛えているといっても一般女性には少々重い。もたもたしながらもなんとか服を一通り着せることに成功して、いちど部屋をでた。
キッチンには、当たり前だけれども、昼食のときに放っておいた皿が洗われずに残っている。食器やグラスが2つシンクにおかれていることには、ヨシフくんがよく家に来ていたからもう慣れたと思っていたのに、なんだかそれがひどく奇妙なことのように思えた。やっぱりまだ、非現実から抜け出せてない。皿を洗って、タオルを干しにベランダにでると、「爪」の世界征服宣言なんてはじめからなかったかのように街はいつもの風景を取り戻していた。さっき買い物に行った時にも思ったけれど、終わってみるとなんてあっけないんだろう。繁華街はいつもの賑やかさを取り戻し、帰宅途中の学生やサラリーマンが下の道でスマホを眺めながら歩いている。調味タワーの周辺は破壊の度合いが激しく、また謎の巨大植物のために復旧の見通しはまだまだ立っていないけれど、県境を超えた首都はもう、その機能を通常通りに果たし続けている。
「……さすがに今日は、布団で寝たいよねえ」
ベッドを譲れとは言わないけど。確か来客用のマットレスが押し入れにしまわれていたはず。この状況でお客さんなんか呼べるわけないし、しばらくはわたしが使うことにしようと決めて部屋の押し入れを開くと、マットレスや敷布団、毛布などを一式取り出してリビングへと運んだ。長引くなら簀子か何かをおいて引きっぱなしにしてもいい。さして必要と思っていなかったけれど一応1LDKの家に住んでいたことが功を奏した——いくらわたしだって、テロリストと同じ部屋で眠るのは少し、抵抗があったので。
食事の前にもう一度島崎の様子を見てみるか、と思って再び部屋に入ると、彼が小さく呻き声を上げた。
「島崎?」
寝転んだままの彼の顔がゆっくりとこちらへ向けられる。いつ見ても変わらない、眠っているのか起きているのかわからないその顔。そのまぶたがゆっくりと、開いた。
その一瞬が、世界の全てが止まってしまったかのように永く、感じられた。
まぶたの向こうには暗い闇が広がっていて。
2つの赤い星が、わたしを真っ直ぐに「視て」いた。
「…みょうじさん」
怪しく光るその瞳に吸い込まれそうになって、何も言えずに立ち尽くしていると、彼に名前を呼ばれてようやく現実に引き戻されて、慌ててはい、と返事をしたけれど、心に芽生えた何か不思議な感情——強い衝動のような、憧憬のような、けれどどこか焦燥したような、何かは、消えない。
「看病していただいたみたいでありがとうございます。包帯も取り替えてくださっていますね」
からだも眠る前よりさっぱりしているようです。
心の動揺を悟られたくなくて、表情を変えぬまま「それはよかった」と返したけれど、それに島崎はふ、と小さな声を上げて笑った。馬鹿にするようなものとは違う、どこか純粋に面白いものを見たときの笑い方だと思う。
「ずいぶんと動揺されているようですが、そんなに私の瞳が珍しいですか?」
「どう、かな……その目は何が見えてるの?」
「そうですねえ、まあ、色々と。本当は対超能力者用の能力なんですが、今は能力者の情報を得る必要がないので」
視力を持たない彼は代わりにたくさんの能力を持っている。わたしにはない、たくさんのものを。そして彼の瞳には網膜にわたしが映すものとは違う何かがきっと、映っている。この男の目から見える世界は、いったい、どうなっているんだろう。そう考えて、気を抜けばまた、その赤い瞳に縛られるように、固まってしまう。
その瞳を見つめているだけで、他の何もかもが世界から消えてゆくような。自分の体が、その瞳の向こうへ堕ちてゆくような。そんな感覚が全身を覆った。
「綺麗な、目」
思わずそう呟いたのを島崎が受け取って、驚いたように、その闇が大きく広がった。
「そのようなことは初めて言われましたよ」
——ありがとうございます。
少し前まで島崎が一番言わなさそうだと思っていた言葉は昨日からもう何度言われたっけ。数えてるわけじゃあ、ないけれど。
ふと気がつくと、その赤い光がわたしの目の前で、光っていた——違う、近づいたのは彼じゃない、わたし。いつのまにかベッドの横まで、歩いてきたらしい。そう気づいたのは、彼のまぶたにわたしの指が触れてからだった。島崎は何も言わずに、ただ静かにその赤い瞳を開いて、じっとわたしを見つめている。はっと気がついて手を引いた。
「ごめん、わたしどうしたんだろ…」
ご飯、作ってくるね。
返事も聞かずに部屋を飛び出して、ばたりと扉を閉めた。自分の感情がよく理解できなかった。初めての感覚がどこか怖くてぎゅっと瞳を閉じると、そのまぶたの向こうにぼんやりとまた、ふたつの赤い光が瞬いたような気がした。