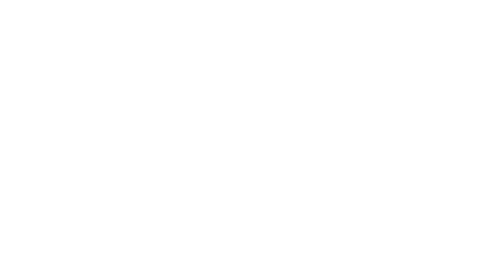
わたしだけがまだ
酷い傷口の数々を見た時から密かに心配していた感染症の症状もなく、熱も次の日には引いてしまって、怪我は数日で落ち着いたようだった。あれだけの多種多様な怪我を負っておきながらその回復力の速さ。もしかしたら超能力者であることと、なにか関係があるのかもしれないけど、医者でもなんでもないわたしにはあずかり知らぬことだった。わたしはただ、食事を作って、ともに食べて、それから隣のリビングに布団を敷いて眠る、それを毎日繰り返していた。あの時以来、彼の瞳を開くところは見ていない。
「島崎は大丈夫なのか、何か不審な行動は…」
「まあなるべく目は離さないようにしてますけど、そうですね。割とふつうです」
いろいろあって休暇は少し伸びたけれど、それでもほんの数日のそれはあっという間に過ぎ去って、「爪」の件などきれいさっぱりなかったことになった公安のオフィスの一角でわたしは「元恋人」と会話をしていた。わたしが島崎を家に入れたことはこの彼と、あとは上司だけが知っていること。
「…何もないんだな?」
「何かっていうのあります?あの人本気で爪に忠誠を誓っていたわけでもないし、わたし殺しても何もメリットありませんけど」
「……そうか」
たった一言そう返して瞳を伏せる彼の中に、心配のほかにどんな感情があるのか、それにはそっと気づかないフリをした。それに満更でもない感情が確かにあったはずなのに、ほんの数日休暇を取っていただけでそれはもう、霞がかったように思い出せない。
――本当に時間だけが理由なのか。心のどこかで誰かがそう、問いかけたような気がしたけれど、わたしはそれにも、気づかないフリ。
溜まっていた書類を片付けながら当たり障りのない話を交わせば、隣の彼と「交際」を始める前の穏やかな日常が久しぶりに戻ってきて、懐かしい気持ちにさえさせられる。「爪」が壊してしまった調味タワーが謎の植物に置き換わってしまったことについては、公安の手に余るとして放置が決まった、などとヨシフさんが話すのを聞きながらキーボードを叩き続ければいつの間にか日が暮れていた。これまでの時間なんてまるでなかったかのようだった。仕事をしていれば気づけばお昼休憩、気づけば退庁時間、気づけば残業。官僚なんて高給だとかキャリアだとかもてはやされるけれど、実際はそこらへんの民間企業も真っ青なブラック企業。日付が回るまで仕事をすることだってまあ、当たり前にあるような体力資本の職場だった。そして今は大きな案件が片付いた直後だから、報告だとかなんだとかで忙しい――はず、だったけれど。
「そろそろ仕事も片付きそうです。残りは明日に回してもう帰りますね」
「ああ、気をつけて帰れよ」
窓からは月が見え、時計は21時を指していた。隣の男はまだ仕事を続けている。
政府が全て曖昧なまま打ち切ることに決めてしまったから、あるはずだった仕事はすべて「なかったこと」になった。「爪」に関わる仕事はいっそ不思議になるくらいに皆無。同じ部屋にいた同僚のほとんどはそれを怪しんでいたけれど、何の権力もない一公務員でしかないわたしは彼らと一緒になんでだろうね?と首を傾げることしかできなかった。
「ヨシフさんは帰らなくていいんですか?そんな忙しいわけじゃないでしょ」
「まあ、俺もあと少しだからな」
なるほど、じゃあ、先に失礼します。そう告げて、背中にかけられた声に右手を上げるとオフィスを出る。隣も向かいも、部屋はどこもまだ明るくて、窓のない廊下を歩いていれば昼間と大差ない。良い意味でも悪い意味でも、いつも通りの日常がここにはもう、戻っていた。エレベータを降りていつものように電車に乗り、いつものように最寄駅へ着き、いつものようにマンションへ入って階段を上がって。
日常に戻ってこれていないのはもしかしたら、わたしだけなのかもしれない。
「おかえりなさい。いつもお世話になっているので今日は夕食を用意してみましたが召し上がりますか?」
ただいま、と声をかけてすぐに返ってきたその言葉に、思わずえ?と瞳を瞬かせた。
――ただいま、の言葉は別に彼からの返事を期待していたわけじゃない。ただ帰宅したことを告げるための言葉、それ以上の意味はなかった。実際昨日までは――まあ体調の問題もあっただろうけれど――わたしのその言葉に返事が返ってきたことはなかった。それどころか家に帰って誰かからおかえり、と迎えられたのはとても久しぶり――高校生以来くらいかもしれない。まして、家に帰ったら誰かが食事を用意して待っている、なんて。確かにダイニングからは美味しそうな匂いが漂っていた。
「もう、食べたの?」
「いえ、先ほど買ってきました」
「でもどうやって、」
「わたしには視力の代わりにちょっとした能力がありましてね」
驚くわたしは再び、その赤い瞳と目が合った。
この瞳には何かが「視えて」いる。そして、彼には先読みの力があるはず。その能力はこんなときにも使えるものなの?どこか拍子抜けしたような思いで、とりあえずありがとう、と笑った。昼食を食べて、それから夕方頃にかるく軽食は取ったけれど、お腹は十分空いている。冷蔵庫にあるもので適当に自炊でもしよう、と思っていたのでたしかにこれはありがたかった。
並べられた中華料理をみて、取り分けようの皿と、それから箸と蓮華をキッチンから持ってきて島崎の座る向いに座って。いただきます、と両手を合わせた。
「この店、繁華街の中華料理屋さん?私すごく好きなんだよね」
「そうでしたか、適当にテレポートして目の前にあった店に入っただけですがそれはよかったです」
それって大丈夫なの?思わず首を傾げたわたしの言いたいことに気づいたのか、島崎はにこやかに感知能力がありますから、ノーマルにバレるようなことはありませんよ、と補足した。なかなか便利な能力をいろいろ持っているみたいで、有効活用しているらしい彼にちょっと羨ましい気がしなくもない。そんなことを考えながら料理を口に差し込めば、程よい辛味と酸味が口の中に広がる。皿に乗せられた料理は二人で食べるとあっという間に消えていった。
「おいしかった。ごちそうさま」
「ええ、私も正直何が入ってるのかよくわからずに適当に注文したものですから、ちゃんと美味しくて安心していますよ」
「……え?」
「なにぶん目が見えないもので。それに手持ちの現金も少なかったので」
「あー…わざわざごめん」
「いえいえ、いつもお世話になっていますから。ああそれと」
家賃です。
ちょっと申し訳ないな、なんて思いで会話していたわたしの目の前に、分厚い封筒が差し出される。え、中身全部お札?何の変哲もない銀行のATMに置かれているあの封筒がこんなに膨らんでいるところなんて見たことがない。おそるおそる中を確認すると、マンションに払っている家賃よりも明らかに多い枚数の1万円札が詰められていた。
「あの、まずうちの家賃こんなないけど…」
「おやそうでしたか、駅からも近いし3階なのでそれなりだろうと思ったのですが」
「それは否定しないけど別にタワマンの40階とかじゃないからさ…」
この人の金銭感覚どうなってるの?今まで一体どこに住んでたの?そもそもこれ、何のお金?テロ活動?「爪」からの給料なの?混乱する頭にはたくさんの疑問符が湧き上がる。では看病もしていただいたのでその分のお金も上乗せされていると思ってください。そうあっけらかんという島崎に混乱は深まるばかりで。
「いや、こんなにもらえないよ」
「いえ、私にはとくに使い道もないので」
どうやら返したところで受け取るつもりはないらしい。お金の出所なんて考えたってしかたない。聞いて答えてもらったって、困るし。ため息をついて考えるのをやめ、お金を全額受け取った。……今日中にコンビニのATMで預けてしまおう。こんな現金ずっと手元にあっても、不安になるだけだ。
「まあ、もう出歩けるようになったわけね」
「ええ、もともと下半身は怪我が酷くなかったもので」
「それはよかった。自宅に帰る?」
「…ええ、そうしたいのは山々ですが、」
実は自宅がなくて。
そう言ってまた笑う島崎に、今度こそ大きなため息を吐いた。