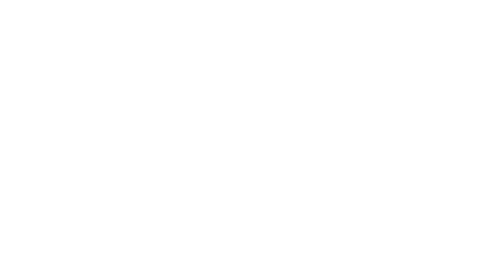
なにも気づかせないで
「…神樹、これかぁ」
久々のヨシフさんとの出張はついこの間までいた場所と寸分違わぬ此処。ほんの少し前の全てがどこか遠い昔のことのように思えて、見渡す景色が懐かしくさえあった。遠くに聳え立つ巨大な植物を除けば、の話だけど。
事後処理、というと少し違うかもしれない。「爪」のことはすべてなかったことになったから。だからこれは別件だけど、その人員としてわたしとヨシフさんを選んでいる時点で「そういう」案件だというのはうっすら伝わってくる。「爪」そのものと関係があるかどうかは別にして。隣の男もどこか困ったような表情でそのブロッコリーを眺めていた。
「…この植物を崇める宗教が、この街で信者を急速に増やしている。超能力がらみでないといいが」
「ヨシフさんはまだしも一般人のわたしに神樹の調査させる上司、何…?」
「そう言うな。お前のことはオレも評価してるんだ」
「そんなこと言われても…」
面倒だ、面倒すぎる。わたしにできることがあるとも思えない。やる気のないわたしの言動にももう慣れたというように、ヨシフさんは行くぞと一言声をかけてわたしを待たずに歩き出す。慌てて小走りでその背中を追いかけた——この人は足が長いからただ歩いてるだけでも引き離されてしまって大変だ。そういえば島崎も背が高いけれど、同じように歩けばそうなるのかもしれないな。彼を連れ立って外出したことがないことに今更気づくのだった。
「爪」の件で最も大きな被害を受けたのは主戦場だったこの調味市、調味タワー周辺だったけれどしばらく訪れないうちに随分とふつうの日々と取り戻しているように見えた。買い物に向かう主婦や、自転車で道の真ん中を駆け抜ける小学生。どこの街にもあるありふれた光景があたりまえに広がっていた。
「二手に分かれよう。何かわかったら連絡してくれ」
「えっ…何かあったら連絡とかできなくないです…?」
「…頼んだ」
今度はヨシフさんが面倒だ、という表情でたしの問いを無視して、商店街の方へと歩き去ってゆく。え、じゃあ結局何かあった場合はどうするんだ……?困惑するわたしを振り返ることはない。ヨシフさんも今回の調査は乗り気ではないのかもしれない。それはそうだろう。あのブロッコリーを見る限り明らかに超自然的な力絡みだし、わたしもヨシフさんもその手の能力に特別の防御手段があるわけではない。人間相手よりよほど危険な仕事だと思う。
「あーあーブラック公務員はやだねー。これ帰ったら業務の続きだしなぁ」
愚痴を呟きながら街を歩く。少し地面が割れたり建物にヒビが入っているのは多少気になるけれど、つい先日まで激しい超能力バトルが繰り広げられていたことを思えばむしろ被害は軽すぎるくらいだと思う。まあ、被害が軽いというのはいいことだから、通りすがる人の顔なんかを眺めながら賑やかな街を歩き続ける。
商店街の終わり、大通りの交差点のそばで背の高い女性が何かを配っているのが目に入った。カゴに無造作に詰め込まれているのは飴のようだった。
「神樹キャンディどうですか?」
神樹キャンディ?
「なんですか?それ」
「我が調味市の名物・神樹の成分を配合した飴です。健康にとってもいいんですよ」
なにその得体の知れないキャンディ。そう思ったことはおくびにもださずにありがとうございます、と言って一つ受け取った。神樹の成分を配合した飴、全く美味しそうではない。でもとにかく神樹関連のアイテムをひとつ手に入れたというのは収穫だった。——街歩いていて何もめぼしいものがなかったらこれを戦果として庁舎に帰ろう。どうせあっちもわたしたちふたりで解決できるとは思ってないだろうし。
そこを通りがかったのは、調味市散歩をはじめて30分くらい経ってからだった。花屋の店先にぼんやりと立っている男の顔をみて思わず立ち止まった。
「…あの、なにか」
「いえ、綺麗な花だなーって。その赤いの、なんていうんですか?」
「ああ、これは——」
花の話を聞きながら顔を再び確認する。
——峯岸。「5超」の一人で、植物を操る人。だったはず。「5超」の人間は皆それぞれに社会復帰をしていて——いや、若干一名ヒモをやっている男がわたしの家にいたような気もするけれど、まあ傷も完治していないし仕方ないよね——確かにこの男は花屋で働いている、そう聞いていた。作戦の間は一度も見かけることさえなかったのにこんなところで出会えるとは。名前はちゃんと聞いてなかったけれど、どうやら説明が終わったのを気配で感じてそれを包んでもらうことにした。どうせなら花束にでもしてもらおう。
「プレゼントですか?」
「…うーん、そうですね。まあ。相手は目が見えないので喜んでもらえるかはわかりませんけど」
「僕の同りょ、いや、知り合いにも盲目の男性はいましたが、花の香りは好きだと言っていましたよ」
「なるほど、香りだけでも楽しめるならいいですね。安心です」
同僚。間違いなく我が家にいるあの男のことだろう。花の香りが好きだなんてそんなロマンチストなところもあったのか。それなら確かに、ちょうどいいと思う。花を選びながら思い浮かべていたのがその男であったことには、気づかないふりをした。
花を包んでもらっている間に店に入って小物を物色していると、店長と思しき人間が神樹の粉、などと何かを峯岸に話しながら飲んでいる。
「…え?」
思わず声が出た。飲んだ瞬間に男の目の色が変わったのを確かに見た。なにか——虚ろな瞳のまま、峯岸に一言二言話すと奥へと消えてゆく。それに気づかない峯岸は不思議そうな表情を浮かべていた。
「あの!」
「あ、すみません。花束、どうぞ」
「え、ええ。ありがとうございます」
2000円の小さな花束。お金を払って店を出て、傍に立ち止まって先ほどの男の様子を思い返し、ポケットに入れた飴を取り出した。この飴にも神樹の一部が入っている、とあの女性は言っていた。
この仕事に就くまでは超能力者の存在でさえ御伽噺のように思っていた。今となってはそれが当たり前の日常の一部で。じゃあ、こんな洗脳の仕方だってありうるんじゃないか?そんな推測が頭の中を巡る。神樹そのものに、何か特殊な力があって。それが、さっきの男のようにこの町中の人を洗脳しようとしているのだと、したら。
ふと顔を上げると、峯岸が店の外へと歩き去ってゆくのが見えた。
あの男も超能力者。何かを掴んでいるかもしれない。少し迷ったけれど、ゆっくりと彼のいる方へと歩き出した。
(……ただの休憩、かなぁ……それとも……)
店のすぐ裏の自販機の前で立ち止まった男。数十メートル離れた別の自販機のそばで立ち止まって飲み物を選ぶフリをしながら様子を伺った。彼は道端に蹲み込んで何かを呟いている。誰かと連絡を取っているのか、それともただ独り言を発しているだけなのかはこの距離ではわからないけれど。ついてきてはみたものの、これからどうすればいいだろう。彼に身分を明かして直接話を聞くのもアリ、だけど。
(まだ……容疑者から外れたわけじゃ、ないからな……)
神樹の成分の含まれたお茶やキャンディ、それに何かがあるとして、それが薬物の類なのかいつもの超自然的な能力の類なのかなんてわからない——まあ十中八九後者だろう。そうなれば持ち帰ったとして何かが解明できるとも思えなかった。峯岸は何か、知っているだろうか。それとも今回の件には無関係、だろうか。さっぱりわからない。
「……だいたいあの人たちは超能力者の犯罪に本気で取り組む気が全然ないよなぁ……」
思わず漏れたぼやき声は賑やかな昼下がりの街並みに溶けて消える。このまま放っておいてはいけないとはわかっていても、取れる手段が限られすぎているのだ。自動販売機で飲み物を選ぶフリをするのもそろそろ限界があるので、適当な飲み物を買って歩き出した。峯岸のいる方へ歩きながら、次は何をしてごまかそうかと考えた瞬間、ぐらりと、峯岸の背中がよろめいた。
「……!?峯岸さん……!」
何かを考えるよりもまず、駆け出していた。
途中で、尾行にバレてしまわないかとか、そもそもどうして倒れたんだと冷静な思考が戻ってくるけれど、一度駆け出したのだからそのまま彼のもとへ向かう方が違和感がないと考え直す。大きな割れ目の入った道のわきで、峯岸は瞳を閉じて昏睡していた。
「あの!起きてください!大丈夫ですか!!」
何度か肩を揺らしたけれど、まるで起きる様子もない。脈拍や呼吸は正常だから、ただ眠っているだけのように見える——でも。別段持病があるようでもない彼がこうして突然昏倒するのは明らかに、普通ではない。ちらりと彼がしゃがみ込んでいたその道を見れば、割れ目の向こうから植物の根が顔を出していた。
「……神樹の……根……?」
植物を操るという。この根を使って何かをしようと、したのかもしれない。あれだけ巨大な植物ならここまで太い根が地面を張っていたって不思議ではない、けれど。こんなところにまで影響が出ているのならさっさと撤去してしまうべきだと思うのに、それがなされていないのはその新興宗教のせいだろう。そして、それはやはり、不思議な力と関係がある。
「……何かあったといえば、あったし。一応連絡するか」
さすがにここで簡単に倒れた彼は9割がたこの件とは無関係だろうなと思う。だから峯岸をそのままにするのは罪悪感があったけれど、ひとまず連絡をしてそれからどこかへ連れてゆこうと、思い直した。救急車が必要なふうでもないし、どこかベンチで休ませておけばたぶん、大丈夫。携帯を開き、連絡帳の一番上に登録されている名前をタップして通話ボタンを押すと、何回かのコール音の後に電話がつながる。どうした、とつい数十分前まで聞いていた同僚の声がスピーカーから響いた。
「……あー、何かっていうか……峯岸を、見つけて」
「峯岸?ああ、『5超』のか」
「はい、それで彼座り込んだと思ったら突然……っ」
くらりと、体がよろめいた。
喋りながら何の気なしにその根に、触れた。愚かな行為だったかも、しれない。
——神樹っていいよね
——うん、最高だよ
頭の中に大きなノイズが響き渡る。神樹、神樹、神樹——
こつんと、音を立てて携帯が手から滑り落ちたことにも、そして、その受話器の向こうから同僚の焦ったような声が聞こえることにも。それからぱさりと、反対側の手で持っていた花束が地面に投げ出されたことにも気づく余裕はなかった。
(誰か、たすけ——)
意識が暗闇に落ちる直前にぱたりと、そのノイズが止んで、それから聴き慣れた誰かの声が大丈夫ですかと、そう叫ぶのを聞いたような、気がした。