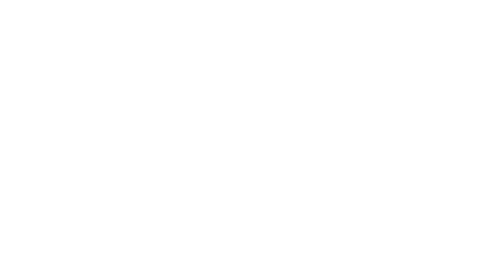
さいごの晩餐
正直に言えば、3度目の邂逅なんてもうないことを祈っていた。けれどそれは、最悪の形で起きてしまった。
「恋人」がまた日本へと帰ってきた。いつものようにバーで待ち合わせ、今度は誰からも二人の逢瀬を邪魔されることもなく、今度は彼の家へ。今はほとんどの時間を海外で過ごす彼の自室は、独身の公務員らしく広くて小綺麗で、けれど少し生活感が薄いと思う。わたしの部屋にはもっと小物とか、消耗品とかが置かれているのに彼の部屋は白い壁に囲まれて、テーブルとベッドと、あと少しの必要な物だけが並ぶだけでひどく殺風景に思える。
「相変わらずヨシフさんの家なんにもないですね〜」
「言ってろ。どうせほとんど使わない家だ」
「とはいえ一応ここが自宅なんですよね?」
じゅうじゅうとフライパンから何かを炒めるような音が響く部屋で、テレビもないのでただダイニングテーブルに座って彼が食事を準備するのを待ちながら、炒め物に負けない声量で会話を続ける。程なくしてその音が消えてしまうと、彼はいくつかの大皿をテーブルに並べて向かいの椅子に座った。両手を合わせてから、その大皿に盛られた色鮮やかな料理を取り分けようの小皿に移してゆく。
「あいかわらず中華料理が上手ですねえ」
「麻婆豆腐は出張中にも少し練習したんだ。アジアンマーケットが近くにあったからな」
「そういう意外と家庭的な先輩素敵ですわ〜」
こういう特に中身のない会話は、わたしは嫌いじゃない。中華料理を作れる「彼氏」なんて結構自慢になると思う。言われる側のヨシフさんだって別に悪い気はしてない、みたいな表情でやめろよ、なんて言ってくるから時折、この人は本当に自分の恋人なんじゃないか、なんて気さえしてくる。
けれどこれは「仕事」でしかないから。不意に会話が止まって彼が真剣な表情を浮かべるので、わたしも姿勢を正す。彼は静かに告げた。
「おそらく、数日以内には動き出す」
「爪」内部の状況や、外国人部隊とよばれる他の仲間になりうる人材を見つけたこと、ボスとも直接会話できる地位にいること。「5超」の能力、顔や名前は把握できていること。そして、実際には破壊への衝動こそあれど、破壊の後のこと、例えば征服した世界をどうコントロールするか、とか、そもそもどんな世界が理想なのか、とか、そういったビジョンがあまりに貧弱な割に力だけは強大すぎるほどに強大なこと。深く眉間に皺を寄せて彼は話し出した。あまりに未熟なその組織が、理念も理想もなく、ただ暴走を続け、そしてまずはじめにこの日本を標的にしている。そのことの意味は彼の表情を見るまでもなくわかった。そしてこの正義感の強い彼がそれに、どれだけの危機感を抱いているかも。
「でも、超能力集団が攻めてくるから防衛体制に入りますなんて言えないんですよね」
「当たり前だ。政府はこの期に及んで超能力者のことを公にするつもりもない」
苦々しい表情を浮かべるヨシフさんは自分の身を危険に晒して仕事をしているのだから、その気持ちは痛いくらいにわかる。わたしだってここでヨシフさんと関わって、明日はそれをそのまま上司に告げなければいけないわけで、リスクは皆無なわけでは、ないし。この後対策を取るにしたって、超能力のことを公にしないと決めてしまった以上は動かせる人員も限られてしまう。
「どうやら総理大臣の誘拐まで考えているらしい」
「は……?正気ですか、いや、正気だったらこんなことできないか……うそー……」
全くもって意味がわからない。総理大臣を誘拐してどうなるんだろう。まあ、話題にはなるかもしれないけど。ああそうか、別にビジョンがあるわけじゃない、この社会を壊したいだけなんだ。それでもあの島崎の——彼には話してないけれど、あの時カフェでみたあの冷たい表情を思い出すと、そのくらいやろうと思えば簡単にできてしまうのだろうし、やろうと思えば平然とやってしまうのだろうとか、そんなことは痛いくらいに理解できてしまう。
——-そういえば。
「明後日、総理が男女平等参画のシンポジウムで講演するんですよね…」
「…それは…」
攫ってくれと言っているようなものでは?
二人の意見が一致して、同時にため息が漏れた。
「おそらく現場に出るのは島崎だ。瞬間移動の能力があれば政府の誰でも好きに人質にできるだろう。政府内部の超能力者の能力などたかが知れている、ろくに使えないのは間違いない。だが俺の能力は島崎のテレポートとは相性が悪い…」
「できること皆無ってわけですか?」
「…当日なるべく内部から切り崩せないか探ってみよう。なまえ、お前は総理のそばにいてくれないか」
「…超能力者のバトルのなかで無能力者にできることなんてあります?」
「お前のその判断力を買ってるんだよ、どうせ公務員エスパーなど爪の幹部の前では無能力者も同然だ」
思わず瞳をぱちぱちと瞬かせてしまう。わたしのこと、そんなに評価してたんだ。さしてやる気があるわけでもないし、人知を超えた能力を持っているわけでもないし。この人と恋人ごっこをやる以上になにか組織に貢献できたと思ったこともない。ヨシフさんの中でのわたしの評価は一体どこから来ているんだろう、と首を傾げてしまう。麻婆豆腐を口に入れて咀嚼しながら、まあでも、期待されてるからにはやらないといけないよね、なんて。わたしの人生はだいたいいつも、そんな感じ。
「まあ、できるかぎりなんとかしますよ」
よろしく頼む、なんてヨシフさんは固い人だなあ。そう思ったけれど、それから優しく笑った彼がわたしの頭を撫でるのが心地良くて、何も言わずにそっと、瞳を閉じた。