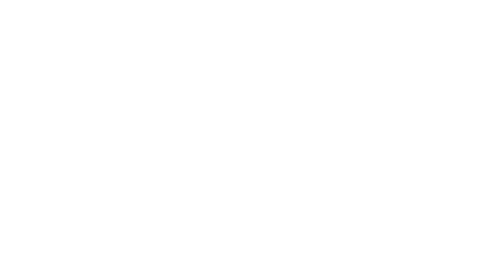
彼の考察
爪に潜入した公務員エスパーであるこの男は、自らの「恋人」である女を彼女自身が思う以上に高く評価していた。それは決して、彼女と「交際」することで得られる付随的なもの——別に本当に愛しているとか、そういうわけではなくても本当なら不要な行為にも付き合ってくれるとかそういうこと——ではなくて、もっと現実の仕事ぶりについて。
「爪」の本部となった調味タワーの男子トイレの一室で、耳元で響く小さな声に、同じように小さな囁き声で返す。
「総理が官邸を出ました。とりあえず総理の服の袖に発信機をつける許可をいただいて一つつけてあります」
「そうか。まあ最終的には此処に連れてこられるのだろうが、その途中で阻止できるようならできる限り阻止してくれ、ただし他の護衛には機密で頼む」
「無茶言いますよねヨシフさん…わたしには何の超能力もないって知ってますか…」
「いざという時のお前の頭の回転を評価しているからこそだ。頼んだ」
「まあ期待はしないでください…がんばります…」
聞こえる声は気怠げで、それが却って彼を安心させた。ぷつりと通話が途切れて、はあ、と小さくため息をつく。政府が隠すと決めた超能力に関することがらについて、それを知っているのは仲間の中でさえそう多くはない。特に必要だと認められたごくごく一部の人々——例えば彼女のようなサポート役だとか、直接指示を出す上司だとか——以外の人間はヨシフのことさえただの潜入捜査官だとしか思っていない。だから、この非常事態にあっても、彼が頼れる人間は非常に限られていた。そのうちの数少ないひとりが、みょうじなまえであって。彼は彼女の徹底した演技力に内心舌を巻いていた。外を歩くときはたとえ彼が共にいてもいなくとも「何も知らないOL」を演じ抜いて、予期せぬん訪問者——例えば糸目の幹部——が現れたとしても決して揺らぐことがない。
「ヨシフ、いないのか?」
「ああ、ここだ、すまないな」
彼が味方につけた男の声が聞こえて慌てて個室の鍵を開いた。彼らは決して頭は良くないが、それは5超の彼らも、またトップであるあの男だって変わらないと、少なくともヨシフや情報を受け取ったなまえは分析していた。ただ——そう、己の力を認めてもらいたいだけの、子どものような存在。外国人部隊の彼らもまたそれは、変わらない。
調味タワーの中には今はもう、「爪」の構成員しか残っていなかった。それは完全な味方がこの場には一人もいないことを意味していたが、文句は言っていられない——言いたくなる気持ちは十二分にあるけれども。
(俺のこれはそうまでして隠さなければいけないものなのか……?)
ヨシフは内心思うが、彼に何かを変える権力があるわけではないし、またこの状況で市民を守るためにはここで文句など言っていられない。ここまできたらもう、やるしかなかった。総理大臣の方には「恋人」が、やはり同じように体を張って護衛をしているのだし。
「行くぞ」
「ああ、そうだな」
暴れられるのか、楽しみだな。何も考えていなさそうな男の顔が楽しげに歪む。それを見てヨシフは、心の中で呟いた。
——こちらはそろそろ始まりそうだ。なまえ、頼むぞ。
これを逃せばもう、チャンスはない。「爪」に日本が壊されるか、それとも彼らがこの国を守り切れるのか、その瀬戸際に立っている。なまえもきっと、内心では愚痴を溢しながらも表面上は真面目を取り繕って状況を見守っているだろう。彼女のその、自らの容姿やふるまい、話術、すべてを使って超能力でさえどうにもならない問題を平然と解決するところが彼は嫌いではなかった。そしてやる気がないとかなんとか言いながらも結局、何も言わずにスパイと本部の中間、危険なポジションに収まっているところも。そうしてその限界を見せない彼女の姿を見ていると、こんな状況にあってもなまえならどうにかしてくれるのではないか、と思わせられた。
それが叶わぬまま終わること、そしてこの事件が民間のエスパー、それも男子中学生によって終わることになるなど、この時の彼はまだ、夢にも思っていなかった。