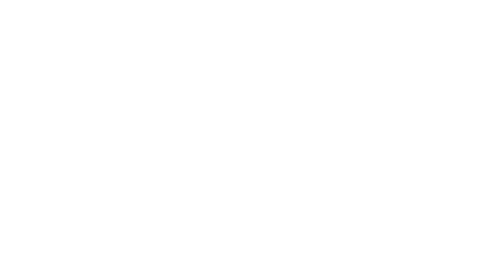
尻拭いなんてむいてない
「総理が会場に到着しました」
トランシーバーからの報告を聞いて、パソコンに表示される位置を確認する。高性能なGPSのおかげで、画面に表示された地図には誤差数メートルの精度で総理大臣の立っている場所が表示されていた。「爪」がアジトとしている調味タワーからはかなり遠く離れているけれど、相手がテレポーターである以上その距離にはなんの意味もない。そして相手がテレポーターである以上わたしにできることだってそう多くはないと思う。せいぜい、一生懸命頑張って総理大臣をお守りするくらい。なんだか小学生の感想文みたいだ。実にばかばかしいと思う。
「超能力者相手にどう戦えって言うんだろう…」
思わずそう、ボヤいてしまう。黒塗りの車の運転席に座って、窓から見える爽やかな青空を眺めていた。どんなときでも広がる青空を眺めていると、なんだか全てのことが些細なことのように思えてくるから、好き。……些細なことだったら、よかったんだけどなあ。視界の端を一台の車が走っていった。
「…ビンゴかな」
トランシーバーの向こうに一応短い報告をすると、了解、と一言告げられる。一体何を了解したんだろう。そっちが問題なければこっちが動く必要はないんだけど、という本心は間違ってもトランシーバーへは流せない。
タワー内部には突発的な戦闘などのリスクがあるから、状況の把握できない島崎は恐らく、人質を無傷で確実に運ぶために調味タワー近くの空き地か公園を経由するだろう、と予想していた。実際ヨシフさんは内部でクーデターを実行中のはずだし、少なくともその間は調味タワーへ総理大臣を入れることはないだろう。一瞬その「彼氏」の顔が頭をよぎって、大丈夫だろうかと心配になってしまうけれど、すぐに首を振った。
「……まあヨシフさんがどうであれ、総理大臣はこっちでどうにかするしか、ないもんね」
わたしたちはただ、できることをするだけ。そもそも連絡さえ取れないんだから、これ以上考えたって仕方ない。フロントガラスから見える車は右折して姿を消してしまう。あっちには駐車場と公園があるけど、どっちだろう。公園の方かな、と考えながらイヤホンから流れる会場の様子に耳を澄ませた。動揺が伝わってくるのになんだか、脱力してしまう——能力者の数が少なすぎるんだ。警護についている人自体はたくさんいるけれど、超能力者、それも「爪」の幹部相手に事情を知らない一般人を何人置いたところで焼け石に水。
「……あらあら」
銃が効かないとか、先読みがどうとか、パニックになっている会場に思わずそう呟きながら額の汗を拭った。此処にいるのはわたし一人だけ——此処に待機することに意味があると、そう分かるには超能力の存在を知っている必要があるけれど、そんな人はわたしの他にそう多くなかった、大変残念なことだけど。
そして次の瞬間、会場を映していた地図から総理の姿が消えて代わりに、現在地周辺を映す地図に白い円が、表示される。
「…!」
ゴクリと唾を飲み込んだ。瞬間移動。聞いていた通りに文字通り一瞬で、県境を超えてここに。そして彼には他に、人の動きを先読みする力があるという。やっぱりだめだったか、という思いと、あの場の能力者に無理だったならそれはもう無理なのでは、という半ば諦めに近い思いとが交じり合って、一瞬思わず空を仰いだ。相変わらず腹立たしいくらいに青々と晴れ渡っている。
「ああもう…やになっちゃうなぁ」
スーツ姿とは言え、パンプスはもう脱いでスニーカーに履き替えてある。スーツもスカートではなくパンツスタイルなのはまあ、こういう時のためだった。パソコンを閉じて助手席に投げてから、車をでる。彼らがいるはずの場所から、大きな音とともに煙が上がったのが見える——仲間への合図か何か?それともなにか、揉め事?急いで向かえば、すぐそばにあるその公園には島崎と総理の他にもう一人、少年がいて島崎と向き合っていた。その雰囲気は到底仲間同士には見えない。
「…あの少年は…?」
感知能力が高いという島崎だが、わたしの気配には気づいていないようだった。そして向かいああう少年も総理大臣も、おそらくわたしには気づいていない。なるべく息を潜めて見守っていれば、少年の背後から突然大きな炎が燃え上がった。思わず両手で口を押さえてその様子を見守る——明らかに超自然的な能力を自在に操る彼もまた、超能力者だろう。けれど、まだ中学生くらいなんじゃなかろうか。そもそもあれは「爪」の仲間割れなんだろうか、それとも「爪」でも政府でもないなにか、第三勢力なんだろうか。
(……まあ、今はそんなことを気にしてる場合じゃないか、)
わたしにできそうなことはといえば、あの少年が島崎に隙を作ることを期待することと、その隙を利用してどうにか総理大臣を奪還すること。いや、難易度高すぎでは。公務員ってこんな職業だったっけ。そもそも目の前の戦闘だって明らかに少年が劣勢だ。純粋な戦闘への慣れ具合でいえば、大人である島崎に軍配が上がるのは仕方のないことだと思う、けれど。
「キミは多彩だな。」
内股で構えていた少年が正面から殴られて気を失ったのはそれからすぐのことだった。
——これ以上待っていても仕方がないか。覚悟を決めて懐の銃に手を伸ばす。
次の瞬間、パン、と大きな音が静かな公園に響き渡った。それに驚いたように総理が振り向き、一瞬遅れて撃たれた男ーー島崎が振り返る。顔を顰めていたのは一瞬のことで、すぐに瞳は閉じたまま驚いたような表情を浮かべた。
「…おや」
「どうもお久しぶりです。2度ほどお会いしたけれど覚えてますかね」
「……ええ、もちろん。お久しぶりですね、みょうじさん」
血がとめどなく流れる左腕を抑えることもなく、ぼたぼたと滴らせながら島崎は、痛みなんて感じないとでもいうようににこりと笑ってそう、わたしに声をかける。まるで道端で偶然旧友に会ったかのような軽い響きにむしろ、緊張が高まってしまう。
「まさか無能力者がここにいるとはね。油断しましたよ。しかし恋人は世界征服に忙しいはずですが——」
——ああ、お二人ともそちら側でしたか。
その言葉が背後から聞こえて反射的に左肘を後ろへ突き出した。予想通りにそれは両腕で防がれてすぐ、正面にテレポートした彼の腕を強く蹴り上げる。再び驚いたように右手を抑える彼はやはり、前情報とは異なってその攻撃に傷を負っているように見えた。
「おや、意外ですね。戦えるんですか」
「公務員ってのは結構大変なんですよ。体鍛えたりスパイやったりね」
武術の経験があるわけではない、らしい。だからたとえわたしの動きが先読みできたって、そこから自然に導き出せる反撃以上のことはできない。そうなれば必然的にわたしの方も、彼の動きがある程度予想できることになるし、なぜかはわからないけれど、予期せず負う怪我を避けることも、できないようで。左足を突き出せば後ろへテレポートするのでそのまま後ろに回転して右腕を突き出せば、やはり頰に直撃し、傷がまた一箇所増えて派手に転がってゆく。
「彼氏」の能力も使い勝手がいいとはいえないなと思っていたけれど、この男のそれもまた万能ではないようだ。よかった、無能力のわたしでも全く役立たずというわけではないらしい。
「総理、大丈夫ですか」
「あ、ああ…」
一瞬離れた隙に総理の元へと行き状態を確認する。動揺しているものの怪我はないようだったのでほっと安心する。何かあれば処分を受けるのは部下や自分ではなく「彼氏」なので。
「おやおや。そちらへ行かれますか」
「し、まざき……!」
それなりの怪我を負っているはずなのに余裕たっぷりの声に、導かれるように顔を上げて瞳を、見開く。誰かは知らないけれど、つい先ほどまで戦っていたあの少年を両腕で抱えた島崎が、不敵に笑っていた。
「……!なにを……!」
「私の任務は総理を無傷で連れ帰ってくることでしてね、こちらの少年の、例えば生死なんかはこの任務の成功の可否には全く関係ないんですよ。言ってることわかります?」
政府の皆さんは総理大臣奪還の方が、市民の命より大切ですか?
思わずキッと島崎を睨みつければ、こわいですねえ、なんてさらに楽しそうに笑う彼。隣で腰を抜かす総理は相変わらず島崎に怯えている。なんて面倒な仕事をさせられてるんだろう、これが終わったら絶対に転職する、もしくは休暇をとるぞと何度目かの現実逃避に走りかけたけれど、どこに逃避したって現実は変わらない。どこにでもある小さく平和な公園にひどくミスマッチなこの光景が消えるわけでもなかった。
「とりあえずこちらに銃を投げてくれません?市民の命が惜しければ、ですが」
こんなわかりやすい脅迫に、わたしは従う以外の選択肢をもっていない。舌打ちをして銃を投げ出した。その瞬間、再び島崎の姿が消えて直後、背中に強い衝撃が走る。蹴られた、と即時に理解したけれどもう、遅い。
「なかなかよくやりましたが、経験不足でしょうか。それとも市民一人の命を惜しんだから、ですかねえ?」
頭から勢いよく滑り台に飛び込んで、激痛で遠のきそうな意識を必死につなぎとめる。その向こうから響いた冷笑的な声に開いた口からは呻き声しか、でなかった。どうにか起き上がった頃にはもう、島崎はいない——隣で座り込んで怯えていたはずの、総理も。
公園には私と、気を失った能力者の少年だけが残されていた。