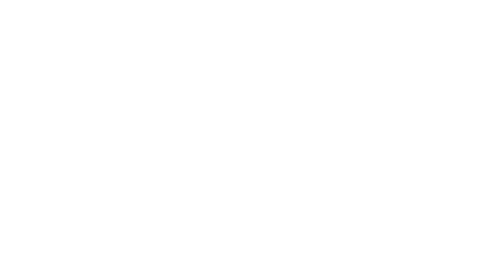
嘘ばかりの世界の片隅で
「総理も守れず、タワーは占拠され内部破壊工作も失敗、打つ手なし、ってことかな?」
「まあ平たく言えばそうなりますね」
超能力を公にしないとか決めた時点でもう、見えていた展開だったとは思うけどな。デスクの向こうの上司は頭を抱えていた。もしかしたら叫び出したかったのかもしれないけれど、此処に立っているのは貴重な公務員エスパーの中でも最強の力を持ってスパイ活動に勤しんでいた男と、その男とこの上司の間のパイプ役というまあまあ危ないポジションについていた女の二人。言ってしまえば今回の件で一番仕事をしたのは流石にわたしたちだと思うし、上司もそれがわかっているから何も言えないのだろう。まあ、怒鳴ったところで現実が変わるわけでもないし。
「…この後2時間後に対策会議だ。それまで休んでいていい、夕食を食べて戻ってきた方がいいよ」
上司は眼鏡を外し、瞼を腕で覆いながらもかろうじてそう発した。窓からは夕日が差し込んでいる。超能力という国家機密に関わる案件だからか、この場に残っているのはわたしたち3人だけで、オフィスに並んだ誰も使っていない灰色の机を夕日が赤く染めていた。もうじき日も暮れてしまうだろう。今晩は家に帰れないかもしれない。だいたい帰宅をあきらめて対策会議なんかしたところでどうにかなるとも思えないけれど、市民、いや国民、世界中の人々の命や安全がかかっている以上誰も簡単に諦めるわけにもいかなかった。
かしこまりました、と上司に頭を下げて夕暮れのオフィスを出る。二人でエレベーターに乗り込むと無言で、ボタンを押した。
「ラーメンでいいか?」
「豚骨がいいですねぇ」
いつもの会話。いつもの店。ビル内の地下にあるラーメン屋でぼんやりと麺をすする間、わたしたちの間に言葉はなかった。彼がスパイであることが相手にばれた以上は「わたしたち」の関係ももう終わり。ラーメンにニンニクを搾りながら、これまでの日々のことを思い返していた。定期的に会って、海外出張にゆく彼を見送って、また帰国したら会って、それを繰り返してもうそれなりに長い時間、本物の恋人のように過ごしてきた。家の外ではいつもこの人のことを恋人と思いこんで生活していたし、これまでの日々の中で彼の些細な癖とか、好きな食べ物とか、仕事の上だけでない彼のパーソナリティについて、もうたくさんのことを知っている。
「ごちそうさまでした」
ぱん、と両手を叩いて箸を置いた。隣ではすでに食べ終わったヨシフさんが、何も言わずに水を飲んで待っていた。ちらりと此方を見ると無言で立ち上がるので、わたしもそれにつられて立ち上がる。
「2時間あるって言われましたけどどうしましょう?正直動くのも面倒なんでわたしは部屋に戻って待機してますけど」
一応年上なので「恋人」でない間は最低限の敬語を使うけれど、それもだんだんと崩れかかっていて、けれどお堅いはずのこの人はそれにも別に何も言わない。ラーメン屋で過ごしたのはせいぜい40分やそこらだから、あと1時間以上は暇だということになる。ここにきたのと全く同じ道を二人で歩いてゆく。他の省庁はふつうに仕事をしているからか、公安のあのフロアとは違って人通りのある地下を抜けてエレベーターの前へとたどり着いた。
「…オレも行こう」
それっきり私たちは話すのをやめた。登り続けるエレベータの中でも無言が続いて、そうして20階に出たところで初めて、彼から口を開いた。
「この1年、色々と迷惑をかけたな」
「えっいや、別にそんな…此方こそいろいろご迷惑をおかけしました…?」
エレベータホールの前には誰もいない――このフロアは今「爪」対策のために貸し切られているから、オフィスに限らずフロア全体に関係者しかいないとか、そんな状況になっていた気がする。関係者というのは超能力者か、無能力者でもその存在を知っているごくごく一部の人たちのことで、それはこの庁内でもほんの十数人。そんなんだから失敗するんだとぼやきたくもなってしまう。ヨシフさんがエレベータ前に設置された小さめのラウンジの壁に寄りかかってタバコを吸い始めるのを横目に、乱雑に置かれた椅子に座った。
「お前の自由を奪ってしまった挙句何もできなかったな、オレは」
「いや、ヨシフさんがいなければ公安も本当にどうしようもなかったと思いますけどね。自由がないのはいっしょでしょ」
懺悔しているのかもしれないと思った。
「爪」には、その能力ゆえに社会に溶け込むことのできなかったものたちが集められていた。そして能力がなくとも社会に溶け込めなかったものたちも集まって、彼らにはなんらかの方法で後天的に超能力が与えられていたらしい。そして目の前で黄昏るこの人も、生まれながらの超能力者。公務員エスパーが少ないのは、超能力者が少ないからではない。超能力を持ちながら、それを国のために使おうと考える人間が少ないから。
「…これから、どうなるだろうな」
「わかりませんね。意外と民間のエスパーがひょいっと倒して終わりかもしれませんよ」
彼の言葉に脳裏に浮かんだのは、昼間出会った金髪の少年。そして二人の男。あの話は結局、誰にもしていない。上司にも、この人にも。わたしの言葉を冗談と受け取ったようで、白い煙が彼の静かな笑いに合わせて何度かもくもくと舞い上がって消えた。
「吸うか?」
少しの無言を経て再び口を開いた男はそんなことを言う。別に吸わないわけではないけれど、普段から積極的に吸うというわけでもなかった。この人みたいにこれが何か不思議な力になったりするわけでも、ないし。まあでも今はタバコでも吸って、気持ちを紛らわせるのもありかもしれない。椅子から立ち上がって隣へ歩み寄ると、前に吸った時と同じ銘柄のタバコを、同じ指から受け取った。ああそうか、わたしがタバコを吸う時っていつも、この人から誘われる時だ。いつもと同じ指が、同じライターでタバコの先に火をつけた。
隣に立つこの人は背が高くてがっしりとしている。タバコを吸う指はすっと細くて長いのに、その腕はいつも力強く私を抱いていた。それももう、おしまい。
――正直に言えば、情が全くないわけではなかった。
もともと恋人がいたわけでもないし、作ろうとも思っていなかったから引き受けたこの役割。お互い困ることもないし、どうせ泊まるのだからと、流れるように体を重ねるようになったのは「交際」を初めてから1ヶ月も経たないうちで。それからはまあ、大人の付き合いなのでそれなりに。この人との距離が単に職場の同僚というよりもずっと近いのはそれが、当たり前の距離感だったから。うまく終われば流れで交際をつづけてーー結婚するんじゃないか、なんて、そんなことも思っていた。相手にその気がないわけでもないだろう、というのはなんとなく感じられることだ。例えば、ふと隣を見上げた時の、その瞳の色から。
「…なまえ」
「…仕事中ですけど」
咎めるように言ってはみたけれど、そんな予防線に何か意味があるわけではない。わたしのそんな心情にだってきっと気づいている彼は、瞳を閉じてタバコを口にくわえる。やがて白い煙とともに、長いため息を吐き出した。もう一度その瞳がわたしの方へと向けられる。何かを言おうとしている、きっと。
「お前は、」
そこで、彼の携帯が突然着信を告げた。虚をつかれたように瞳を見開いた彼にどこか、名残惜しいような、残念な気持ちが心に湧いた。こんな時間に一体なんだろう。相手側の声は聞こえないけど、上司かな。何かあったんだろうか。そう思って見ていれば、携帯を開いて通話を始めた彼の表情はみるみるうちに驚愕のそれへと変わった。今どこにいるとか、そんな会話を少しした後に通話を切ると、次の瞬間にはもう、仕事の時の顔をしていた。
「…今すぐ会議室へ向かう。みょうじもきた方がいい」
「えっまだあと1時間…」
「事情が変わった、急ぐぞ」
――あの「民間のエスパー」が、本当に「爪」を壊滅させたのだと分かったのはそれからすぐのことだった。