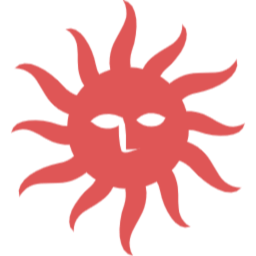
11
「ナマエ、ショーヨーに好きって言ったんだろ?」
楽しげに言うエイトールの言葉にフォークを持つ手が止まる。私が何か言うよりも先に、ニースが「どういうこと!?」と目を見開いて私を見る。
ニースがエイトールにプロポーズした翌週、私はニースに誘われて二人の家に来ていた。その言葉はご飯を食べている最中の事で、むせ込みそうになるのをなんとか耐えながら私は水を飲み干す。
「い、いや、わりとラフな感じで言っただけだから。そんな大々的なことじゃないし。え、翔陽から聞いたの?」
「聞いたっていうか⋯⋯珍しく相談したいって言うから、話聞いてみたらそうなんじゃないかって俺が思っただけ」
「相談⋯⋯」
「ショーヨーは友達の話にしたかったみたいだけどバレバレだし、わかりやすいし、ああこれはナマエと何かあったなって思ったわけ」
「何も聞いてないわ、ナマエ⋯⋯」
話がややこしくなるよりは先に全部伝えたほうが良いと判断した私はニースとエイトールに先週の出来事を話す。ふたりと別れ、翔陽と共に並んで歩いた帰り道の事を。
「まずね、日本だと付き合う為には告白が必要なの。ムードだけじゃ付き合ったにはならなくて、明確に互いが好きって言って恋人関係が始まるのね、大方は。もちろん中にはただ伝えるだけでいいってパターンもあるんだけど、あ、私はどっちかと言えばこのパターン。で、なんていうのかな⋯⋯あの時は言わなくちゃいけないっていうか、言わないほうがどうかしてるって思っちゃうくらいに気分が高揚してて? ふたりのこともあったし。だから翔陽には好きだよって言っただけ」
ニースとエイトールは顔を見合わせ苦い顔をした。文化の違いは時々、どう説明しても伝わらないものがあると私はもうすでに学んでいる。
「あー⋯⋯ふたりはじゃあ付き合うわけではないのね?」
「うん」
「Ficante?」
「もっとないよ!」
文字通り私が翔陽に告白しただけであるということを理解した2人は悩まし気な顔をするだけだった。
棚に置かれたウェディング雑誌。テーブルにあるパンフレットもきっとその類のものだろう。幸せの真ん中にいる2人にこんな微妙な話をするのも良くなかったかなと思った時、エイトールは言った。
「そうだ。ショーヨーも呼ぶ? バイトあるって言ってたけど夜ならフリーになってるかもしれないし」
「えっ」
「ナマエが嫌なら呼ばないけど、ショーヨー次どんな顔してナマエに会えば良いか迷ってたみたいだし、一緒の時のほうが気まずくないだろ?」
翔陽がエイトールにどんな風に相談をしたのかはわからなかったけれど、せめてあの時の言葉が翔陽にとって迷惑でないことを願う。
「じゃあ⋯⋯翔陽が嫌じゃないなら⋯⋯」
エイトールはにこやかにスマホを操作するだけだった。
「ハッ名前がいる⋯⋯!」
私の顔を見るなりそう言った翔陽は次の瞬間、ロボットのように固まって「コ、コンバンハ」とかろうじて出したのであろう挨拶を口にした。
「こんばんは、翔陽」
伝えたことに後悔は何もないけれど、もう少し考えてから言ったほうが良かったかなと心が曇る。
「ショーヨー夜ご飯食った? ニースが作ってくれたハバーダあるけど食う? あ、ポンデケージョもある」
「えっ! 食う!」
「ナマエもプジンいる?」
「いる!」
エイトールの声掛けに対する返事に、私と翔陽は顔を見合わせる。食欲旺盛な2人の日本人。それが多分可笑しくて私達は困ったように笑いあえた。ようやくまともに翔陽と対面できたような気がして安堵すると同時に、少し残る緊張がスパイスのように作用していた。
「私がいたら来ないかなってちょっと思ったから翔陽来てくれてよかった」
「えっなんで?」
「この前のことがあるからちょっと心配だったんだ」
思い出させるような私の言葉に、翔陽はわかりやすく頬を紅潮させた。
「アッいやアレは⋯⋯ていうか名前がいるの知らなかったからビビったけど、そんな避けるようなことはしないし⋯⋯ンンッでも待って俺今なんかちょっと緊張してるっぽい気がしなくもない⋯⋯」
「素直か」
ああ、でも大丈夫だ。緊張はしても気まずいということはないだろう。確信できて私は笑いかける。
「普通にしててよ。ね、翔陽」
「ウ、ウス!」
私の確信は間違ってはいなくって、4人でプジンを食べる頃、時間がほんの少しだけ戻ったように私と翔陽はいつものように笑いあえていたのである。
(21.03.02)
※ハバーダ⋯⋯牛テールの煮込み料理
※ポンデケージョ⋯⋯チーズパン
※プジン⋯⋯ブラジルのプリン