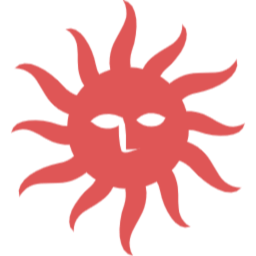
13
ビーチ沿いを歩くときにビーチバレーに目が引かれるようになったのはきっと翔陽のせいだ。その中に少し小柄のオレンジ色の髪の毛の人がいないかどうかを探すようになったのもそうだ。実際、翔陽の姿を見つけたことは1度もなかったけれど、水面が太陽の光で照らされて光り輝くのを見るたび私の心は高揚した。
『電気代の請求きた!』
海辺の風を浴びて地下鉄の入り口へ向かおうとした時、翔陽からの連絡は届いた。11月半ば。今日もリオデジャネイロは変わらずに蒸し暑い。請求書の写真が添付されていて『ペドロと割り勘!』という文字になんだか私は笑ってしまう。
『私も帰ったら郵便受け見てみる!』
『帰ったらってことは今、外?』
『うん』
『マンゴーいらない!? 安いからペドロと大量に買ったんだけど食べきれなくて今困ってる! 近くで会えそうなら持ってくけど、どう?』
瞬きを数回繰り返した。マンゴー。食べきれない。気の抜けるような笑い声がついもれてしまう。
ブラジルは一年を通して気温がほとんど変化しないから南国フルーツの供給が安定している。日本では値が張るようなフルーツもここではとても安く購入できてしまう。だから翔陽の気持ちもわからなくないのだ。つい買っちゃう。私もこの前ジャックフルーツを買いすぎてニースに助けを求めたことを思い出しながら人の邪魔にならないところで立ち止まり返事をした。
『いる! マンゴー好き! これから地下鉄乗って帰るところだったから翔陽のとこの最寄りまで行くね』
地下鉄への入り口はそのまま、方向だけを変えて地下を走る電車に乗り込む。車両には所々消されない落書きがあって治安の悪さを物語っている。もちろん普通に生活する分には命を脅かされるような事件には巻き込まれないけれど、そうやって日本と比べたときに感じる治安の悪さは私を逞しくさせた。
鞄がちゃんと閉じられているか確認してしっかりと抱きしめる。最寄り駅まで乗り換えなしの30分。電車の中でうたた寝をしてしまう私はもういないのだ。
『駅まで着いたよ』
地上に出てすぐに翔陽に連絡をとる。最寄り駅がここだという事は聞いていたけれど実際に翔陽が住んでいる家がどこなのか、具体的には知らない。
『今行く!』
自転車に乗って街を軽快に走る翔陽が思い浮かぶ。Tシャツの裾がめくれて見えるインナー。揺れる毛先。翔陽は知らないだろう。私がそんな風に翔陽の事を思い出すことを。思い出して口角が上がってしまうことを。
「名前」
約5分ほど待っただろうか。後ろから名前を呼ばれて翔陽が着いたのだとわかった。振り向いてその姿を視界に入れれば、ほらやっぱり。自転車だ。
「え、なんで笑ってんの! 俺、格好変!?」
「ううん。違う違う。翔陽多分自転車で来るんだろうなって想像してて、そしたら自転車だったら正解したなって。部屋、ここから近いんだっけ?」
「歩いたら15分くらいかな」
「そうなんだ。私ここで降りたの初めてだけど結構いろいろお店あるんだね」
「安いスーパーあるから助かってる! 安すぎて今回はマンゴー買いすぎたけど」
「あはは、そうだった。マンゴー好きだから嬉しい。声かけてくれてありがとう」
そう言って笑いかけると私と目を合わせて会話をしていた翔陽が一瞬、空気を止めたように黙って私を見た。何か思考を巡らせるような顔つきに私は首を傾げて翔陽の名前を呼ぶ。
「翔陽?」
「エッ⋯⋯あっマンゴー!」
我を取り戻したように翔陽は背負っていたリュックを前にかけて中からマンゴーの入った袋を取り出した。想像よりも袋に詰められているマンゴーに少し怯む。この量、毎日2回はマンゴーを食べることになるかもしれない。
「俺がマンゴー箱買いしたらペドロも箱買いしてて今マンゴーだらけ」
「部屋がいい匂いしそうだね」
「最近部屋が甘い匂いすると思ってたけどこれか!」
ずっしりと袋に詰まったマンゴーを受け取る。
「マンゴーって言ったら完熟された甘いマンゴーがそうと思うけど、タイだと青いマンゴーのほうがよく食べられてるんだって。かたくて甘酸っぱくて、ナンプラーとかにディップして食べるんだって。タイの子が言ってた」
「へー!」
「ジャムにしてもいいし、ジュースにしてもいいし、案外すぐなくなっちゃりして」
「ジャムは盲点だった⋯⋯!」
「私もめんどくさがってジュースばっかりしちゃいそうだけど。でもいい香りだし美味しそうだし、本当にありがとう」
お礼を言って時計を確認すれば、帰ろうとする私に珍しく控えめに声をかけた。
「あー⋯⋯もう帰る?」
「うん。勉強あるし」
「そっか」
「なにかあった?」
「なにかってわけじゃないんだけど、なんとなくもう少し話したいなって思ったから。でも勉強の邪魔になったら悪いから俺も帰る!」
さっきと同じように瞬きを数回繰り返す。どんな意図であろうと、いや意図がなかろうとその言葉は私にとって嬉しいものには変わりなかった。
「再来週試験あってそれまで勉強漬けなんだけど、終わったら連絡するから、そしたら私と会ってくれる?」
私を見つめて笑みを浮かべた翔陽は言う。
「もちろん!」
(21.03.06)