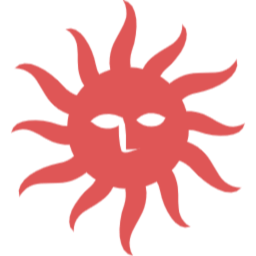
23
いつぶりだろう。リオデジャネイロに来てすぐのときだから半年ぶりかな。
(リオにいるって感じする)
コルコバードの丘から見えるリオデジャネイロの景色。丘の上にあるキリスト像は今日も変わらずにこの街を見守っている。熱を孕む1月下旬の空気は、ただそこに立っているだけでもじわりと肌に汗をにじませた。
「今日めちゃくちゃ暑いね。雨降らなくて良かった」
雨季に当たる今、こんな風に空が晴れ渡っているのは久しぶりのことだ。
「熱中症になんないように気をつけないとな。休憩したかったらいつでも言って! 水もある!」
「ありがと。翔陽もね」
今にも溶けて液体になりそうだと思ってしまうくらい太陽の光は燦々と照っていて帽子を目深にかぶる。それでもあと1ヶ月も経てばこんな真夏の中でもカーニバルが始まるんだから、やはりリオデジャネイロの人々は逞しい。
「あっでも逆光になる前に写真撮んないと!」
「確かに。そろそろ危ないね」
「俺のスマホでいい?」
「うん。どっちのでも大丈夫だよ」
高さ約30メートル。左右に広げられた両手は28メートルにもなる巨大なキリスト像は1931年にブラジル独立100周年を記念して建立されたものだ。それから何十年もずっと、リオデジャネイロのシンボル的存在としてここに君臨している。
場所柄、午後には逆光になってしまうから大抵の観光客は午前中に訪れる。私達もそんな大勢の観光客のうちの一組になって、キリスト像と共に写真を撮るのだった。
約束を果たそうと先に言葉にしてくれたのは翔陽だった。年末年始の休みが終わり授業が再開されてしばらく経った頃、翔陽から届いたのは『コルコバードの丘に行く約束。果たさないで帰国出来ないから、名前の空いてる日教えてくれると嬉しい!』という連絡だった。
初日の出を一緒に見た日から何度か連絡を取り合って、たまに予定が合えば一緒にご飯を食べに行ったりして、途切れることなく翔陽とはやり取りを重ねてきたけれど、こうやって1日をかけて何かをするような事はお正月以来だ。
年の瀬の名残もすっかり消えて、世間はもう次のイベントへとベクトルが向かっている。そろそろ私からお誘いの連絡をしようと思っていたタイミングの連絡だったから返事は悩むことなく打てた。
「めっちゃいい感じに撮れてる!」
そう嬉しそうに言う翔陽を見つめて私も嬉しくなる。やっぱり今日、晴れて良かった。
「本当? 見せて見せて」
「どう?」
「わ、いい感じ! 観光客っぽい!」
「な!」
翔陽の手元にあるスマホを覗き込む。見えやすいように私の方に傾けてくれた画面にはキリスト像を真ん中に私と翔陽が笑顔で写っていた。逆光を免れて私達の顔もはっきり認識できている。
ああ、多分私この写真ずっと眺めてられる。口には出さなかったけどそう思う。自分の恋が凝縮したような1枚にただただ嬉しさを噛みしめる。
「ねえ、もう1回景色見にあっち側行っても⋯⋯」
きっとここに来るのもこれが最後になりそうだから、と翔陽にそう言いながらスマホの画面から視線を外して、翔陽本人に視線を向けようとした。
「あ⋯⋯」
いつもよりも距離が近いことにお互いが気が付いたのはその瞬間だった。そしてその距離感を意識したのも多分2人同時だった。
茹だるような暑さを忘れたその一瞬、私の世界は確かに止まる。きっとこれまでもこうやって刻まれてきたのだろう。心のどこか深くて見えにくい部分に。自分自身も気が付かないうちに。
「ご、ごめん!」
翔陽が慌てて謝って、私もハッと意識を取り戻す。お互い羞恥心を隠しきれないまま、意図的に距離を取って動揺を隠すように笑った。
「う、ううん。私もごめんね」
不快な思いが一切ないのに一体何に対して謝っているのか自分でもわからなかったけど、謝る以外の言葉が見つからない。心地よくも奇妙な空気が流れて、この空気を生み出してしまった事への謝罪になるのかな⋯⋯なんて現状を分析でもしないと冷静ではいられないような気がした。
心が熱いのか、リオの空気が暑いのか。のぼせてしまいそうになる原因は私にはもう分かりそうもない。
「えっと⋯⋯景色だっけ」
「あ! うん。そう。そうそう。景色」
「あっち側行く?」
「い、行く」
場を立て直してくれたのは翔陽だった。でも、切り揃えられた髪の毛から覗く耳が赤い。見てはいけないようなものを見てしまった気がして、冗談でも「翔陽耳赤くなってる」なんて言えない気がした。その指摘はそのまま自分に返ってくるだろうから。
気が付かないふりをして、翔陽からはぐれないように街を見渡せる場所へと向かった。キリスト像はこんな日でもやっぱり、私達をじっと見守るのだろう。
(21.04.27)