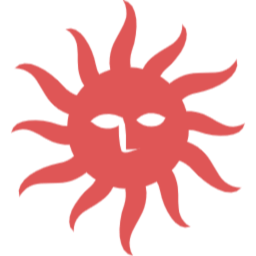
24
湿気を纏う空気が私達の間を抜ける。頬を撫でる風は快適とは言えないのに心はどこか浮足立っていた。
遠くに見えるコパカバーナの海。私の住む地区。最寄りの地下鉄の入口。ロドリゴ・デ・フレイタス湖。気がつけばリオデジャネイロの街がわかるようになっていた。来たばかりの頃はここから街を見渡しても何もわからなかったのに。
「実は俺、今日結構⋯⋯いや、すごく⋯⋯? 楽しみにしてて」
いつもよりも小さい声に私は耳を傾ける。覇気がないというよりも、どう言葉にするか迷っているような紡ぎ方に珍しいなと思った。いつの間にか私は翔陽の、こういう変化にだって気がつけるようになった。
「私もすごく楽しみだったよ」
翔陽を見つめながらそう言う。お昼時で少し人が減ったとは言え、それでも人はいるから意識して翔陽の言葉を聞かないと聞き逃してしまいそうになる。
今日だけじゃない。翔陽と過ごした時間はいつも楽しかった。この丘から見渡せるあの街で翔陽を知った。出会って、もっと知りたいと思って、恋をして。ぎゅっと濃縮された思い出はどれもこれも大切で愛しい。これから先、日本でリオの景色が映っている映像や写真を見たら私はここで過ごした日々を思い出すのだ。一生懸命勉強してニース達と笑いあって、翔陽に恋したことを。
「あー⋯⋯あっ! そうだ、これ名前に渡そうと思ってたんだった」
見つめ合って数秒。ハッとした翔陽は声量をいつもの調子に戻して、クロスさせていたボディバッグの中からラッピングされた小さな袋を取り出した。
「バイト中に見つけたんだけど見た瞬間名前の顔思い浮かんで、そんで、買わなくちゃって思って」
「私にくれるの?」
「でも安物だし好みとかあるだろうしいらなかったら全然受け取らなくても! 本当に全然! 衝動的に買っちゃったようなもんだから!」
値段は関係ない。「嬉しい」と一言添えて、そっと翔陽の手のひらからそれを取る。袋の中から出てきたのはブレスレットで、太陽の光があたってキラリと眩しく光った。
かわいいと呟くように言ってから右手首につけようとしたけれど、私の背中を押したのはやっぱりリオデジャネイロの景色だった。
「⋯⋯翔陽がつけて」
「えっ!?」
自分でつけられないわけじゃないけど、どうせなら。叶うことなら。私の申し出に翔陽は驚きはしたものの遠慮がちに、そして丁寧にそれを私の腕につけてくれる。繊細な手付きに思わず笑ってしまいそうになるのをこらえて、ブレスレットのつけられた腕を少し上げれば、それはより一層輝きを増したように思えた。
「どうかな? 似合ってる?」
「とても、よく、似合って⋯⋯マス」
「えへへ良かった。ありがと。大切にするね」
壊れ物に触れるように優しく触る。
翔陽が言うように、素材を考えればきっといつかは錆びてしまうんだろうけれど、たとえ錆びたとしてもこれが私にとって大切な代物であることは永遠に変わらない。太陽の光を受けて輝いたって、輝かなくたって私にとっての唯一だ。
「⋯⋯それで俺、名前に話したい事があって」
「うん。なに?」
控えめに翔陽は言った。その瞳はいつもと違って、どこか緊張しているようにも見える。それでも声色も瞳も揺らぐことのない様子は翔陽を翔陽たらしめるものだった。
「前に名前が俺に言ってくれたことなんだけど」
「私が翔陽に言ったこと⋯⋯」
その言葉にこれまでの事を思い返す。私が翔陽に言った言葉はたくさんあるけれど、この瞬間、翔陽がこんな雰囲気を作ってまで言いたいこと。
過去を振り返る私に、現実が呼びかけた。鞄の中から聞こえてくる音。これは私のスマホの着信音だ。考えることをやめて慌てて電話に対応したけれど、電話の向こうの悪い内容に私は電話を切った後深くため息を吐いてから翔陽に伝えた。
「⋯⋯ごめん翔陽、いまやってるグループワークでトラブルあったみたいで寮に戻らなくちゃいけなくなった」
どうしてこのタイミングなんだろうと考えても仕方ないのにそんなことを考える。
「えっ大丈夫?」
「わかんない。データ消えたかもしれなくて、来週の初めに発表あるから復旧できなかったら結構やばいんだ。とりあえず戻ってデータ消えたとき用の準備しなくちゃいけないからドタキャンみたいで本当に悪いんだけど⋯⋯」
「俺のことはいいから! やばいんだったら早く戻んないと!」
直前までの空気は完全に消え去って、私と翔陽は登山電車の乗り場に向かった。落ち込む私に翔陽は責めるどころか心配してくれるばかりで、それがより一層翔陽に対して申し訳なさが立つ。
ここから見える景色は美しいのにどうしてもっと一緒にいられないんだろう。
(21.04.27)