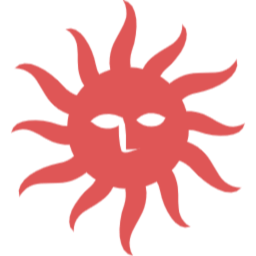
27
ゆっくりと色を変えていく空に気が付かないふりをしようとも時間は当たり前に過ぎていって、その時は着実に私達のすぐそばまで迫っていた。
どちらから今日の終わりを告げる言葉を言うか。頭の片隅でそんな事を考えては、いやでもまだ私からは言わないでおこうとずるい私が顔を出す。
「名前、疲れた?」
「えっ」
翔陽の指摘にパッと顔を上げる。疲れてはない。でもさよならするのが寂しいなと思ってた。言えば困らせてしまうだろうか。一瞬迷って、包み隠しても仕方ない感情を結局私はそのまま露呈した。
「疲れてないんだけど、多分そろそろバイバイの時間だろうから、ちょっと寂しいなって」
困らせないように翔陽が迷ってしまわないように、できるだけ笑っていう。
ずっと欲しかったものを買ったわけでもない。SNSで見たおしゃれなカフェに行ったわけでもない。なのに今日という一日はどうしてこんなにも私の胸に刻まれるのだろうか。好きな人がいるというだけでどうしてこんなにも世界はキラキラと光るのだろうか。
「俺もその⋯⋯もっと一緒にいたいなと思ってて、でも遅くなるのは駄目だから寮の前までは送りたいんだけど、いい?」
翔陽の耳はほんの少し赤かった。
長いこと友達だったわけじゃないけれどそれでも友達の期間はそこそこあったから、恋人としての距離感を私達はまだ図りかねている。どれくらい近づいて良いのか、どれくらい触れても良いのか。どれくらいわがままを言っても良いのか、とか。
「⋯⋯いいの?」
「か、彼氏だし! それに、そうしたい。だから寮まで送らせて」
「じゃあ⋯⋯お願いします」
どちらからともなく歩きだして地下鉄の入り口へ向かう。地下鉄の構内では小銭稼ぎの音楽家が陽気な音楽を奏でていて、歩調をそのままに音の前を通り過ぎながら音楽を耳に残す。それが去年流行った恋愛ソングだとわかったのは寮の最寄りの駅を降りてからだった。
「さっきの曲」
「え?」
「去年ニースがおすすめって教えてくれた曲だったの今思い出した。サブスクで何回か聞いたんだけど、楽器が変わるとあんな感じになるんだね」
ポルトガル語で歌われた歌詞を今ならより深く理解出来る。
願わなかったはずなのに望まなかったはずなのに、形になると多くを求めてしまう。欲は尽きないのだと思わされる。名前を呼びたいとか呼ばれたいとか、可愛くなりたいとか、頑張りたいとか。恋に心が支配されるのはどこか痛くて気持ちが良い。
そんな風に歌っている曲に「わかる」と頷ける。翔陽を想うこの気持ちはどこかを強く刺激して、そしてそれはどうしようもなく心地よい。
「やっぱり寮までもあっという間だったね」
苦笑して言う。地下鉄の中でどんな話をしても、駅から寮までの道で手を繋いでも、満たされた瞬間、すぐに次の願いが生まれる。
離し難いこの手をそれでも離さなくてはならない。もう少しゆっくり歩けば良かった。自分勝手にそんなことを思ってしまう。
「⋯⋯翔陽?」
だけど、結ばれた手と手は簡単にはほどけなかった。
「あー⋯⋯いや、えっと⋯⋯」
迷うような声色は翔陽の視線を泳がせる。指先に全神経が注がれたんじゃないかってくらい翔陽の細やかな動きにも敏感にわかる気がした。実際、ほんの少し翔陽の指先に力がこもったのがわかって、そしてそれは私にも伝うように移る。
「今日、楽しかった」
「う、うん。私も」
何か覚悟を決めたような翔陽はじっと私を見て、一歩分距離を詰めた。まさに眼前。見上げよりも先に背中に翔陽の腕が回って抱きしれられてるいるのだと理解する。
手を繋いでいたときとは違う体温。腕と腕がなんの隔たりもなく触れ合っていて気持ちが勝手に上昇していく。気持ちを整理できぬまま、程なくして離れていった翔陽を私はずっと見つめるだけだ。
「⋯⋯じゃあ、また」
呟くように翔陽が言う。そうして後退る足元。じゃあ、また。わかってる。別に電話だってメールだって連絡手段なんてたくさんある。四六時中一緒にいたいけじゃない。
でも今は。抱きしめられた今は。
翔陽の腕を掴んだのは、それこそ無意識だった。
「え」
「あ⋯⋯ご、ごめん。えっと、じゃあ、また」
何を求めていたのか自分でもわからないまま、ハッとして翔陽の腕を離す。さよならの方法を知らない子供じゃあるまいし。今度こそ私が踵を返す。
「待って、名前」
その声で振り向く。夜を背負った翔陽が月明かりに照らされていて綺麗だと思った。
「俺、ちゃんと言えてなかったけど、名前のこと好きだから」
撫でるように髪の毛を触られて、私の体は硬直したように動かない。紡ぐべき言葉すらわからなくて翔陽の言ってくれた言葉を頭の中で繰り返すだけだ。優しい手付きは翔陽らしいと思うのに、どういうわけか緊張する。
そして次の瞬間唇に柔らかいもの優しく触れたけれど、それがなんであるのかを理解したのはやっぱり眼前にいる翔陽が離れてからだった。
「⋯⋯帰ったら連絡、します」
「は、はい⋯⋯」
「じゃあ今度こそ、また」
優しく柔らかく甘いキスの余韻が唇の上に残っている。苦しいくらいに温かく締め付けてくる刺激は痛いけれど、でもやっぱり心地よくて、果てのない「好き」という気持ちがまた増えていったのを感じた。
(21.05.04)