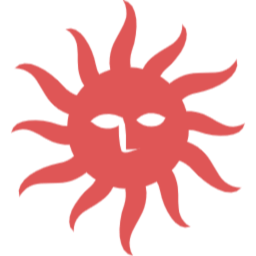
もっと触れたい
翔陽のもっと深い場所に存在できていれば良いのになと思う瞬間がある。
例えば、会えない日が続いたとき。
例えば、練習見学に行って真剣な眼差しを携えた横顔を見たとき。
例えば、いつまでも耳に残るような声をスマホ越しに聞いたとき。
そういうふとした日常の節々に、急にそんな気持ちが現れる。奥深くの、翔陽ですら気づいてこなかった部分にそっと優しく触れることが出来たなら、と。
「さっきのお店うまかった!」
「よかった。私も散歩してて偶然見かけて入ったお店なんだけど、すっごい美味しいなって思ったから翔陽と一緒にまた来たいなと思って」
夏の真ん中の温い夜風に揺れた翔陽の毛先。緩く優しく笑ってくれる表情が、私の心にまた淡い願望を芽生えさせた。
「部屋まで送って大丈夫?」
「あー⋯⋯」
曇りのない眼。まるでそうするのが当然のように翔陽は言う。私の住むマンションまではあと少し。近所のお店でご飯を食べたから、翔陽がそう言うのはおかしいことではないけど。
「翔陽は明日練習あるんだっけ?」
「一応。午後からだけど。名前は?」
「ゼミあるけど、私も午後からで」
言うか言うまいか迷っている言葉を正当化出来る気がした。消えないままの淡い感情が私の背中を押す。
それは独占欲によく似ている。
「私、まだ翔陽と一緒にいたい」
翔陽は少し驚いたように私を見つめた。
「⋯⋯入らないの?」
「はい、る。入るけど」
場所や時間を考えても行先は私の部屋以外考えられなかった。玄関の扉を開けて入室を促したけれど、翔陽はその場で立ち竦んだまま中へ入ろうとはしない。やっぱり強引すぎたかな。わがままに無理やり付き合わせた感じになちゃったかな。突如として襲ってきた不安に私もまた、それ以上何も言えないままだった。
「その、ほらよく考えると、名前の部屋入るの初めてだなって」
「そうだよね。いつも外だもんね。でもブラジルから持ってきた荷物もちゃんともう片付いているし、そんなに汚くないから大丈夫だよ」
「玄関の時点で良い匂いするし、その、普通に緊張っていうか、今日まさか部屋に入るとは思ってなかったから」
羞恥に見舞われながらもしどろもどろに話す様子を見て、素直に触れたいと思った。今、私が触れたら翔陽はどんな表情をしてくれるんだろうという好奇心が働く。触れて、好きって言ったら、翔陽はもっと動揺するのかな。こんなことを考えてしまう私は、おかしいのかな。
「あの、普通に友達の家に遊びに来た時みたいな感じで全然、問題ないから。でも、翔陽の気が進まないなら全然ここでお別れでも」
「気が進まないとかじゃなくて! あの⋯⋯じゃあ、お邪魔します」
良かった。私は安堵した。
靴を脱いで、翔陽が部屋の中に入る。一人暮らし用の1Kマンションに翔陽がいるだけで、途端にこの長方形の部屋が小さな箱みたいに思えてきた。普段自分が寛いでいる空間に好きな人がいる。高揚感。多幸感。充実感。
湧き上がってくるたくさんの喜びに満ちた感情が手に負えなくなって、私は前触れもなく翔陽に抱き着いた。少し力を入れて翔陽の背中に手を回してみても、びくともしない。
「あの、えっと、名前さん⋯⋯?」
「なんか私、翔陽にくっつきたかったんだと思う」
「え」
「外だと限界があるし、人目を憚らないで痛いくらいぎゅっとしてみたかったのかも」
言い終わると同時にもっと強く翔陽を抱きしめてみた。それでも翔陽が痛さを感じている様子はなくて、半袖の服を隔てて、翔陽の心臓に耳を当てた。優しく心地の良い音と共に、生きている人間の証が確かにそこに存在しているのを感じる。
そうだ。うん。私は触れたかった。翔陽に。思いのままに。
「翔陽の匂い好き」
近くにいるからこそわかる香り。柔軟剤がほんのり混ざる、甘い香り。この香りも音も、世界で1番好きだと思える。
「一応聞くけど⋯⋯名前お酒飲んでないよね?」
「翔陽」
「う⋯⋯ごめん、だってそんなに甘えてくるとは想定してなくて⋯⋯!」
「⋯⋯ごめん、嫌だった?」
「嫌じゃない! どっちかって言うとかなり嬉しい! けど、心臓が破裂しそうなので、お手柔らかにしてもらえると、助かる」
見上げた翔陽の耳が赤く染まっている。心臓が破裂しそうなのは私も同じだ。
「3ヶ月ぶりに空港で翔陽と会ったとき、私、ドキドキしてた。翔陽が目の前にいることがすごく嬉しかった」
「それは、俺も、だけど」
「帰国してからバタバタしててあんまり会えなかったし、完全な翔陽不足だったんだよ。だから私、翔陽に触れたいなあって思って、今も我慢出来なかった。なんかどんどんわがままになって言ってる気がするんだけど、嫌わないでね」
力は緩めて、だけど翔陽の背中に腕を回したまま言う。お手柔らかにってどうしたらいいんだろう。どうしたらお手柔らかにくっつけるんだろう。
悩む私をゆっくりと優しく引き剥がした翔陽は、私の両肩に手のひらを置き、少し屈んで目線を合わせた。まるで小さい子に話かけるときのように。
「そんな風に言われると、触れたくなるから困る」
「ご、ごめん?」
「わがまま全部聞けるかわかんないけど言って。我慢されるよりそのほうが良い。それで嫌いになるとかは絶対にないから」
「うん」
「あと」
「あと?」
「⋯⋯キスしていいですか」
赤らめて言う翔陽の言葉に私ははにかみながら頷いた。
そっと触れ合う。壊してはいけないものを触れる時のように優しく。何かと対比なんてできないくらいの幸福がやってきて、私達を包んだ。
(21.06.18 / 80万打企画)