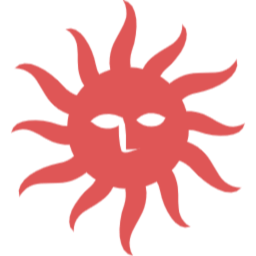
05
「ショーヨーとはあれからも連絡取り合ってるの?」
久しぶりにバイト先に向かうと、開口一番にニースに言われた。皆でシュラスコを食べた日から五日しか経っていないのに報告出来るような事はもちろんあるはずもないと私は首を横に振る。
「連絡は何回かしたけど、ニースが想像してるようなことはないかな」
それでもあの後、連絡先を交換して私の自転車を貸して、次の日一緒にビーチバレーを見たということを伝えれば、ニースは満足そうな笑顔を見せた。
「ニースなんか嬉しそうだね?」
「ナマエから男の子の話聞くなんて初めてだし」
「そう? 前にクラスにいるチリの男の子と植物園行ったじゃん」
「あれはただの課題でしょ?」
「まあ⋯⋯」
でも、私と翔陽もただ夕日を眺めたと言えばそれまでだ。
ニースと店内のテーブルを拭きながら先日の出来事をできるだけ詳細に思い出そうとする。翔陽はビーチで朝日を一緒に見ようと言ってくれたけど、今のところのその誘いもない。
「ふたりとも。客足も落ち着いたから一緒に休憩行ってきていいよ。好きなの食べて」
キッチンから顔を出した店長から声をかけられて、私とニースは顔を見合わせる。今日は何食べる? 瞳で会話しながらサンドイッチを作って、裏の休憩室に向かった。
サンドイッチを頬張った後、ニースは再度翔陽の話題を繰り出した。
「まあ、ナマエの好みもあるしね」
「⋯⋯好みで言うなら、翔陽は私の好みから外れてないけどね」
「え、本当に?」
「うん。多分、日本で知り合ってたとしてもいいなって思う」
一目惚れはしないけど、多分、話したらすぐに良いなって思う気がする。もちろん翔陽にも選ぶ権利があるけれど。自分の好きを貫けられるところとか、純粋そうなところとか、努力を苦と思わなさそうなところとか。そういう尊敬出来る部分がある人は、心を惹かれる。
「だからって好きとかじゃないよ? さすがに」
「別に好きになっても変じゃないのに」
あっけらかんとニースは言う。一応、私は勉強の為にリオにいるわけだし。翔陽だって似たようなものだろうし。そもそも、翔陽のことは良いなとは思うけど、恋人として付き合ってるビジョンまでは全然思い浮かばない。
「あ。噂をすれば」
「ショーヨー?」
「うん」
机に置いていたスマホが震えてメッセージが届く。翔陽の名前が表示されたのを確認すると、私はすぐにメッセージを開いた。
「なんて?」
「えっと、これは⋯⋯デートのお誘い?」
「えっ?」
「ごめん、冗談。次の土曜空いてたら一緒に朝のビーチ行かない? だって」
「デートみたいなものじゃない」
デート、と言うよりは約束を果たしたと言うほうがしっくりくるような気がした。
「案外ショーヨーの方がナマエのこと好きになっているのかも」
それはないと断言出来るけど、言葉にはしなかった。この誘いは多分、好きとかそういうのじゃない。翔陽からそういう雰囲気みたいなものは微塵も感じられなかったから。それに出会って数日しか経ってないからお互いのことなんて全然知らないし。
ただ、翔陽は約束を破ることはしない人なんだろうと思う。それが細やかなものであっても、何気なく交わした口約束だとしても。
「コパカバーナビーチから昇ってくる朝日は綺麗なんだって」
「へぇ。ショーヨーって意外とロマンティックなんだ」
「ね。私は朝起きられるか不安だけど」
ニースと会話をしながら翔陽に『行く!』と短い返事をする。
『じゃあ土曜日の朝5時30分に寮の前まで迎えに行く』
5時30分。確かにこの時期の日の出はそれくらいじゃないと見られないけれど、そんな時間にアラームをかけたのはいつぶりだっけ、早起きすることに不安を覚える。
「ショーヨーと何かあったら教えてね」
「ないよ、なにも。寝坊しないように頑張るくらいかな。それよりも私はニースとエイトールの話のほうが気になるよ」
「エイトールとの話は休憩時間じゃ話しきれない。今度ショッピング行きましょ。その時ゆっくり話すわ」
「わかった。楽しみにしてる」
サンドイッチの包み紙をゴミ箱に放って、フロアに戻る。数名のお客さんが席に座っていて、デリバリーサービスの配達員が注文の商品を取りにきていた。わかっているのに、もし彼が翔陽だったら、なんてことを考えてしまった自分に驚く。
指折り数えて楽しみに待つほど乙女らしい思考は持ち合わせてないけれど、それでもスマホのカレンダーに翔陽の名前を記入するくらいにはその日を楽しみにしている自分がいた。
新鮮な日々に新鮮な風が吹いたみたい。太陽みたいな翔陽の笑顔を思い出して、私の口角は自然と上がった。
(21.01.25)