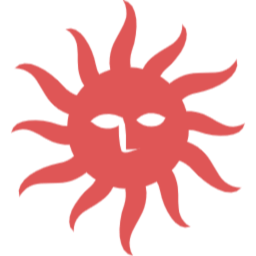
06
約束の日、目覚ましの時間通りに起きられたことに安堵した。
これから朝がやってくるなんて嘘みたいと思えるくらい、外はまだ濃紺に色を染まっている。車の音も、人の騒ぎ声もなにもない。人が寝静まっているのが分かる不思議な感覚。翔陽が迎えに来てくれる前に準備を終わらせないと、と私は慌てて支度を始めた。
動きやすい服を選んで、化粧も変なところはないか鏡の前に立って、鞄の中を確認して。全ての準備を済ませ終わるとタイミング良く翔陽からの連絡が届く。
『おはよ! 寮の門の前についた。自転車で行けるなら自転車が良いと思うんだけどどう?』
『おはよ。自転車オッケー! いま外に出るね』
スニーカーに足を入れて、静寂を壊さないようにそっと寮を出る。こういう時、二人部屋じゃなくて良かったと心底思う。まるで忍者のように歩み寮の外に出れば、門の前で空を仰ぎ見る翔陽が目に入った。その横顔に一瞬心が奪われたから出来るだけ優しい声で名前を呼んだ。
「翔陽、おはよ」
「名前、おはよ! 行ける?」
「うん」
私のシティサイクル自転車とは違う、翔陽のロードバイク。そう言えば初めて会った時もこの自転車でハンバーガーを届けてくれたのだと、少し前の出来事を思い出す。翔陽のロードバイクは、どこまででもひた走って、世界の果てまででも連れて行ってくれそうだ。
「最初会った時、翔陽が夜ご飯運んできてくれたの思い出した。そんなに前のことじゃないのに、すごく昔のことみたい」
「わかる! 俺あの時日本語で烏合って言われてすげぇ驚いた。リオで日本語!? って」
「私も」
その一件がなくても、ニースとエイトールを会して結果的に私と翔陽は出会うことになっていたんだろうけれど、その件があったから、私と翔陽は今こうしていられる気がする。
「じゃあ出発するけど、いい?」
「うん」
ペダルを漕ぐ。まだ暗い街の中を自転車で駆け上がって、翔陽が先頭を切ってくれるのを遅れないようについていく。時折振り向いて私がちゃんとついてきているかを確認してくれる翔陽に手を振ったり、声をかけたりするのがなんだか楽しかった。治安を考慮して出来るだけ大きい通りを通ってくれているけれど、昼間とは違う街の様子や空気感になんとなく、違う街に来たような気持ちになる。
早朝の空気が肺いっぱいに満たされて、まるで飛行機がこれから飛び立つときのような高揚感を得る。翔陽と会う日は、いつもこんな気分になる。嫌じゃない。むしろ心地良い。
「なんか」
「んー?」
前を見ながら聞き返される。朝を待つ解放感が私の背を押した。
「翔陽が違う世界に連れてってくれてるみたい!」
風を切るようにして自転車を加速させる翔陽に向かって言葉を紡いだ。叫ぶように言ったものの、返答はなかったからちゃんと届いたのかはわからない。けれど翔陽の背筋が一層、伸びた気がした。
闇に覆われていたような夜もそろそろ朝を迎えようとしている。海辺からはほんの少しずつ太陽の光が放たれて、夜と朝が交代する瞬間がやってくる。
「昇ってきてるね」
「やばい、急がないと」
日の出に間に合うように少し急いでビーチの駐輪場に自転車を止めると、人気が少ないながらも近くに交番があるような場所を選んで翔陽は腰を下ろした。
「間に合った」
「うん」
隣で翔陽が大きく息を吸い込む。気持ちや身体を整えるように綺麗な呼吸を繰り返して、凛とした姿勢のまま私の方を見つめた。
ああ、そうだ。この雰囲気。全てを奪われてしまうような、この雰囲気。
「そろそろ見える」
翔陽の言葉で我に返り、海の方へ視線を向けた。一足先に光が空を照らし、水面に滲むようにゆっくりと太陽が昇る。もちろん直視は出来ないけれど、街を起こしていくように太陽は姿を見せ、私達を照らした。
美しいとか、綺麗とか、ロマンティックとか。そういうありきたりな言葉しか浮かばない自分が悔しくなる。私の心を揺さぶる光景。もし私が写真家だったのなら、この一瞬を永遠に残すことが出来るのにと、ぼんやりと非現実的なことを思った。
「どう?」
落ち着いた声色と、満たされるような表情で翔陽が訊ねる。
「⋯⋯想像以上に綺麗で驚いてる」
「だよな!」
朝日に負けないくらい眩しい笑顔。私、翔陽といて嫌だなって思う瞬間が一度もないんだなと気がついた。
「翔陽はここでよく精神統一してるの?」
「たまに。時間ある時とか、自分と向き合いたい時とか」
「すっごく効果ありそう」
「あるある」
リオデジャネイロのビーチに昇る朝日に再度息を呑む。
一日が始まる。希望に満ちた一日が。
「早起きしてよかった」
一緒に見る相手が翔陽で良かった。
確かに私はそう思った。
(21.01.25)