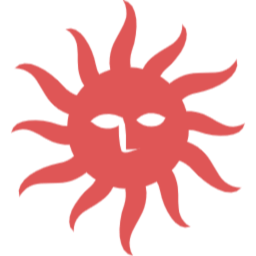
07
太陽がすっかり昇りきったのを見届けると、情けない音を立てて私のお腹の虫がなった。波のさざめく音に混じって奏でられたその音は、穏やかなコパカバーナビーチでは誤魔化すことも出来なかった。
朝ごはん食べてから出れば良かったと思ったけれど、五時三十分は早すぎてお腹も空かないよと、ようやく声を上げた私のお腹を宥めるように撫でる。聞かなかったふりをされるくらいならいっそ笑ってほしい。と願う私に、翔陽は変わらない様子で言った。
「俺もお腹空いた! 朝飯、一緒に食べよ」
「い、行く!」
翔陽が微笑みを向けてくれる人で良かった。
立ち上がりお尻についた砂を払う。スニーカーを履いているとは言え、砂の上だと足場は悪い。難なく歩いていく翔陽の背中を追いかけて小走りで駆寄ろうとすると、転倒してしまった私の膝は砂に埋もれる。
「翔陽待って、転んだ」
「えっ平気? ごめん、先歩き過ぎたかも」
「ううん。私が砂に慣れてなくて⋯⋯」
砂場だから怪我はないけど、お腹の音に加えて転ぶなんて恥ずかしい。
手についた砂を払って立ち上がろうとする私に、翔陽は手を伸ばした。影が落ちたその一瞬、差し出された手を取るか迷って、結果、そっと手を重ねると翔陽の体温がじんわりと私の手のひらに移ってくる。
立ち上がり、膝についた砂を払ってお礼を言えば翔陽は足元の砂を慈しむように見つめながら言った。
「わかる。俺も最初そんな感じだった」
翔陽にとって砂は、風は、ビーチバレーとはどんな存在なのだろう。容易に色んなことを聞ける間柄ではないけれど、私はもっと翔陽を知りたいと思った。
「あっ怪我は!?」
「平気。砂場だし」
「ゴミとか空き瓶とか」
「それもなかったから大丈夫」
翔陽は安堵した表情を見せ、今度は私の隣に並んで歩いてくれた。遊歩道までたどり着き、駐輪場に置いていた自転車を手で押しながら、近くにあるお店でモーニングをやっているところを探す。
「何食う? 食べたいのある?」
「なんでもいいよ。朝早いし、パダリアで食べる?」
「美味しいところ知ってる?」
「んー⋯⋯あっ自転車ならここから十分くらいのところに美味しいお店あるよ」
「じゃあそこ行こう!」
今度は私が先頭になって翔陽を導く番だ。
ブラジルの朝ごはんと言えばパンとコーヒーが主流で、街中にはコンビニのような機能を併せ持つパン屋さんがある。それがパダリアと呼ばれていて、初めこそパン屋さんなのにお菓子やアルコール、加工肉なんかも売っているのが面白いなんて思ってたけど、今となっては生活になくてはならない存在。レストランに比べると値段も格安で、しがない留学生にとっては外食の救世主だ。
「何がオススメ?」
「どれも美味しいからオススメ」
コパカバーナ海岸を背に北上し、ウマイター地区まで行けばそのお店はある。既に店内の殆どの席が現地民で埋まっており、私達が入店すれば物珍しいのか数人の人がこちらに視線を向けた。慣れたつもりでいたけれど、やっぱり慣れるものでもないなと思う私とは反対に、翔陽は集まる視線を気にすることもない様子だった。
考えてもみればビーチバレーで注目を集めている人なんだから、いまさら他人からどう見られたところで思うところはないのかもしれない。
「私クロワッサンとスムージーにしようかな」
「俺は、ハムエッグトーストとサラダとアサイー!」
注文した商品を受け取って空いている席に座った瞬間、近くにいた中年の男性が翔陽に声をかけてくる。突然のことに驚いたけれど、会話に耳を傾ければ、どうやらいつもビーチバレーを観戦していて、翔陽のことを応援しているらしい。
握手と写真撮影を求められ、翔陽が対応する。満足そうに去っていくおじさんの背中を見届けてから言う。
「翔陽って本当に有名人なんだね。あ、いや、ニースも言うくらいだしわかってたんだけど」
「有名って自覚はあんまりないけど」
「でも握手してほしいって言われるのは有名だからだよ。すごいね」
「ビーチもすっげー楽しいし、好きだけど、俺がやりたいバレーはやっぱりインドアのほうだから」
凛とした瞳だった。インドアのバレー。バレーと言われて大半の人が思い浮かぶ方のやつだ。
「そう言えば翔陽はずっとバレーやってて、それでこっち来たって言ってたね」
「うん」
私はビーチバレーの翔陽しか見たことないから、インドアのバレーをやっている翔陽はイメージが出来ない。スポーツの詳しいこともわからないけれど、バレーのためにビーチバレーを選んで、そしてブラジルまで来ることは バレーボールと言うスポーツにおいても普通の選択肢ではないということはなんとなく分かる。
それを選ぶくらい、翔陽はバレーが好きで、これから先もずっとバレーと共に生きていくのだろうと言うことも。夢を叶えるために日本からブラジルにやってきたという共通点はあるのに、翔陽との距離が近いようで遠い感覚に陥る。
目の前でハムエッグトーストを頬張る翔陽を見つめながら、私達の間にある見えない距離を推測してしまった。
(21.01.26)