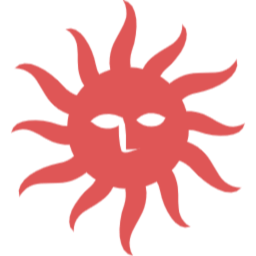
08
「名前は何でリオデジャネイロ留学選んだの?」
「私は留学自体が学校のカリキュラムの1つでもあるんだけど、通訳の仕事したくて」
「通訳!」
凄い、と翔陽は言うけれど私からすれば翔陽だって十分凄い。むしろカリキュラムで決められている私と、身1つでここまで来た翔陽じゃ全然凄いレベルが違う気がする。
「じゃあ日本帰ったら資格? とかとるんだ?」
「通訳者自体は資格がないから英語とポルトガル語の試験受けたり、あとは実績積んでツテも増やしたりとか。正直狭き門だしこれで食べていけるかわからないけど、でもやっぱりずっと夢だったから諦めたくないなって思ってて。なりたい自分があるから勉強が大変でも頑張れるんだよね」
「それわかる! その時辛いなって思っても思い返したら結局バレーって楽しいってなる」
「翔陽は? いつ日本戻るんだっけ?」
「3月。元々2年の約束だったから。戻ったらトライアウトやってるチームで1番強いところ受けて、そんで、バレーの選手になる予定」
嬉々として語る翔陽は楽しそうでそれだってきっと楽な道じゃないのに、似たような環境でお互い夢を追っているんだなと思うと、必要以上に親近感が湧いてしまう。
なれるよとか大丈夫とか、無責任なことは言えないけれどそれでもなんとなく翔陽はちゃんとそれ叶えるんだろうなと思った。
「じゃあ、数年後には日本代表の有名人だ」
「そうなるべく⋯⋯頑張ってます!」
その頃私は世界のどこにいて何をしているんだろう。ちゃんと翔陽の事を応援出来ているかな。スムージーを飲み干して、呟くように言った。
「翔陽がするインドアのバレーも見てみたいな」
「日本帰ってきたら試合来てくんないの?」
私の言葉をこぼすことをしなかった翔陽は平然と、当たり前のようにそう言って私を見つめる。
「え」
「えっ」
「行く、けど」
「ビビった! 来てくれないかと思った!」
意外だった。意外というより、翔陽の中で日本でも私と会おうとしてくれていることに少し驚いた。
「翔陽、私と日本でも会ってくれる気だったんだ」
「え⋯⋯え!? 俺図々しいこと言った!?」
「いや。なんかちょっと嬉しいなって」
「よかった⋯⋯」
よかったは多分、私のセリフだ。そうであってほしいと願っていたから。
「俺もまずは目の前のことちゃんとやんないとだけど」
「競技会?」
「うん」
互いに目を合わせて頷きあう。私達は夢を叶えるためにここにいる。その夢の途中で翔陽と出会えたことは私の人生のかけがえのない一部になるんだろう。
食事を終えた翔陽が手を合わせて「ごちそうさまでした」と綺麗な姿勢で呟く。
「美味かった!」
「お腹でいっぱい幸せ」
「エネルギー補給も完了」
私も翔陽にならうように背筋を伸ばして手を合わせた。あんなに朝早くに寮を出たのに気がつけばもう朝の10時で時間の流れの速さに驚いてしまうけれど、それでも早く起きた分だけまだ1日は長いと思うとなぜか少し得した気分にもなる。
「翔陽は今日何するの?」
「練習! 明日試合あるし」
「そっか。競技会の最終日は3日後だもんね」
「うん。スコールが降らなければその日に終わる」
「ニースと一緒に応援しにいく予定だから」
パダリアを出て、停めていた自転車に手をかける。そうか、今日はこれでお別れかと思った瞬間、考えるより先に口が動いた。
「ねえ」
「なに?」
「今度一緒にコルコバードのキリスト像見に行かない?」
「えっ名前まだ行ったことないの?」
「ううん。あるけど、私あそこから見える景色好きだから翔陽と一緒に見たいなと思って」
「俺も好き。一緒に行こう!」
「じゃあ、約束」
「約束」
この約束が果たされるのはいつか。誘った私にもわからないけれど、きっと果たされる。そして私はその日を楽しみに過ごすのだろう。
「じゃあ、また明後日」
「ニースにもよろしく」
「エイトールにも」
自転車に跨った翔陽は、私の寮とは反対方向に向かって自転車を漕いでいく。人出の増えた大通り。賑やかな声。太陽の日差し。パンの香り。大通りの角を曲がってその姿が見えなくなるまで私は見つめ続けていた。翔陽の、揺るぎない強さが滲むその背中を。
(21.01.27)