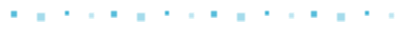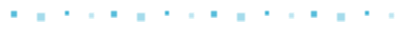
再開
この空は、一体どこまで続いているんだろう。
海というのは、一体どこまで大きいんだろう。
世界には、一体どれほどの人間が生きているんだろう。
知りたい。
叶わぬ夢をいつも見て、僕は今日も“今日”を生きていく。
「おい!早くしろよコクリ」
ガサガサと草木を掻き分けて、五人ほどの少年少女が山の中を進んでいく。
集団で一番前方にいる17歳ほどで体格のよい少年が大きな声を後方に投げた。
「待ってよ。今行くってば」
答えたのは集団から少し離れて最後尾を歩く細身の少年だ。
彼が急ぎ足で距離を縮め、五人は一列のまま奥へと進んでいく。
そして、木々が僅かに途切れて出来ている開けた場所に着くと、小さな円陣を作った。
体格のよい少年が口を開く。
「うっし!今日も張り切って探すぞ皆!
いつも通り太陽が傾き出したら終わり!ここに集合!遅刻したやつは置き去りだからな!
明日の隊長は一番キノコをとってきた奴だ!じゃあ始めっぞ!」
「オー!」「はいよー」「りょーかーい」「わかった」
少年の言葉に四人がそれぞれ返事をする。
体格のよい少年は、大きな篭を背中に背負って意気揚々と山のさらに奥へと歩いていった。
日焼けをした小柄な少女は、軽い足音を立てて今来た道を戻るように走っていく。
つり目の少年は少しばかり考える仕草を見せ、やがてやって来た道から右側の斜面を下った。
明るい髪色の少女は、気だるそうにしながら体格のよい少年と同じ道を進んでいく。
最後に、黒い髪をうなじで束ねた細身の少年は誰も進まなかった、つり目の少年と正反対側にある木々の間へと足を向けた。
太陽による暑さも和らいできた涼しさのある季節、山では色とりどりの木の実やキノコといった食物が顔を覗かせる。
東林山の麓にある水白(ミナシロ)村では主に子どもがそんな山の幸を集めていた。
遊びと、食べて良い物か悪い物かの判断を覚えるための学習を兼ねた日課。
コクリはそんな日課に飽きたような顔をしながら、それでも新しいものを探してゆっくり森を歩く。
腰に下げた小さな篭には既に幾つかキノコが入っていた。地味な色の、いかにも毒性のなさそうなキノコたちはコクリが歩くのに合わせて篭の中で小さく跳ねる。
暗い色をした木の根本にまたキノコを見つけて、コクリはそれを迷うことなく摘み取って篭に入れた。
明らかに慣れた動作。
何回も何回も繰り返して、いつしか篭にはキノコの山が出来上がる。
「これくらいでいいかな……」
呟き、木の葉が風に揺れる音の中でコクリは空を仰ぐ。
暗緑の隙間から覗く大空の色はどこまでも透けた青。
太陽が眩しいだろうに、彼はじっと宙を見つめ続ける。
薄い雲が風に流されて、ゆっくりと空に溶けていく。
『あの白はどこに消えてしまったんだろう』
『どうして色は変わっていくんだろう』
『何で季節があるんだろう』
ぼうっとしながらコクリは上を向いたままフラフラした足取りで歩き始める。
『どうして風は吹くんだろう』
『どうして山はあんなに高いんだろう』
『その向こうにも、誰かがいるのかな』
彼の鮮やかな橙色の瞳が映すのは空であって、空ではない。
『知りたい』
何処へ行くと決めもせず歩いていたコクリは、ふと足を止めた。
夢現から目覚めたように目を瞬かせ、辺りを見渡す。
山の麓の森の中、その状況は空を見上げた時となんら変わりはない。しかし、コクリは不安げに顔をしかめた。
「何か……ここ、変?」
キョロキョロと何度見回したところで景色は変わらない。
太さのまちまちな木々がひしめき合う、見慣れた光景。
しかし、どうしてもつきまとう違和感にコクリは不安を募らせる。
空は相変わらず青く晴れ渡り、見るものの心を軽くするような明るい光で太陽が眩しく森を照らしている。
なのに、突然暗い場所に閉じ込められたような奇妙な閉塞感がどうしても拭えない。
暫くして、コクリは全く風が吹いていないことに気がついた。
そのせいで木の葉も揺れず、彼の足元で草を踏む音だけが周囲に響くだけ。
―おかしい。
例えば、生き物があまり動かない冬の宵は静かなものだ。
けれど、そんな夜にもどこかしらから響く音が必ずある。
だが、コクリが今いる場所には微細な音すらない。
静寂。
自分しか音を立てていない、つまり自分以外に動く物のない空間。
一歩、踏み出してみる。
クシャリと葉の潰れる音がして、すぐに消えた。
それから、二歩、三歩、コクリは歩いていく。
彼の表情からは先程までの不安が薄れていた。
代わりに浮かんでいるのは、好奇心。
怖いもの見たさといったところだろうか。歩く歩幅が少しずつ広くなり、速度も徐々に早くなる。
あまりに無用心な行為ではあるが、コクリはそれを気にしている様子がなかった。
ただ、己の行きたいままに歩いて、歩いて歩いて、時間の感覚も忘れて進み続けた。
そして、彼は見つけた。
木々の間から、太陽とは違う白い光が漏れている場所。
恐る恐る近づいていくと、森の中とは思えない光景が眼前に広がる。
地面も、木の幹も、葉も、なにもかもが白い世界。
まるで境界線でも引かれているかのように突然青々とした草木が消え、そこは全てがガラスのように透き通った物質でできていた。
コクリがもっと寒い地域で暮らしていたなら、彼は目の前に広がる景色を氷でできた世界だと思ったことだろう。
明らかに人為的なものではない。しかし、自然に出来たものとも言い難い。
およそこの世のものとは思えない景色。
「綺麗だ……」
思わず溢れた声はすぐに消えた。
ぐるりと目に見える白い世界を見渡し、それからコクリは今まで足をつけていた草の絨毯から右足を離す。
そして、まるでこっそり誰かの家に入る泥棒のように、ゆっくりと音を立てぬようまっ平らな地面に足を乗せる。
コツン……。
透き通った音がコクリの耳をすり抜ける。
残る左足を今度は遠慮なく移動させた。先程よりも大きい、けれど透き通った音がまた辺りに響く。
「すごい……すごい、すごい」
ただの靴音なのに、その音は楽器を奏でるように美しい。
踏み鳴らした数だけ透き通った音が生まれ、反響し、新しく生まれた音と絡み合ってより深い音へと変わる。
いつしかコクリは満面の笑みを浮かべて楽しそうに足を動かしていた。
「ハハ、アハハ!アハハハハ!」
ついには笑いだして、どこまであるか分からない白の地面を走り出す。
笑い声すら綺麗に靴音と重なって、それが余計にコクリを楽しくさせた。
面白くてしょうがないと言わんばかりに彼はめちゃくちゃに走る。
「ハハハハハ!ハハ……は、はぁ……はぁ……」
はしゃいだあまり息が切れたところでコクリは足を止め、一番近くの白い木に背中を預けた。
温度のない木は火照った体にはひんやりと心地がよく、コクリは静かに目を閉じて息を整える。
いつまでもドクドクと落ち着かない心臓を感じながら、他にもなにかないか白い世界に目を向けた。
すると、コクリから向かって右側の開けたところに色が見えた。
そちらに目を凝らしてみる。
遠くて不鮮明だが、白い中にポツンと見えるのは赤色のようだ。
深く考えることもせず、コクリは右へと足を向ける。
コツン、コツンと音を鳴らしながら何かに近づいていき、その距離が1クローになったところで彼は息を呑んだ。
始めに見えた赤色は、衣服だった。
村では見たことのない形をした真紅の鮮やかな衣。
上半身に近づくにつれて薄紅へ、薄紅から白になる色の変化が見事だ。
そんな派手といえる衣装を身に纏って地面に横たわっているのは、少女だった。
白と赤の上に散らばる黒髪は露に濡れているかのように艶やかに輝き、純白の肌を引き立てている。
しっかり閉じられた目蓋。長いまつげが呼吸に合わせて細かく揺れ動く。
どうやら眠っているらしい。
僅かに聞こえる寝息はとても穏やかだ。
「……綺麗な子」
少女の傍らまで近づき、コクリはその場にしゃがみこむ。
見れば少女は耳の裏側で束ねた髪に白い花飾りを差していた。
コクリは花に詳しくないので分からないが、大きく柔らかい花弁のその花はとても少女に似合っていると思った。
「んん……?」
花から視線を戻してから気づいたものに、彼はまじまじと少女を見つめる
正確には少女の耳。
緩く反り返っている筈の耳の一番先がピンと尖っている。
指を伸ばしてツンとつつく。返ってくる感触は柔らかい肌のもの。
首を捻りながら、コクリは他の箇所も見ていく。
体格からしてコクリとそう年は変わらないだろう。体には耳のように特別気になるところはない。
ただ、強いて言うと少女の胸元を観察する時間が数秒ばかり長かった。それだけだ。
最後に顔を見つめる。
形のよい小さな鼻。
ふっくらとした頬は薄く染まった朱と相まって柔らかく見える。
赤く色づいた唇は熟れた果実のようで、唯一そこだけは少女ではなく女性としての色気を感じさせた。
「本当……綺麗だな……」
静かにコクリは右手を少女の頬へと近づける。
触れてみると仄かに温かい。滑らかな肌は弾力があって、コクリの指にふわりとした感触を伝える。
『もっと、触れてみたい』
腰を屈めて、より距離を縮めた。呼吸の音がハッキリと聞こえる。
右手で撫でる頬はとても気持ちがよくて、ずっとそうしていたくなるような魅力があった。
だが、惹かれるままに撫でれば撫でるほど罪悪感のようなものが彼の内側でムクムクと膨れ上がる気がした。
何かとても悪いことをしている気持ちになって、コクリは静かに少女から手を離す。
その時だった。
「………――?」
ぴく、と小さな身動ぎを見せて、少女の固く閉じた目蓋がゆっくりと持ち上がった。
その瞳を見た瞬間、コクリは体が石のように固まってしまったのではないかと錯覚した。
深く鮮やかに光る赤紫の宝石がコクリを見つめる。
あまりの美しさにコクリは呼吸すら忘れて少女に見入った。
潤い、輝く瞳には驚いた顔で少女を見るコクリが写り込んでいる。それが不思議とコクリの胸を熱くさせた。
少女も、やや驚きを含んだ瞳でコクリを見つめる。
互いの視線が絡む時間がほんの数秒にも、何時間に渡るものにも感じられた。
そっと少女が横たえていた体を起こす。
真っ直ぐコクリと向かい合う形で少女の赤い唇が小さく動いた。
「コクリ……?」
「…………え?」
聞き間違えでなければ、今少女は彼の名前を口に出した。
初対面であるはずの少女から紡がれた己の名前にコクリは目を丸くする。
『どうして?』
口に出そうとして出せない。いや、出せなかった。
静かに少女が両手でコクリの顔を包み込んだから。
ほんの小さな温もりだというのに、じわじわと熱が顔に集まる感覚がコクリを襲う。
少女の手は顔から滑り落ち、コクリの両脇に差し込まれた。そして、ごく自然な動作で小さな体を少年へと寄せる。
コクリは黙ってそれを見ていた。自分にされていることなのに、まるで遠くから観察しているように出来事が遠い。
なのに、伝わる温もりと柔らかな感触はひどく鮮明で、それがコクリの胸の中を激しくかき乱した。
その感情の揺らめきがなんと言うものなのか、動揺するコクリには分からなかった。
ただ。
ただ、まるで眠っているような心地の好いこの時をいつまでも感じていたい。
身を委ねる少年の橙の瞳の前で、白い可憐な花が風もないのに揺れた。
戻る
小説トップへ戻る