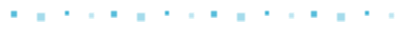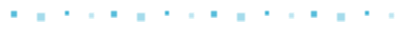
冷厳の盾2
「これでディミルダの声も聞こえるし、姿も見えてるだろ」
「……意外だな。人の形になるのか」
「まーオレらなんて生き物の未練とか感情の塊から産まれるし?多分コイツの中で思い出しやすい形が人間だったんじゃねーの?」
「ねーの?」
塊からはっきりとした呟きが漏れる。
表情はぼんやりとしているが、体を支える足は細いながらしっかりしていた。
数秒前の不安定さは微塵も感じられない。
「まあ、契約ができるならいい……お前」
「ん?お前?お前……おれ、わたし、ぼく……ボクを呼んだ?」
「そうだ。お前にとって俺がどんな存在かは理解できているか」
「存在。あなた、ボクを喚んだ。呼び寄せた。連れてきた人。ぬし、主……あ、ご主人様!」
塊はたどたどしい言い方でご主人様と連呼しながらパチパチと手を叩く。
声は楽しげだが真顔なのでまだ行動と表情が一致していていないようだ。
小さな溜め息を吐きながら、ディミルダは言葉を重ねる。
「主人でまあいい……お前、名は?」
「な?」
「名前だ。契約に必要だからな……字(あざな)なり真名なりさっさと教えろ」
「字なんて使ったら後でギッタギタにして真名を引きずり出すくせに……」
「ラース、何か言ったか?」
「気のせいじゃないかぁ?」
「名前……名前?」
ヒューヒューと口笛を吹きながら向けられたキツい視線をそらすラースの傍らで、塊は初めて表情を動かす。
眉を潜め、唇を引き結んだ姿は困っているようだ。
塊は暫く唸りながら足元を見つめてから、先ほどのぼんやりした顔でキッパリとこう言った。
「ボクは、名前がない!」
「なに?」
ディミルダの顔が不快そうに歪む。塊が体を僅かに震わせるが再度、同じ言葉を彼に告げる。
名前がない、と。
ガリガリと乱暴にディミルダが髪を掻き乱す。そして、不快さを露にしたままラースへと言葉を放った。
「おいラース、お前が何とかしろ」
「へぇ!?ヤダよ!名付けとか面倒くせぇ!」
「やれ。また俺に叩いてほしいのか?」
「うぐ……くそっ今回だけだかんな……」
チッと舌打ちをしてムッツリしたラースがつかつかと塊に近づいていく。
魔界で生まれた者同士であるためか、塊はラースに対して警戒心を見せない。先ほど食われそうになったにも関わらず、だ。
その様子に呆れたのかラースははぁと溜め息を一つ吐くと、瞬時に紅い眼を鋭く光らせる。
「光栄に思え、オレ程の悪魔に名付けて貰うんだからな。体に、魂に刻め、不変の流れに幾度流されようとも永遠に消せない、そんな真名を与えてやるよ!」
ニタリと笑ってラースの右手が塊の胸の中心掴んだ。
そのまま皮膚にズブズブと指を食い込ませていく。
カハッという乾いた声を溢し、塊の体がラースの方へと折れ曲がる。
「――――――」
空気を音ではない何かが震わせる。
ピクリと俯いた塊の体が震え、ゆっくりと顔を上げた。
先程より若干青ざめているが、瞳はまるで人が変わったかのように爛々と輝いている。
『人形に命が吹き込まれたみたいだな』
傍観しながらディミルダはそんな事を思った。
それからラースは右手を引き抜きつつ一言二言告げると後ろに下がった。
そして、塊が感情の籠った瞳をディミルダへと向ける。
「問題は片付いたか」
「オッケーオッケー。これで後は契約するだけだな」
「ケーだなー」
ラースの言葉を楽しそうに真似して塊が小首を傾げる。
それを了承と受け取り、ディミルダは新しい言葉を紡いだ。
「我が導きに応えし者よ。我が名と力を以てそなたを縛る。そなたは我の魔脈に沿いし者。為ればその脈が尽きるまで我が元でその魂を燃やせ」
「……仰せのままに」
スッと紅い瞳を細めて塊がクスリと笑う。
そうして仰々しく礼をした。垂れた頭にディミルダが黒杖を突き付ける。
『歪みから出でし者よ、証を捧げよ。深淵より出でし魂を、魂より出でしその名を、契りの証として、我に』
ボゥとディミルダの胸に光の円環が生じる。その光を掬うように手を伸ばし契約を結ぶ悪魔は無邪気な笑みを溢した。
『何もかもをご主人様の仰せのままに。わたしは、オレは、僕は、ボクは……ラスト』
瞬間光の全てが塊―ラストの胸に吸い込まれる。光はほどけて文字となり、するするとラストを照らして、やがて消えた。
そしてラストは己の主となった人物を見つめニコリと微笑んだ。
+++
「さて」
無事に新たな使い魔との契約を終え、ディミルダ達は部屋に帰ってきた。
名前を与えられた悪魔―ラストは部屋に入るなり感嘆の声をあげてチョロチョロと動き回った。
そんな使い魔をディミルダは襟首を掴んで捕まえると、そのままずいとラースの方につき出した。
「躾とけ」
「ハアァァァァァァ???バカかよお前。何でオレがこんな奴の面倒見なきゃ……」
「返事」
「いてっ!だからっ!同じとこを叩くなっ!!」
ドゴッ、ドゴッと容赦ない見えぬ手刀が再三ラースの頭に振るわれる。
寸分違わず同じ箇所ばかり痛めつけられ、ラースはまたも目尻に涙を浮かべた。
それでもディミルダは一切の手加減なく魔力を振るう。
「――ッ!分かった!分かったよ!見りゃいいんだろ!クソハゲ!」
「ハゲ?」
「喧しい言葉を覚えさせるんじゃないぞ」
釘を刺してからディミルダはラストを掴んでいた手を離す。
解放されたラストはとことことラースの隣に自ら歩み寄った。
並ぶとラストの方が頭一つ分は大きいため外見的にはラースが弟のようにも見える。
そんな使い魔を見やるとディミルダは体の向きを変えた。
「オレはやることがあるので書斎にいる。終わるまでにはしっかりものを教え込んどけ。
……魔力の方は死なない程度に好きにしろ」
ラースがハッとしてディミルダを見るが、彼はさっさと書斎へと入り扉を閉めてしまった。
使い魔だけになった空間でラースが不敵な笑みを浮かべる。
「オイ、お前」
「おまえ、わたし、ボク?」
「そうだ。お前、運が良かったな……他の奴なら今頃頭から食われてただろうに。オレに優しく、生きたまま嬲られるんだからな……!」
チロリと唇の端から紅い舌を覗かせてラースは愉しそうに笑うと、ラストの胸ぐらを掴んだ。
それをどう解釈したのか、ラストはまるでラースの真似をするかのように似ても似つかない無邪気な笑顔を浮かべた。
何冊目かの本を閉じ、ディミルダはその場でぐっと伸びをする。
ラースにラストを預けてからおよそ三時間ほど経っていた。
その間一心に読み耽っていた彼は、念入りに体を解すと書斎を出るために扉へ向かう。
リビングに行けば、使い魔達は何かしらをしてるところだろう。
別に面倒だから彼はラースにラストを押し付けたわけではない。
あれでも長寿のラースなので、魔界での生き方は骨まで染み付いている。
そんな彼にしか分からない力の上下関係や流儀はいくらでもあるだろう。
さっさと死にはしない限り悪魔は基本的に人間より長寿の生き物だ。人間の生き方より同じ悪魔にしごかれたり、痛めつけられた方が将来のためだろう。
あくまで、死なない限りは。
勢い余ってラースが食ってしまっても不思議ではない。
むしろ魔力が枯渇している―腹を空かせているラースからすれば魔力を自ら生み出し蓄えるラストはまさに極上の“餌”だ。
いくら共通の主人を持っていても万が一ということはある。
だが、それは然したる問題ではない。
食ってしまえばその分ラースは力を付けるだろうし、使い魔の補充が利かないわけではないと先程分かった。
なので扉の向こうがどういう事になっていても彼は驚かないつもりだった。
軽い動作でリビングへと繋がる扉を開ける。
「……ん?」
が、そこには誰の姿もなかった。
散らかった様子もないところを見ると、この部屋は使われなかったらしい。
ディミルダは首を動かして探知の魔法を巡らす。
すると寝室の方に魔力を見つけた。
一つの塊しか見当たらないのは余程密着しているか本当に一人しかいないか、どちらにせよ終わらせているか確認するため寝室の扉に歩み寄った。
ディミルダにとっては自室であるためノックもなく扉を開けて、彼は目の前の光景に眉を寄せた。
「…………何をしてるんだ、お前ら」
部屋の中央の寝台。
その上に一塊になった彼の使い魔がいた。
四本の脚は絡み合い、二つの胴はピッタリ隙間なく密着している。
上側から生えた二本の腕は二つの頭部を覆うように巻き付き、下側から生えた二本の腕はダラリとシーツの上に投げ出されていた。
「あ、ご主人様!」
上側の、覆い被さるようになっていたラストがディミルダに気づいて顔を上げる。
その顔は艶々としていて頬は赤く上気している。どうも興奮しているらしい。
ディミルダは眉間の皺を解しつつ口を開く。
「ラスト……ラースはどうした」
「え?ラースならここにいますよー!」
「やけに饒舌になってないかお前……?」
ニコニコしたラストがぐいと自らが覆い被さっていた体を抱き起こす。
そこには確かにラースがいた。
いたのだが、ラストに抱き抱えられた彼は若干、干からびていた。
腕同様に背中の翼もダラリと垂れ下がっている。
絶不調のサインだ。
「何をしてたか説明しろ」
「はい!えーと、ラースのお手本通りにぎゅーって貰う魔法を教えてもらいました!」
「……コイツ、コイツふざけてる……何が“生産型”だ……吸収狂いの淫魔じゃねぇか…コッチの魔力を搾り取りやがった……くそっ……」
そこで力尽きたようにラースの首がカクリと下を向いた。
そんな様子を見ておきながらそこまで追い詰めた本人であるラストは無邪気にラースの体を抱き締め頬擦りをする。
「ラース、すっごく美味しいのです!いっぱいいっぱい味わいたくなる、好き!」
人形を可愛がるように頬擦りを続けるラスト。
されるがままの虚脱状態のラース。
一通り観察をすると、ディミルダは静かに寝室から退室した。
「限りなく面倒くさいが退屈させない人材がきたもんだな」
そう呟いてリビングのソファにどっかりと座り込む。
彼の唇は愉快そうに弧を作っていた。
どうして生まれたんだろう。
それはきっと、彼らと出会うため。
育て育て帝の盾。
いつか帝すら自らに取り込んでしまう日まで、育て。
戻る
小説トップへ戻る