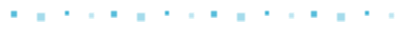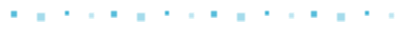
男装執事と女嫌い主人
思い付いたとこだけなので唐突に始まる。
+++
ニタニタと笑う相手に掴まれた腕ごと壁に押し付けられる。
心臓がドッドッと早くなるのが体の内側から嫌でも響いてきた。
「離してください」
先程よりも強い口調を使うが、男は笑みを浮かべるのみだ。
手のひらが汗ばんでいく。
「まぁそんなに嫌がるなよ。俺と遊ぶのは楽しいぜ?」
「お断りします。手を離してください」
「さっきから同じことばかりだな。つまらないって言われないか?」
品悪く顔を歪ませ男が顔を近づけてくる。
真っ青な心の内に真っ赤が混ざりあった気分になる。
瞬間、沸いた衝動のままにその言葉は勝手に口から出ていた。
「では、貴方の顔面を殴ってもいいですか」
一拍置いた後、男から笑みが消えた。
ぽかんとしたままこちらを五秒は見つめると、徐々に顔をしかめる。
「あー…何か言ったか?」
「わたしは貴方の顔面をボコボコに殴ってその体を張り倒してもよいかと言ったんです」
「…何を言い出すかと思えば、そんなことをしたらどうなるのか分かってるのか?お前のご主人様の顔に泥を塗るんだぞ。ん?」
掴んだ手に力を込めながら男が器用に右の眉だけ吊り上げる。
馬鹿にしているような態度に最早呆れている自分がいるのを自覚しながら、自由な方の拳を握りしめた。
主人の客に手をあげるなど、小学生でも分かるくらい愚かな行為だ。
ましてや執事見習いがそんなことをすれば、それこそ将来はないだろう。それでも、
「主人に、客へ甘んじて体を差し出すような使用人を抱えさせるくらいなら、殴って職を失う方が数万倍もマシだ」
言い切ってから、少しばかり我慢していた分を出し切るように掴まった腕を振って抵抗する。
驚いた男が慌てて取り抑えようとする動きに、自由な腕に力を込めた。
身動ぎにより一層近づいた歪んだ顔にありったけの嫌悪を向けて一発。
「成る程。忠誠心に溢れてるな、うちの使用人は」
殴ろうと振りかぶったところで、聞き慣れた凛とした声が響いた。
男がピタリと動きを止め、目を見開く。
小刻みに震え出す男ごしに、不吉な笑みを浮かべた主人―礼於(れお)が見えた。
わざとらしく高らかに靴音を鳴らしながらこちらへ近づいてくる。
すると、男はさっと掴んでいた腕を離すと、大きく息を吐き出してから奇妙に口角を上げて振り返る。
「おや?こんなところでどうしたんだ。まだパーティーの途中だろう?」
「そっくりそのままお返ししてやろう。こんな場所で遊びに興じているとはいい身分だな」
「誤解しないで頂きたい。これはこの者の方から…」
「そちらこそ何を勘違いしているんだ?全てを聞いた上で俺はこの場にいるのだ」
ひゅっと息を呑んで男が固まる。
礼於はいつの間にか笑みを消して、冷めた視線を男に向けている。
普段より華美な服装と相まって鋭さに磨きのかかった雰囲気は、直接見つめられてもいないのに背筋がゾクリと震えるほど恐ろしい。
それを一身に受ける男は青ざめたまま冷や汗をだらだら流す。
そして、全身を震わせて一歩後退ったかと思うと、よろめきながら礼於の傍らを走り抜けて部屋から出ていった。
遠くからガタンと騒々しい音が何度も響いた辺り、転げながら逃走していったようだ。
やがて騒音が消えると、勝手に肺から大きく息が溢れた。
体を見下ろせば掴まれていた腕が小さく震えていた。
「大丈夫か?」
先ほどの雰囲気が嘘だったように落ち着いたいつもの礼於が近寄ってくる。
完全に隣へ立たれる前に背筋を伸ばし、彼に大きな首肯を返した。
震えてしまいそうになる喉を深呼吸で宥めて、問いかける。
「…いつからいらっしゃったんですか」
「お前が壁に追いやられた辺りからだな」
「ということは始めの方から見ていたんですね…」
ならばもっと早くに手を差しのべてくれたらという言葉は呑み込む。
そもそも、助けられる立場でもないのに窮地を救われたのだ。そんな贅沢が言えるはずもない。
「…長く会場を外していて大丈夫なのですか?」
「なに、一通りの挨拶は済ませてある。特に問題はないだろう。
それにしても…」
不意に黙った礼於が不思議で、俯きがちになっていた顔を上げた。
真っ直ぐ見つめた先、目元を柔らかく下げて微笑む礼於の姿に思わず息を呑む。
互いの距離は一メートルほどで、いつもより僅かに近い。
整っていることは知っていたが、近いというだけで普段より目も、鼻も、口も、形が良いものに見える。
それでいて髪は艶やかに光り、肌は滑らかなのだ。
改めてこの人は綺麗だと思ってしまうのが不思議で仕方ない。
更に見慣れていない微笑を口許に浮かべているのだ。
嫌でも惹き付けられて、そちらへ意識を集中してしまう。
集中すれば、徐々に自分が見られていることが恥ずかしく思えてきた。
美形に無言で見つめられる圧力を感じて息苦しくなる。
礼於は喋らない。
一分ぐらい経ったところで恐る恐る口を開く。
「あの…どういたしましたか?」
「ん?ああ。お前が言っていた言葉を反芻していたんだよ」
「忘れてください」
「いいじゃないか。なかなか良かったぞ?流石は源次の孫だな」
「もう……」
茶化したように言われると自分の言葉をつい思い出してしまう。
これでもすごく怖かったのだ。
悔しさもあったから口が回ったけれど、彼の助けがもう少し遅ければヤバかった。
今更ながら全身が冷えきっていく感覚に襲われる。
もう一度深呼吸をして、落ち着くよう自分に念じた。
「とにかく、お前が無事で何よりだ。
折角仕事が定着し出した貴重な人材を失うのは勿体無いからな」
「そうですか」
「ああ。それに、深い忠誠心も見ることができたしな。今後に期待しているぞ、ひなた」
ニヤリという擬音が聞こえそうな笑みを礼於は浮かべた。
戻ってきた通常運転に非日常の恐怖が消え、代わりにドッと疲れが押し寄せる。
思わず目を細めながら溜め息を無理矢理呑み込んだ。
「このままちゃんと勤められるか、僕、物凄く不安なんですけれど…」
「なに、気にすることはないだろう。お前はただ俺に仕えていればいい。それだけだ」
それが不安なんですけどと浮かんできた言葉を、そっと胸に仕舞って苦笑した。
とりあえず、我が主人の機嫌が良いだけでもよしとしよう。
他のことは忘れる。忘れた。
よし、今日のあと数時間を頑張ろうか。
戻る
小説トップへ戻る