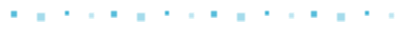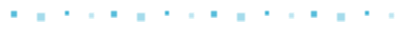
同じ色なのに
ギジュ…ギシュ…。
この世のものだと信じたくない耳障りな音が狭い洞窟内に響く。
全身を走る悪寒に体を震わせれば、温かな感触がそっと寄り添ってくれた。
不快な音は徐々に近づき、やがて、狭い入り口にそれは姿を表した。
狭いとはいえ二メートルはある入り口を埋め尽くす大きな体。
全身は見えないが、首から頭まで羽毛に覆われており、サッカーボールほどの眼球が飛び出している。
口には大小不揃いの牙がのぞき、間からは絶えずねっとりした涎のようなものが滴り落ちて地面を濡らした。
「ギ―――シァ――ェ」
ブルブルと小刻みに揺れながら奇怪な鳴き声を化け物が発する。
すると、その声に答えるように背中合わせの体温が動いた。
どんな会話をしたのかは分からない。
けれど、化け物は何か納得したらしく首をガクガク動かした。
そして、狭い穴の中で大きな体がゆっくり反転していく。
露になる化け物の全身に身の毛がよだった。
首の羽毛から下に一切毛はなく、体表はナメクジみたいにテラテラ光っていた。
下半身には何百を越える足とは思えない器官が蠢いていて土を蹴る。
まるで小さなウジ虫が餌に群がり動いているようだった。
寒気と、胃からせり上がってくるものに感じて目を逸らす。
ボクの様子を直ぐに察したのか、視界が黒に覆われた。
幾分か楽になって、こっそりと伺うように黒の隙間から化け物の方を見る。
不気味な音はするが、姿はすでに見えない。
遠ざかる音にホッとして、視界を覆う黒を静かに退けた。すると、今まで洞窟に転がっていなかったものが目に入る。
多分、あの化け物の涎や体表なんだろう粘ついた液体にまみれた身体。
ピクリと動かない、いつまでかは人間だったものが、四肢を投げ出した状態で捨てられていた。
「だい…丈、夫?」
鈴を転がしたような涼やかな声がこちらを伺ってくる。
恐る恐る肩に触れてきた部分は少し震えてた。
正直、大丈夫なんかじゃない。でも心配してくれる気持ちに心が落ち着いた。
だからボクは笑って、しっかり目と目を合わせて気持ちを伝える。
「大丈夫だよ。ありがと」
振り返った先。
ぐちゃぐちゃになった大きな瞳孔に、歪んだ笑顔のボクが写り込んでいた。
+++
それは、不意に訪れた。
ボクの人生は凡そ平凡で。
両親と一緒にアパートで暮らして、学校に行って、部活に熱中する毎日。
ただひとつ人に自慢できるとしたら、可愛い妹みたいな存在がいたこと。
それだけだ。
あの日だって、ボクは休みでダラダラとテレビを見てた。
前触れなんて何もなく、理不尽に変化は始まって、止める間もなく加速した。
お昼の地元番組の生放送。
まず、女子アナの顔がいきなり風船みたいに膨れ上がった。
え、と目を見張ったときにはすでに顔だったものが何倍にも大きくなっていて。
何の兆候もなく、爆ぜた。
ビチャビチャという水音。
何十もの悲鳴。
思い切り画面がぶれて、固いものが倒れた音と共にテレビ画面が砂嵐になる。
「なんだよ、今の…」
今更ながら気持ち悪くなって洗面台に向かおうと立ち上がる。
ふと、台所で母さんも片付けをしながらテレビを見ていたことを思い出した。
『あれ、なんだったんだろうね』
聞こうとした言葉はテーブルが両断された音にかき消された。
考えることも忘れて、走り出した。
玄関の扉を乱暴に開けて、走る。
台所にいたモノが何かなんて知らない。見てない。ボクは何も見てない。
真っ赤に裂けた大きな口が、鮮烈に頭に焼き付いていた。
外の景色は、地獄だった。
アパートの他の部屋からはみ出してる現実的ではないモノ。
道路に撒き散らされた赤や、青や、緑の液体。
じわじわと鼻の奥に広がる酸っぱくて腐っているような臭い。
時々転がる身体の一部だったモノたちが、ぐにゃぐにゃ動き回りながら形を変えている様に吐き気がした。
立ち止まったらいけない気がして、気持ち悪さを堪えながら走った。
考えたくなくて頭がズキズキ痛む。
そうして走った先で着いたのは、心愛の家だった。
生まれた病院が一緒だった縁で仲良く遊ぶ相手。
どうしてここに来たのか分からないけど、来てみたら途端に心愛が心配になった。
この状況で、怖がりな彼女はどんなに怯えていることだろう。
意を決して心愛の家に入る。
玄関から先は半分壊れて瓦礫になっていた。
心愛の部屋まで向かってみると、なんとかまだ壊れていないようだ。
安心して真鍮のドアノブに手をかける。
「心愛?大丈夫か?」
太陽の光が射し込む小さな部屋。
壁にはポスターが貼られ、棚の上にはぬいぐるみが置かれた可愛い女の子の部屋。
その中の薄暗い一角。
チェックの布団が敷かれた布団の上から緑色の肉塊がこちらを見つめていた。
「ち、イ…?」
爛れ、溶けた大きなひとつ目がギョロリと動く。
肉に細かく走った血管が絶えずびくびく震えていた。
足が地面に縫い付けられてしまったかのように動かなくて、ただ大きな肉の塊を見つめていた。
すると、肉の塊がどうやってかは知らないが逃げるように部屋の隅へ動き始めた。
目蓋のない目が壁と肉の間に隠される。
「、ないで…見ないで、見ないで見ないで見ないでえぇぇぇ!!!!」
部屋を震わせるほど響く叫び。
あの体のどこに口が、声帯があるのかは分からない。
分からないけど、耳に馴染んでいるその声を聞いた瞬間、全身から熱が引いた気分になった。
高いのに柔らかくて、優しい鈴みたいな少女の声。
「………心愛?」
ビクリと肉塊が震える。
そしてそいつは壁に擦り付けた体を小さく、丸く縮ませた。
まるで怯えるように。
一歩、踏み出す。
依然からだの内側が凍えたように寒い。
だけど止まらない足が動いて、肉塊の前へ。
「心愛…なのか…?」
ガタガタと震える右手をゆっくり肉塊に伸ばす。
触れて。怖くなって手を引っ込めて。そして、もう一度ちゃんと触れた。
視界から入る色の情報を裏切るように温かい温度。
ドクドクと動いているのがわかる感触。
そっと、隠された瞳に向けて顔を近づける。
微かに聞こえる呼吸の音が自分のものなのか、誰かのものなのかは定かではない。
ただ、ボクもそれも、ひどく心臓が動いていることは分かっていた。
薄暗さに目がゆっくりと慣れて、暗がりに隠された目が露になる。
ぐちゃぐちゃに潰れて濁った色に面影などない。
しかし、その目から流れる透明な水を見て確信してしまった。
この肉塊は、心愛であると。
+++
化け物は一日で地上を埋め尽くし、人々の文化の証だった景観は跡形もなくなくなった。
荒涼とした世界を化け物は我が物顔で歩き、自分より下等な生き物を飼うようにまでなった。
それは人間がペットを飼うように、化け物は人間を飼い出したのだ。
ただでさえ化け物に変化して少なくなっているのに、残った人間はいいように化け物の玩具にされた。
あるところでは見世物に、
あるところでは雑用に、
あるところでは食材に、
人間はされるがまま、抵抗もできずになすがまま。
そんな世の中でボクは幸運なのかもしれない。
心愛はどういうわけか、姿が変わっても人の意思を持っていた。
彼女はボクを自身のペットだと偽り、守ってくれた。
お陰でボクは人のように話し、動き、考えられた。
始めこそ、ボクは心愛を受け入れきれなかった。
変わり果てた姿を信じたくなくて逃げようと考えた回数は数えきれない。
でも、その声だけは変わり様のない心愛のものだった。
ボクの名前を呼んで、ボクに話しかけてくれる、昔から変わらない愛しい声。
「心愛」
「なぁ、に?チイちゃ、ん」
どこから声を出しているだなんてどうでもいい。
心愛は心愛だ。
ボクより一回り大きな丸い体と過ごすうちに手のようなエラがあるのがわかった。
今では小さな頃のように抱き締め合うこともできる。
瞳の動きで感情も分かるようになった。
最近では少しずつ、心愛がまた明るい表情を見せてくれるようになって嬉しい。
朝は一緒に起きてご飯を探して。
昼は目的もなく行きたいところを行きたいように二人で見て回り。
夜は小さな寝床で身を寄せ合うように共に眠る。
それを繰り返すだけの毎日。
でも、それでも幸せだと思った。
何もかもなくなった世界で、かけがえのない家族と生きる。
これ以上の幸せなんて、きっとどこにもない。
そして、この幸せはきっと変わらない。
二人でいる限りずっとずっと続く。続き続ける。
「行こう、心愛」
「うン。」
大きな丸い瞳が楽しそうに揺らいで、その体に包まれるよう抱きしめられた。
心を落ち着かせる緑色は、優しすぎるくらい温かかった。
―報告日誌No.57
―人類復興計画・推進課・特攻部の第4隊が一級クリーチャーを発見
―緑という珍しい体色を持ったクリーチャーは人奴を1人所有
―4隊が発見した際、人奴はクリーチャーに襲われており、隊員は直ちに戦闘及び救出を開始
―幸い負傷者はなく、所有されていた人奴も無事保護完了
―保護された少年は人格に激しい損傷有り
―現在精神課にて精密検査中である
―なお、排除したクリーチャーに関しては死亡確認後、即刻焼却による処分を行った
―以上
真っ白な部屋で、埃の臭いを嗅ぎながら横たわる。
人が話している。
人が動いている。
人に呼ばれている。のに、最早何も感じなかった。
目を閉じれば、脳裏に鮮烈に焼き付いたあの時が浮かぶ。
笑った瞳が歪みながら潤んで、愛しい声が「さよなら」と言った。
心安らぐ緑色は、真っ赤に塗り潰されてもうどんな色をしていたか思い出せない。
流れ出た血は同じ色なのに。
戻る
小説トップへ戻る