僕が何故こんな場所に居るかと言うと、それは紛れもなく彼女が呼び出したからに他ならない。
おい、呼び出しておいて黙りか。
彼女の脳内に直接話し掛ければ、遠い景色を眺めていた彼女がここで振り向いた。若干強めの海風に、彼女の腰まである髪が攫われる。
「ごめんごめん。綺麗だなって思って、つい見惚れてた」
悪びれもなくはにかんだ彼女は、僕より一つ上の先輩だ。それでも敬語を使わないのは、性分ゆえのと使うような関係ではないからだ。
今日はピンクなんだな。
彼女がまとっている服は、マゼンタピンクのワンピースだ。脛の半分までの長さがある。日差しを満遍なく跳ね返す辺り、素材は恐らくサテンだろう。マゼンタピンクをベースにしたワンピースには、白のレースが上から掛かっていた。彼女の足には白いパンプスが履かれていた。
「うん。最後になるんだしせっかくなら好きな色がいいなって」
そうか。
鼻を刺すようなつんとした潮の匂いが少し懐かしい。ここは以前彼女と来た場所である。所謂デートだ。その時はこれほど明るい時間ではなかったが。太陽もまだ高い位置にあるせいで暑い。汗を拭っても意味をなさない。すぐにまたじんわりと汗が浮かんでしまう。こんな時間に呼び出されて何かと思えば馬鹿なことを言われる始末。
俺は正直に言って腸が煮えくり返っているところである。
「そんな怒らないで。楠雄にやらせるの、結構罪悪感あるんだよ。これでも」
だったら今すぐここへ戻って来い。
僕からだいぶ離れた場所に居る彼女へそう言った。
「ごめんね。もう決めたことだから」
お前のことだ、どうせ一つのことに囚われてくだらない決断でもしたんだろ。
「くだらないって酷いなぁ。って、わたしの方が酷いか」
ほんとうにやるつもりか。
「この状況でやっぱ止めますなんて言わないよ」
言え。
「え?」
遠くからでも明瞭に聞き取れるのは、なにも僕の耳が発達しすぎているだけではない。彼女の声は、どこに居ても聞き取れる。声だけに留まらず、それは全てにおいてそうだった。彼女の一挙一動に、神経が占領されてしまうのだ。
言ってしまえ。今ならまだ許してやる。
手を伸ばしても彼女には届かない。ここで声を発しても同じく届かないだろう。そんな所に彼女は立って居るのだ。風がさっと吹く。暑い暑い太陽の下、辛うじて立っていることができるのは、氷にも似た冷たさを孕んだ潮風が涼しいからだろう。無ければ今頃きっと家に居る。
「ごめん」
彼女は静かに、申し訳なさそうに呟く。
「どうしてもこの気持ちは拭えないんだよ。楠雄にも言われたけど、わたしが幸せになるにはこれしかないの」
幸せ? 今からお前のすることのどこに幸せになる要素があると言うんだ。
「少なくとも今よりマシになるよ。もう耐えられない。もう泣きたくないの……」
脱力したような声は、震えていた。僕は息を呑んだ。彼女の見る初めての一面にはっとし、また言葉を失ったのだ。細く透明な線は太陽光によってきらきらと輝いていた。それは彼女の双眸から止まることなく溢れ続ける。笑うように細められても、瞳はいつにも増して輝き涙は頬を濡らしていく。
ほんとうにするのか。
「うん」
僕の気持ちを知った上でこの役をさせるなんて、お前はどこまでも酷い奴だな。
「ごめんなさい。貴方にこんな役を押し付けてしまって。ほんとうに悪いと思ってる」
僕の何が足りなかった。
唇を噛み締める代わりに拳を握る手に力が篭った。彼女はやんわりと首を横に振る。
「楠雄が悪いんじゃない。この選択を選んだのは、自分がどうしようもないくらい弱いから。貴方を信じきれなかった、強く在ることができなかった自分が悪いの」
だから自分を責めないで、と彼女は加える。
最早何を言っても無駄なようだな。
肩を落とす僕に、彼女は不器用に、申し訳なさそうに笑った。
「ありがとう、楠雄」
礼を言うや否や彼女は僕に背を向けた。かかとを浮かせ、下を覗き込む。その光景に駆け出したくなった衝動を抑えるように拳を強く握った。爪が平に食い込むなんていうことは、今はどうだってよくなっていた。姿の消えない彼女に、僕はどうしたのか疑問を抱いた。もしかして戻って来てくれるんじゃないか、そんなことを思った瞬間胸に一縷の希望が灯る。そしてその願いが叶ったのか、彼女が浮かせたかかとは地に着いた。
―――!!
自分でも解るほどの安堵感。重い岩が肩から降りたかのような安心感に頬が綻ぶところだった。彼女がこちらに振り向き、白いヒールで駆け寄って来る。
「楠雄!」
涙で潤んだ瞳に僕の顔が大きく映る。肩に置かれている手は、小さいながらも震えていて、唇には押し付けられた暖かな感触が伝わる。それが彼女の唇だと理解すると、その唇がうっすらと濡れていることに気づいた。
なっ……。
驚きに目を瞬かせるも、言葉を発する前に彼女が僕から遠のいてしまった。
「じゃあね楠雄」
おいっ……!!
咄嗟に手を伸ばしたが、その時には既に遅く彼女は届かない範囲にまで走って行ってしまっていた。そして今度は振り返ることなく地の境界線を飛び越してしまう。一瞬にして視界から消えてしまった彼女の体。何が起こったのかと理解する時には、ドボン、と海面に何かがぶつかる音がした。弾かれるように現実へ引き戻された僕は、普段は決してしない全速力で、人が立っていられる地の境界線のぎりぎりにまで近付いた。息が上がって呼吸が乱れるが、それを気にすることなく目を右往左往と動かす。睨み付けるように隈無く行き渡らせるが、彼女の姿はない。
くそっ……。
喉を迫り上げる異物を吐き出してしまいたくなった。かつてないほど、心臓が苦しい。苦々しい気持ちで充満したこの胸を落ち着かせるには、どうしたらいいのか。それは超能力を持ってしても、実現できるものではない。立っていられるはずもなく膝から崩れ落ちてしまう。岩のゴツゴツとした感触に膝を打ち付け、痛みがするもそれを上回る胸の痛みによってそれは掻き消えてしまった。
あの馬鹿っ……!
最後に見た彼女の顔は、今までで見たことがなかった顔だった。胸が満たされたと、心から笑みを浮かべた瞬間だった。嬉しそうに頬を綻ばせ、白い歯を見せて笑った彼女は、僕の腕に掴まることなくするりと抜けて、居なくなった。
あんなに幸せそうに笑ってっ……!
僕ではさせてやれなかったあの表情。見たかった表情ではあったが、それはこんな場面ではない。遠い未来、誓うであろう一生の時、その顔が見たかった。だが、それはもう叶わない。僕は呼吸を落ち着かせ立ち上がった。彼女から任されたことが一つある。全神経を自分に集中させる。そしてそれを一気に外へ放出する。瞬間、風が吹き荒れ木々がざわめき、崖を打ち付ける波が荒々しくなった。思わず風に体が乗せられそうになったが、なんとか持ち堪えた。だがそれは束の間の出来事で、一分もすると嘘みたいにしんと鎮まった。あれだけ木々をざわつかせていた風もぴたりと止み、汀を打つ波もすっと引く。太陽は素知らぬ顔で空で輝いている。再び暑くなったことに舌打ちを零す。いっそのこと太陽を消滅させたくなるが、それはぐっと堪えた。僕は彼女に関する記憶を持つ人達から、彼女の記憶だけ抜き取ったのだ。彼女という人間は元から存在しないと、記憶を改ざんした。今頃家では彼女の私物に、親が首を傾げていることだろう。写真からは彼女のみが消え、当然のように学校のクラスメイト達の脳内からも消えてしまった。戸籍からも彼女のものは無くなっているはずだ。
こうさせたのは他でもない、彼女本人だ。
『親からも友人からもバイト先の人達からも、自分と関わった人達からわたしに関する記憶を全て消して欲しい。』
僕に超能力が備わっていることを知った彼女は、存在を消して欲しいと頼み込んできた。当然ながら一度は拒否したが、彼女はそれでも粘り強く頼み込んできた。
冗談じゃない。誰が恋人の存在を消したいと思うんだ。
だが彼女は、僕だからお願いしてるだの楠雄じゃなきゃ無理だの誉めそやして僕にこの役を押し付けたのだ。だから僕は尋ねた。何故そうしてまで消えたいのかと。
『悲しまないためだよ。』
そう答えた。では、存在を知っていてなおかつ恋人の僕は悲しんでいいということか。
『できることなら楠雄の記憶からも消えたいよ。でも、どこか楠雄に覚えて居てほしいという気持ちもあるの』
僕を一生縛るつもりかと聞けば、彼女は慌てふためきながら違うと言うだろう。だが結果は同じだ。実際に僕は体験したことのない胸の痛みと、生きながらに焼かれるような耐え難い苦痛を味わった。こんな痛みを忘れられると思うか。
恨むぞ。
僕から離れたお前を。僕の愛する恋人を奪ったお前自身を。僕にお前を愛する権利を奪ったお前を。一生恨み続けてやる。だが何より恨めしいのは、彼女を救えなかった自分だ。彼女の自殺への執着と依存は最初から知っていたことだ。自分は無価値だと頑として譲らない自己肯定と、自身の体など顧みない無鉄砲さ、そして死んだ方が幸せという到底理解できない思考回路。それは人に相談して変えられるようなものではなく、身に染みて拭えない、言ってしまえば人が呼吸するのは何を持ってしても変えられない事実であるように、彼女にとっての自殺は、何にも変えられない幸福感を与えてくれるものであるのだ。まるで死を崇高し崇拝する彼女に、そうちょっとやそっとの甘い言葉や無責任な言葉は、全くもって意味をなさない。当たり前だ。そんなので彼女の死への執着が無くなるというのなら、マインドコントロールでもして無くしてやる。彼女のは単に理性で語っているのではない。本能が既に生きることを拒否しているのだ。だから彼女の心や思考は常にどう死のうかの一点張りであった。
僕の言葉なんて、最初から届いていなかったのだ。
何度抱き締めても、何度話し掛けても、彼女には届いていなかった。その証拠があの笑顔だ。満ち足りたという感情を惜しみもなく顔に浮かばせたあの笑顔は、僕は見たことがない。あんなに幸せそうに笑う彼女は、この先僕では見せられない顔だろう。「死」に嫁ぎに行く花嫁の如き純粋無垢な笑みは、やはり「死」というものが、そうさせたものに他ならない。
「一生忘れてやらないからな」
お前が忘れろ忘れろと懇願しても、置いて行ったお前の言葉なんて受け入れるわけがないだろ。久しく零した自分の言葉は、柄にもなく震えていた。
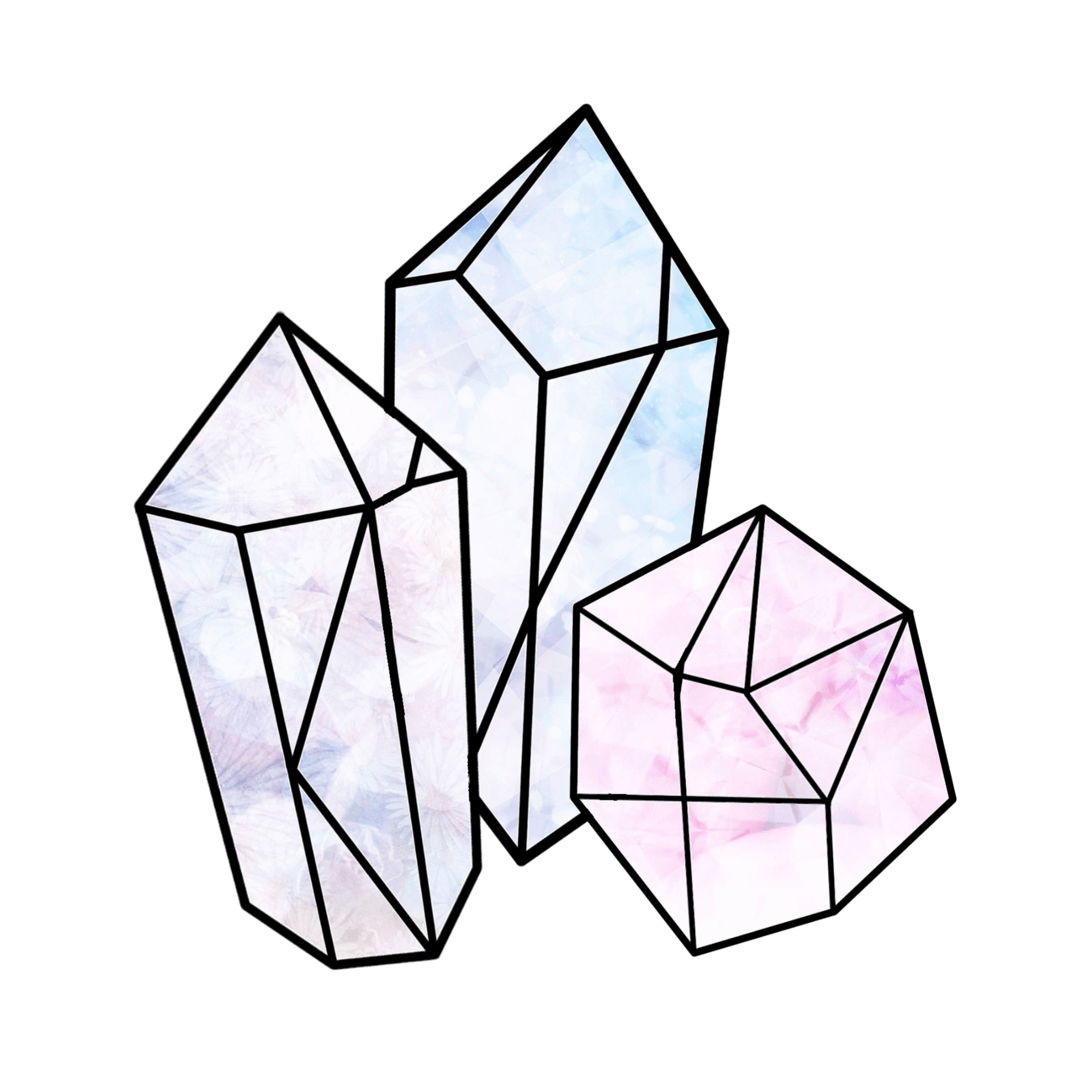
そうして彼女は居なくなった
、