電話でいきなり「来て」と短いメッセージが来た時は、首を傾げる程度だった。だけど今は来てほんとうに良かったと思ってる。動転する心臓を今は置いといて、床で喘ぐアイチの肩を抱く。
「アイチ、アイチ。しっかりして」
私の存在を知らせるように揺さぶる。でも彼は私を見ているようで見えていない。まるで私を通して何かを見ているよう。彼の瞳は昏い海に呑まれていた。時折喉を絞められているような、短い悲鳴を漏らしながら歯を震わせる。その振動が彼の手を抱く私の手を伝って、心臓まで揺さぶった。彼の感情が伝染してくるようだ。悲しく、辛く、それでも逃げられない。息苦しいだけの痛み。こうやって彼の肩を抱いてやることしかできないなんて。喉の奥に感じた痛みを押し込めて、彼の名を強く呼んだ。
「アイチ。もう大丈夫、ここにはあんたを傷つけるものなんてないんだよ」
彼を貶す言葉も、彼を突く奴らも、彼を見下す冷たい視線もない。ないはずなのに、彼にはその情景が見えてしまっている。私の言葉なんて届かないはずだ。胡乱な目をしたアイチに普段の優しい彼の面影などなく、そこには過去に囚われた優しいが故に苦しめられている理不尽しかない。ぎりっと奥歯を噛み締める。何故彼が。私が同じ学校であれば。そう思うのは何度目だろう。けれど過去は変えられないし、そこへ繋ぐ鎖も断ち切ってやれないのだ。逃げるように俯いた私の耳に、アイチの細い声が聞こえてきた。私を呼ぶ震えた声。繰り返される度言外に責められているようで、目の奥で様々な思いが弾け飛ぶ。
「もうどこにも行かないよ、絶対。私が着いてる」
この手を離したりするもんか。傷ついて泣くアイチなんて見たくないのだから。言い聞かせるのは私か、彼か。けれども「大丈夫」と言い続けるうちにアイチの嗚咽が小さくなり、小刻みに跳ねる肩が次第に平生を取り戻していく。彼がぽつりと吐露した。
「いつもごめんね、迷惑かけちゃって」
「アイチなら歓迎だよ。なんてね。迷惑じゃないから気にすんな。アイチは悪くないんだから」
「うん」
深く呼吸してなんとか宥めているようだが、やはり彼の曇った表情は晴れていない。何か言うべきか逡巡した。彼の肩が少しでも楽になるようなら言葉をかけるべきかもしれないが、取り繕うとする姿勢は彼が立ち上がろうとしている意志かもしれない。その意志を掬うならあえて何も言わない方がいいかもしれない。アイチの肩を支えていた自分の腕を下ろす。床に着けた手を彼がすくい上げて、ぎゅっと握った。力を込めていないそれは、込めていないのか込められないのか。縋るように絡められた手を、今度は私が強く握り返した。繋がった手から気持ちが伝わればいいのに、歯痒さを殺して彼を見据えた。
「ずっと一緒。ずっと、ずっとね」
「なんで名前はこんな僕に優しくしてくれるの?」
「んーと、友人だからじゃダメかな。私、アイチのこと誰よりも大切な友人だと思ってるんだけど」
「僕を?」
「他に誰が居るってのさ」
「だ、だって、君はいつも人に囲まれてるから。僕なんて友人と言ってもらえる価値ないって、そう」
「まぁーた暗くなる。アイチのそういうとこ、謙虚通り越してもはや卑下だよね。やめなよ」
気落ちする雰囲気を一掃するように、彼の頭をさっと撫でて立ち上がる。道中新しい店ができているのを思い出したのだ。決して余裕があるわけじゃないけど、今日くらい使ってもいっか。必要経費ということで親にお小遣い前借りしよう。甘いものを食べながら言い訳を考えることにした私は、床に座って上目遣いに見上げる彼に手を差し伸べた。
「気分転換に外出よ。行きたいとこあるんだ」
「うん。あ、あの!」
「ん?」
「ありがとう。いつも」
「気にしないで」
「名前は」
「なに?」
離されたばかりの手に彼の手が重なる。目を丸くし、繋がれた手を見つめていれば、彼は遠慮がちに開口した。
「僕から離れないよね?」
不安なんだろう。あの時アイチはひとりだった。肝心な場面で私は別の場所に居て、できたことはせいぜい話を聞いて肩を抱くことだけ。責めるだろうと覚悟していた私を、彼は何を言うでもなく、私の言葉に耳を傾けて信用してくれている。私はその信用と、彼との関係を大切にしたい。何より彼自身を。粒子程度の不安が肩に降りかかるなら、それを私は払い除けたい。アイチ、私は絶対に離れないよ。押し込めた気持ちを伝えるようにその手を強く握り返した。
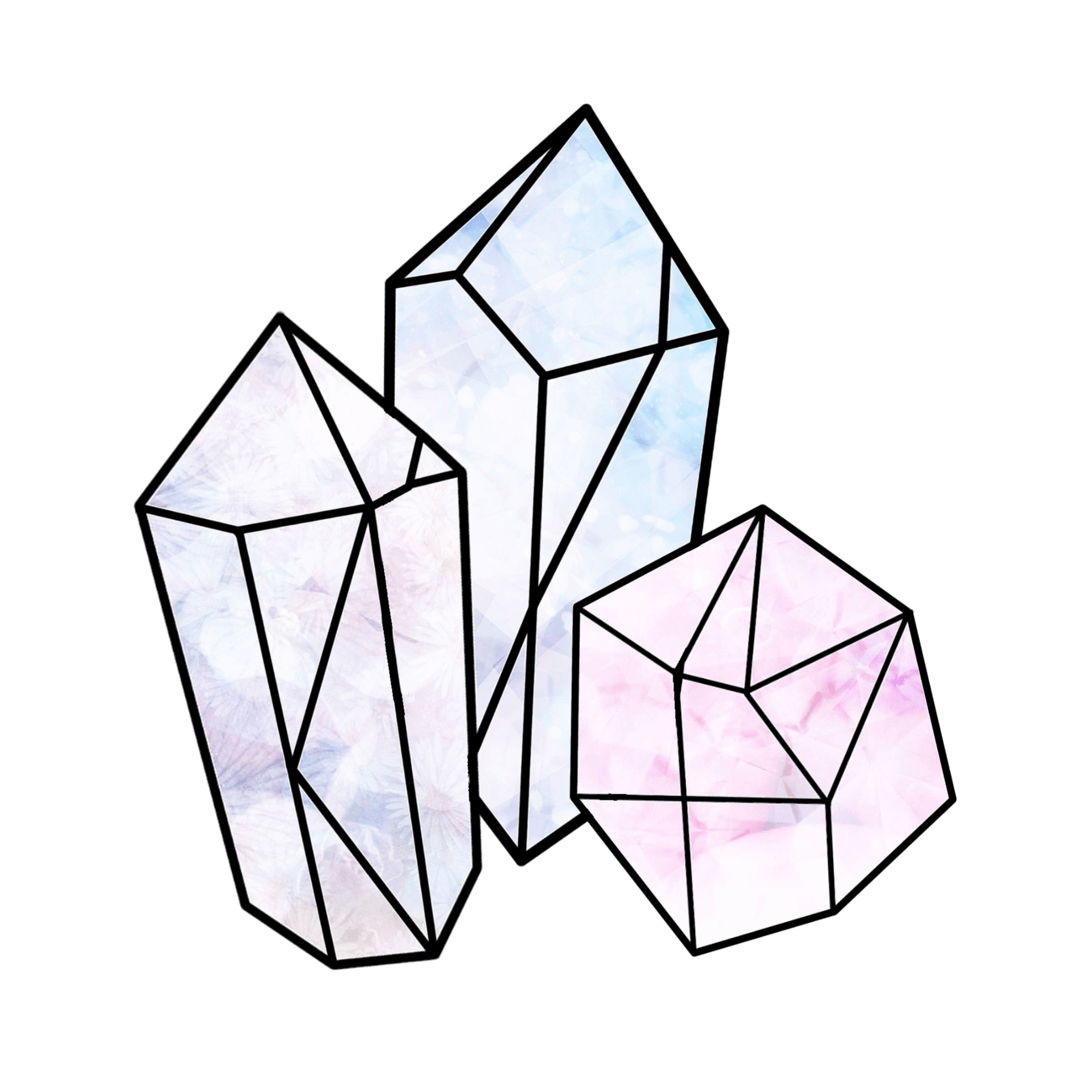
沼に落ちる音
、