※気が強いアイチ。
あ、これアカンやつや。リビングの戸を開けて即座に理解した。外の冷気が立ち込める玄関先を忍び歩き、オレンジの暖かみある灯りが磨り硝子から漏れる扉をなるだけ音を立てないよう開けたつもりだが、室内に居た彼はおもむろに顔を上げた。
「おかえり」
それはもう見事な笑顔と言えよう。聖母と見紛う程の優しさに満ちた微笑みを浮かばせ、首を傾げる動作に海のように青い髪がさらりと揺れた。扉を開けっぱなしで直立不動の私に駆け寄って、アイチは私から鞄をさらっていく。
「お腹、空いたよね。座って待ってて、すぐ温め直すから」
すみません、飲み会の帰りです。頭を下げて謝る隙も与えずに椅子に座らされた。鞄を置きに私の寝室に入ったのを見届けてからようやく呼吸をする。やばい、完全に怒らせた。アイチから「ご飯食べる?」と来たのが定時になる一時間前の四時。食べると返したのは四時十分。彼から「出来たから待ってる」と来たのは六時。それに「今から帰る」と返事したのは数分後。そして今。時計の針は日付を大幅に過ぎている。
「やっちまった……」
携帯の着信履歴は九時から十分刻みにアイチの名前で埋められている。メッセージだって八十以上入ってた。開いたのは同僚と上司に誘われた居酒屋を出た後だったが。煽てられるがままハシゴなんてするんじゃなかったと、満面の笑みを浮かべるアイチを見て後悔し始めてるが、事はもう後の祭り。滅多なことでもないと眉毛すら逆立てない彼がああなっては腹を括るしかない。過去に一度だけ、今と同じ態度の彼を見たことあるが、自分が悪くないと解っていても折れそうになった。心が。仏の顔も三度までと言うが、彼の場合は三度どころか十度くらい仏の顔を見せるので、その分怒った時はそりゃあもう末恐ろしい限りである。ともかく、だ。今はアイチにひたすら謝るしかできない。何言われても、何されても謝ろう。きっと明日になれば許してくれる。はずだ。私の寝室から出てくるアイチを見て、我先にと口を開く。
「あ、あの……」
「ごめん、待たせちゃったね。今温めるね」
「えっ。え、ええと……」
「今日は君の好物を作ったんだ」
どうしよう、全っ然話聞いてくんない。それどころか目すら合わせてくれない気がする。なんとか謝ろうと機会を探るが、ことごとく彼に先手を取られてあえなく撃沈した。金魚のように口を開閉させても時間は過ぎるもの、彼の怒りも減らぬもの。レンジのチン、という音が部屋に響き、彼は軽い足取りでそれを取りに行く。嬉しそうに、平然と。ぐっと固唾を飲み込むが、この状況を打破する名案は浮かばない。彼の機嫌を治すどころか彼の作ったご飯を食べないといけないプレッシャーに胃痛がしてきた。胃に入れまくった酒が出てきそう。借りてきた猫の状態で肩を縮こませていると、目の前に続々と皿を並べられた。
「召し上がれ」
「あの、アイチ……」
「口に合うと嬉しいな。さ、食べて食べて」
促されてはもはや選択肢はない。普段ならおかわりする量さえ、この状態においては大盛りにすら見える。堆く積まれた白ご飯が湯気を燻らせ、グリルでこんがり焼かれた鯵からは心無しか哀れみの眼差しすら錯覚した。ええい、ままよ。頂きます、そう言って箸を取る。目を細めて対面に向かい合うアイチに見られながら、白ご飯を限界の胃袋に詰め込んだ。あかん、吐きそ。喉に戻ってきそうになっても当然だが吐けない。吐けるわけない。悲鳴をあげる胃袋を無言で黙らせる。
「ご、ご馳走様でした……」
やったよ母さん。私、頑張ったよ。母さん他界したけど。内心で自分を褒め讃える。逆にそうでもしないとこの空気に耐えられないのだ。にっこにこのアイチから放たれる雰囲気は、とてもだが胸を撫で下ろせるものじゃない。彼に聞かれたことのみを口にし、それ以外はすべて喉の奥に引っ込める。これくらいしないとアイチの琴線をぶち破りかねない。箸を置くのを見て、彼は満足そうに頷いた。席を立つ。
「うん、お粗末様でした」
私が食べ終えた皿たちをせっせと重ね、キッチンへと持っていく。その背中を見てようやく意思のとおりに身体を動かせた。
「私が……! 私が洗うよ」
「ううん、大丈夫だよ。座ってて」
「いや、さすがにそれくらいは……」
「いいから。座ってて」
ね? と語尾に付け加えられ、椅子に再び腰を落とした。こ、怖すぎる。言葉は優しくても、半端ないくらい怒りが含まれている。力強い「ね?」には一生敵わない気がする。大人しくアイチの帰りを待っていると、皿を洗い終えた彼が戻ってきた。椅子を引いて向かい側に座る。
「――それで? 何か言いたいようだけど、どうしたの?」
謝るなら今しかない。
「ごめんなさい!!」
「ごめんって、何が?」
「アイチからの連絡に気づかなかったこととか、飲み会に行くって伝えなかったこととか……」
「飲み会に行ってたんだ」
「うっ。はい、そのとおりです。上司に誘われて断れずにそのまま……」
「楽しかった?」
「えっ?」
「飲み会、楽しかった?」
「う、うん……。それなりに……」
何が聞きたいんだろう、アイチは。いつもの彼からは結び付けられないほど落ち着いていて、私を捉える視線もいつもどおり。喜怒哀楽が素直なアイチじゃないのだと、改めて思い知る。そしてこの状態の彼に、私はあまりにも無力だ。冷静沈着のその腹に何があるというのか。
「前から何度も言ってるよね、僕。飲み会に行くのは構わないけど、ちゃんと連絡してって。十時過ぎるなら迎えに行くからって」
「はい……」
「これで何回目かな。定時になる一時間前に連絡したのに、たった一時間でそのこと忘れたんだよね? なんのために携帯があるのか解ってる?」
「返す言葉もないデス……」
「注意して直してくれないなら、させないようにするしかないよね」
「と言うと?」
「会社が終わるのは五時だよね。じゃあエントランスで待ってて。迎えに行くから」
「えっ、そんな大袈裟な」
「それと飲み会禁止。携帯、出して」
「な、何する気?」
「何って、位置情報を共有できるよう設定するんだよ」
「ちょ、やりすぎでしょ! 何もそこまでっ」
突拍子もない要求に勢い余って椅子から飛び起きる。大きな音を立てて椅子はそのまま床に倒れたが、私は目の前に座っている彼に言葉を続けた。これが初めてじゃないけど、でもこれからはちゃんとする。定時前に返事もするし、出た後もこまめにチェックするし、万一飲み会に行くことになってもちゃんと、絶対に事前に連絡する。
「だから……!」
「ダメだよ」
「アイチ……っ」
「名前の『これから』は信用できない。よく聞いて、僕は何も君を縛り付けようとか、疑ってるわけじゃないんだ。僕と違って、社交的で明るい名前に何か遭ったらと心配なだけなんだよ」
「信じてよ、アイチ……」
心臓に杭を打ち込まれたようだ。激痛が走り、上手く息ができない。頭がぐわんぐわんする。好きな人に疑われるなんて。信じてって、どうやったら彼は受け入れてくれるんだろう。でも目の前のアイチはゆるりと首を横に振った。
「僕を好きなんだよね?」
「そりゃあもちろん、好きだよ」
「ならできるよね。安心させてくれるよね、名前なら」
「でも!」
「――もういいよ」
がたん、とアイチが席を立つ。視線を落として吐いた言葉は思わず全身が固まるほど冷たくて、鼓膜を突き破って脳を縛り付けた。俯く彼の顔色は窺えない。でも、何となく察せる。そしてとうとう琴線をぶち破ってしまったことも、察してしまった。ゆらりゆらりと歩み寄って、彼の動向ひとつひとつに食い入る私の頬に手を宛てがった。身長は僅かばかりに彼の方が高いので必然と見上げる形になるが、アイチの青い髪がまるでカーテンのように私の顔に落ちてきて、濃い影が広がった。仄暗い視界でぎらつくふたつの目玉。ぎょっとすると同時に、気道が締められる感覚を抱いた。
「どこにも行かないようにしよう。会社にも。大丈夫だよ、君ひとりを養う稼ぎはあるんだ。だから安心して」
それってつまり監禁するってことじゃないか。アイチの稼ぎは私を軽く凌ぐほどだが、誰かに寄生して生きるなんて望んでない。それに私だって飲み会に行きたいし、友人とどんちゃん騒ぎだってしたい年頃だ。報連相はちゃんと守るけど。でも、望まない温室のために自由を手放すなんて嫌すぎる。首を横に振った私に彼は言った。
「ご飯は美味しかった?」
「えっ、うん。美味しかった、けど……」
どうして今それを問うのだろう。私の答えに満足そうな顔を見せるが、何か関係でも? と思った時、思考が弾けた。
「まさか……」
あのご飯に何か混ぜたと言うのか。だからアイチはこんなにも笑っていて。そう考えた時、足元から得体の知れぬ何かが這い上がってくるような感覚に、全身の毛が逆立ち、目を限界まで見開く自分の顔をアイチの瞳を鏡として見て取れた。
「何も入れてないよ」
途端にそう言われて「は?」と間抜けな声が漏れる。この脈絡では誰でも何か入れたと考えるだろう。でも彼は違うと首を振る。顔が引いていき、落とされた影は部屋の明かりに溶けた。呆然と見つめる私に彼は笑みをその口に湛えながら手を差し出した。
「携帯、出してくれるよね?」
この顔と声音で言われたら誰でも首を縦に振るだろう。私みたいに恐怖からではなく、心の内から絆されて。アイチは普段はとても温厚で、誰にでも分け隔てなく接する物腰の柔らかい人物だ。だけど怒ると反論のしようがないほど詰めてくる。改めて肝に銘じた。アイチを怒らせてはいけないと。おずおずと「はい……」と言うしか、私に選択は残されていなかった。
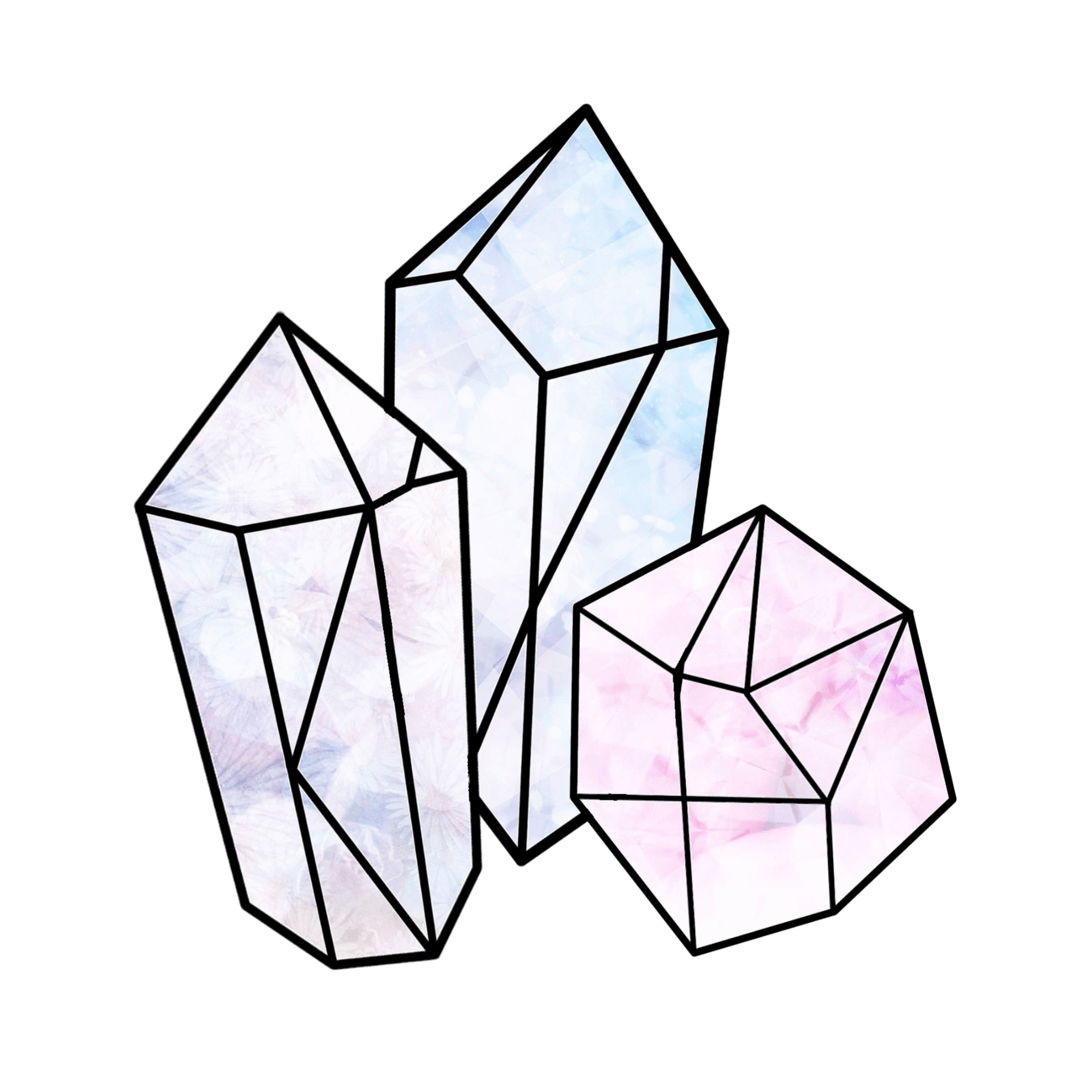
私の恋人は恐ろしい人
、