熱湯はすっかり冷めてしまい、突っ込んだ指先から震えが駆け上ってくる。ぼやきながらも水の中から引き上げた服をばさっと広げ、胸元を注視する。好きで好きで、大好きで堪らない服なのだけど、今ばかりは好きなものを前にしても渋面は和らがない。薄くも目を引く一点の染み。こうして何度も洗剤を溶いた水に浸けて擦っているが、一定段階から染みの濃度は薄まらないでいる。泣きたい気持ちに駆られた。
「さっきから何してる」
染み抜きにレモン汁を当てるかと苦悶する耳を、落ち着きを払いすぎて冷たい印象さえ残る低い声が叩いた。洗面台の戸口に彼は立っていた。染髪剤を使っても決して同じになれない彼の綺麗な茶色の髪が視界に飛び込む。よく見かける制服はタンスの中で、家の中ではもっぱらラフな格好をしている。そんな彼は不思議そうに私を見ている。隠してしまいたくなったが、どうせ自分のスキルじゃ子供ひとり騙せやしないので大人しく白状することにした。
「服の染み抜きしてる」
「汚したのか」
眇られる視線は「またか」という意志を込めていた。言外に責めるその視線を正面から否定するべく、掲げていた服を彼の前に突き出した。見ろと言わんばかりに。
「これ! この位置でどう汚せって言うのよ」
「汚されたのか」
「そう。昨日知人と会ってくるって言ったじゃない? カフェに行ったんだけど、その時すれ違いざまに肩がぶつかってしまって、相手が持っていた珈琲が掛かってしまったの」
あの後すぐお手洗いに駆け込んで水を浸したが薄くさせるだけで、完全に抜き取ることは不可能だった。物は試しと洗濯機に放り込んだが、結果はご覧の有様。おかげで指の熱は失われて、冷たさが肌に張り付き感覚が少し麻痺している。それを知った櫂に手が拐われる。拍子に服が落ちてしまい、水分をしとどに含んでいるそれは洗面台のタイルに叩きつけられた。爪先に水飛沫が飛ぶ。
「ちょ、櫂……?」
「一体いつから水に浸けていた」
「大袈裟ね。何も死にやしないんだから、そんなに構わなくても」
「お前が構わないから俺が構うんだ」
「過保護なことで」
忠告と言うか、前置きしておくが私と櫂は決して恋人と言う関係ではない。夫婦でも家族でもない。ただの腐れ縁という関係だ。年齢に匹敵するくらいの付き合いなのでこのように互いの家に入り浸ることもしょっちゅう。家族同然みたいに育ったし、長時間一緒に居ても苦痛と感じる仲じゃないから、時折顔を出す私の両親でさえ関心の留めるところでない。なんなら土産は櫂の分も含めて買ってくるほど。
「学校の女子がこんな場面知ったら卒倒するよ……」
「何か言ったか?」
「なにも。それより、櫂、今日のお昼はなに?」
「クリームシチューだ」
「ブロッコリーあげるね」
緑野菜は嫌いだ。特にグリーンピースとブロッコリー。匂いからしてもう駄目で、それらは余さず櫂にあげている。納得しない顔をしながらも頑として食べない私に折れてくれ、律儀にも毎回食べてくれるのだ。ありがたい、ありがたい。タイルに張り付く自分の服を拾い、水を張った樽にまた沈める。櫂は「まだするのか」と呆れた風情で見遣る。
「お気に入りの服だから大切にしたいの」
「……わからんやつだ」
「でしょうね。ほら、さっさと行くよ。シチューが冷めちゃうじゃない」
何か言いたげな櫂の眼差しを無視して洗面所から追い出す。「早く来い」という櫂の声を適当に流しながら服に目を落とす。樽の底に沈む服。これは自分のお気に入りだが、それは単に好みのデザインだからではなくて、誰にも興味ないといったふうに無愛想振りまく彼が、誰でもない私のためにと選んでくれた物だから。向こうはただの幼馴染としてしか認識してないようだけど、私の中ではとっくに好きな人へと変わってしまっているのだ。だから、きみが贈るすべてのものを大切にしたいと思ってしまうの。この関係を変えるのは、まだ先でいいのだけどね。
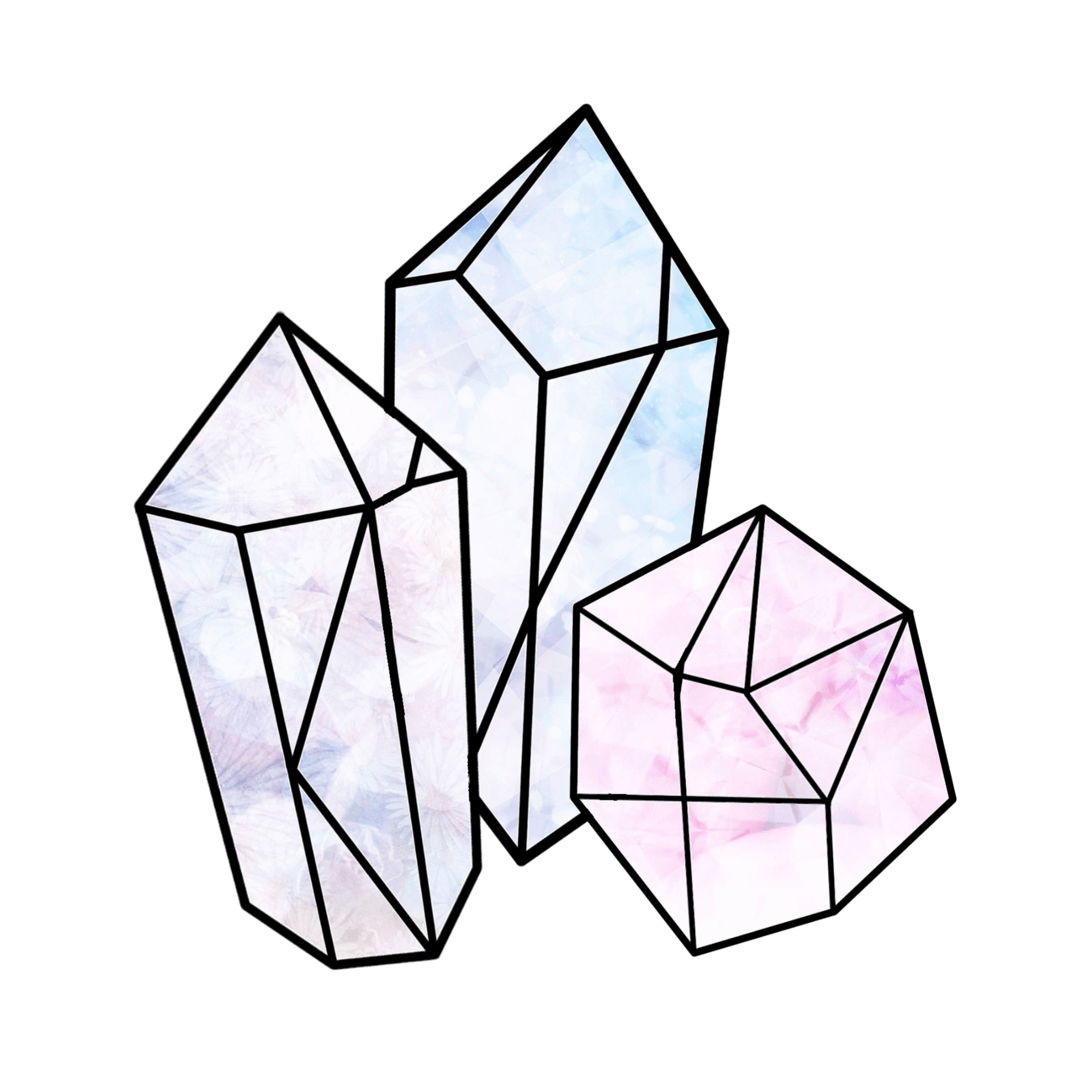
沈めないと気が済まない
、