蝉も鈴虫も寝静まった夜は時間を忘れてしまうまでに異質だ。いつしか風は絶え、蒸した夜気がたれこめる。幸いなのはここが奥羽であること。故郷の壱岐は通年暑く、潮風が少々辛い。反対に奥羽は冬は厳しいものの海から幾分離れているため夏は冷涼に過ごせる。
「寝れねえのか」
「政宗様……」
庭に面する廊下に現れたのは夫だった。見慣れた甲冑や六刀は携えておらず、肌小袖一枚に打掛けを羽織っている。庇に切り取られた月明かりが崩れ落ち、枯茶色の髪や双眸に冷ややかな光が乗る。問われたことにどう返答するか迷って沈黙していると、傍までやってきた彼は自分の打掛けを私に掛けた。
「これでは貴方様が風邪を召されてしまいます」
困惑する私を一笑に付してみせる。
「んな弱くねえ」
「……ありがとうございます」
それきりお互いの空間に言葉はなかった。音なく吹いた風に衣がなびき、視界を覆った髪を抑える。夏の匂いが鼻を掠めた。雨上がりの土の匂い。青葉の香り。今日も変わらぬ夏の匂いが満ちている。荒々しい日常などなかったかのように泰然とやってくる太陽と月。変わらない、なにも変わってない。変わったのは私達の方だ。胸を突き上げる寂寞を吐き出すように言う。
「今宵は一緒に寝てくれませんか?」
袂を握ってしまう弱さを見逃してほしい。袂に隠す弱さを咎めないでほしい。真っ直ぐに見られない弱さを否定しないでほしい。一度湧いてしまったら最後、数え切れないくらいの目も当てられない惨憺たる気持ちが胸を飲んでしまう。すると袂に隠した手をそっと握られた。咎めるふうでも、否定するふうでもない。優しい手つきに感じた。硬い指がそれぞれの指の間に割って入り、複雑に絡められる。隙間もなく密着した彼の手は私の手など覆ってしまうくらい大きくて、暖かい。背を見せた彼が歩き出すと縫い付けられていた自分の足も歩み出す。小さな歩幅は彼の体躯には見合わない。やがて視界がうっすら滲む。
「夜の雨は体に障る」
そっと夜空を見上げる。重い雲がたれこめる中、一点の星がきらりとこぼれ落ちた。それを皮切りに、堪えきれなくなった粒たちが頬を滑っていく。ごめんなさい、ごめんなさい。口にできない謝罪を胸の内で繰り返す。私を愛してくれた者達が瞼の裏に蘇る。こんなにも鮮やかな色を持つのに、その彼らは全て記憶の中でしか息をしない。変わらない温かさを持っているのに、立場が変わってしまったがためにその温かさは捨てなければいけない。ゆるして、ゆるして。あなたたちを置いていく私の弱さをゆるして。こんな時でも我が身可愛さを考えてしまうのだから神も救い難い。冷たい雨音が響く中、けれども握られた手だけは確かな熱を持っていた。
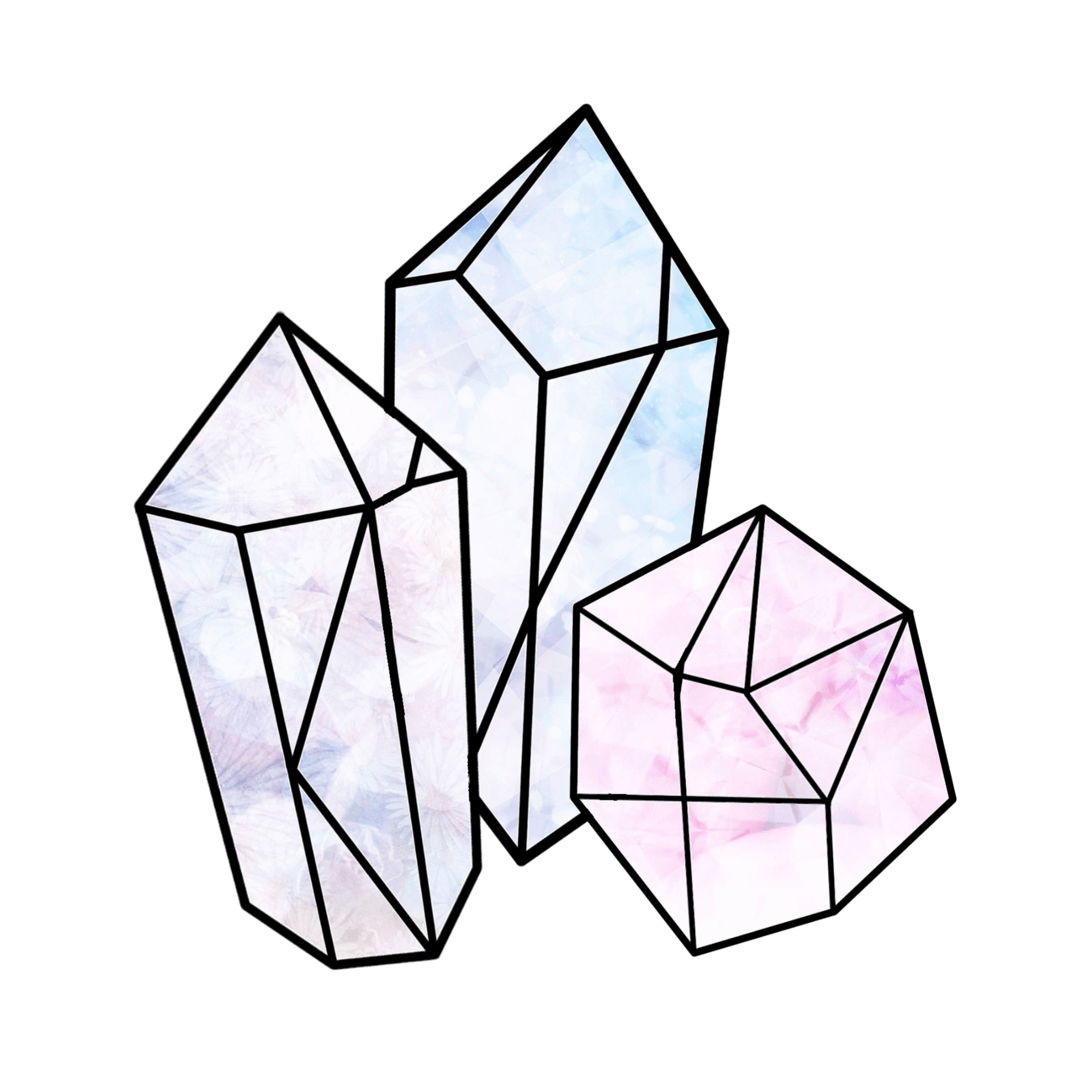
その先に何を見るか
、