午後八時。日がどっぷり沈んだ空には雲が渋滞を起こして今にも雨が降りそうだ。折り畳み傘も持っていないので足早に家へ向かう。夜闇に浮かぶ目当ての家の明かりに肩が軽くなるのを感じて引き戸に手をかける。
「たっだいまー!!」
入ってすぐの土間で靴を脱ぐと同時に眼前の襖が開かれた。現れたのは政宗のお目付け役の片倉さんだった。いかつい面も疲労困憊で遅くに帰宅した私を心配する優しさも健在で、そんなんだから「遅くなるなら連絡しろといつも言ってるだろう」というお小言にも嫌な気はしない。
「片倉さん片倉さん」
「政宗様なら諸用で席を外しておられる。おい、靴を脱ぎ捨てたままにするんじゃねえ!」
「いいよぉ、政宗の顔見たら帰るもん」
「そういって寝落ちすんだろうが」
「あー、なんのことかわかりませーん聞こえませーん」
「てめえ……」
「今日のご飯はなんだろ」
青筋を立てる片倉さんは置いといて大広間に立ち入る。私と政宗は幼馴染だから子供の時から何度も来ていて、大人になった今でもこうして仕事帰りに立ち寄って夜ご飯を一緒している。なんといっても片倉さんの作るご飯が美味すぎるのだ。母親は早くに亡くなり、父親は仕事人間。そんな家庭だから政宗に「なら俺の家で食え」と言われて以降お邪魔している。今は完全に自炊が面倒すぎるっていう理由だけど。
「疲れたー……」
だだっ広い広間に寝そべる。スーツのままで。シワになるとか汚れるとかこの際知らんぷりした。天井の照明から壁にかけてある時計に目を移すと八時半過ぎてもうすぐ九時。いつの間にか片倉さんの姿が消えているのは夜ご飯を温め直しているからだろうか。嬉しさもあるし申し訳なさもある。政宗の幼馴染っていうだけで要らない負担かけちゃってるし。でも仕事柄帰宅して自炊とかできないのでなんだかんだ甘えてしまっている。今度野菜でも買ってこようかな。そこへ政宗が戻ってきた。
「今帰ったのか」
「そうだよぉ、くたくたになっちゃった」
「今日も頑張ったな」
「もー超頑張った! ぎゅうして!」
「OK. Come on.」
腕を広げた政宗の懐に飛び入る。背中に腕を回してぎゅうっとなけなしの力を込めて抱き締めると、「まるでガキだな」と鼻で笑われながらも頭を優しく撫でられた。昔から政宗はこうだった。嫌なことあるとすぐに放り出して駄々をこねる私を撫でて抱き締めて慰めてくれる。中学の時も高校の時も変わらなかったから、今でも甘えてしまう癖は抜けない。彼自身が気にしてない様子だし直す気もないけど。ぐりぐりと硬い腹に頭を擦り付けるとふいに名前を呼ばれた。ん、と顔だけを上げる。大きな手が額の髪を払い除けて薄い唇が落とされた。
「お疲れ様」
ふ、と薄く笑むその様に心臓が痛いほどに痺れた。
「もー! 相変わらず顔がいいね、政宗は! 大好き……」
「おいおい。顔だけかよ」
「うぅ、顔良すぎる……。目の保養だぁ……」
「聞いちゃいねえな……」
呆れたように息を吐く。やだな、顔だけじゃなくて私を甘やかすところもちゃんと好きだよ。言い置くが私と政宗は別に恋人ではない。甘え気質が抜けない私が一方的にべたべたしてるだけの、幼馴染の域を出ない仲だ。
「仕事嫌だな、行きたくない……」
ぽそ、と呟くと、それまで撫でていた手がぴたりと止まった。
「辞めるか?」
静かに問われたそれに一瞬頷きそうになった。迷いを断ち切るように首を振る。
「……まだ頑張る」
大嫌いな職場で大嫌いな人達と、大嫌いな仕事をする。嫌いづくしで日々参るけど、こうやって政宗が撫でてくれて片倉さんの美味しいご飯を食べれるうちはまだ向き合っていられる。踏ん張れる力を貰える。やっぱり明日野菜買ってこよう。
「……Don’t push yourself too hard.」
「どういう意味?」
聞いても返事は来ず、ただ頭を撫でられるばかりであった。がんばるよ、がんばる。私を応援してくれる政宗や片倉さんのために、頑張って立ってみせるよ。もう逃げまくってた昔の私じゃないもの。意識は緩やかに微睡みの中へと落ちていった。
◆◆◆
十分も経たずとして寝息が聞こえてきた。腕の中で眠る彼女を起こさないように抱き上げ、広間を出る。俺より軽くて俺より細い奴は、俺のためにと言ってその体を酷使して帰る。日に日に窶れていく顔付きと黒ずんでいく目元に気づかないと思っているのかと口にしたくなる。
「隠せてねえんだよ」
苛立ち混じりに呟くと「政宗様」と前方から小十郎がやってきた。手には眠るこいつのためにと作られたご飯があったが、すうすう寝る彼女を見て眉をひそめた。
「また寝やがって……」
「疲れてるんだろ」
「起こしますか?」
「いや、寝かせておく」
「かしこまりました。ではこれは朝食へ回します」
「ああ」
いつもなら奥へ下がっている小十郎だが、今日はその気配を見せない。
「どうした」
「騙せているのかと思いまして」
「思ってるんだろうよ、こいつの中では」
こいつはそういう女だ。昔は逃げ回る彼女を引っ捕らえることに苦労したが、今はどう逃がそうかとばかり苦悩する。俺が願うことは昔から変わらない。母親を早くに亡くし、父親はこいつを気に留めることもなく家を留守にしていた。そんな中でこいつが他の誰でもない、俺だけに頼ってくることに嬉しささえあった。初めて小十郎の飯を食って「いっそ政宗と暮らしたいよ」と初めての弱音を吐いた時も、精神的にも肉体的にも弱ったら俺を頼るようになった時も、俺は嬉しくてしょうがなかった。だというのに今では俺から離れようとする。一人で立っていようとするときたもんだ。なんのためにここまで彼女の全てを許してきたと思っているんだ。
「離れるって言うなら力づくにでも閉じ込めるだけだ」
彼女を苦しめる職場から、人間から、全てから。彼女を奮い立たせる彼女自身の意思からも引き剥がして、俺の元からどこへにも行かさないようにするだけだ。だが、今はまだその時ではない。彼女の知らぬところで準備は進んでいる。あとすこし、その時が来れば。何も知らぬ彼女は安らかな寝顔を無防備に晒していた。
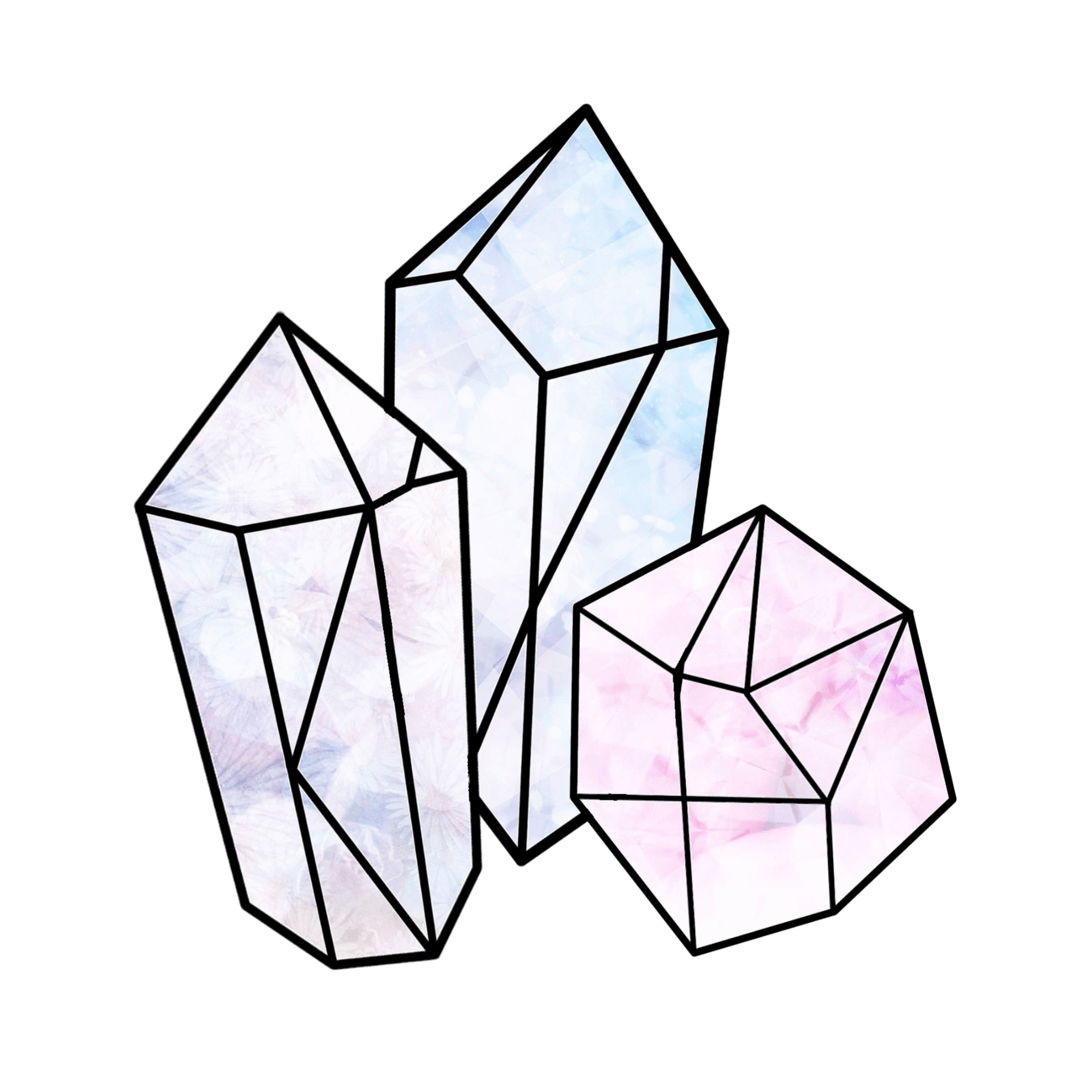
これをなんと呼ぶか
、