彼氏と別れた。元親に簡潔的かつ端的に伝えたら「分かった」とだけ返され通話が終了する。慰めてもらいたかったわけじゃないけど、彼らしからぬ冷たさにじんわりしていたら家の外からけたたましいバイクの音が聞こえてきて、二階の自室から顔を覗かせた私に「行くぞ」とこれまたぶっきらぼうにヘルメットを投げ寄越した。
「つめたい」
私専用にと購われたヘルメットとバイクに跨る元親に視線を交互にやっていたら「さっさと来い」と促され、困惑も緩和されぬままバイクで攫われた。そしてやってきたのが瀬戸内の海。ただいまの時間は四時半。午後だと思うでしょ? 朝の四時半である。そんな時間帯に電話かけた自分が言えた義理はないけど、何も朝の四時半に海辺に連れて来なくてもと思ってしまうのは私が冷たいのに大変弱いからである。本人はと言えば静謐に横たわる黒々しい海面を、さながら太陽でも見ているがごとく眩い眼差しで見ていた。
「冷たいよ、寒いよ」
ぶうぶうと文句垂れて隣に座る彼の裾を摘めば、海を見ていた顔を私に向けて呆れたような表情をうかべる。
「お前なぁ……。黙って海を見れねえのかよ」
「だって寒いもん。ねー、寒い」
「だぁー引っ張んな! ガキか!」
「元親が連れて来たんでしょ。いーもん、鼻水出たら元親の服で拭いてやる」
「もたれかかんな!」
ぐりぐりと肩に押し付けていた頭を軽く叩かれた。女子に無体を働くなんて男の風上にも置けない。そんなんだから隣の女子からは海賊だのヤンキーだの不良だの怖がれるんだい。元親と私は所謂幼馴染というやつで、彼が姫とか言われて揶揄されてたのも知ってるくらいの古い仲である。あの後私が親の仕事を理由に長く離れていたのだが、高校進学を気にまたこちらへ戻ってきた。再会した時は図体のでかさと携えていた男衆に目を見張ったものだ。だって白い肌と柔らかい髪と可愛らしい笑顔が印象に強かった元親が、よもや筋肉累々の大男になってるなんて誰が想像できよう。しかも舎弟なんか作っちゃってるし。長く顔を会わせていなかったとはいえ昔みたいに話せることはとても嬉しかった。元親以外の友人とはきっぱり縁が切れちゃったし、地元だというのに新天地に来たような心細さしかなくて、懐かしさなんて全くなかったから。元親が居たから親と離れても寂しくなかったし、楽しい日々が送れたと思う。自立できたから。できたから、好きな人だっていたのに。
「やっと静かになったな」
頭頂部を雑に撫でられる。やめてとか髪が崩れるとか、思う言葉はいっぱいあるけど、どれも言葉にできなかった。つんとしたものが胸を突き上げ、嗚咽が漏れる。鼻を通る空気はちょっぴり潮辛くて視界がいっそうぼやけた。風に撫でられる海の音が耳に届き、香水と海の香りが混ざった人工的な匂いが鼻に届く。いつもうるさい元親が黙って傍に居てくれるので頭を傾けた。香水より海の匂いが強くて笑いそうになった。元親は海が好きだ。特に瀬戸内の海が。冷たいのが嫌いな私は「海はいやだな。冷たいし危ないし」と言ったことあるが、その時は「危なくねえ、それにあったけえ海なんてないだろ」とあしらわれて馬鹿にされた気持ちになった。だけど今になって彼のあの時言いたかったことが少しだけ分かった気がした。温かい海なんてない。海はいつも冷たいものだ。冷たくて、危なくて、海は生命の母なんて言うけど安心感とか全く抱けない。だけどそういうものひっくるめての海だ。たぶん、この世界どこにも絶対なんてない。それでも生きたいと欲張らずにはいられないのだから、私は明日も海がすぐ傍にあるこの地に足をつける。
「……元親」
「どうした」
「ありがと」
全てを投げ出したくなっても、嫌になっても、明日が来るし私は生きる。返答の代わりにさっと頭を撫でられた。分厚い雲を光の筋が穿つ。いくつもの細い筋はやがて海面に広がり、目を見張るような鮮やかなオレンジへと染め上げていった。
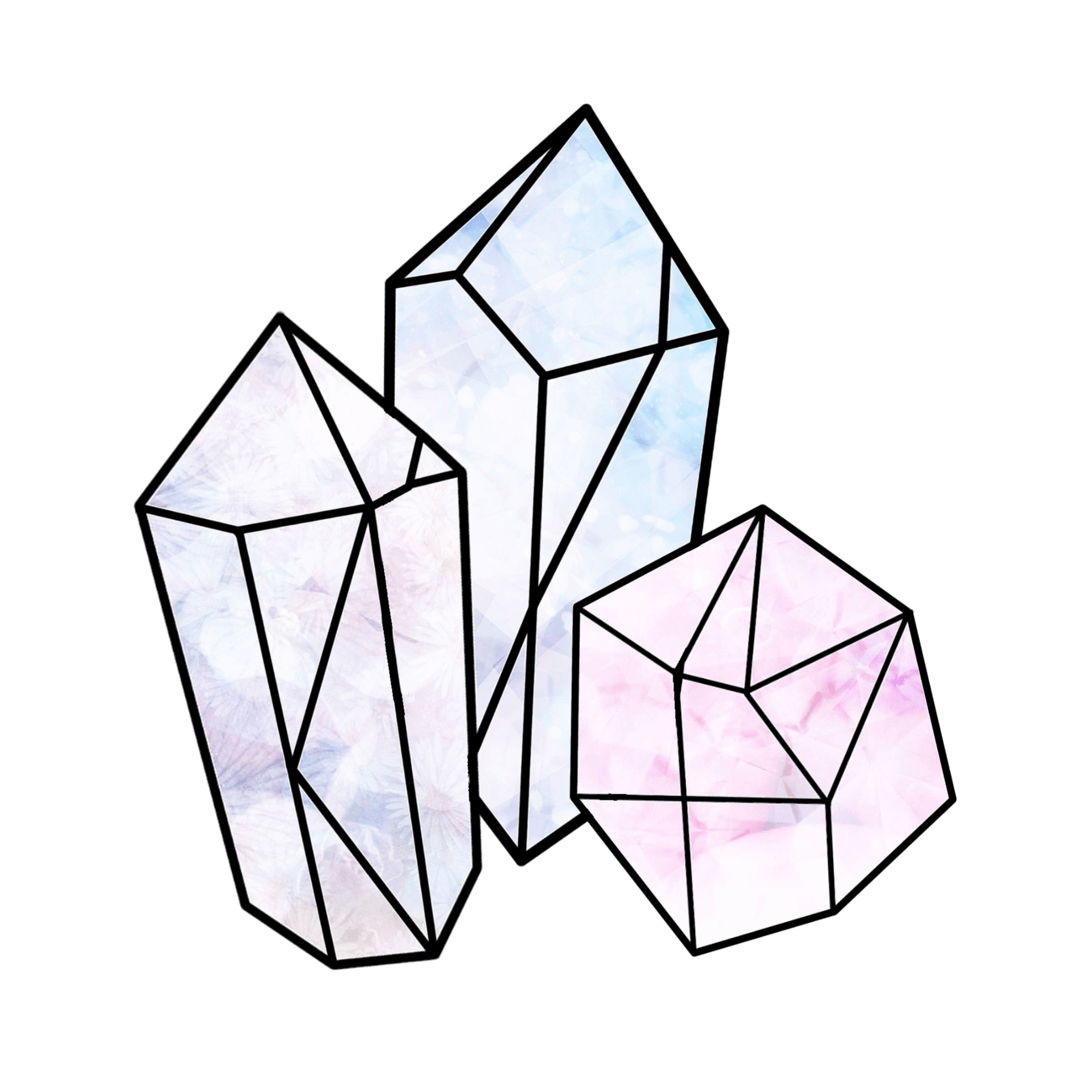
起きる海、笑うきみの温かさ
、