吐き気が止まらない。体の違和感に気づいたのは顔を洗ってる時だった。腹の辺りがなんだか重い。最初はその程度だったのだ。一時的なものだろうと気に留めずご飯を食べて家を出て教室に荷物を置いた頃、不調は悪化した。一限、二限、三限と腹の不調は続きしまいには吐き気さえ伴っている。三限の授業が終わると同時に机に突っ伏す。浅い呼吸で息をしながら目蓋を伏せている間は少しは和らぐからだ。きもちわるい、きもちわるい。耳へなだれ込む雑多が煩わしく感じて教室を離れたくなったが、ぐるぐると中を掻き混ぜられているような腹を抱えて歩ける自信はなかった。保健室行こう、そう思うものの脚が動かない。
何も喉元を突き上げないが、吐きそうな強烈な違和感はある。最悪の体調だ。額から流れた汗が冷たい。腹を擦る手が服をぎゅっと摑んだ。この間も昼休憩の雑多はうるさくなっていき、まるで耳元で何十人もの声を聞かされているよう。ああだめ、これ以上は無理。なけなしの体力と気力で教室を出て保健室へ向かう。自教室の隣は階段になっているが保健室は階下の反対側にあるのでそこそこ距離がある。いつもならなんともない距離だが、この状況下では遥か遠くに感じられた。重い体を引き摺るように保健室へ入ればそこは無人だった。先生も居ないのかと見渡すがもぬけの殻。仕方ない、誰も居ないのは却って好都合。そう思い、ベッドを囲むカーテンを開けたところで一人の男子生徒と顔が合う。
「珍しいねこんなところで会うなんて」
目を丸くして軽口叩く佐助に言い返す気力なんてなく、そうだねと返して空いている方のベッドで横になる。スプリングが音を立て、白いシーツに深々と沈んだ。後ろの方で何やら音が聞こえるものの、構う余裕はないので無視することにした。目蓋を閉じ息を深く吐き出す。気持ち悪さが和らいだ気がする。このままだったら眠れそう。だが、それをさせてくれないのが猿飛佐助という男である。
「随分顔色悪いね、また我慢して授業受けてたでしょ。もー、俺様が何回言っても聞きやしないんだから」
ぎし、とベッドが音を立てて大きくへこむ。背後に彼が乗り上げたのだと解った。世話焼きといえば聞こえはいいものの、佐助の場合は通り越してオカンである。しゃもじ片手に呆れる姿が容易に想像ついて笑ったこともある。慣れたことなので放置して寝入ることに集中した。
「……手のかかる子だよほんと」
ふいに気配が動いた。さらりと髪が揺れる。撫でられているのだと理解する。これもいつものことなので放置。撫で慣れているような手つきにイラッとしたが、こんなことに目くじら立てたら自分が疲弊してしまう。それにそんなことしてる余裕もない。とろ、と意識が転ぶ。徐々に呼吸が深く静かになっていく。
「こんなことすんの、お前だけなのにな」
撫でられる手つきにふわふわした感覚を抱き、最後の方何を言っていたか聞き取れなかった。
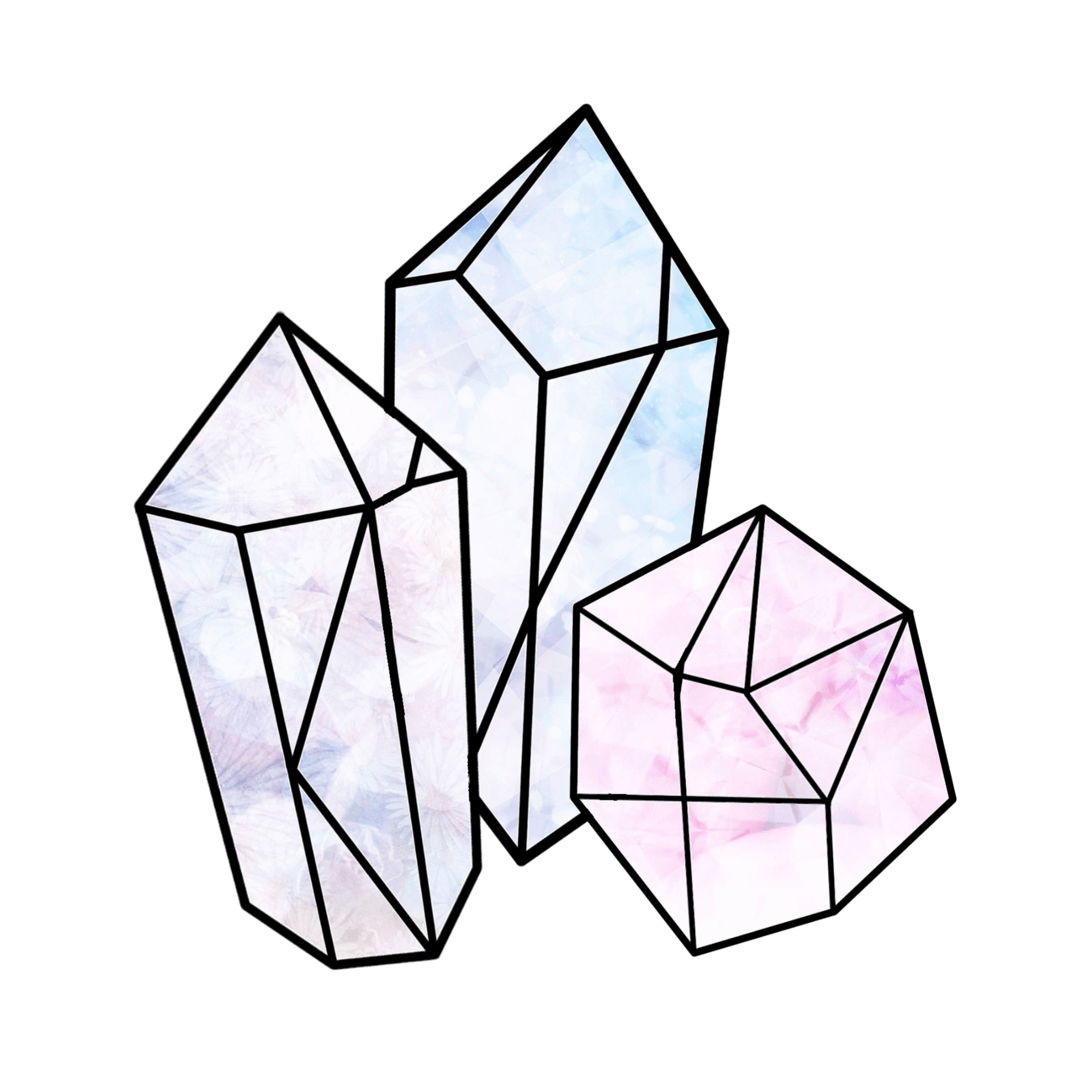
ゆらり、ゆらり
、