奥村雪男は名前負けしてる奴だと思う。泣き虫だし、色白美肌だし、女みたいに線が細いし、抱き締めたら温かくて柔らかかったし。雪男、なんて。
「よう、女男。今日もカリカリしてんな、量多い日か?」
「……ここは公共の場ですよ」
「んな朝っぱらから登校してる奴なんざあたしらしかいねえよ」
昼間は正十字学園の生徒として校舎へ行くのだが、今の時間は始業時間一時間前。当然だが教室には自分と雪男以外誰もいない。それは隣のクラスも含めて。日直でもないのにこんな時間に登校するのは、祓魔師としての出勤と雪男自身の性格に由来するんだろう。同い歳なのに雁字搦めな生き方してるのを見てると胸が苛立ちでいっぱいになる。静かな教室内に携帯の呼出音が鳴り響く。雪男のだ。対応した彼は席を立つ。
「仕事か?」
「ええ」
「おいおい……。三十分前だぞ」
「開始時間には間に合います」
待ての二文字すら言わせてくれる前に出て行った。雪男の席には教科書が詰め込まれた鞄が置かれている。
◆◆◆
あの後、雪男は言った通り授業開始前に戻ってきたし、なんの代わり映えもなく午前の授業が流れたし、いつも通り女子の鬱陶しい誘いに苦笑している。入学当初よりかは慣れた手つきで誘いを去なし、裏庭のこぢんまりとした東屋で風呂敷を広げていた。
「そこ詰めろや」
「急ですねほんと……!」
「お、今日は唐揚げか。燐のやつ料理の腕ますます上げたな。ありゃいい嫁になる」
「人のおかずに手を出すほど足りないのなら学食を使えばいいでしょう……」
「たっけえの。その割に量もねえし。あーあ。燐くらい料理できる上か下かいりゃあよかったなあ……」
「意外ですね」
「んあ?」
「あなたなら兄さんに集るか僕のを丸ごと持っていくと思ってました」
「カツアゲかよ」
「実際昔はよくしてたでしょう」
奥村兄弟とはここへ来る前、つまり藤本神父の元にいた時からの付き合いだ。だから雪男が泣き虫であることも、燐が喧嘩を理由に獅郎から絞められてたこともよく知ってる。その過程で燐の手料理を食べたことだって何度もあるし、家庭事情を知ってる獅郎から何度も誘われたこともある。二人には言ってないけど。いやあ、こうして振り返るとどの記憶に兄弟が出てくんのな。濃ゆい付き合いだよまったく。
「気分じゃねえや」
そう言って購買部で買った焼きそばパンの袋を開ける。作り置きだから当然温かいわけもなく、焼きそばのソースの味が舌に味気なく広がる。こっちに来てからあんまり燐に会ってない。雪男と殆どいるからたまに会うことあるけど、前みたいに絡むことはしなくなった。最初はその変化に顔を合わせる都度物言いたげな顔をしていた燐だったが、頑なにいつも通りですアピールと不必要な絡みをしないことを徹していたら、いつしか向こうからも顔を出さなくなった。
「……兄さん、寂しがってましたよ」
燐はそういう奴だ。良い奴なんだ。親でも友人でも、自分みたいな奴でも。悪魔の血とか関係なしに人を引き寄せてはあっという間に人の輪を自分の周りに作れてしまうような奴だ。だからそこから外れようとする奴には目敏く気づくし、まるで自分がなにかしたんじゃないかってふうに見てくる。自分の感情を隠そうともしないあいつだから雪男もこんなに素直に言ってくるんだろう。
「じゃあお前はどうだよ」
「なにがです」
「寂しいか?」
「なにに対して寂しがるんですか」
「ほんとにわかんねえの?顔いっぱいに書いてあんのに」
「……わけのわからないこと言って僕で遊ぶのはいい加減やめてください」
疎ましげに眼鏡の奥から眦を吊り上げる。鋭い眼光に肩を竦ませてパンを頬張った。嘘じゃねえんだけどな。どうせそう言ったところで雪男はこっちの言い分になんか耳を傾けてくれない。そんなところは名前通りにならなくていいのに。
「なあ雪男」
「なんですか。くだらないこと言うようなら戻り」
「言わなきゃ伝わんねえもんってあるんだぜ」
隣の空気が変わるのを肌で感じとる。下りた沈黙の幕で、言葉を続けた。
「たとえ親子でも兄弟でも、言わなくても伝わることなんてねえんだ。口にしなきゃそれはないも同じ」
「……なにを言いたいんですか」
「燐は人の素直な気持ちを蔑ろにしない奴だってことは、お前がよぉく知ってると思うぜ。それを踏まえてアドバイスだが、お前はもう少し自分の気持ちを大切に」
「必要ありません」
自分の言葉は雪男のそれで先を切られた。空になった弁当をてきぱきと片付け風呂敷をきつく結ぶ。雪男、と呼んだ声に彼は振り向くことをしなかった。東屋の庇に切り取られた向こう、青い空に向かって真っ直ぐ立つ雪男の背中はいつの間にか大きくなっていて、黒い壁にも思えた。ざあっと風が吹く。冬の気配を乗せた肌寒い風だ。昔はこんな風にさえ寒いと言って肩を震わせていたのに。どんな表情か見えないが、彼は寒がる様子を見せない。それはどうしようもなく虚しく感じた。
「僕に必要なのは兄さんを守れる力だ」
「それでいいのかよ。このままだとお前の方が早くに壊れちまう」
「壊れませんよ。……僕がいなくなったら兄さんは一人になってしまうから」
その瞬間に見せた綻んだ笑みに心臓がきつく締め付けたれた。なんで。なんでだよ。何故お前はいつもそうやって泣きそうな目で笑うんだよ。悲しそうな顔すんなよ。雪男、と呼んだ声に彼は反応しなかった。青い空の向こうに消えていった。ざあっと風が吹く。傍に植えられた枯れ木が身を震わせた。雪男はこんな木みたいに既にボロボロの体を引っ張って銃口を向ける。なあ雪男。お前はいつも燐に隠れてあたしに「兄さんを守れる強い祓魔師になりたい」と言ってたよな。あの時、どんな顔してたかお前は思い出せるのかよ。あたしは覚えてる。泣き虫には相応しくないほど幸せそうな顔だったんだ。「兄さんと一緒にいたい」という理由だけでお前はそう言ったんだ。なのに、今はお前はどうだ。泣きそうな目で、悲しそうな顔で、燐が無事でいるならと今にも死にそうな覚悟で。
「お前自身の気持ちはどうなるってんだよ、馬鹿野郎……」
お前が燐を守りたいように、あたしはお前を守りたくてどうでもいい祓魔師になったんだ。ほんとうは悪魔が見える私を嫌悪する両親に、取り巻く環境に、そしてそう産まれてしまった自分自身に嫌気が差していつでも死ぬ気でいたんだ。獅郎に何度諭されても変わらなかった自分が変わったのはお前が理由なんだよ。懐から脇差を出す。ほんとうに死にたくなったらこれで貫こうと常時帯刀してるこれは、いつしか悪魔に突き立てる武器になっていた。あの頃と比べて成長したはずなのに、あたしは今もお前に近づけていないんだな。
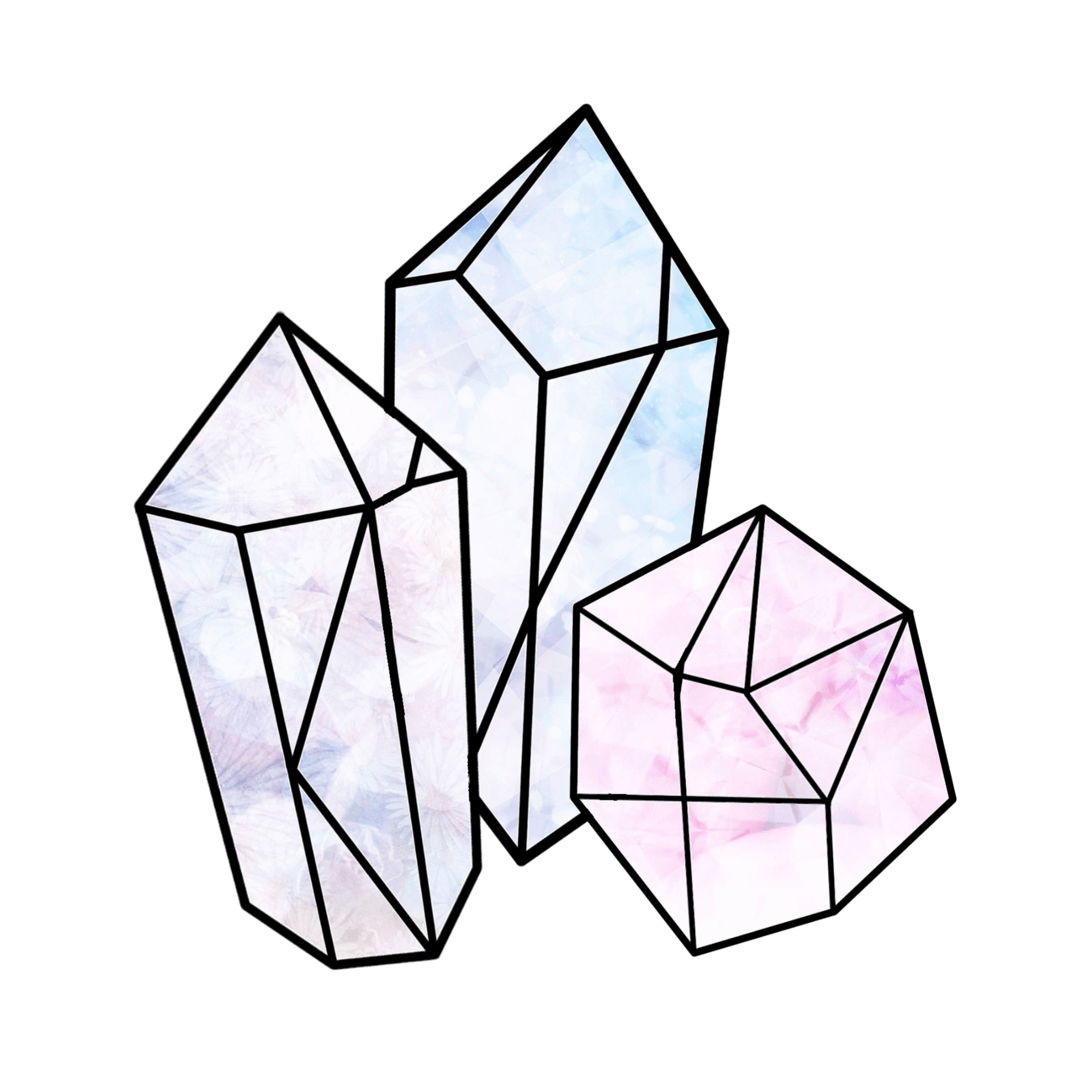
逃げられない離れられない
でも叶わない
、