限りない壮大な天上を太陽が真っ赤に染め上げていた。人為的な火災の赤よりも獰猛で惹き込まれるような赤色。西日に輝く太陽の頭部は天高く光の筋を伸ばしている、それは金色の道のようにも見えた。涼を孕んだ微風が草木澄み渡る草原を撫でる。すべての世界から切り離されたように静謐で、美しいこの時間が私は心地良かった。邪魔する人一人居ない自然に包まれた世界。
「今日も来てるんだな」
それに飛び込んできた金色の蓬髪が特徴的な男性。黒いスーツをまとい、明朗な笑みを浮かべて手を振っている。雑草を踏みながら私の隣に腰を落とす。若葉の涼しい匂いの中で人の手によって造られた香水の匂いが異彩を放つ。重厚感のある苦い香りは、私は好きじゃない。
「先客が居てはだめ?」
「いや? むしろ居てくれて助かる。この時間にひとりで居るのは気が滅入るんだ」
ガキみたいだろ? と子供のように笑った彼は自身の髪を雑に掻き乱す。スーツの袖口から伸びた手首。大雑把に手入れされた無骨な手の甲。黒い炎の刺青が白い肌とは対照的に目立っている。ひとりが嫌いなら帰らないといけない場所へ帰ればいいのに、そう思っても口にはしない。それは改めて私が言うでもなく彼も知っていることだろう。
「寒暖差が堪える時期だな」
「全くそう。おかげで着る服にも気を配らなければならないし」
「そう顰めっ面するなって、似合ってるぞ」
「似合わない服は着ないでしょ」
「そういうところあるよなぁお前」
「褒めてくれなんて言ってない」
「それもそうだ」
悪態を吐いても彼は通じていないのか、それとも気にしていないのか、声を上げて笑い流すだけだった。見上げた空は先程よりも紫色が強くなっていて、どれほどここに居たのか考えさせられる。吹き撫でる風は冷たさが少し勝っていた。これから先薄いショールは出番ないなと肩に羽織るそれを見ながら思った。
「そろそろ戻るとするか」
腕を伸ばして仰け反った彼は溜息を吐いて立ち上がった。金色の蓬髪が風に揺れる。いつ見ても美しい髪だとらしくもなく見惚れてしまう。そして彼は踵を返した。
「またな」
「ええ」
手を振って夕暮れの空に溶け消えてしまう。再び訪れた静寂。寒さが深まる時期でも隣に居た熱はそのままに、苦い香水も鼻腔にこびり付いて消えない。名前を知らぬ存ぜぬな顔で聞かない私たち。交わす言葉も取るに足らないものばかり。けれど、私貴方と居るこの時間は好きよ。それが束の間の逃避行だとしても。
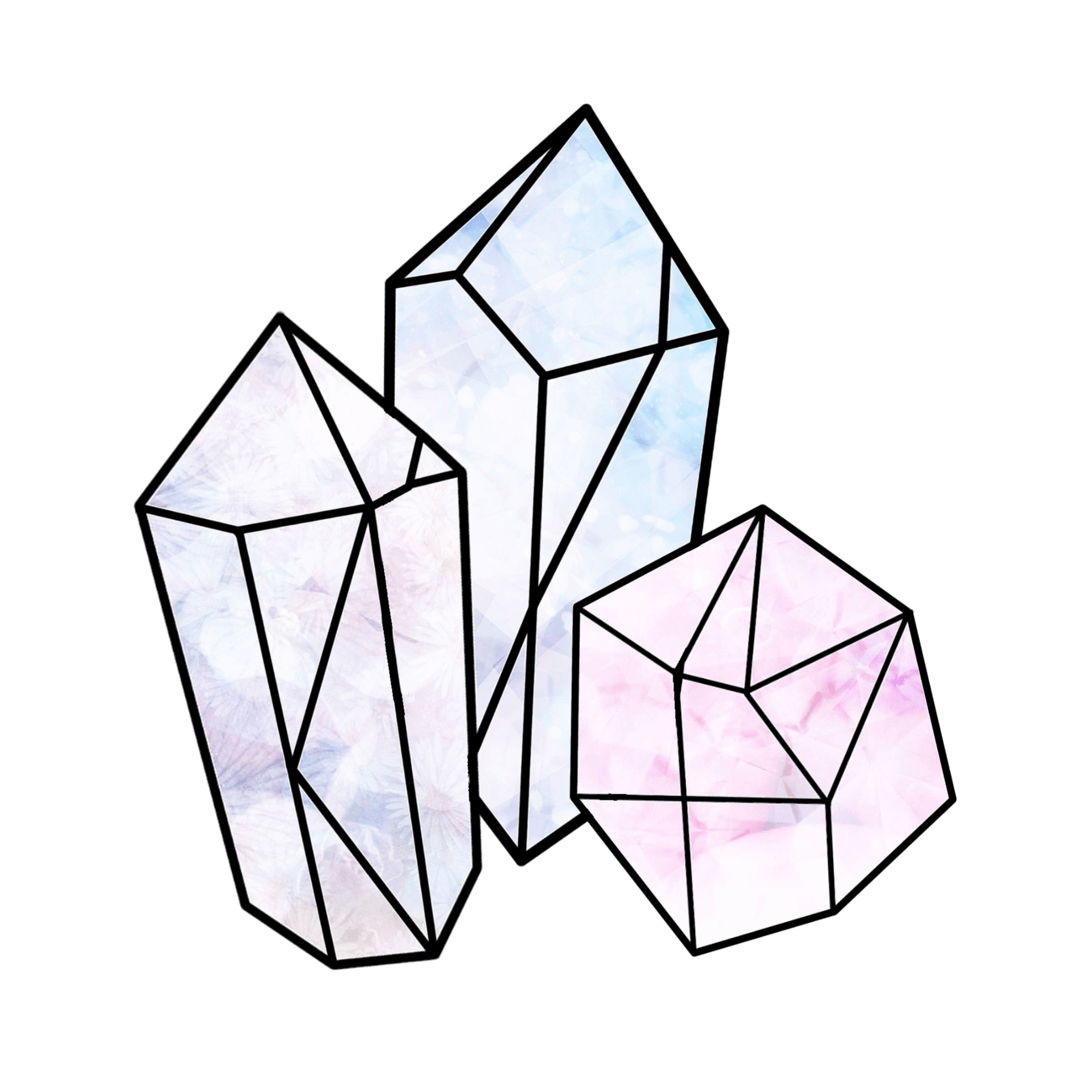
夕暮れの休息
、