怒号にも似たやり取りが絶えず飛び交う様は鬼の如し。戦場にて幾万もの雑兵を、真一文字の竹のような薙刀で葉でも斬るように次々と倒していく、歴戦の勇士すらも怖気付くような覇気。それは我が上司の全身から迸っていた。
「胸の内にまで響く文才だねぇ。私まで斬られそうだ」
「斬られる雑兵の顔じゃないですよ、太宰さん」
今日も独歩さんは鬼だなぁとぼやく私の肩を叩くは、上司がひとり、太宰さんだった。今日も砂色の外套を優雅にはためかせ我が物顔で社内の椅子に腰を落ち着かせている。その様はかのシャーロック・ホームズを彷彿とさせるが、なるほど確かに太宰さんも彼に似ている。薄っぺらい美辞麗句を喜色として騙る彼を、浮かべただけの笑みであしらえば、「おや、そうかい?」と神妙な面持ちをして鏡を見つめた。白々しいこと千万に尽きる。
「おはようございます。今日も遅刻ですか」
「心より残念だよ、遅刻なんて。今朝たまたま通りかかったのだけどそれはもう美しい川を見つけてしまって、思わず飛び込んだのだよ。逝けると思ったのだけどこのとおり失敗してしまってね。いやぁ、非常に残念だ」
「床が濡れるので乾かしてくださいね」
「冬の陽射しのように暖かくもからっとした冷たい言葉! 心にくるねぇ、やはり私と心中を」
「独歩さーん、太宰さんがまた仕事サボってますー」
面倒な勧誘に付き合う時間が惜しいのでそそくさと独歩さんに告口すれば、それまで一心不乱でパソコンを睨んでいた独歩さんは太宰さんの襟を掴んで引き摺っていった。たっぷり水を含んだ砂色の外套から滴る水滴が跡を引く。これは私が掃除するのだろうか。おのずとふたつの肩は朝早くに深深と沈むはめとなった。太宰さんというはた迷惑な宗教勧誘がなくなり仕事も捗ること数時間。射し込む光の位置が低くなり影が餅のように伸びていた。
「もうお昼じゃん」
「そうだよ、もう昼なのだよ」
「外回りお疲れ様です太宰さん」
「酷いじゃないか〜。おかげで国木田君の説教が倍に増えた」
「お昼行ってきますねー」
上司の自業自得を赤裸々に明かされても腹は満たされないし逆に時間と精神が摩耗していくだけなので、私は早々に見切りをつけて席を立った。がたっという音に新入社員の敦くんが気付き、春の太陽もかくやの浄化される笑顔で「行ってらっしゃい」と見送られて探偵社を出る私だった。虎化の異能を持つ敦くん。素直で仕事に意欲的で、実に胸を張って自慢できる可愛い後輩である。学生時代に「先輩」と呼ばれてみたいなんてささやかな願望があったけども、まさかこの歳で成就するとは。しかもこんな可愛い後輩だ、喜べ過去の自分よ。からっ風を正面から受けて身が震えた。早く暖まりたいと、脱兎のように一階の喫茶店に飛び込んだ。
「で、なんで太宰さんも同伴してるんです?」
「つれないこと言わないでおくれよ、私と君の仲じゃないか」
「押し売りはパワハラですよ、太宰さん」
「辛辣! でもそこがまた君の魅力だ」
「すみません、ミルクココアひとつとサンドウィッチひとつください」
「私には珈琲をひとつお願いしよう」
「かしこまりました」
黒髪の可愛らしい女性店員は、恭しく一礼して奥へ下がって行った。大きな窓に面したソファ席には机を挟んで向かい合う私と太宰さん。呼ばれずとも来るスタンスの彼と食事を共にするのはこれが初めてではないが、呼んでないのに来るので毎度話す議題に困ってしまう。ミルクココアが来るまでずっと見つめ合わなきゃいけない拷問はあいにく間に合ってるので全力で遠慮したい。太宰さんはさして気にする風情もなく、大きな窓を見遣って通り過ぎる通行人を興味深く観察している。「あ、あの女性は心中してくれるかな」「あぁ、実に綺麗な手だ、私を絞めてくれないだろうか」「今日も実に良い自殺日和だ」と見惚れる様に、どうしようもなく呆れた溜め息がこぼれた。冷え切った己の手を温めるのではない溜め息は机に向かって吐かれ、喫茶店の空気に溶けて消えた。ちらりと視線を持ち上げれば、視点は太宰さんの細い手首に巻き付く白い包帯を捉えた。
「太宰さんはどうして死のうとしてるんですか?」
別に深い他意はない。興味無い相手に場を持つため当たり障りない質問を投げるように、ミルクココアが来る間の場を持つがため、そして何度も心の奥にしまいこんでいた疑問を問うてみた。平然と「心中」だの「死にたい」だの口にする太宰さんでも嫌な気になるだろうかと言った後に思ったが、眼前の彼は顰蹙することもなければ長年の想いの丈を打ち明ける面持ちもしなかった。予想していただろう質問に用意していただろう回答を口にする。いつもと変わらない風情で。
「では君は何故生きるんだい?」
彼もまた純粋な疑問のように見えた。私と同じように、昔ながらの疑問を深い他意を伴わずに問うてくる。茶色の双眸は幼げな知的好奇心に染まり、けれども大人が持つ一歩引いた俯瞰も孕んでいる。窓から崩れ落ちた斜陽がふたりの影を引き伸ばして、私の瞳をくすぐった。
「知りたいですか?」
「知りたいねぇ、とても」
入り交じるように見つめ合う視線。太宰さんの瞳って外套よりも深い色だと思ってたけど、間近で見てみたら意外と薄い色してるんだな。太宰さんの双眸に私の面持ちが見えた時、私の視線は一刀両断された。
「お待たせしました。ミルクココアと珈琲です」
「ありがとうございます」
女性店員は「ごゆっくり」と聞き馴染みのセリフを吐いて踵を返した。私の前には、もくもくと白色の湯気を昇らせ甘い香りを漂わせるミルクココア。太宰さんの前には、彼の瞳を混ぜたかのような色の苦々しい香りを燻らせる珈琲。私は砂糖の袋をひとつ、指に挟む。昼食時間は限られていて、尚且つ次は社用で外出しなければならない。いくら体力に自信があると言っても腹が空ではたとえ訪ねたとしても力尽きて倒れるのが目に見えている。メインディッシュが着くまで軽く腹を満たして、そして身体を暖めておこう。砂糖の袋を摘む私の手の甲を、覆い被さる大きな手のひらは動きを禁じた。視線をずらせばほくそ笑む太宰さんが私を見ている。
「聞きたいな」
「どうしてもですか」
「どうしても」
「大したものではありませんよ」
「私には大したことさ」
「私が生きる理由なんてそんなの、太宰さんが居るからですよ」
嘘偽りなく言ってやれば私の手はすんなり動いた。千里おろか三千里先も見通す慧眼を持つ太宰さんもさすがに意表を突かれたようで、私を捉える双眸が小さく揺れたのを見逃さなかった。袋の先端を千切ってミルクココアに傾ける。さささ、と細やかな粒の砂糖が雪崩を起こしてミルクココアの中に落ちていく。砂糖が混じったミルクココアは、いつもより少しだけほんのり甘かった。
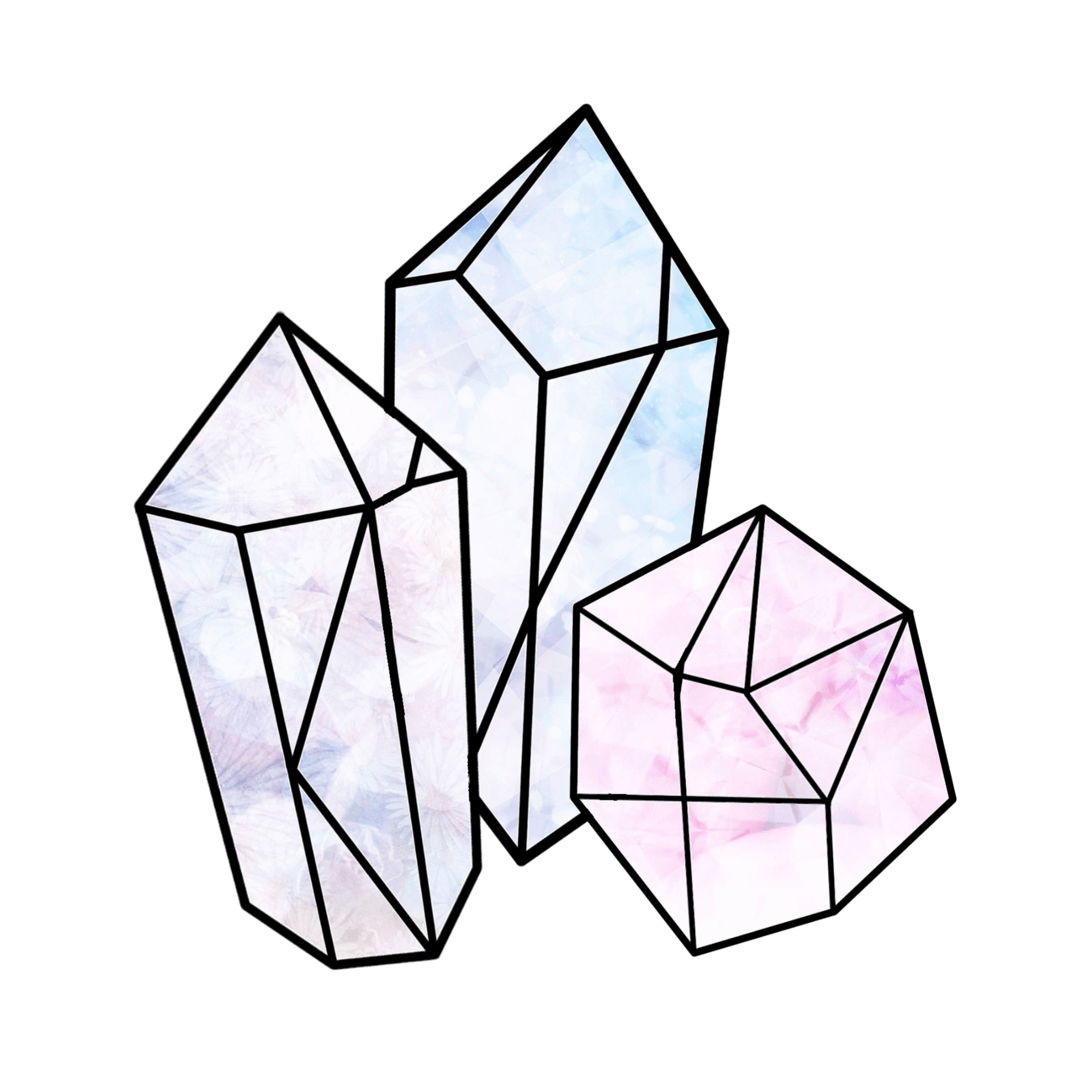
驚きました?
、