人は悪夢を覚えていることが多いと聞いた。もしかしたらそれは単純に体質によるものかもしれないが、特に私はそうだった。小さい頃から割かし悪夢を頻繁に見て鮮明に覚えていた。成人して自立した今となってはあまり見ないが、それでも時々見てしまう。そしてその内容を、私は覚えてしまう。だけど、現実にそれが起こったことは一度もないし、夢は所詮夢だと片付けてしまう性格なゆえに一度たりとも気にしたことはなかった。この日までは。
「寝られない?」
「うん。だから一緒に寝ていいかなって」
月も真上を通り過ぎた時間、私は夫のレギュラスの部屋に訪れていた。決して夜這いではない。こんな時間に夜這いなんてどうかしてる。扉から顔を覗かせた彼の顔は、今しがた起きたという顔で、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。彼は彼で朝早くから仕事があるというのに、こんな夜更けに起こしてしまった。半目な彼は自身の目を擦りつつも。
「いいですよ」
「ありがとう」
快く承諾してくれた。夫婦別室の生活を送っているゆえに彼の寝室がどうなっているかは、あまり詳しくない。彼はいつも寝室で過ごしていないので入る必要がないのだ。室内は広くて、壁や床はブラウンのウッドだが、家具全般は黒白で統一されている。ベッドの向かい側にある彼の身長を優に越す本棚だって黒だ。彼の部屋は確かに入る必要性がないくらいに整頓されていて、それどころか必要最低限の調度品しかないのでむしろ味気ないとさえ思う。だけどよくよく見てみれば、どの家具も奥ゆかしい装飾が施されていて、見るからに頑丈かつ高級そうだ。窓辺に設置されたダブルベッドの端に腰を下ろす。ギシッと音を立てて沈んだ。そのまま一つの枕に後頭部を投げて横になる。レギュラスも続いて隣で横になった。
「ごめんね、起こしちゃって」
向かい合わせになって彼を見た。
「構いませんよ。寝られないと夜泣きされるよりマシです」
「泣かないよ」
顔は半ボケなのに思考は意外とはっきり回るようだ。日常で慣れた彼の毒が、寝起き状態でも発揮されている。そんな彼に、珍しく私は安堵した。
「おやすみなさい」
彼の額にキスを落としてくるりと寝返りを打つ。布団を肩まで被る。シルクの滑らかな肌触りが気持ち良くて、これならすぐに寝られそうだと息を吐いた。だけど言葉を続けたのは意外にもレギュラスだった。後ろから抱き締めてきたのだ。懐に押し込まれるように強く抱擁される。びっくりしたのもあるけど、こうやって二人一緒に寝るなんて久しぶりだから、暖かくて彼っていい匂いなんだなと夢見心地な気分になった。洗濯し終えたばかりの柔軟剤の香りが鼻をくすぐる。柔軟剤選びは彼の雰囲気に合わせて選んでいるので、内心ガッツポーズをした。
「どうしたんですか? 隠し事など貴女らしくない」
唇を耳に近付ける。くぐもった低い声と吐息が耳に直に触れて、そのくすぐったさに身を捩った。彼の黒い髪が首筋を撫でる。彼は至って真面目なんだろうけど、この状況ではまともに答えるどころか、むしろ変な気分になってしまいそうだ。ううっ、無駄な色気ここで発揮させないでほしい。
「聞いているんですか?」
「いひゃいっ」
長くてごつごつとした細い指が頬に触れたかと思うと、遠慮なく一気に抓ったのだ。チーズフォンデュとでも思っているのか、いっそう力を入れて伸ばす。あまりの痛さに彼の手をばしばしと何度も叩いた。痛い!痛いから!彼は自業自得だと言わんばかりの「貴女が悪いんです」という声で指を離した。まだジンジンする。腫れてるよこれ。
「で?ここへ来たのは何故です? 眠れないのなら貴女はココアでも飲むでしょう。ぼくの部屋に夜這いはせず」
「夜這いなんてしないから!」
「はいはい」
ほんとのこと言ったのに何故負けた気分になるのだろうか。
「悪夢を、見たの」
ぽつりと零す。それまでの茶化した雰囲気というか、緩い雰囲気は静かに霧散した。しんと静まった空気に十月特有の寒さが交じる。私が悪夢を見るのは、彼と一緒に寝るのと同じくらい久しぶりだった。夢の内容は至ってシンプルなもの。
そこは荒廃しきった世界だった。建物が崩れ落ち死体は累々と散らばっていて、見上げれば真っ青な空は灰色一色に染まっていた。黒煙が至る所から空へ昇っていて、鼻を刺す匂いはそれは酷い悪臭だった。人を燃やす強烈な匂いと血の強い匂いが交じったような、吐き気を催す匂いだ。灰色と黒しかない景色を少し進むと、足元に何かがぶつかった。それは子供の死体だった。五、六歳くらいだろうか。女の子と思わせるその死体は骨はあらぬ方向へ捻じ曲がり口は大きく開かれ折れた歯や血に染った舌が乾いた唾液と共に流れている。
目はカッと見開かれ焦点はどこにも合わさっていない。煤に覆われた体の至る箇所の皮膚が爛れ落ち、外気に晒された赤い肉に蛆が大量に湧いていた。髪の毛も抜け落ち後頭部の骨が晒されている。そんな無残な死体を見て思わず胃酸が込み上げてきた。「うっ」と手で口を抑えつつ逃げるようにしてその場を走り去る。やがて足が疲れて立ち止まった。ここがどこの世界かも解らない。何故こうなったのか、誰がこうしたのか、一体これは夢なのかさえも。起きろ、起きろ、起きて!!人間かさえ疑ってしまいたくなるような死体はもう見たくない!
心を刺すように望んでも視界は変わらない。とたんに得も言えぬ強烈な恐怖感に襲われた。ここはほんとうに夢なのだろうか。ここは現実ではなかろうか。であれば、いつからこうなっているの? 魔法界はどうなってしまったの? そうだ。彼は? 私の夫はどこへ? 彼は無事なの? 生きているの? たとえ酷い怪我をしていても構わない。生きてさえくれれば、それで。どこ、どこ、どこなの? 首が痛くなるのも構わず辺りを見渡す。左を見ても右を見ても同じ光景しか広がらないことにいっそうの恐怖が心を蝕む。早く彼を見たい。彼を見て安心したい。彼が居ててくれれば。逸る思いから駆けた。
瓦礫が足裏に刺さって足取りが辿々しくなるが、私はそれでも一刻も早く彼の姿を見たかった。その想いが通じたのか、見慣れたローブがそこに立っていた。黒いローブに緑のネクタイ。懐かしさを覚える服装に、心から愛した人の顔。それは紛うことなき夫のレギュラスだった。黒い髪がぬるりとした生暖かい風に揺れる。黒い瞳が私を捉えてぴくりとも動かない。あれだけ強ばっていた顔が彼を見て一瞬で頬が緩んだ。心が掬われた思いだ。だけどそれも一瞬だった。心が緩むのも彼の体が地面へ崩れるのも、ほんの一瞬の出来事だった。
ばさりと音を立てて地面へ横になった彼の体。悲鳴も上げられないまま全速力で彼の体を掻き抱いた。人形のように整えられた顔を私に向けた瞬間、その顔がさっき見た女の子の死体の顔を被ってしまったのだ。痩せこけた顔に焦点の合わない目、そしてだらりと垂れた舌と肉が見えるところに湧く蛆たち。私は夫のレギュラスであるにも関わらず、甲高い悲鳴を上げて投げ捨てるようにさっと体を離した。落ちた彼の体が動かない。動くはずもない。死んだのだから。なのにゆっくりと首が回って私を見た。
可笑しい可笑しい可笑しい!!やだ、怖い、なにこれ、どうなってるの。本来ならば回るはずもないくらいに首が回り骨が悲鳴を上げる。白くなった瞳と大きく開けられた口が物語るのは、恨みだ。私が彼に恨まれることでもしたのか、解らない。だけどそう感じた。
それと同時に私は飛び起きた。
「大人になっても夢ひとつに怖がるなんて、子供っぽいよね。ごめん」
見た夢を掻い摘んで語たった。終わると、なんだか自分が凄く馬鹿らしく思えてきてへらっと笑ってみせた。たかが夢だ。実現するはずがない。現にあれは夢で、こうして彼の腕に抱かれてベッドの中に居るのだから怖がる必要なんてない。そう、怖がる必要なんて。
「この腕が煤に汚れて蛆を湧かせるなど、それこそ夢のまた夢です」
ぎゅうと一段と強く抱きしめられた。私の肩に彼の額がこつんと当たる。フローラルな香りが鼻をくすぐる。夢で見た肌が焼かれるような悪臭ではない。
「そんな腕では貴女を抱き締められないでしょう」
「一生湧かせないでほしい」
「死ぬなと?」
「そうだね。人が死ぬ夢を見たら長生きすると聞いたから、レジーにはもっともっと、それこそダンブルドア校長を上回る時間を生きて欲しいな」
「それは嫌です」
ムスッとしたのが解った。
「ぼくはまだ貴女の死ぬ夢を見ていません」
「私の死ぬところを見たいの?」
「そうですね。貴女がぼくと一緒に長生きしてくれるのでしたら我慢します」
「嫌かも」
「ぼくもですよ」
とても泣き叫んだ夢の後とは思えない心境だ。くるっと輾転して彼を見上げた。黒い瞳は私を捉えているし光は消えていない。恨みなんて露もない。頬を撫ぜる髪は艶をなくしておらず瑞々しい。月の光が射し込んだカーテンを背に、鈍く照らされる顔もどこにも傷跡はなくて肉も晒されていない。蛆なんているわけない。絵から飛び出てきたような美しい顔のままだ。彼が私の手を取って自身の薄い胸板に宛がった。とくん、とくん、と静かに一定のリズムを刻んで浮き沈みを繰り返しているのが、生きている生物が持つ温かな体温と共に伝わってきた。
「ぼくは生きています」
「うん」
「貴女の隣でこうして心臓を動かしている。夢の中のぼくは幻であって、それは現実ではない。貴女が心を揺さぶられるほどの相手ではありません」
「うん」
ひとつひとつ丁寧に言い聞かせてくれる。徐々に恐怖心が薄れていった。彼の腰に腕を回し腹部に顔を押し付けた。ぐりぐりと回す。
「正夢にしないで」
忘れさせてほしいのであれば、記憶にこびりつかせないで。貴方の死に顔はああであってほしくない。もっと安らかに穏やかに、満ち足りた顔であってほしい。私は彼の支えとなるためにブラック家に嫁いできた。名家でもない私が彼の妻になるためにはいくつもの試練があって、彼自身が課した難題もあった。けれど、その上で私は彼と一緒に生きたいと誓ったんだ。彼を支えて幸せにするために。彼が幸せなら私も幸せになれる。そう願って嫁いできたのだから、どうか、レギュラスの最期の顔が悪夢でみた顔でありませんように。私は貴方を笑顔にするためならなんだってできるの。
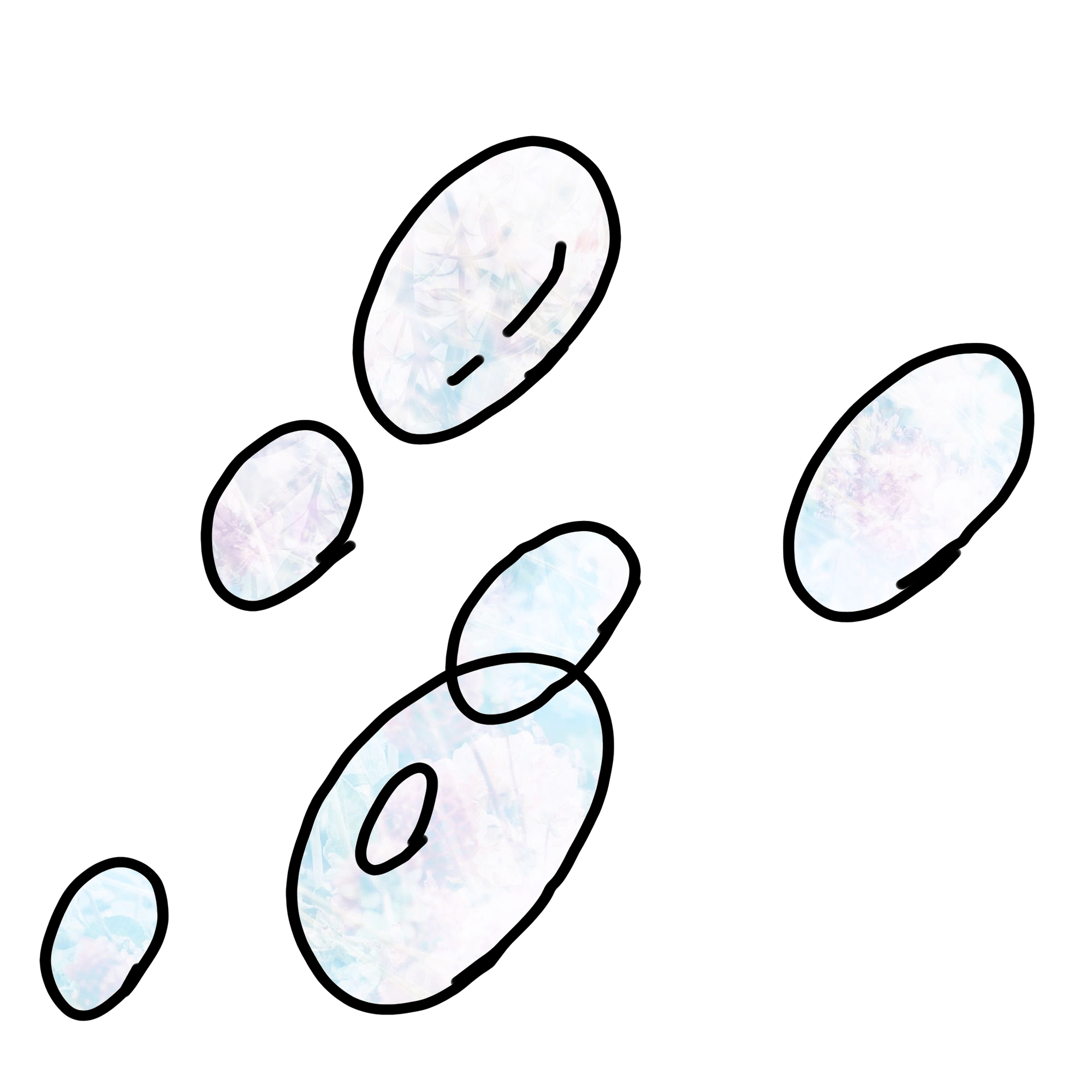
ナイトメアにあなたの顔を見た
、