泣くくらいなら最初から人を愛さなければいいと思う。痛みを抱えるなら、人を好きにならなければいいと思う。所詮恋なんて叶わなければ苦痛の塊でしかないんだから。生徒全員が寝静まったグリフィンドールの塔。消灯時間なんかとっくに過ぎていて、窓から差し込むのは、燦々と照らし付ける太陽の光ではなく、白くて大きな眩しい月の光だ。真上を通り過ぎた月の時刻。本来ならベッドの中に居なければならない時間だが、俺は談話室に居た。人が一人も居ない談話室に、小さく反響する啜り泣く声。鈴を転がしたような声で泣くのは、幼馴染の女生徒である。膝を丸めてその頭に顔を押し付けて泣き続ける。俺はこの光景を見慣れていた。
「おい、いい加減泣きやめよ」
「うっさいっ、泣き止められるならとっくに止めてるっ」
「へーへー」
ったく。こいつは泣く時も悪態つくのかよ。可愛げのねー奴だな。この時間帯にソファの上でうずくまって泣くのは後にも先にもこいつくらいだろうな。こいつは昔からそうだった。何かと傷つきやすいこいつは、人気のない時間帯に一人で外へ出ては両目を腫らして帰ってくる。真っ赤になっているのも関わらず、俺やレギュラスに見つかってはへらりと笑ってみせ「ちょっと目を強く擦り過ぎた」というなんともヘタクソな嘘を吐いてその場を凌いできた。ホグワーツでは夜遅くの外出は認められていない。外へ出れば厳しい罰則と共に寮の点数が大幅に減らされるため、こうやって談話室で涙を流して憂さを晴らしている。俺がこれに付き合うのはいつからだったか。何が理由かさえ思い出せない。泣くだろうな、ってふとした時に気づくから、その時はこの時間帯にベッドを抜け出す。そして泣き続ける彼女の傍で俺は窓の外を眺める。これが恒例となった。
「自分でも解っていただろ。あいつを好きになれば間違いなく失恋するって」
今この歳になってガキみたいに泣き目を腫らすのは、恋愛が理由だ。失恋だの好きなやつに恋人が居ただのですぐ泣く。こいつは見る目がねえからそんな目に遭うんだと嘲笑していたが、今度好きになった奴は今まで以上にこいつの見る目のなさを露呈させた。
「馬鹿だろ。なんでジェームズに惚れたんだよ」
見る目がないのか運が無いのか。不運にもこいつはジェームズを好きになってしまったのだ。それもあいつがリリーと出逢ってしまった後に。渦中の本人はこいつの気持ちに露も気付いていないだろうが、俺と、おそらくリーマスは気づいている。
「あいつにはリリーしか見えていねえのは知ってるだろ」
「うっさいなぁ。知ってるよ、そんなこと。それでも好きになってしまったの!」
解るでしょ、と半ばイラつき半分八つ当たり半分で睨まれた。だがそいつの両目は涙を浮かばせて潤んでいる。声を漏らさないように下唇を噛んでいる。
「んな目で睨んでも怖かねえよ」
「泣かせてよ。どうせ笑ったって叶いやしない恋なんだから、せめて泣かせて」
ふいっと顔を背けてしまう。俺はめんどくさく感じて、後頭部を乱雑に掻き乱した。俺にはこいつの気持ちは全っ然解んねえし、解りたくもねえ。どこの馬とも知れない奴に気持ちを馳せ、向こうも同じ気持ちとは限らねえのにそいつのためにと一生懸命になって、想いが通じあわなければ、最後に残るのはどんなに取り繕ったって痛みだけだ。想いが通じ合わないと苦しみ、受け入れてもらえなければ痛みに泣く。そんなめんどくせえこと、俺はしない。だから誰かを好きになって涙を流すこいつの気持ちを、馬鹿らしいと一蹴する気持ちもあれば、それほど人を好きになれる奴なんだと少し羨ましく思える時もある。
「なら明日は笑えよ」
「話理解して」
「ジェームズの前でも泣く気か? お前」
「しないよそんなこと」
「なら笑え。ブッサイクな顔でも笑え。そしたら自然と泣かなくなる」
そいつの頭を雑に掻き回す。髪型が少し崩れたところで手を止めた。彼女の目から涙が止まっていることに気付いた。不格好でも目を細めて笑みを零すこいつを見て、肩が下がる。
「そうやって笑ってろ」
「シリウスはこういうところを全面に押し出せばもっとモテるのに」
「興味ねぇ」
「ありがとう」
「おう」
こいつはこの先もこうやって誰かを好きになって涙を流すだろう。しょーもねぇ理由で泣いたりして俺の気分を損なわせると思う。こいつは泣いても泣いても結局は、人を愛し続ける。こいつはそういうやつだ。だけど俺も俺で相変わらずそんなこいつの隣で、悪態をつきながらも頭を撫で回すのだろう。結局は俺もこいつのことを愛せずには居られないのだ。そういう面では俺とこいつはある意味似た者同士かもしれないな。
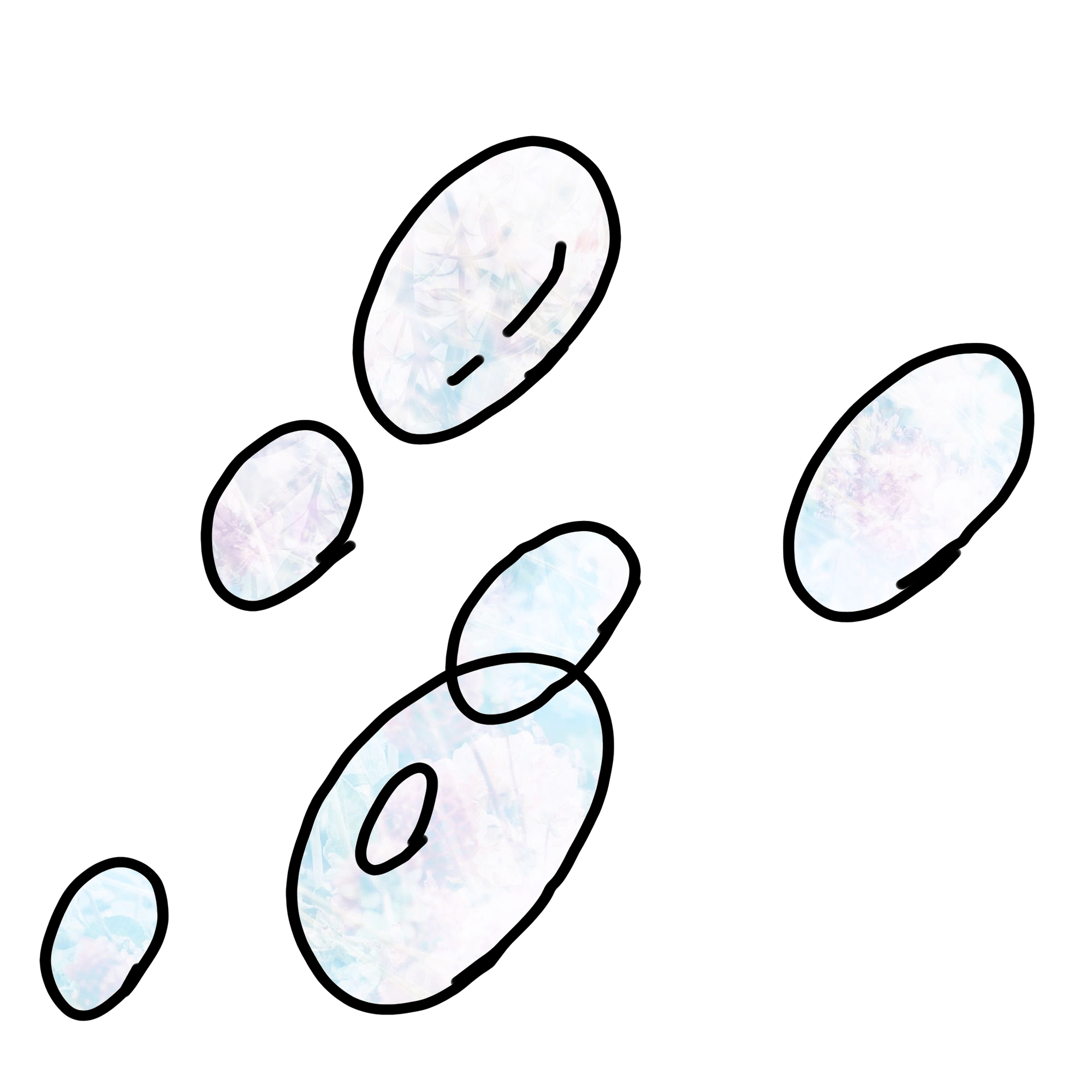
それでも彼女は愛し続ける
、