※百合注意。
「リリー!ちょっとこれ見て!」
慌ただしく駆け寄って来た彼女は、手にしていた紙を突き出すようにして、私に差し出した。
「『クリスマス限定。ハニーデュークスオリジナルのキャラメルチョコチップチョコレート』? 何だか胃もたれしそうなチョコね。これが如何したの?」
真っ赤な紙に、大々的に書かれたその文字は、金色に染っており、縁を雲のようなデザインで装飾されている。以下にもクリスマスらしい広告だ。中央には、丸くチョコレートの写真が載っていて、二つに切られ身が溶け出している。
「買いに行きたい!」
元気良く返事した彼女を見て、そういえば極度の甘党だったなと思い出した。如何やら、キャラメルシロップでコーティングされた四角いチョコの中は、バニラとチョコチップが入っているという、まさに彼女が食い付きそうなお菓子だ。
「行くのは構わないけれど、今度の土曜しか空けれないわ」
それまでは授業、そして月曜には帰省しなければならない。彼女は、残り組で二週間別れてしまうのだ。言い換えれば最後のデートともなる。
「大丈夫! 今度の土曜日行こっ!」
申し訳なさそうにする私の心情を知ってか知らずか、明るい笑顔で手を振った。そんな時、ふと、疑問が湧き上がった。彼女は寂しくないのかしら。短いとは言え、二週間も会わず話さずなのだ。少しは寂しいと思ってもいいんじゃないかしら。何故そんなにも明るくできるのか、私には理解できなかった。現に私は、戻りたいと思わない家に戻る倦怠感よりも、彼女と離れるのが嫌と思っている。彼女は如何なんだろう。
「リリー?」
「ねえ」
「わっ、りっ、リリー!?」
彼女の右手を引っ張れば、何の抵抗も無く私に引き寄せられた。椅子に座る私を覆うような体勢であり、全体重を私に預けたわけではなく、椅子の側面の僅かな隙間に彼女の膝が、支えとして割り込み、紙を落とした左手は、肘掛を掴んで、身を起こしている。私が少し身を浮かせば、口付けできる距離になり、彼女は頬を真っ赤にさせた。それは、瞬く間に耳まで広がる。
「リリーっ!ここ、談話室だよ!?こんな事したら誰か来た時に」
「音を立てなければ大丈夫よ」
他の寮生は全員部屋に居る。何故か、それは消灯時間十分前なのだから。大きな音でも立てない限り、減点を恐れて皆来ない。
「バレたら如何するのっ」
恥ずかしいのか、身を離そうと左手に力を入れるが、私が簡単に話す訳もなく、曲線を描く彼女の細い腰に手を回した。右手を持ったまま、腰に力を入れ、強く引っ張った。すると、彼女のバランスは一気に崩れて、私の両膝を挟んで座る形になった。
「私は構わないわ。その時は、貴女が私の可愛い恋人だと言って、触らせないようにする」
「ばっ、馬鹿っ」
「寂しくないの?」
「え?」
「二週間会えなくても大丈夫なの?」
彼女の瞳が揺らぐ。俯いた彼女は、ややあって首に両手を回し、正面から抱き着いた。
「寂しいよ。二週間どころか、一日話せないだけで嫌だもん。二週間なんか、もっと嫌」
肩に顔を埋めるのが解った。打ち解けてくれた本音が、嬉しかった。私だけかと思ったけど、向こうも同じように、それどころか一日たりとも離れたくないとまできた。これ程嬉しく、可愛い本音があるだろうか。気付けば、彼女がむっと眉をひそめ、拗ねるように見つめていた。
「笑わないでよ、ばか」
如何やら笑みが零れていたらしい。自分でも気づかないうちに、私は彼女をそこまで愛していたのだと実感した。温かさを感じる心は、決して談話室の暖炉の炎ではないだろう。私の膝に座ってようやく同じ視線になった彼女の髪を撫でながら名を呼んだ。
「なに?」
くすぐったそうに目を細める。まるで擦り寄る猫のよう。
「今度の土曜日、楽しみね」
「うん!」
彼女の唇に自身のを押し当て、離す。突然の事に彼女は、硬直したままだった。
「好きよ。愛しているわ」
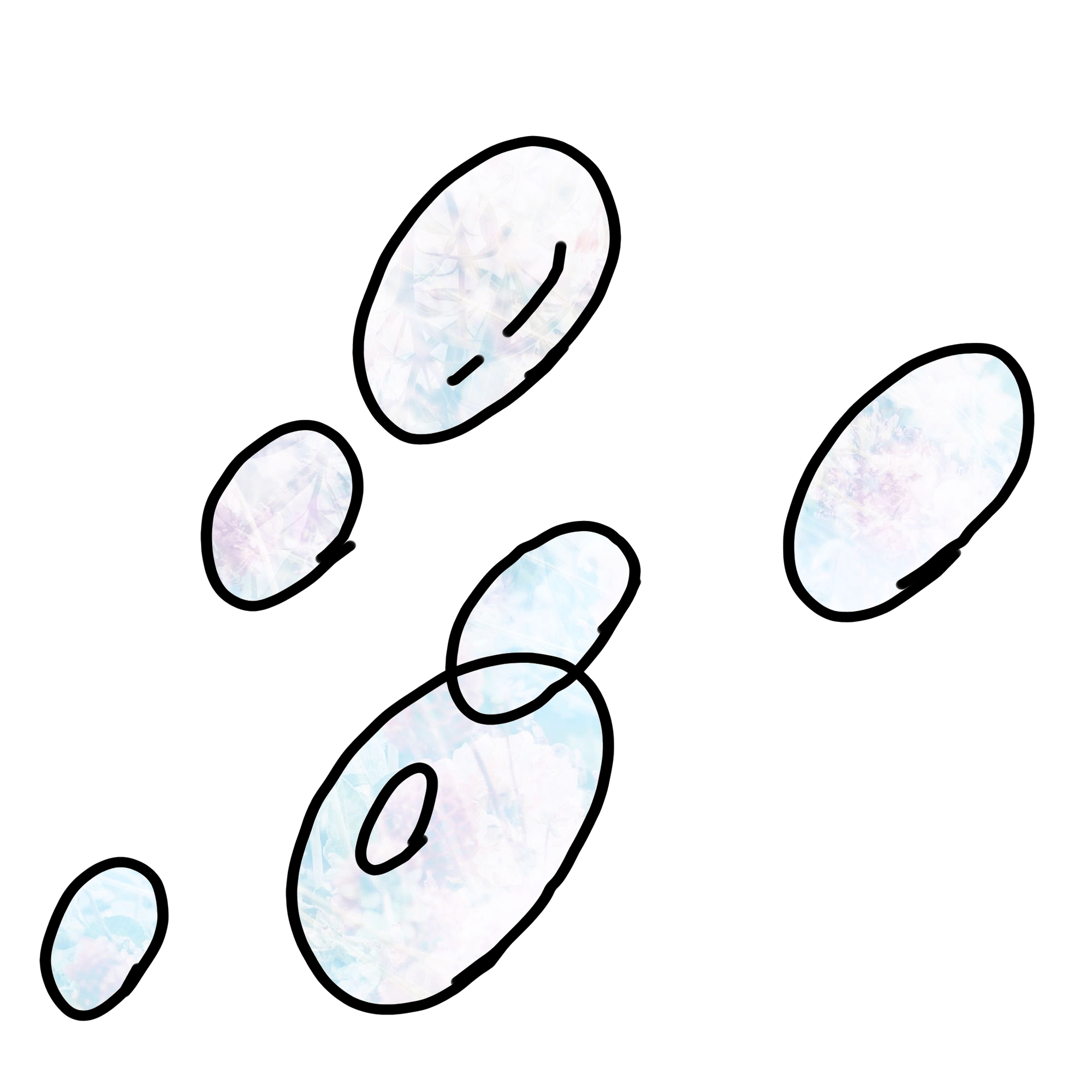
キャラメルチョコレート
、